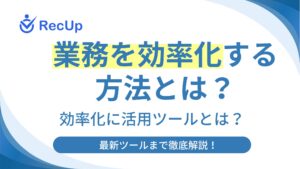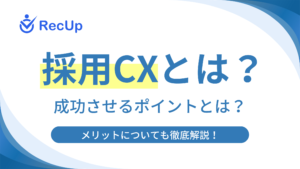Z世代の採用はどうすればいい?成功のためのポイントについても徹底解説!
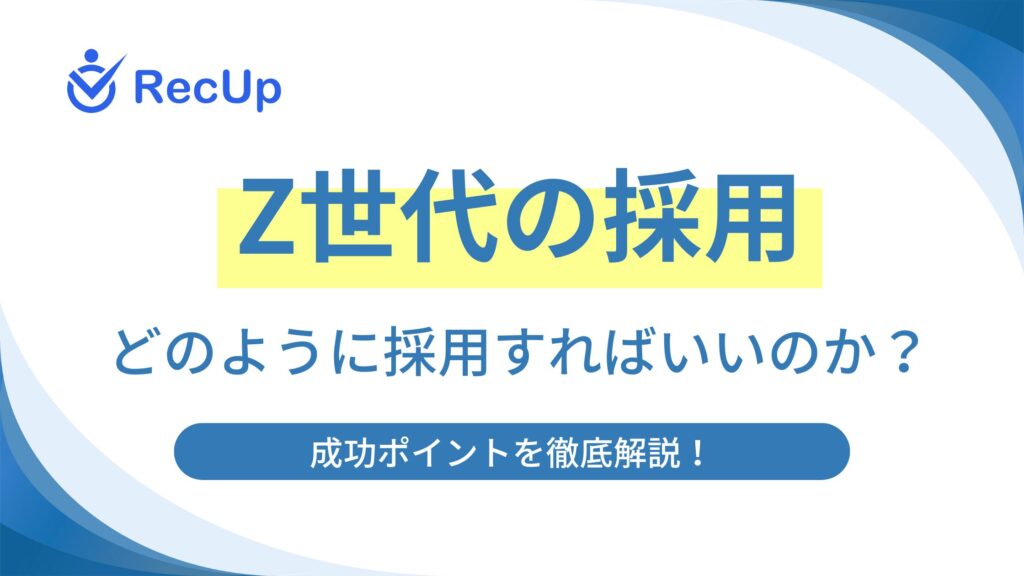
企業にとって採用は会社の未来を左右する大切なテーマです。とくに今の時代、Z世代と呼ばれる1990年代後半から2010年代前半生まれの若い世代をどう採用するかが大きなカギとなっています。Z世代はデジタルネイティブで、情報の扱い方や働き方に独自の価値観を持っているため、昔ながらの採用方法ではなかなか響きません。彼らは働き方やキャリアの考え方も変わっており、待遇だけでは満足しない傾向にあります。
この記事では、そんなZ世代の特徴を詳しく解説しつつ、なぜ採用がうまくいかないのか、成功するための具体的な方法や導入すべき施策、採用後の定着を高めるポイントを分かりやすくご紹介します。これを読めば、自社の採用活動を次のレベルへと引き上げ、魅力的な職場としてZ世代から選ばれる企業になれるはずです。
Z世代とは?

Z世代とは、一般的に1990年代後半から2010年代前半にかけて生まれた若い世代のことを指します。
彼らは、生まれた瞬間からインターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育ち、テレビよりもYouTubeやSNSから情報を得るのが自然な世代となっています。情報技術への親和性は抜群で、感覚も従来の世代とはまったく違います。
さらに、この世代はリーマンショックやコロナ禍といった大きな社会変動をリアルタイムで経験し、不安定な時代を生きる現実主義者でもあります。安定だけでなく、「自分の時間」や「自由」を何より大切にし、無駄をそぎ落とした合理的な生き方を選ぶ傾向が強いのも特徴です。
また、Z世代の多くは環境問題や社会貢献への意識が高いということもポイントです。企業を選ぶ際には「この会社が社会にどんな価値を提供しているか」「CSRやサステナビリティに取り組んでいるか」という視点で選ぶことも少なくありません。だからこそ、給与や福利厚生だけでなく、自社の社会的意義をしっかりと発信することが、Z世代のハートを掴む採用のカギといえるでしょう。
Z世代の特徴を解説!

Z世代を採用する際にまず必要になるのは、彼らの根本的な価値観や特性を理解することです。企業側が従来の世代を基準にして採用活動を行うと、なかなか共感を得られず、「なぜ応募が集まらないのか」「なぜ内定辞退が多いのか」といった課題に直面します。Z世代にはZ世代特有の行動原理や意思決定の基準が存在しており、それを理解したうえで施策を組み立てることで初めて期待する成果が得られるのです。
ここでは具体的に、Z世代の特徴をいくつかの観点から整理していきます。ワークライフバランスの価値観から、キャリア志向や仕事の意味づけ、タイムパフォーマンスの考え方に至るまで、他の世代とは異なるポイントが数多く見受けられます。これらを踏まえることで、採用活動の設計や選考プロセスでどのような工夫が必要かが見えてきます。
ワークライフバランスを重視している
Z世代が働くうえで最も重視する価値観のひとつが「ワークライフバランス」です。彼らにとって仕事は人生の一部に過ぎず、プライベートな時間や趣味、家族や友人との関係性も同じくらい大切です。したがって、終身雇用や長時間労働による自己犠牲を前提とした働き方は魅力的に映りません。それよりも、働きながら自分の生活を楽しみ、自己成長にも時間を割くことができる環境を重視します。
また、コロナ禍を経てリモートワークやテレワークが一般化した影響も大きく、時間と場所を選ばない柔軟な働き方が求められるようになりました。Z世代は企業選びの段階でこの点をチェックしており、「柔軟な勤務制度があるか」「無駄な残業を強いられないか」「自分のライフプランに合う働き方があるか」が志望度に直結します。そのため、企業の採用ページではワークライフバランスを実現する具体的制度や実績をわかりやすく提示することが重要です。
デジタルネイティブで情報収集力が高い
Z世代は「生まれながらのデジタルネイティブ」であり、情報収集のスピードや精度が非常に高い世代です。彼らは就職活動においても、企業の公式サイトだけでなく、SNS、口コミサイト、社員のブログやインタビュー動画などあらゆる情報を組み合わせて判断します。そのため、企業側が一方的に発信する広告的なメッセージには敏感であり、透明性や正直さのない情報はすぐに見抜かれます。
加えて、SNSを活用することでほかの応募者や社会人のリアルな声にも簡単にアクセスできるため、従来よりも「情報格差」が小さいのが特徴です。つまり、採用担当者が思っている以上に、求職者側は会社の雰囲気や裏側まで把握しているのです。
このように情報リテラシーの高い世代に対しては、虚飾のないリアルな情報発信が最も効果的です。例えば若手社員の働く姿を動画で伝えたり、社内イベントをSNS発信したりすることで「この会社なら自分らしく働けそう」と感じてもらいやすくなるでしょう。
キャリアアップに消極的
Z世代は従来の世代と比べると、キャリアアップや昇進を積極的に目指す姿勢がやや弱い傾向があります。ミレニアル世代以前では「管理職に就くこと」や「早く昇進すること」が大きな成功の指標とされてきましたが、Z世代にとってはそれが必ずしもやりがいや幸福感に直結しません。上位の役職に就くことで責任が重くなり、自分の時間を失うのであれば、それよりも現場で専門スキルを磨いたり、自分らしい働き方を確立したりする方が魅力的に感じるのです。
この価値観の背景には、社会の変化のスピードが早まり、既存のキャリアモデルが「必ずしも唯一の正解ではない」と認識されている点があります。また、転職が一般化した現代では、同じ企業で一貫して昇進を重ねるより、環境を変えて自分に合う仕事を探したほうが効率的だと考える人も多くいます。Z世代にとってキャリアとは「出世の階段を登ること」ではなく、「自分が納得できる経験を積み重ねること」と捉えられているのです。
採用活動においては、この考え方を理解したうえで候補者にアプローチすることが大切です。例えば「入社して数年でリーダー職を目指せる」といった訴求ではなく、「業務を通じて幅広いスキルを身につけ成長できる」「社内外で横断的に活躍できる経験が積める」といった情報のほうが魅力的に受け止められます。つまり、従来型のキャリアモデルを提示するより、「多様なキャリアの選択肢」を示すことが、Z世代に刺さるアプローチとなります。
社会的意義や企業文化への関心が強い
Z世代は働くうえで「何をするか」よりも「なぜその仕事をするのか」という視点を重視します。彼らは給与や福利厚生といった外的条件だけでなく、自分の仕事が社会にどのような価値を生み出すのかを強く意識しています。例えば「環境に配慮した取り組みをしているか」「ダイバーシティやインクルージョンに積極的か」「地域社会に貢献しているか」といった企業姿勢は大きな判断材料となります。
これは、幼少期から社会問題や環境問題に多く触れてきた世代背景が関係しています。学校教育におけるSDGs(持続可能な開発目標)の浸透や、SNSを通じた社会問題への意識の高まりも影響しています。このことから、企業選びにおいては、給与や待遇よりも「自分の価値観と合致するかどうか」がより重視される傾向にあるのです。
また、企業文化への関心も無視できません。たとえば、風通しのよいコミュニケーションがあるか、年齢や役職に関係なく意見を出し合えるかといった点は、就職の意思決定に直接つながります。企業のカルチャーが自分に合わないと感じれば、たとえ条件面が良くとも選ばれないケースも多いのです。採用プロセスでは、経営理念や組織文化を具体的に伝える工夫が求められます。事業の意義・価値を伝えるパンフレットや動画、社員インタビュー記事などは、Z世代にとって企業理解を深めるための有効なコンテンツとなります。
タイパを重視している
Z世代にとって「タイムパフォーマンス(タイパ)」は大きな価値観のひとつです。YouTubeやTikTok、サブスクリプション型サービスの普及により、彼らは「短時間で効率的に最大の価値を得る」という感覚を日常的に身につけています。そのため、仕事や学習に対しても「時間をかける=成果がある」とは考えず、時間効率と学びのバランスこそが重要と考える傾向が強いです。
この意識は採用活動においても顕著に表れます。たとえば、選考過程が冗長で不透明だと「時間を無駄にされた」と感じやすいため、結果的に辞退につながりやすくなります。反対に、説明会や面接において「要点を端的に伝える」「オンラインで効率的に参加できる」といった工夫をすれば、ポジティブな印象を持たれることも多いでしょう。
また、入社後の業務においても同様で、非効率な会議や曖昧な業務指示は早期離職のきっかけとなりがちです。Z世代を採用・定着させるためには、成果を得やすい環境や時間を生かせる制度、デジタルツールの導入など、効率的に働ける工夫が欠かせません。タイパを重視する姿勢を理解すれば、単なる「効率第一主義」ではなく、「時間を大切にしながら価値ある仕事を求めている」という積極的な働き方志向として受け止めることができます。
給料はそこまで気にしていない
Z世代にも安定した収入を求める意識は当然ありますが、給与額だけを軸に会社を選ぶ傾向は薄いことが明らかになっています。むしろ重視されるのは「給与に見合う働きやすさ」や「自分らしい働き方が実現できるか」といった点です。この感覚は、バブル崩壊や不景気を経験し「収入の多寡」=「幸福」では必ずしもないと学んできた社会背景と関連しています。
そのため、採用において「うちは高給与」というメッセージは必ずしも魅力にならず、場合によっては「大変な仕事を強いられるのではないか」という不安にさえつながります。むしろ、給料は平均的でも「裁量がある」「キャリアの選択肢が広がる」「スキル習得の支援制度がある」など、プラスアルファの魅力があれば、応募意欲は高まります。
企業が発信すべきは「給与条件に加えて何を提供できるか」です。学習補助制度や副業可制度、柔軟なキャリアパスの提示、社会的意義のある仕事への関与など、給与以外の魅力を具体的に伝えることがZ世代採用に直結します。彼らは単に生活のために働くのではなく、自分らしさを発揮し、人生をより豊かにする手段として仕事を位置づけています。その視点を理解し、メッセージ設計に反映することで、効果的な採用活動が可能になるでしょう。
Z世代の採用が上手くいかない企業の特徴は?

Z世代は他の世代と違い、企業選びの基準が大きく変わっています。そのため、企業側が従来の価値観や採用手法に固執していると、応募を集めにくくなったり、内定辞退や入社後の早期離職といった問題につながってしまいます。採用活動がうまくいかない企業には、いくつかの典型的な共通点が見られます。
ここでは、Z世代採用が思うように進まない企業の典型例を取り上げ、なぜそうした状況に陥るのかを解説していきます。
①リモートを選べない
Z世代はライフスタイルに合わせて柔軟に働ける環境を強く求めています。そのため、リモートワークやハイブリッドワークといった多様な働き方を選べない企業は、それだけで大きく不利になります。特にコロナ禍以降はオンラインでの授業や活動が日常化していたため、「場所や時間に縛られない働き方」が自然な選択肢となっています。
古い体制のまま「出社が基本」「対面でなければ仕事は進まない」というスタンスを固持している企業は、Z世代にとって魅力を感じにくい職場と受け止められます。リモートを完全に排除している企業は「柔軟さがない」「デジタル化が遅れている」といった負のイメージを持たれやすく、応募段階で候補から外されてしまうことさえあります。
もちろん職種によっては出社が必要な場合もありますが、それでも「一部リモートが可能」「フレックスタイム制度がある」といった選択肢を用意しているかどうかで印象は大きく変わります。Z世代が求める柔軟性を受け入れられない限り、採用の成功は難しいといえるでしょう。
②業務内容がはっきりしていない
Z世代は未知の状況や曖昧さを嫌う傾向があります。そのため、募集要項や面接で具体的な業務内容がイメージできなければ、「入社後にどんな仕事をするのか分からない」「自分が成長できるか不安」と感じ、応募を避けたり内定辞退につながったりするリスクが高まることになります。
従来の採用では「入社後に成長しながら仕事を覚えていく」というスタンスでも問題ありませんでしたが、Z世代にとってそれは「リスクの高い選択」に見えるのです。仕事の役割や期待される成果、習得できるスキルを具体的に説明できない企業は「社員教育が不十分で放置されるのではないか」という懸念を抱かれます。
また、情報収集力の高いZ世代は、曖昧な表現と具体的な説明の差を敏感に見抜きます。企業が抽象的な言葉でしか業務を語れないと、信頼性そのものが揺らいでしまい、結果的に「透明性のない会社」と評価されるのです。業務内容が不明瞭な状態で採用活動を続けることは、Z世代に刺さるどころか、むしろ拒絶反応を引き起こす危険があるといえるでしょう。
③残業が多い
「たくさん働いて成果を出すことが評価につながる」という価値観は、Z世代にとっては共感しにくい考え方です。この世代は人生のバランスを重視しており、休暇やプライベート活動も仕事と同じくらいの価値を置いています。そのため、残業が常態化している企業や、休日出勤を前提とした働き方には強い抵抗感を持ちます。
さらに、就活生は口コミサイトやSNSを通じて「長時間労働の会社かどうか」を簡単にリサーチします。求人票には魅力的なことが書かれていても、「社員の声」として残業の多さやワークライフバランスの悪さが広まれば、応募前に候補から除外されてしまうのです。つまり残業体質の改善ができていない企業は、優秀なZ世代人材を永遠に取り逃がしてしまうリスクを抱えることになります。
もちろん、ある程度の業務量が発生することは仕方ありません。ポイントは「無駄な残業をしなくても済むような仕組みが整っているかどうか」です。効率的に働ける業務フローやツールが導入されていれば、多少の繁忙期があっても「社員を大切にしている会社」と評価されやすくなります。反対にそれがない企業はあっという間に敬遠されるのが現実です。
④社風が古い
Z世代が最も敏感に察知するのは「企業文化の古さ」です。上下関係が厳格で上司の言うことが絶対、若手が意見を言いにくい環境の企業は、それだけで応募の選択肢から外れます。この世代はフラットなコミュニケーションを好む傾向にあり、社歴や年齢に関係なく意見を出せる環境を望んでいます。
さらに、「男性中心の文化」「多様性のない組織」といった風土は、Z世代にとって大きなマイナスポイントです。ダイバーシティやインクルージョンの価値を自然に受け入れている彼らにとって、社風が古いことは自分の価値観と合わないと感じる要因になります。時代遅れの体質を持つ会社ほど「成長できそうにない」「長くは続けられない」と判断されやすいのです。
採用説明会や面接においてもその空気感は伝わってしまいます。例えば、面接官が高圧的であったり、多様性に関する質問に具体的に答えられなかったりすると、候補者は瞬時に「この会社は古い」と感じてしまいます。反対に、若手社員が前に出て自然に意見を交わしている雰囲気を見せられれば、「ここなら自分も活躍できそう」と好印象につながります。
Z世代に刺さる採用施策を紹介!
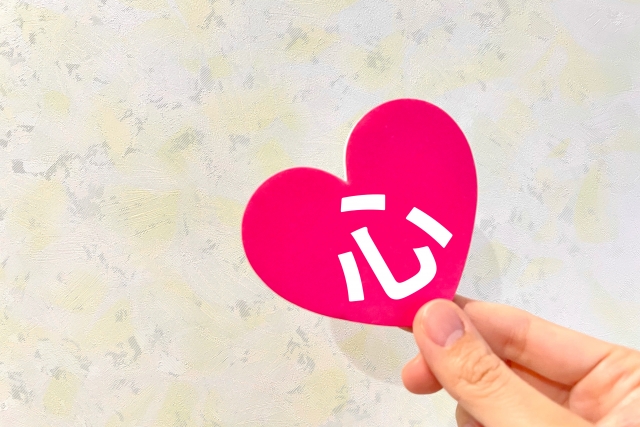
Z世代を効果的に採用するためには、単に求人広告を出すだけでは不十分です。Z世代はデジタルネイティブであると同時に、自分の価値観に合うかどうかを重視する傾向が強く、従来の一方的・画一的な採用手法では響きません。彼らの特徴を踏まえたうえでコミュニケーション設計を行い、情報発信や接点の持ち方に工夫をすることが不可欠です。
ここでは、Z世代の心を掴む採用施策を、それぞれの効果や導入のポイントとともに解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
ダイレクトリクルーティングを活用する
まず注目すべきは、ダイレクトリクルーティングの活用です。従来の求人媒体に掲載して待つだけの採用では、Z世代との接点は限定的になってしまいます。情報収集能力が高く、また就活の方法も多様化しているZ世代にとっては、自分の価値観と合うかどうかが最も重要なため、企業から能動的にアプローチする仕組みが効果的です。
例えば、スカウトメールやSNSを通じた個別アプローチでは「あなたのプロフィールを見て、こういう点に共感した」といった具体的なメッセージを添えることで、Z世代の心に刺さりやすくなります。彼らは大量の機械的メッセージには敏感に違和感を覚えるので、個別性があるかどうかが重要な分かれ目になります。
また、ダイレクトリクルーティングのメリットは、企業側が欲しい人材に直接アプローチできる点でもあります。Z世代の求職者に対して早い段階から「この企業に自分の存在を評価されている」と感じてもらうことで、応募や内定承諾の確率を高められる仕組みです。待つだけではなく攻めの採用にシフトすることが、Z世代攻略の第一歩といえます。
SNS・動画活用を活用する
Z世代は情報源としてSNSや動画コンテンツを積極的に利用しています。企業研究も企業ホームページよりYouTube、Instagram、TikTokなどの媒体で得る割合が増えており、言葉だけでなく「雰囲気」「リアルな社員の姿」「現場の空気感」に触れることで志望度を高める傾向があります。
SNSや動画を採用活動に取り入れる際は単なる広告ではなく、等身大の企業の様子を伝えることが大切です。例えば、社内イベントの様子、若手社員の一日の働き方を紹介するショート動画、インターン参加者の体験談といったコンテンツはとても効果的です。Z世代は飾られた表面的な情報に敏感であり、「リアリティがあるかどうか」を必ずチェックしています。
さらに、動画は情報を短時間で理解できる強力な手段となります。Z世代が重視するタイムパフォーマンス(タイパ)に合致するため、長文の情報よりも短い動画で要点を伝えた方が信頼を得やすい場合が多いです。「1分でわかる○○部の紹介」といった形で発信することで、興味を惹きつけられるでしょう。
インターンや内定者プログラムを充実させる
インターンや内定者向けのプログラムを充実させることも、Z世代の採用では欠かせません。この世代は実際に体験して「自分に合うかどうか」を重視するため、体験的な接点を持つことがとても大切です。Web説明会や募集要項だけよりも、実際の社員や現場に触れることで魅力を感じやすく、志望度が高まる傾向があります。
短期インターンであれば「雰囲気を知るための体験」、長期インターンであれば「業務を通じて実力を発揮する場」と位置づけ、学びの機会を豊富に用意することで効果が高まります。Z世代は「与えられる作業」よりも「自ら考えて行動できる課題」を求めており、そこでの実体験によって「ここで働きたい」という確信に変わります。
また、内定承諾を得た後の内定者フォローも極めて重要です。入社までの期間に孤独感や不安を持たせないために、同期との交流イベントやオンラインコミュニティを提供することで愛着を高めることができます。これにより、内定辞退や入社後の早期離職を防止し、定着率向上にも繋がります。
柔軟な働き方やキャリアパスの提示する
Z世代にとって、働き方やキャリアの柔軟性は最重要ポイントです。
これまでのように「まずは下積み」「何年か経ってからようやくキャリア形成が始まる」というスタイルでは共感を得られません。入社段階から、どんなスキルを習得できるのか、どのようなワークスタイルを選択できるのかを提示することが大切です。リモートワーク、フレックスタイム、副業制度、ジョブローテーションなど、多様な働き方を明確に打ち出すことでZ世代は安心し、応募意欲も高まります。
また、「キャリアは一方向ではなく選択肢がある」という考え方を提示すると、彼らの価値観にマッチさせられるでしょう。たとえば、「管理職を目指すキャリア」と「スペシャリストを目指すキャリア」を並行して制度化し、どちらを選んでも成長できる道を用意しておけば、自分の志向に合った働き方をイメージしやすくなります。Z世代は出世だけを成功と考えず、多様な人生選択を尊重する文化に共感を覚えるため、このアプローチは非常に効果的です。
社会的意義・企業文化を具体的に伝える
最後に重要なのが、企業が持つ社会的意義や文化を明確に伝えることです。Z世代は「誰のための仕事なのか」「社会にどう役立つのか」をとても重視しています。単に事業内容を説明するのではなく、「このサービスが人々の暮らしをどう豊かにするか」「この事業が社会にどのように貢献しているか」といったストーリーを提示することが求められます。
また、企業文化に関しても、抽象的な言葉よりも具体的な事例が響きます。例えば「風通しの良い職場です」と伝える代わりに、「新卒入社3年目の社員が新規プロジェクトのリーダーを任された」といったエピソードが効果的です。実際の社員の声を交えることで、Z世代は「この職場なら自分も成長できそう」と実感を持ちやすくなります。
さらに、サステナビリティやダイバーシティ、多様な働き方支援など、社会課題にどう取り組んでいるかを可視化することも欠かせません。Z世代はSNSを通じて世界の動きを敏感にキャッチしているため、企業が時代に即した文化と取り組みを発信しているかどうかが、採用の決め手となるのです。
Z世代採用の定着率を上げるポイントを解説!

ここまで、Z世代の価値観や採用のポイントについて詳しく解説しました。しかし、大事なのは入社後に長期的に活躍してもらうことです。Z世代は「合わない」と感じれば短期間でも転職を選びやすく、企業にとってはコストも大きな損失になりかねません。定着率を高めるためのカギは、Z世代の価値観を理解したうえで、内定から入社、そしてその後のキャリア形成までを一貫してサポートすることにあります。
ここでは、「内定者フォローやメンター制度」「フィードバック・評価の仕組み」「オンボーディング・研修」の3つの視点から、定着率を飛躍的に高める具体的ポイントを紹介します。
内定者フォローやメンター制度を導入する
Z世代にとって、入社前の不安感を放置されることは大きな離脱要因になります。内定から実際の入社までに数カ月のタイムラグが生まれる場合、その間に「本当にこの会社でいいのか」という迷いが生じやすく、結果として内定辞退に至るケースがあります。これを防ぐためには、内定者をしっかりとフォローする体制を整えることが大切です。
内定者同士が交流できるオンラインコミュニティや定期的な懇親イベントを設けると、安心感と仲間意識が芽生えやすくなります。また、現場で働く若手社員を「バディ」や「メンター」として内定者につける制度も有効です。年齢が近い先輩社員からのリアルな経験談は就活情報サイト以上に信頼感を持たれやすく、「入社後のイメージ」が具体的に湧くようになるでしょう。
メンター制度の効果は入社後にも続きます。社会人として新しい環境に飛び込む際、Z世代は孤立感を抱きやすいので、いつでも相談できる存在がいることは退職リスクを減らすために非常に重要です。フォローアップ体制を制度化すれば企業に対するロイヤリティを高められ、早期離職の防止につなげられるでしょう。
Z世代が求めるフィードバック・評価の仕組みを作る
Z世代は常に「自分が成長しているか」「努力がどう評価されているか」を知りたいと考える傾向があります。彼らは学校教育やSNSを通じて即時的なフィードバックに慣れており、「やってみてほったらかし」の状態が続くと、不安や不満につながりやすいのです。
そのため、年に数回だけ行う従来型の人事評価ではなく、短サイクルでのフィードバックを導入することが効果的です。例えば、上司との1on1ミーティングを毎月実施する、業務終了後に小さな振り返りを行うといった習慣を持たせることで、自分の成長度合いや改善点を実感できます。
また、評価指標を明確にすることも重要です。「頑張ればその分認めてもらえる」「取り組みが正しく可視化されている」という仕組みがなければ、Z世代は正当に扱われていないと感じてしまいます。透明性の高い評価制度や成果と行動を結びつけた指標の設計は、モチベーションを高める大きな要素となります。
さらに、フィードバックは一方通行ではなく双方向であることが大切です。Z世代は自らの意見を大切にする世代なので、上司からの指摘だけではなく、本人の自己評価や意見を取り入れる仕組みを構築すると、主体的に成長意欲を持ち続けることができるでしょう。
オンボーディング・研修を強化する
入社直後の数カ月は、Z世代の定着にとって極めて重要な期間です。最初にポジティブな経験を積めるかどうかで、その後のキャリア観やロイヤルティが大きく変わります。ここで機能するのが「オンボーディング」と呼ばれる入社初期のフォロー体制や研修です。
しっかりと設計された研修やオンボーディングを通じて「自分はこの会社に必要とされている」と感じられれば、安心して仕事に取り組むことができます。反対に、放任状態で右も左も分からないまま業務に追われると、強いストレスを感じ、早期離職のリスクが高まります。丁寧な受け入れ体制は企業にとって欠かせない投資なのです。
有効なオンボーディング施策の一例としては、入社直後のオリエンテーションで会社のビジョンやミッションを具体的に伝えること、実務に必要なスキルをワークショップ形式で学べる場を提供することが挙げられます。また、初期段階で小さな成功体験を積ませ、上司からの肯定的なフィードバックを与えることで「自分はこの職場でやっていける」という自己効力感を醸成することが大切です。
さらに、研修は一度きりではなく、段階的かつ継続的に行うことで定着効果が高まります。Z世代は常に「学びの機会」を求めているため、入社後も定期的にスキルアップ研修やキャリア形成プログラムを提供することで、会社への信頼とエンゲージメントを深めることができるでしょう。
Z世代のターゲットに合わせた採用ならAIスカウト「RecUp」

この記事では、Z世代の特徴を明らかにし、効果的な採用施策や入社後の施策について解説しました。Z世代の採用成功には、彼らの多様な価値観に合わせた戦略的アプローチが必要です。
そこで注目を浴びているのが、優秀な人材に企業が声をかけるという攻めの採用、ダイレクトリクルーティングです。上記でお話したように、個人にあてたメッセージを送ることで、「この企業なら…」と応募を決める求職者も多いです。しかし、個別のメッセージは、タイトルも文面も作成するのに多くの時間と手間がかかってしまうのがネックで、多くの求職者から条件の合う人材を見つけるのも苦労してしまいがちです。
そこでおすすめなのが、AIスカウトサービス「RecUp(リクアップ)」です。RecUpは、AI技術を駆使し、膨大な求職者データから最適な人材を自動抽出し、求職者ごとにパーソナライズされたスカウトメールを自動生成・配信します。これにより、高いセキュリティ基準のもと、採用担当者の業務負担を大きく軽減しながら大量のメールを効率的かつ個別に最適化して送信できるため、効率よく採用活動を行うことができます。
RecUpは、効率やパーソナライズを重要視するZ世代の採用に、特に最適なパートナーとなるでしょう。ぜひこの機会にご検討ください。サービスについて、詳しくは下記よりご覧ください。
監修者プロフィール

-
株式会社Delight
RecUp事業部 カスタマーサクセス部門責任者
新卒から求人広告事業に従事し、企業の採用課題に向き合う中で、実践的な支援スキルを培う。その後、自社開発のAIを活用した採用支援ツール「RecUp」の営業責任者として、プロダクトを活用した採用戦略の設計・実行支援に従事。並行して自社の採用活動にも深く関与し、事業成長フェーズにおける人材要件定義、母集団形成、採用面接など、実務から戦略まで幅広い領域を担当。現在はカスタマーサクセス部門の責任者として、100社以上の採用支援実績をもとに、採用活動の最適化を支援している。実務と戦略の両視点を持つ実践型の採用コンサルタントとして、現場に寄り添いながらも成果に直結する支援に定評がある。
最新の投稿
- 2025年9月12日採用戦略採用ミスマッチの原因とは?ミスマッチを防ぐ改善策を徹底解説!
- 2025年9月12日採用戦略採用の歩留まりとは?計算方法や改善策について徹底解説!
- 2025年9月11日スカウトツールエンジニア向けスカウトメールとは?返信率を上げるポイント徹底解説!
- 2025年9月11日採用戦略採用CXとは?メリットや成功させるポイントについて徹底解説!