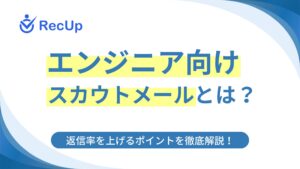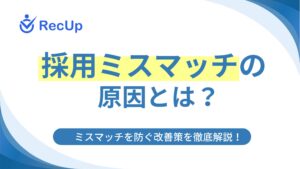採用の歩留まりとは?計算方法や改善策について徹底解説!
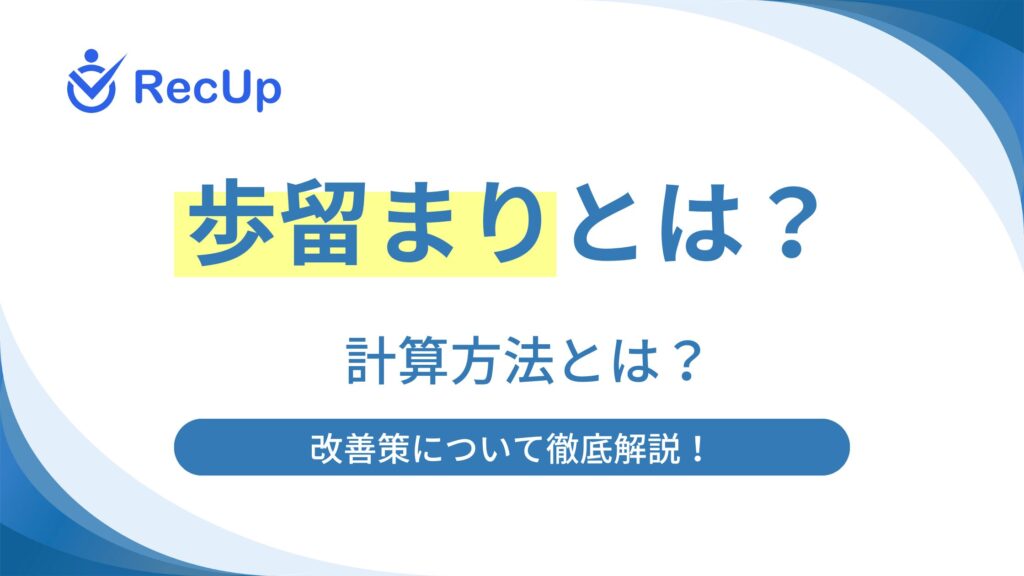
企業が採用活動を行う際、応募数や内定数といった結果だけに目を向けてしまいがちですが、その過程を正しく把握し改善していくことこそが採用の成功につながります。特に注目すべきなのが「採用の歩留まり」です。
本記事では、採用の歩留まりの基本的な意味から計算方法、発生する原因、さらに改善のための具体策までを徹底解説します。採用効率を高めたい人事担当者や経営者の方にとって必ず役立つ内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
採用の歩留まりとは?

採用の歩留まりとは、採用プロセスの各段階で候補者がどの程度残っているかを表す割合のことです。例えば「応募者数」「書類選考通過者数」「面接通過者数」「内定者数」「入社者数」といったフェーズごとに算出し、採用活動の効率性を把握するために活用されます。
この数値が低い段階があれば、その部分に課題が潜んでいると判断できます。応募は多いのに面接通過が少ない場合は求人内容に問題があるかもしれませんし、内定から入社に至る歩留まりが低ければ、条件面やフォロー体制に改善の余地があると考えられるでしょう。
例としては、求人を出した際に多くの応募があったとしても、面接に進む候補者が少なければその段階で歩留まりが低いことになりますし、最終的に内定を出しても入社につながらなければ、せっかくの採用活動も成果が限定的になってしまいます。
このように歩留まりは、単に数値的な指標ではなく、採用活動全体の健全性を示す重要なものです。歩留まりの計算方法を理解することで、自社の採用プロセスにおける課題が見えやすくなり、改善策を講じることができます。
採用における歩留まりの計算方法とは?

採用の歩留まりを把握するためには、まず計算方法を理解する必要があります。歩留まりは「応募者数」「書類通過者数」「面接通過者数」「内定者数」「入社者数」といった各段階ごとの数値を基に算出されるのです。
正しい計算式を用いれば、どの段階で候補者が離脱しているのかを明確に知ることができます。ここからは、採用における歩留まりの正しい計算の仕方について解説していきます。
採用歩留まりの計算式
採用歩留まりを算出する方法はシンプルです。基本的には「あるプロセスに進んだ人数 ÷ 前段階の人数 × 100」で計算します。例えば、100人が応募して50人が書類選考を通過した場合、書類選考の歩留まりは50%です。同じように、50人中20人が一次面接を通過したなら、その段階の歩留まりは40%になります。
例に挙げたように各段階の割合を数値化することで、どこに課題があるのかが可視化されます。もし応募数に比べて書類通過率が極端に低い場合は、求人内容や応募条件に問題があるかもしれません。
最終的な「内定承諾率」や「入社率」も重要な指標です。内定を出しても承諾につながらないケースが多い場合は、条件や待遇に課題があると考えられます。逆に、承諾はされても入社前に辞退が相次ぐ場合は、候補者とのコミュニケーション不足やフォロー体制の不備が原因となることが多いです。
なぜ採用で歩留まりが発生するのか?主な原因について詳しく解説!

採用活動において歩留まりが発生する背景には、いくつかの共通した要因があります。候補者が離脱してしまう理由を理解することは、改善の第一歩です。
ここでは、なぜ採用時に歩留まりが発生してしまうのかの代表的な原因を具体的に解説します。
母集団形成が上手くできていない
採用活動で歩留まりが低くなる大きな原因の一つに、母集団形成の失敗があります。母集団形成とは、そもそも採用活動で集める候補者の“母集団”を十分に確保することです。
母集団が小さいと、書類選考や面接で辞退者や不適格者が出た場合、そもそも選考対象となる人数が不足してしまい、歩留まりが低下します。人気企業や知名度が低い企業では、求人媒体や広告の出し方によって応募数が大きく変動します。
求人票の内容が曖昧であったり、仕事内容や待遇が具体的に書かれていなかったりする場合も、母集団形成を阻害しかねません。候補者が「自分に合う仕事か判断できない」と感じると、応募をためらったり、選考途中で辞退したりする傾向があります。
母集団形成の失敗は採用活動全体に連鎖的な影響を与えます。改善策としては、求人媒体の見直し、ターゲット層に合わせた広告表現、社内での魅力的な条件整理などが効果的です。
選考条件が厳しい
採用歩留まりが低下する原因として、選考条件の厳しさも大きな要因です。企業はスキルや経験、資格などをもとに候補者を絞り込もうとしますが、条件が厳しすぎると応募者自体が少なくなり、書類選考や面接の段階での通過率も下がってしまうのです。
条件が厳しければ、応募者の心理的ハードルも上がります。「自分は条件を満たしていないかもしれない」と感じると、応募を控える人も増えるのです。さらに、選考過程で条件に合わないと判断されれば、候補者は途中で辞退してしまうこともあります。
このため、企業は必要条件と望ましい条件を明確に区別することが重要です。必須条件は絞りつつ、柔軟な対応が可能なポイントは柔らかく記載することで、母集団を維持しつつ質の高い候補者を確保できます。
選考条件の見直しは歩留まり改善に直結します。具体的には、条件の優先順位を整理し、必須・歓迎条件を明確化すること。さらに、未経験者やポテンシャル採用を検討する場合は、教育体制や研修制度を明示することで、応募者の安心感を高められます。
内定までに時間がかかる
採用活動において内定までの期間が長引くことも、歩留まり低下の大きな原因です。候補者は複数の企業を同時に受けていることが多く、内定が遅れると不安を感じ、他社を優先するケースが増えます。特に人気の高い人材や優秀な人材ほど、待たされることによる不満が大きく、内定辞退につながる可能性が高いのです。
時間がかかる原因としては、社内での選考スケジュールの調整不足や、面接官の都合調整の遅れなどが主です。複数のステップを踏む選考フローの場合、各段階での合否通知が遅れると、候補者は「自分は重視されていない」と感じ、モチベーションが下がります。その結果、内定承諾率や入社率に悪影響を及ぼし、歩留まりが低下するのです。
改善策としては、選考フローの短縮や面接官のスケジュール調整の効率化、通知のスピードアップが重要です。また、候補者に対して「次のステップはいつ頃決定するか」を明示するだけでも安心感が生まれ、辞退率を下げられます。
候補者のフォローアップができてない
選考中や内定後のフォロー不足も、歩留まり低下の重要な原因です。候補者は選考の過程で不安や疑問を抱くことが多く、それに対して企業側が適切に対応できないと、辞退につながります。
具体例を挙げると、面接後のフィードバックが遅い、選考結果の連絡が不明瞭、内定後に必要な情報提供が不足している場合などが該当します。候補者は「自分は軽視されているのではないか」と感じ、他社に流れるリスクが高まるのです。
特に内定後のフォローは重要です。承諾から入社までの期間に連絡が少ないと、候補者のモチベーションは低下し、入社辞退率が上がってしまうでしょう。定期的に連絡を取り、疑問や不安を解消することで、候補者は安心して入社を決断できます。
フォローアップの方法としては、メールやチャットでのこまめな情報提供、選考ステータスの共有、内定後の入社準備に関する説明などが有効策になりやすいです。面接官や担当者の対応態度も重要で、丁寧なコミュニケーションは候補者満足度も高められるでしょう。
求人情報と乖離している
求人情報と実際の仕事内容や条件が乖離している場合、候補者の離脱率が高くなり、採用の歩留まりが大きく低下します。例を出すと、求人票に「残業ほぼなし」と書かれていたにもかかわらず、実際には頻繁に残業が発生していた場合、候補者は入社前に期待していた働き方と現実のギャップを感じ、内定承諾を辞退する可能性もあるでしょう。
こうした乖離は、企業の信頼性や採用ブランドにも影響を及ぼします。候補者が「企業の情報は正確ではない」と感じると、応募時点から不安が生じ、書類選考や面接の通過後でも辞退につながることがあるのです。
改善策としては、まず求人票の情報を実態に合わせて見直すことが必須です。仕事内容、勤務時間、給与や福利厚生など、候補者が判断に必要な情報を漏れなく具体的に記載することが挙げられます。
採用の歩留まりを改善する施策について紹介!

採用活動では、応募者が途中で離脱することで歩留まりが低下し、採用目標を達成できないこともあるでしょう。歩留まりの低下は、母集団形成の失敗や選考フローの複雑さ、内定までの時間の長さなど、さまざまな要因によって起こるのです。
ここからは、企業が取り組みやすい改善策を順番に詳しく解説していきます。
採用フローを見直す
採用フローの見直しは、歩留まり改善の最も基本的かつ効果的な施策です。複雑な選考ステップや長期間かかるフローは、候補者の負担を増やし、途中離脱の原因となります。例えば、面接が複数回に分かれている場合、候補者は日程調整の手間や時間的負担から辞退することが少なくありません。
改善策としては、選考ステップを整理し、無駄な面接を削減することが有効です。一次面接と二次面接を統合したり、書類選考の条件を事前に明確化して候補者を絞り込んだりすることで、全体の選考期間を短縮できます。そのほか、評価基準を統一し、面接官間の認識のズレをなくすことも重要です。
結果として、フローを見直すことで候補者のストレスや不安を減らし、途中離脱を防げるため、採用歩留まりの向上につながります。採用活動の効率化と同時に、候補者体験の向上にも直結する施策です。
求人情報を見直す
求人情報の精度を高めることも、歩留まり改善には欠かせません。求人票の内容が曖昧であったり、実際の業務や条件と乖離していたりすると、候補者の期待と現実に差が生まれ、途中辞退の原因になります。例として「残業少なめ」と記載されていたのに実態は多いとなれば、候補者は入社意欲を失い内定辞退や入社後の早期退職につながります。
改善策としては、仕事内容、給与、福利厚生、キャリアパスなど、候補者が判断するうえで必要な情報を具体的に記載することが基本です。企業文化や職場の雰囲気も可能な範囲で伝えることで、候補者がミスマッチを感じにくくなります。
社内で求人情報と実態が一致しているかを確認することも重要です。現場社員や面接官に正しい情報を共有し、質問に対して誠実に答えられる体制を作ることで、候補者の信頼度が上がります。
正確で透明性の高い求人情報は、応募数や質の向上につながり、採用フロー全体の歩留まり改善に直結します。
オンライン面接を導入する
オンライン面接は、歩留まり改善に大きく貢献する手段です。従来の対面面接では、移動時間や日程調整の負担が候補者の辞退理由になることが多くありました。特に地方在住者や在職中の候補者にとって、オンライン面接の導入は参加のハードルを大幅に下げる効果があるのです。
また、企業側にとっても日程調整が柔軟に行えるメリットがあります。面接官のスケジュールに合わせやすく、選考期間の短縮につながります。さらに、録画機能を活用すれば、複数の面接官が同じ面接内容を確認できるため、評価のブレを減らすことも可能です。
オンライン面接は、候補者の心理的負担を減らすだけでなく、選考スピードを高めるため、内定までの時間短縮にもつながります。現代の採用活動では、オンライン面接の導入はもはや必須とも言える施策です。
適切なターゲットにアプローチする
歩留まりを改善するためには、母集団形成だけでなく、適切なターゲットにアプローチすることが重要です。幅広く募集するだけでは、条件に合わない応募者が増え、書類選考で大量に落とす必要が生じるなど、歩留まりが低下します。
具体的な方法としては、求人媒体やスカウトサービスで自社の求める人物像にマッチする候補者を優先的にアプローチすることです。また、SNSやダイレクトリクルーティングを活用して、興味関心の高い候補者に直接メッセージを送ることで、応募意欲を高めることも可能です。
ターゲット層に合わせた求人表現や条件提示を行うことも、ミスマッチを減らすのに繋げられます。適切なターゲットへのアプローチは、応募数の増加だけでなく、書類選考や面接段階での離脱を防ぎ、最終的に入社に至る歩留まり向上に直結する施策です。
採用CXを向上させる
採用CX(Candidate Experience:候補者体験)の向上も、歩留まり改善に欠かせません。候補者が応募から入社に至るまでの過程で感じる体験の質は、辞退率に直結します。例えば、連絡が遅い、選考フローが不明確、面接官の対応が不親切といった経験は、候補者の不安や不満を生み、歩留まり低下の原因になります。
改善策としては、面接や連絡のスピードを高め、候補者にステータスを適時伝えることが重要です。また、面接官の対応教育を行い、候補者に対して丁寧で一貫性のある対応を徹底します。オンラインツールを活用して選考フローを明確化し、候補者が次のステップを把握できるようにすることも有効です。
採用CXを高めることで、候補者は安心して選考を進められ、内定承諾率や入社率の向上につながります。結果として、全体の歩留まりが改善され、採用活動の効率化と企業ブランド向上の両方を実現できます。
採用の歩留まり改善にはAIスカウト「RecUp」

採用活動における歩留まり改善は、応募者の母集団形成から選考フロー、内定後のフォローまで、あらゆるプロセスにおける課題を総合的に見直すことが重要です。しかし、すべてを手作業で行うには時間も労力もかかり、人事担当者の負担は大きくなりがちです。
そこで注目したいのが、AIを活用した採用支援ツールです。中でも「RecUp」は、候補者データをAIが分析し、自社にマッチする人材を自動でスカウトできるサービスです。
従来の手法では見逃してしまう潜在的な候補者にもアプローチでき、精度の高い母集団形成が可能になります。採用歩留まりの改善を目指すなら、従来のフロー見直しだけでなく、AIスカウト「RecUp」の導入を組み合わせることが有効です。
監修者プロフィール

-
株式会社Delight
RecUp事業部 カスタマーサクセス部門責任者
新卒から求人広告事業に従事し、企業の採用課題に向き合う中で、実践的な支援スキルを培う。その後、自社開発のAIを活用した採用支援ツール「RecUp」の営業責任者として、プロダクトを活用した採用戦略の設計・実行支援に従事。並行して自社の採用活動にも深く関与し、事業成長フェーズにおける人材要件定義、母集団形成、採用面接など、実務から戦略まで幅広い領域を担当。現在はカスタマーサクセス部門の責任者として、100社以上の採用支援実績をもとに、採用活動の最適化を支援している。実務と戦略の両視点を持つ実践型の採用コンサルタントとして、現場に寄り添いながらも成果に直結する支援に定評がある。
最新の投稿
- 2025年9月12日採用戦略採用ミスマッチの原因とは?ミスマッチを防ぐ改善策を徹底解説!
- 2025年9月12日採用戦略採用の歩留まりとは?計算方法や改善策について徹底解説!
- 2025年9月11日スカウトツールエンジニア向けスカウトメールとは?返信率を上げるポイント徹底解説!
- 2025年9月11日採用戦略採用CXとは?メリットや成功させるポイントについて徹底解説!