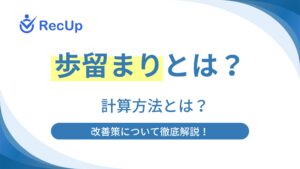採用ミスマッチの原因とは?ミスマッチを防ぐ改善策を徹底解説!
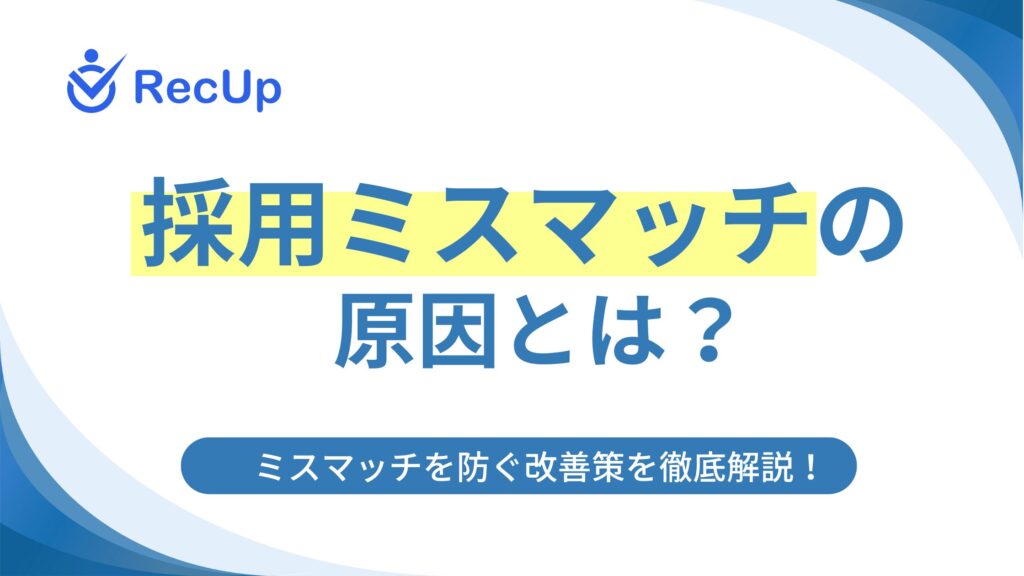
採用活動において「せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまった」「期待した成果が出なかった」という経験は、多くの企業が直面する課題です。こうした事態は「採用ミスマッチ」と呼ばれ、企業と従業員双方に大きな損失をもたらします。
本記事では、採用ミスマッチの基本的な意味から、具体的な原因、さらに防止するための改善策までを徹底解説します。正しい理解を深め、効果的な採用活動につなげていきましょう。
今すぐ無料で相談する採用ミスマッチとは?

採用ミスマッチという言葉を聞いたことがある方も少なくないのではないでしょうか。人材不足が叫ばれる中で、採用そのものに成功することが重要視されがちですが、実際には「入社後に活躍できるか」「長期的に定着できるか」が本当の意味での成功につながります。
このセクションでは、採用ミスマッチの意味や、それが企業の離職率や生産性にどのように影響するのかについて整理していきます。
採用ミスマッチの意味
採用ミスマッチとは、採用活動で入社した人材と、企業が求めていた人材像や仕事内容がうまくかみ合わない状態を指します。例えば、応募者は「挑戦的で裁量の大きい仕事ができる」と期待していたのに、実際はマニュアル通りの業務が中心だった場合、不満を感じやすくなるのです。
逆に企業側も「即戦力として成果を出してくれる」と考えて採用した人材が、経験不足やスキル不足で思うように活躍できないと感じることもあります。こうした相互のズレは、信頼関係を損ない、定着率の低下につながりかねません。
つまり採用ミスマッチは単なる「能力の不足」ではなく、企業と従業員双方の期待が食い違っている状態といえるのです。
離職率・生産性低下との関係
採用ミスマッチは、離職率の上昇や生産性の低下と密接に関係しています。入社後すぐに違和感を抱いた社員は、早期退職に至る可能性が高くなると考えられており、厚生労働省の調査でも、新卒社員の3年以内の離職率が3割を超えることが示されていますが、その背景には採用時の情報ギャップが大きく影響しているといえるでしょう。
また、すぐに辞めない場合でも、仕事内容に納得感を持てないとモチベーションが下がり、成果を出すまでに時間がかかることもあります。結果的に、企業は再び採用活動にコストを割き、現場では教育の負担が増大するのです。
つまり、採用ミスマッチは「採用コストの無駄」だけでなく「組織全体の効率低下」という二重のリスクを引き起こすものといえるでしょう。
主な離職理由は?

従業員が会社を辞める理由はさまざまですが、共通しているのは「期待と現実のズレ」が背景にあることです。人間関係、仕事内容、労働条件、給与など、退職理由には一定のパターンがあります。
これらを整理して理解することで、採用や定着施策の改善に役立ちます。ここでは代表的な離職理由を取り上げ、それぞれが採用ミスマッチとどのようにつながっているのかを解説していきましょう。
人間関係が合わなかった
職場における人間関係は、働き続けるうえで最も重要な要素の一つです。たとえ仕事内容や給与に満足していても、上司や同僚との関係がうまくいかないと、強いストレスを感じて離職を検討するケースが多く見られます。
特に、職場の雰囲気やコミュニケーションのスタイルは求人情報からは分かりにくいため、入社後にギャップを感じやすい部分です。また、組織風土が個人の価値観と合わない場合も、早期離職の原因になりやすいといえます。
こうした問題を防ぐには、面接や採用プロセスの中で「どのような雰囲気の職場か」「どんな価値観を大切にしているのか」を伝えることが重要です。企業文化を十分に理解してもらうことで、人間関係に起因するミスマッチを軽減することができます。
仕事内容に興味が持てなかった
仕事内容への関心の薄さは、離職理由として非常に多い要素です。入社前は「やりがいのある仕事に挑戦できる」と期待していたのに、実際に配属された業務が単調だったり、自分の強みを活かせる環境でなかったりすると、モチベーションが急速に低下します。
近年の若手社員の場合、自己成長や具体性のある経験につながるかどうかを重視する傾向が強いとされています。実際の仕事から期待していたスキルアップの機会が得られなければ、短期間で転職を考えることも珍しくありません。
仕事内容に関する情報は求人票では抽象的に書かれることが多く、入社して初めて実態を知るケースも少なくありません。こうした情報の不透明さは、採用ミスマッチを引き起こす大きな原因となります。
企業側は業務内容を正確に伝えるだけでなく、その仕事が持つ意義や魅力、キャリア形成との関連性を示すことも義務と言えます。よって、入社前の段階で実際の社員に仕事内容を語ってもらう、あるいは職場体験の場を設けることで、期待と現実の差を小さくできるでしょう。
労働条件が悪かった
労働条件に不満を抱くことは、離職理由の中でも特に多く挙げられる項目です。具体的には、長時間労働が常態化していたり、休日が少なかったりするケースです。ワークライフバランスを重視する働き方が一般的になっている現代において、労働条件の悪さは社員の定着に直結します。
労働環境が整っていない企業は、社員のモチベーションを下げるだけでなく、生産性そのものも低下させてしまいます。業務量が多すぎれば本来の力を発揮できず、ストレスが積み重なることで早期退職に至るリスクも高まるというわけです。
特に近年は「ブラック企業」という言葉が浸透していることもあり、労働条件に対する目が厳しくなりました。求職者は企業の評判をSNSや口コミサイトで簡単に調べられるため、実態と説明が異なると悪評が広がり、採用活動そのものに支障をきたす場合もあります。
したがって、採用活動においては労働条件を誇張せず、正直に伝えることが重要です。制度面の改善が難しい場合でも、現場の働き方改革や柔軟な勤務形態の導入を進めるなど、求職者に理解してもらえる工夫が求められます。
給与が見合わなかった
給与に対する不満も、離職理由の代表格です。仕事内容や責任に比べて報酬が低いと感じると、従業員は「努力が正当に評価されていない」と考え、働き続ける意欲を失いやすくなるのです。
給与は単なる生活費の問題にとどまりません。社員にとって「自分の存在価値」や「成果の正当な評価」を示す重要な指標でもあります。
そのため、給与が期待に届かないと「この会社ではキャリアアップが見込めないのではないか」と不安を抱き、長期的なキャリア形成を考えた結果、他社へ移る決断をする人も少なくありません。
一方で、企業が給与を大幅に引き上げるのは難しい場合もあります。その場合は、評価制度の透明化や昇給・賞与の基準を明確にすることが重要です。「成果を出せば適切に評価される」という安心感を持てるかどうかが、社員の定着につながります。
つまり給与が見合わないと感じる背景には、金額そのものだけでなく「評価の納得感」や「将来の成長可能性」に関する不安も潜んでいるといえるでしょう。採用時に提示する条件はもちろん、入社後も継続的に評価や待遇を見直す仕組みを整えることが、離職防止に直結するのです。
採用ミスマッチが起きる主な原因5選!

採用ミスマッチは偶然起きるものではなく、必ず背景にいくつかの要因があります。求人情報と実態の違い、面接時の見極め不足、過度な期待、候補者へのフォロー不足、そして組織文化との不一致など、企業が気をつけるべきポイントは多岐にわたっているのです。
これらの原因を理解することで、採用の精度を高め、入社後の定着率を改善することが可能です。ここでは代表的な5つの原因について詳しく解説します。
①求人情報との相違
採用ミスマッチの最大の原因は、求人情報と実際の業務内容が食い違っていることです。求職者は求人票や会社説明をもとに応募を決めるため、そこで伝えられる情報は大きな影響力を持ちますが、「やりがいのある仕事」「残業は少なめ」といった曖昧な表現が多用されると、入社後に「聞いていた話と違う」と感じやすくなります。
また、実際にはルーチン業務が多いにもかかわらず「裁量の大きな仕事」と表現してしまうと、挑戦的な環境を期待した人材が早期に離職する可能性が高まります。逆に過酷な勤務状況を隠したまま採用すると、不信感から短期間で辞めてしまうケースもあるでしょう。
こうした問題を防ぐには、求人票を正確かつ具体的に記載することが重要です。業務内容を細かく示すだけでなく、「繁忙期は残業が発生する」「最初の半年は研修中心」など現実的な情報も伝える必要があります。
企業にとって不利に思える内容であっても、正直に説明することで信頼関係を築くことができます。結果的に、入社後のギャップを減らし、長期的な定着につながるのです。
②面接時の見極め不足
面接は、企業と求職者の相性を見極める重要な場面です。しかし実際には、短時間の面接でスキルや人柄を正確に判断するのは容易ではありません。担当者が表面的な印象や話し方に左右されてしまうと、本来の適性を見逃してしまうリスクがあります。
また、企業側が自社の良い面ばかりを強調してしまうと、候補者は実際以上に魅力的に感じて入社を決めることがあります。その結果、働き始めてから「思っていた環境と違う」と不満を抱き、早期離職につながってしまうのです。
改善策としては、複数回の面接を実施し、人物像を多面的に評価することが挙げられます。スキルチェックや課題選考を取り入れるのも効果的です。
求職者に職場の雰囲気や課題を正直に伝え、質問に丁寧に答える姿勢を持つことも信頼構築につながります。面接は単なる「選考」ではなく「相互理解の場」と捉えることが、採用ミスマッチを減らす第一歩です。
③期待が大き過ぎた
採用時に企業が過度な期待を抱くことも、ミスマッチを生む原因の一つです。「即戦力としてすぐに成果を出してくれる」「リーダーシップを発揮してチームを牽引してくれる」といった期待を一方的に持って採用すると、入社後にその期待とのギャップが問題になります。
求職者自身も「この会社なら自分を大きく成長させてくれるはず」と期待を膨らませて入社してくるものです。しかし、現実の業務が地道な作業の積み重ねだった場合、期待との落差が大きく、やりがいを見失ってしまいます。
防止のためには、採用段階で「入社後にどのような成長プロセスを歩むのか」を具体的に示すことが大切です。短期的に成果を求めるのではなく、段階的にスキルを伸ばす仕組みを伝えることで、期待のギャップを埋めることができるでしょう。
④候補者のフォローができてない
採用活動は内定を出した時点で終わりではありません。内定承諾から入社までの期間に十分なフォローを行わないと、候補者の不安が大きくなり、辞退や早期離職につながるケースがあります。
特に新卒採用では、複数社から内定をもらう学生が多く、他社と比較する中で「この会社に本当に入社していいのか」と迷いを抱くことが珍しくありません。
フォローが不足していると、候補者は「自分は本当に歓迎されているのか」と不安に感じ、モチベーションが低下します。結果として入社しても職場に馴染みにくく、短期間で離職してしまうリスクが高まるのです。
有効な対策としては、定期的な連絡や懇親会の開催が挙げられます。内定者同士や先輩社員との交流の機会を設けることで、安心感と帰属意識を高めることができます。また、入社までに必要な準備や研修情報を伝えることも効果的です。
⑤新しく入った人が活躍しにくい組織風土
最後に挙げられるのが、組織風土との不一致です。どれほど優秀な人材でも、受け入れる組織の文化や価値観が合わなければ、能力を十分に発揮できません。
例えば、挑戦を重視する人材が安定志向の組織に入った場合、意見が通りにくくフラストレーションを感じやすくなります。逆に、協調性を大切にする人材が競争的な職場に入ると、ストレスを抱えやすくなるでしょう。
現在でこそ少なくなりつつありますが、日本企業では「年功序列」や「暗黙のルール」が根強く残っている職場もあり、こうした風土に新しい人材が適応できないと、疎外感を覚え、定着しにくくなります。
解決策としては、組織風土を採用段階で丁寧に伝えることが重要です。「うちの会社は挑戦より安定を重視する」「成果主義で競争が激しい」など、実際の文化を隠さずに共有することで、ミスマッチ帽子につながるでしょう。
採用ミスマッチを防ぐ対策とは?入社前後でできる対策をそれぞれ解説!

採用ミスマッチを防ぐためには、単に候補者を選ぶだけでなく、入社前から入社後にかけて一貫した工夫が求められます。そのため、ミスマッチ防止の対策は多岐にわたるのです。
ここでは具体的な9つの対策について、順番に解説していきます。
欲しい人材像を明確化する
採用活動の出発点は「どのような人材を採りたいのか」を明確にすることです。スキルや経験だけでなく、価値観や仕事に対する姿勢なども含めて整理しておくことで、採用の精度は大きく向上します。人材像を曖昧にしたまま採用を進めると、面接官ごとに判断基準がバラバラになり、結果的に企業と候補者の相性がずれてしまいます。
これを防ぐためには、採用担当者だけでなく現場社員やマネジメント層とも協議し、求める人物像を言語化することが必要です。そのうえで、求人票や採用ページに明確に記載し、候補者が事前に理解できるようにすることが効果的です。
また、人材像を具体的に描くことで、面接時の質問や評価の観点も整理されます。「この人が自社で活躍できるのか」という視点を持てるため、感覚に頼らずに判断できるのです。結果的に、候補者との相互理解が深まり、入社後のギャップを減らすことにつながります。
ダイレクトリクルーティングをする
従来の求人広告や人材紹介だけに頼るのではなく、企業が主体的に候補者にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」も有効な手段です。企業が欲しい人材像を明確にしたうえで、自社にマッチしそうな人材に直接声をかけることで、精度の高い採用が可能になります。
この手法のメリットは、候補者に対して自社の魅力を早い段階で伝えられる点です。候補者も「自分が必要とされている」と感じやすく、入社へのモチベーションが高まりやすくなります。また、採用担当者が候補者の経歴やスキルを事前に把握してアプローチするため、ミスマッチが起きにくいのも特徴です。
一方で、候補者とのやり取りには時間と労力がかかるため、専用のツールやデータベースを活用するのが一般的です。LinkedInなどのビジネスSNSや、スカウト型の転職サービスを利用することで効率的にアプローチできます。
ダイレクトリクルーティングを導入する際には、単なる「声掛け」で終わらせず、候補者の関心に合わせて情報を届けることが大切です。例えば「このスキルを活かせる部署があります」「あなたの経験が役立つ具体的な業務があります」と伝えることで、リアルなイメージを持ってもらえます。
確認する
適性検査を行う
採用ミスマッチを防ぐには、面接だけでなく適性検査を取り入れることも効果的です。適性検査では、候補者の性格特性や行動傾向、ストレス耐性などを数値化して把握できるため、面接では見抜きにくい部分を確認できます。
例えば、営業職に向いているのはコミュニケーション能力や挑戦意欲が高い人材ですが、数字でその傾向を示すことで客観的に判断できます。また、管理職候補にはリーダーシップや調整力が求められるため、検査の結果から適性を測ることが可能です。
ただし、適性検査は万能ではなく「合否を決める基準」として使うのではなく「判断材料の一つ」として活用することが大切です。検査結果だけに頼ると、本来の強みを持ちながらもうまく評価されないケースが出てしまいます。
最も効果的なのは、面接での印象と適性検査の結果を照らし合わせ、総合的に判断する方法です。客観的データと主観的な評価を組み合わせることで、採用の精度を格段に高めることができます。
カジュアル面談を行う
採用プロセスにおいて、形式ばった面接だけでなく「カジュアル面談」を導入することは、ミスマッチを防ぐ上で非常に有効です。カジュアル面談とは、合否を判断するための場ではなく、企業と候補者がフラットに情報交換を行うための機会です。
通常の面接では候補者が「評価される立場」であるため、どうしても本音を隠しがちです。しかしカジュアル面談であれば、「この仕事にどんな期待を持っているか」「どのような働き方を理想としているか」など、率直な意見を聞き出しやすくなります。
また、カジュアル面談は企業にとってもブランディングの機会です。候補者は「選考プロセスの丁寧さ」や「社員の人柄」から企業の魅力を感じ取るため、応募意欲を高める効果があります。
ただし、合否に直結しない場であることを明確に伝え、候補者が安心して話せる雰囲気をつくることが重要です。カジュアル面談を通じて候補者がリアルな情報を得られれば、入社後の後悔を減らすことができ、採用ミスマッチの防止に直結します。
リファラル採用を導入する
リファラル採用とは、社員の紹介を通じて人材を採用する方法です。従来の求人媒体や人材紹介と比べて、ミスマッチを防ぎやすいという大きな特徴があります。なぜなら、社員が「この人なら自社に合う」と考えて紹介するため、スキル面だけでなく性格や価値観も含めてマッチする可能性が高いからです。
また、候補者にとっても、信頼する知人からの紹介であれば入社前にリアルな情報を得やすくなります。仕事内容や職場の雰囲気、働き方の実態など、公式な求人票では分からない部分を事前に知ることで、入社後のギャップが小さくなります。
リファラル採用の成功には、社員にとって紹介しやすい仕組みを整えることが大切です。例えば、インセンティブを設ける、専用の応募フローを用意するなど、社員が積極的に動ける環境を作ると効果が高まります。また、紹介された候補者に対して特別扱いをせず、通常の選考フローでしっかり見極めることも忘れてはいけません。
この仕組みを活用すれば、採用コストの削減と定着率の向上を同時に実現できます。リファラル採用は「信頼の連鎖」に基づく方法であり、ミスマッチを防ぐ効果が特に大きい手法といえるでしょう。
インターンを実施する
インターンシップの実施は、候補者と企業の相互理解を深めるうえで非常に有効です。候補者は実際に業務を体験することで、仕事内容や職場の雰囲気をリアルに知ることができます。一方、企業側も候補者の仕事への姿勢や適性を確認できるため、選考時の判断材料を増やすことが可能です。
特に長期インターンでは、候補者が実際のプロジェクトに参加し、社員と協働する機会が得られるため、表面的な適性だけでなく継続力や協調性も見極められます。短期のインターンでも、会社説明会では伝えきれない現場の雰囲気を体験できる点で有効です。
また、候補者が「実際に働いてみて自分に合うかどうか」を判断できるのも大きなメリットです。入社後に「思っていた仕事と違った」と後悔するリスクを減らせるため、早期離職を防ぐ効果があります。
企業にとっても、インターン経験者を採用することで入社後の立ち上がりが早くなり、教育コストを削減できるという利点があります。つまり、インターンは採用活動の一環としてだけでなく、ミスマッチを防ぐ「事前の適性確認」としても大いに活用できるのです
実際の社員との交流の場を増やす
候補者が入社前に実際の社員と交流できる場を設けることも、採用ミスマッチを防ぐ有効な方法です。説明会や面接だけでは、候補者が得られる情報は限られていますが、実際に働いている社員と話すことで、仕事の実態や職場の雰囲気をリアルに感じ取ることができます。
例えば、座談会形式のイベントや社内見学会、懇親会を開催することで、候補者は「ここで自分が働く姿」を具体的にイメージしやすくなりますし、社員のリアルな声を聞くことで、会社の強みや課題、日々の働き方まで理解が深まるのです。
また、候補者にとっては「自分がこの環境に馴染めるか」を判断できる大切な機会です。逆に企業側にとっても、候補者の人柄やコミュニケーション力を自然な形で知ることができます。こうした交流の場を増やすことで、採用後の相互理解が進み、定着率の向上につながるのです。
候補者のフォローアップをする
内定から入社までの間にフォローアップを行うことは、候補者の不安を軽減し、早期離職を防ぐために欠かせません。特に新卒採用では、複数の内定を持つ学生が「この会社で本当にいいのか」と悩むケースが多くあります。
フォローアップの方法としては、定期的な面談やメールでの連絡、内定者研修や懇親会の開催が効果的です。社員や同期と交流できる機会を提供することで、入社前から仲間意識を育むことができます。また、入社後の業務内容やキャリアパスを具体的に説明することで、候補者は安心感を持ちやすくなります。
このように、候補者へのフォローアップは「入社意欲の強化」と「入社後の定着」の両方に直結する施策です。採用活動を単なる「内定出し」で終わらせず、入社後を見据えたサポートを行うことで、採用ミスマッチを防ぐことが可能になります。
本人との明確な目標設定を行う
入社後に候補者が安心して活躍できるようにするには、本人と一緒に明確な目標を設定することが重要です。目標が曖昧なままでは、社員は「自分の仕事が評価されているのか」「どこを目指せばいいのか」が分からず、不安や不満を抱きやすくなります。その結果、早期に離職するリスクが高まります。
具体的には、入社後3か月、半年、1年といった短期・中期の目標を段階的に設定し、定期的に振り返りを行うことが有効です。上司やメンターが伴走する形でサポートすれば、社員は自分の成長を実感でき、モチベーションを維持しやすくなります。
また、目標は企業が一方的に決めるのではなく、本人のキャリア希望や適性を踏まえて設定することが大切です。こうすることで「自分の意見が尊重されている」と感じ、組織への信頼感やエンゲージメントが高まります。
最終的に、明確な目標設定は社員の成長を促すと同時に、企業と本人の期待のズレを防ぐ仕組みとなります。採用後の定着率を高めるには欠かせない施策といえるでしょう。
採用ミスマッチを防ぐならAIスカウト「RecUp」

せっかく採用した人材がすぐに離職してしまう「採用ミスマッチ」。さまざまな改善策がありますが、限られた人事リソースの中で全てを徹底するのは難しく、効率的に候補者とのマッチングを進められる仕組みが必要です。
そこで役立つのが、AIスカウトサービス「RecUp」です。AIが求職者のスキルや志向性を解析し、自社に合う人材を効率的に見つけ出せます。また、候補者のプロフィールに合わせて、カスタマイズしたスカウト文面の作成をAIが行ってくれるので、効率的な母集団形成にはもってこいのサービスになっています。
採用活動を効率化しつつ、ミスマッチを防ぎたい企業にとって、RecUpは大きな助けとなるでしょう。
監修者プロフィール

-
株式会社Delight
RecUp事業部 カスタマーサクセス部門責任者
新卒から求人広告事業に従事し、企業の採用課題に向き合う中で、実践的な支援スキルを培う。その後、自社開発のAIを活用した採用支援ツール「RecUp」の営業責任者として、プロダクトを活用した採用戦略の設計・実行支援に従事。並行して自社の採用活動にも深く関与し、事業成長フェーズにおける人材要件定義、母集団形成、採用面接など、実務から戦略まで幅広い領域を担当。現在はカスタマーサクセス部門の責任者として、100社以上の採用支援実績をもとに、採用活動の最適化を支援している。実務と戦略の両視点を持つ実践型の採用コンサルタントとして、現場に寄り添いながらも成果に直結する支援に定評がある。
最新の投稿
- 2025年9月12日採用戦略採用ミスマッチの原因とは?ミスマッチを防ぐ改善策を徹底解説!
- 2025年9月12日採用戦略採用の歩留まりとは?計算方法や改善策について徹底解説!
- 2025年9月11日スカウトツールエンジニア向けスカウトメールとは?返信率を上げるポイント徹底解説!
- 2025年9月11日採用戦略採用CXとは?メリットや成功させるポイントについて徹底解説!