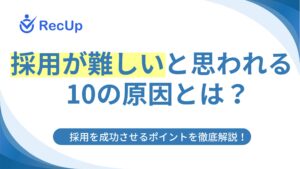カジュアル面談とは?採用率を上げるポイントを徹底解説!
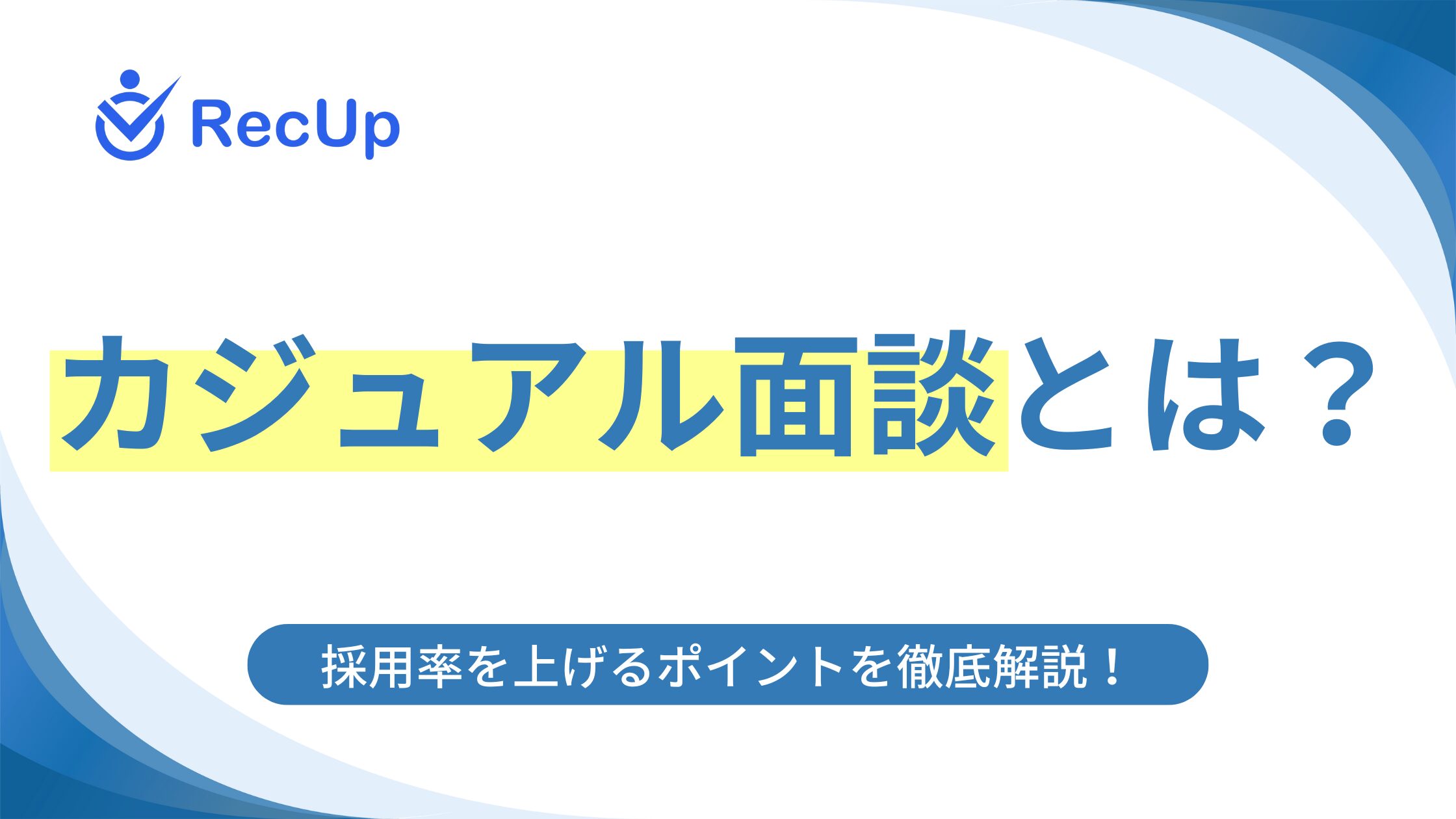
カジュアル面談は、求職者と企業が本格的な選考前に行う非公式な面談です。形式ばった面接ではなく、企業文化や仕事内容、働き方についてざっくばらんに話す場として活用されます。
採用活動においては、候補者の理解を深めるだけでなく、企業の魅力を伝えたり、応募者の本音を引き出したりする重要な役割もあるのです。本記事では、カジュアル面談の基本からメリット・デメリット、採用率を高める具体的なポイントまで詳しく解説します。
今すぐ無料で相談するカジュアル面談とは?

カジュアル面談という言葉を聞いたことはあっても、実際にどんな場面で行われるのか、どんな目的があるのかはイメージしにくいかもしれません。
形式ばった面接ではなく、ざっくばらんに働き方や社風を知る機会として設けられることが多く、求職者にとっても企業にとってもお互いを知るための第一歩といえます。そこでまずは、カジュアル面談の目的を解説します。
目的
簡単に解説すると、カジュアル面談は企業と求職者が選考前に気軽に話す場です。緊張せずに話せることから、応募者の本音を引き出すきっかけにもなる面談だといえるでしょう。
カジュアル面談の主な目的は、企業と求職者がお互いを理解することにあります。具体的には、企業側は求職者のスキルや経験だけでなく、価値観や働き方のスタイル、キャリア志向を把握可能です。
一方、求職者は社風やチームの雰囲気、実際の業務内容を知ることができ、自分に合った会社かどうかを判断する材料を得られます。さらに、カジュアル面談は採用活動の入口としても機能し、候補者に会社の魅力を伝えたり、興味を持ってもらうことで、本選考への応募につなげる役割もあります。
従来の面接よりも緊張感が少なく、自由なコミュニケーションを通じて双方にとって有益な情報交換の場を作れることが最大の特徴です。
カジュアル面談の採用率はどれくらいなのか?

カジュアル面談を導入する企業は増えていますが、実際にどれくらいの人が本選考に進むのか、最終的に採用に至るのかは気になるポイントです。 面談自体は堅苦しい面接ではなく、あくまで相互理解のための場であるため、全員がそのまま採用に結びつくわけではありません。
ここでは、面談から本選考への進行率や最終採用率の目安を紹介しつつ、数字から見えるカジュアル面談の役割や活用法を整理します。
本選考に進む割合は30%~40%ほど
カジュアル面談を経て本選考に進む候補者は、おおよそ30%から40%程度といわれています。
これは、面談を通して企業の雰囲気や仕事内容を理解したうえで、「もっと深く知りたい」と思った人が選考に進むためです。逆に、面談の段階で仕事内容や社風が自分に合わないと感じた候補者は、自然と選考を辞退するケースもあります。
企業側から見ると、この段階で候補者の適性や価値観をある程度把握できるため、選考の効率化にもつながっているのです。また、全体の3〜4割が本選考に進むという数字は、面談の目的が「採用するための予備選考」ではなく、「企業理解を深めるための場」であることを示しています。
候補者がリラックスして話せることで、本来のスキルや性格も見えやすくなり、後の選考でのミスマッチも低下。面談に進む候補者の割合は必ずしも低い数字ではなく、むしろ質の高い採用につながる指標として捉えることができます。
採用に至るのは10%ほど
では、カジュアル面談から最終的に採用に至る候補者の割合はどのくらいでしょうか。 一般的名採用率としては、約10%程度とされています。
これは、面談の性質上、多くの人がまず「相性の確認」や「企業理解」のために参加するためです。全員が採用されるわけではなく、あくまで企業と候補者双方が納得した場合のみ次のステップに進むため、数字は少なくなります。
しかし、この10%は非常に重要な層です。面談でお互いの理解が深まった候補者は、企業に対する理解度も高く、入社後の定着率やパフォーマンスにも期待できます。
また、採用率が低いからといって面談の効果が薄いわけではありません。面談を通じて得られる候補者の情報や関係構築は、将来的な採用活動や人材プール作りに役立ちます。
つまり、数字だけにとらわれず、カジュアル面談を「採用効率と質を高める戦略的な手段」として活用することが重要です。
カジュアル面談のメリットを解説

カジュアル面談には、企業と候補者双方にとって多くのメリットがあります。 単に面接の前段階として存在するだけでなく、採用活動全体の効率化や、応募者の質を高める役割も果たすのです。
では、具体的にどんなメリットがあるかについて、ここから詳しく解説していきます。
応募辞退率を低下させる
カジュアル面談を導入する大きなメリットのひとつは、応募辞退率を下げられることです。面談の場では、候補者が企業の雰囲気や仕事内容をじっくり知ることができます。
その結果、「入社後のイメージと違った」という理由で辞退するリスクを大幅に減らせます。特に、初めての転職や若手人材の場合、企業情報だけでは不安が残ることも多いため、事前に面談で理解を深めてもらうことは非常に効果的です。
さらに、カジュアル面談は候補者との関係を構築する場としても活用できます。面接のような緊張感のある場では聞き出せない本音や不安も、リラックスした環境であれば自然に話してもらいやすくなります。
このように、面談を通じて候補者の疑問や不安を解消することで、応募者の満足度を高め、最終的な辞退率を低下させることが可能です。
企業の魅力を伝えられる
カジュアル面談は、求人票やウェブサイトだけでは伝えきれない企業の魅力を直接伝える絶好の機会です。面談中に、社内の雰囲気や働き方、制度やキャリアパスの具体例を紹介することで、候補者に企業のリアルな姿を知ってもらえます。
こうした情報提供は、単なるスキルマッチだけではなく、価値観や社風への共感を得るきっかけにもなりますし、候補者が質問しやすい環境を作ることも大切です。
質問に対して丁寧に答えることで、企業の透明性や信頼性をアピールでき、面接段階での安心感や好印象につながります。結果として、面談を通じて企業の魅力を体感してもらうことが、入社意欲の向上や選考進捗の促進に直結するのです。
優秀な人材との接点になる
カジュアル面談の大きな魅力のひとつは、まだ選考に進むかどうか迷っている段階の候補者とも気軽に接点を持てることです。
面談を通じて関係を築くことで、将来的に優秀な人材が本選考に進む可能性を高められます。面談時に企業の雰囲気や働き方を理解してもらい、候補者が「ここで働きたい」と思える環境を提供することができます。
さらに、面談で得られる情報は、単なる採用判断だけでなく、長期的な人材戦略にも活用可能です。「今はまだ応募の意思が固まっていないが、将来的にフィットする人材」をプールしておくことで、採用の幅を広げられます。
特に競争の激しい業界や、スキルが希少なポジションでは、早期に接点を持つことが重要です。面談を通じて候補者のキャリア志向や価値観を把握できれば、適切なタイミングで選考やオファーを提示することもできます。
このように、カジュアル面談は「今すぐ採用するためだけの場」ではなく、将来的に優秀な人材との関係を育む場として活用することができるのです。企業側も候補者側もプレッシャーが少ないため、自然なコミュニケーションを通じて、より本質的な理解を深められる点が大きなメリットとなります。
候補者の本音を引き出せる
カジュアル面談では、候補者がリラックスして話せる環境が整っているため、面接では聞き出しにくい本音を知ることができます。志望動機やキャリアの希望だけでなく、働き方に関する不安や疑問も自然に引き出せるのです。
こうした情報は、企業が選考を行ううえで非常に重要です。候補者の価値観や考え方を把握することで、組織との適性を判断しやすくなります。また、面談の段階で信頼関係を築くことで、応募者が安心して選考に臨める環境を作ることができます。
さらに、候補者の本音をもとに入社後のサポートやキャリア設計を考えることも可能です。単にスキルや経歴だけで判断するのではなく、内面的な部分を理解することでミスマッチを減らせます。
結果として、カジュアル面談は採用の精度を高め、入社後の定着率向上にもつながる重要な機会となるのです。
カジュアル面談のデメリットとは?

カジュアル面談は多くのメリットがありますが、導入する際には注意すべき点もあり、 特に時間やコスト、選考への直結性の低さなど、運用上の課題が存在します。面談自体は選考の前段階として位置づけられるため、効果的に活用しないと企業側の負担だけが増えかねません。
ここでは、カジュアル面談の注意点やデメリットについて整理し、運用時に気をつけるべきポイントを解説します。
選考に直結しない
カジュアル面談は選考の一部ではありますが、正式な面接ではないため、必ずしも採用に直結するわけではありません。候補者が面談を経ても本選考に進まない場合や、採用に至らないケースも少なくありません。
このため、面談を「採用率を上げる直接的手段」としてだけ捉えると、期待外れに感じることがあります。企業側としては、面談の目的を「相互理解」や「関係構築」に置き、数字だけで成果を測らないことが重要です。
また、選考に直結しないことにより、面談の実施頻度や時間配分も慎重に計画する必要があります。準備や対応に時間をかけすぎると、他の採用業務や現場の負担につながる可能性があります。
面談そのものは、長期的な採用戦略や候補者プール作りの一環として捉えることが効果的です。短期的な採用目標だけで判断せず、面談から得られる情報や関係性を次のステップにどう活かすかを考えることが、成功の鍵となります。
コストがかかる
カジュアル面談を導入する際のデメリットのひとつは、時間やコストの負担が発生することです。面談自体は短時間でも、準備や候補者とのスケジュール調整、面談後のフォローなどを含めると、企業側の工数は意外と大きくなります。
特に、候補者が多い場合や遠方からの参加が必要な場合は、交通費や会場費などの経費もかかります。さらに、人事担当者や現場社員が面談に時間を割くことで、通常業務に支障が出ることも少なくありません。
そのため、コストを抑えつつ効率的に運用するためには、面談対象者の絞り込みやオンライン面談の活用が有効です。また、面談の目的やゴールを明確に設定することで、無駄な時間を減らすこともできます。
カジュアル面談は単なる情報交換の場ではなく、将来的な採用戦略の一環として位置付けることが重要です。コストがかかる点を理解したうえで、戦略的に活用することが成功のポイントとなります。
入社意欲が読み取りにくい
カジュアル面談では、候補者がリラックスして参加するため、本音で話す一方で、入社意欲の強さを正確に判断しにくいというデメリットがあります。面談の場では、スキルや経験よりも価値観や働き方への共感が中心になることが多く、採用意欲の強さは見えにくいこともあるでしょう。
そのため、面談だけで「この人はすぐに入社するだろう」と判断するのは難しく、企業側は選考の進め方を慎重に設計する必要があります。面談後にフォローアップを行うことで、候補者の関心度や入社意欲を確認する工夫も重要です。
また、面談中に見せる態度や質問内容だけで判断せず、全体のやり取りや候補者の背景を総合的に見極めることが求められます。入社意欲を正確に把握するには、面談と選考を分けて戦略的に活用することが、カジュアル面談を成功させるポイントとなります。
自社でのカジュアル面談導入はどう進める?

カジュアル面談を自社で導入する際は、ただ形だけ整えるのではなく、戦略的に計画することが重要です。どの候補者を対象にするか、面談で何を聞き出すか、そしてその後どのように選考に誘導するかを明確にしておくことで、面談の効果を最大化できます。
そこで、カジュアル面談の導入をどう進めていくべきかについて、段階的な形で解説していきます
ターゲット設定を行う
カジュアル面談を実施する際は、まずどの候補者を対象にするかを明確に設定する必要があります。全ての応募者に対して行うのではなく、特に将来的に必要とされるスキルや経験を持つ人材、企業文化にフィットする可能性の高い人材を優先的に対象とします。
ターゲット設定により、面談の効果も最大化可能です。例えば、面談対象者を絞ることで人事や現場の工数を節約でき、より丁寧な対応が可能になるだけでなく、候補者にとっても「自分を特別に見てもらっている」という印象を与えられ、好感度や信頼感が高まるのです。
さらに、ターゲットを明確にすることで、面談の目的や質問内容も最適化できます。候補者の価値観や志向に合わせたヒアリングができるため、有益な情報を引き出しやすくなります。戦略的にターゲットを設定することが、カジュアル面談導入の成功に直結するのです。
ヒアリング項目を決めておき、面談を行う
面談を効果的にするためには、事前にヒアリング項目を決めておくことが重要です。例えば、候補者のキャリア志向、価値観、スキルセット、働き方の希望など、企業が知りたい情報を整理しておきます。
面談中は、あらかじめ決めた項目に沿って会話を進めつつ、柔軟に雑談も交えることで候補者がリラックスしやすくなります。形式ばった質問だけでなく、自然な会話から本音を引き出すことが面談のポイントです。また、聞き逃した情報があれば、面談後のフォローで補完できる体制を作ることも大切です。
事前準備が整っていると、面談は単なる情報交換の場ではなく、候補者との関係構築や選考への誘導のステップとして活用できます。ヒアリング項目を整理することが、面談を戦略的に機能させる鍵となります。
選考へ誘導する
カジュアル面談の最終的な目的のひとつは、候補者を本選考にスムーズに誘導することです。ただの情報交換で終わらせず、面談を次のステップにつなげる工夫が重要です。
面談中は、候補者が企業の魅力や仕事内容を理解できるように意図的に情報を整理して伝えます。例えば、社風やチームの働き方、キャリアパスの具体例など、候補者が「ここで働きたい」と思えるポイントをわかりやすく提示することが大切です。
面談後のフォローも重要です。感謝の連絡や面談内容の振り返り、選考案内を適切なタイミングで送ることで、候補者の関心を維持できます。加えて、面談で話した内容を活かして候補者の疑問や不安を解消することで、選考への心理的ハードルも下がります。
さらに、現場社員やマネージャーとの接点を作ることも有効です。面談で話した内容を基に現場の声を伝えることで、候補者は企業をより具体的にイメージしやすくなり、選考参加の意思も高まるでしょう。
採用率を高めるカジュアル面談のポイントを解説!

カジュアル面談はただ行うだけでは効果を最大化できません。採用率を上げるためには、事前準備や候補者との関係構築、面談後のフォローなど、全体のフローを戦略的に設計することが重要です。
面談の目的を明確にし、ターゲットを絞り込み、候補者に合わせたアプローチを行うことで、面談を採用成功につなげることができます。ここでは、具体的にどのようなポイントに注意すべきかを解説します。
ターゲットを明確にしておくカ
カジュアル面談の成功には、まずターゲットとなる候補者を明確にすることが欠かせません。誰に面談を行うのかを定めることで、面談準備や質問内容を最適化でき、効果的な面談が可能になります。
ターゲットを設定する際は、必要なスキルや経験だけでなく、企業文化や価値観にフィットするかどうかも考慮すると、面談を通じて得られる情報が採用判断に活かしやすくなるでしょう。
さらに、ターゲットを明確にしておくことで、リソースの無駄を省きつつ、より丁寧な対応が可能です。候補者は自分が注目されていると感じやすく、企業への印象も良くなります。結果として、ターゲットを絞るだけで、面談の質と採用率を同時に高めることができます。
ターゲットにスカウトを送る
カジュアル面談を活用するには、ターゲットに向けて適切にスカウトを送ることも重要です。候補者が自社に興味を持てる内容や、面談で得られるメリットを伝えることで、参加意欲を高められます。
スカウトメールやメッセージは、形式的にならず、候補者の状況やキャリア志向に合わせたパーソナライズが効果的です。例えば、具体的な業務内容や成長機会、社員の働き方の例などを盛り込むことで、候補者に「話を聞いてみたい」と思わせることができます。
ターゲットに対して適切なタイミングでスカウトを送ることで、面談参加率の向上だけでなく、候補者との信頼関係の構築も期待できます。戦略的にスカウトを活用することが、採用率アップのポイントとなるでしょう。
面談後のフォロワーアップを行う
面談後のフォローも採用率を高める上で欠かせません。面談で話した内容を整理してメールや連絡で伝えることで、候補者は自分の意見や質問がきちんと理解されていると感じやすくなるものです。
さらに、面談で得られた情報をもとに、次のステップである本選考への案内やキャリア相談を行うことで、候補者の関心を維持できます。フォローのタイミングや内容を工夫することで、面談後の自然な選考誘導が可能になります。
面談後のフォローは、単なる礼儀としてだけでなく、入社意欲や選考参加率の向上につながる重要なプロセスです。ここを疎かにせず、戦略的に実施することが採用成功の鍵となります。
社員との接点を作る
カジュアル面談では、人事担当者だけでなく現場社員との接点を作ることも重要です。候補者に実際の業務やチームの雰囲気を伝えることで、企業理解が深まり、入社意欲も高まります。
社員との接点は、候補者に企業文化を体感させる絶好の機会です。具体的な業務やキャリアの話を現場社員から聞くことで、面接では得られない情報を提供できます。また、リアルな声を聞くことで候補者はより具体的に自身の働くイメージを描けるのです。
こうした接点は、信頼関係の構築や面談後の選考参加率向上にも直結します。面談における社員との関わりは、採用率を高める戦略的な施策として非常に有効です。
ターゲットに合わせたスカウトなら「RecUp」

採用活動では、候補者に合ったスカウトを送ることが重要です。しかし、ターゲットに合わせた最適なアプローチを行うのは簡単ではありません。そんなときに活用できるのが「RecUp(リクアップ)」です。
RecUpは、企業がターゲットに合わせて効率的にスカウトを送れる採用支援サービスです。候補者のプロフィールや志向に応じてメッセージをパーソナライズできるため、面談参加率や選考参加率の向上が期待できるのです。
企業はRecUpを活用することで、ただ大量にスカウトを送るのではなく、戦略的にターゲット人材にアプローチできるようになります。採用の効率化と質の向上を同時に実現できるツールとしてぜひ検討してみてください。
今すぐ無料で相談する監修者プロフィール

-
株式会社Delight
RecUp事業部 カスタマーサクセス部門責任者
新卒から求人広告事業に従事し、企業の採用課題に向き合う中で、実践的な支援スキルを培う。その後、自社開発のAIを活用した採用支援ツール「RecUp」の営業責任者として、プロダクトを活用した採用戦略の設計・実行支援に従事。並行して自社の採用活動にも深く関与し、事業成長フェーズにおける人材要件定義、母集団形成、採用面接など、実務から戦略まで幅広い領域を担当。現在はカスタマーサクセス部門の責任者として、100社以上の採用支援実績をもとに、採用活動の最適化を支援している。実務と戦略の両視点を持つ実践型の採用コンサルタントとして、現場に寄り添いながらも成果に直結する支援に定評がある。
最新の投稿
- 2025年9月12日採用戦略採用ミスマッチの原因とは?ミスマッチを防ぐ改善策を徹底解説!
- 2025年9月12日採用戦略採用の歩留まりとは?計算方法や改善策について徹底解説!
- 2025年9月11日スカウトツールエンジニア向けスカウトメールとは?返信率を上げるポイント徹底解説!
- 2025年9月11日採用戦略採用CXとは?メリットや成功させるポイントについて徹底解説!