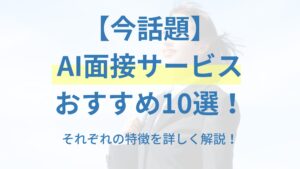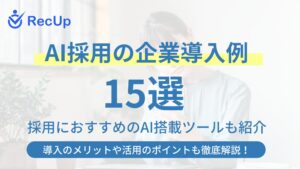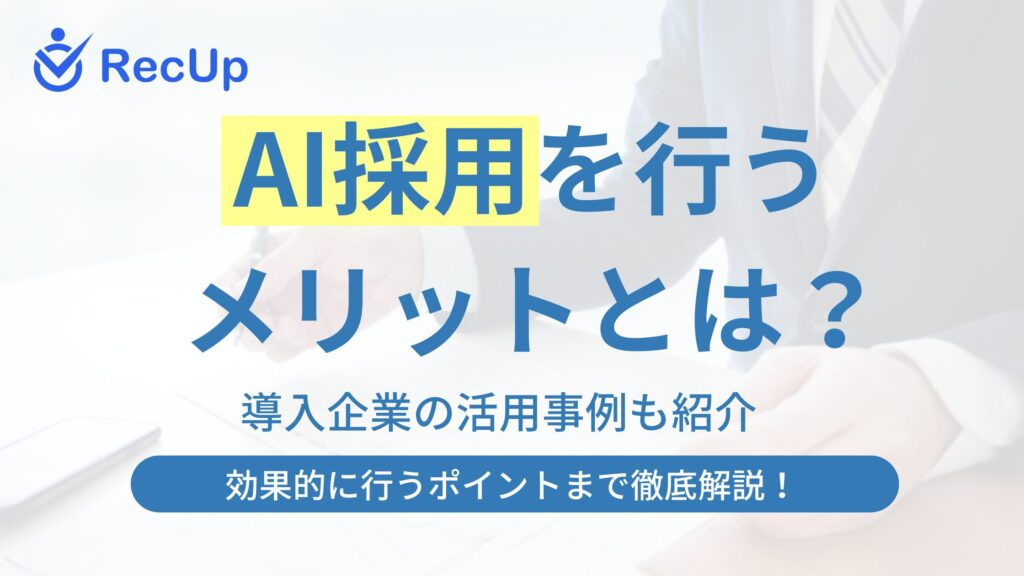
求人スカウトや書類選考、面接などにAIを活用する「AI採用」は、デジタル技術の進化や働き方の多様化により、導入する企業が年々増加傾向です。
効率化や公平性の向上といったメリットがある一方で、バイアスの再現や人間的な魅力の見落としといったデメリットも存在します。
本記事では、実際の採用現場でのAIの活用事例をもとに、その利点と課題について詳しく解説します。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
AI採用とは?

AI採用とは、採用活動の各プロセスにAI技術を活用することで、業務の効率化や選考の質向上を図る手法です。
書類選考や適性検査の分析、面接スケジュールの調整、チャットボットによる一次対応など、これまで人手で行っていた業務をAIが自動化・サポートします。
ただし、すべての判断をAIに委ねるのではなく、人の直感や経験と組み合わせることで、より精度の高い採用が可能となります。
また、AI採用はエンジニアや専門職に限らず、アルバイトやパートなど幅広い職種・雇用形態で活用が進んでおり、企業規模を問わず導入が広がりつつあるでしょう。
AI採用における現状

2023年度の調査によると、採用活動においてAIツールを「活用した」と回答した企業は全体の43.0%に達しており、一定の普及が進んでいることがわかります。
中でも活用が多かったのは「求人票の制作」(60.5%)で、「スカウト」「WEB面接」(各31.4%)、「選考の評価」「適性検査」(各27.9%)など、採用フローのさまざまな場面でAIが利用されています。
一方で、マイナビの転職動向調査では、2023年に転職した人のうちAI面接を「受けたことがある」と答えた割合は17.7%で、過去2年よりやや減少傾向です。こうしたデータから、AI採用はまだ一部企業にとどまるものの、現実的な活用が進んでおり、今後さらに広がっていく可能性があることが示されています。
AI採用のメリットが特に大きい採用業務・シーンを解説!

企業の採用活動において、AIを活用した採用手法が注目を集めています。採用フロー全体を見渡すと、定型的な作業や反復作業が多く、人手による対応には限界があることも少なくありません。
ここからは、特にAI採用の効果が大きい具体的な業務とシーンについて解説していきます。
求人票作成・スカウト文作成
求人票やスカウト文の作成は、採用活動における最初の接点として重要な役割を果たす業務です。従来は採用担当者が一件ずつ文章を考え、候補者に合わせた内容を作成していましたが、AIを活用することで過去の応募・採用データをもとに反応率の高い文面を短時間で作成できるようになりました。
AIは過去のスカウト文の開封率や返信率といったデータを学習し、効果的な訴求ポイントや文章構成を自動で抽出します。これにより、定型業務を自動化しつつも、各候補者の経歴や志向性に合わせたパーソナライズが可能になり、採用担当者は訴求軸の設計や企業の魅力整理といった戦略的な業務に時間を割けるようになります。
文章の精度が安定することで、担当者による品質のばらつきを抑えられる点も特長です。繁忙期でも送信品質を維持できるため、母集団形成の量と質を両立しやすくなります。候補者との最初の接点であるスカウト文の質が向上することで、その後の選考プロセスへのスムーズな移行が期待できます。
母集団形成・候補者探索(AIソーシング)
母集団形成において、自社の求める要件に合致する候補者を効率的に探し出すことは、採用成功の鍵を握る重要なプロセスです。従来の方法では、人事担当者が求人サイトやデータベースを手作業で検索し、一人ずつプロフィールを確認する必要があり、膨大な時間と労力を要していました。
AIソーシングを活用すれば、膨大な候補者データから自社要件に合致する人材をAIが効率的に抽出できるため、探索工数を大幅に削減できます。AIは職歴、スキル、経験年数、資格といった基本情報だけでなく、過去の採用成功者のパターンを学習することで、より精度の高いマッチングを実現します。
特に注目すべき点は、人の目では見落とされがちな潜在候補者にもアプローチできることです。例えば、完全に条件を満たしていなくても、過去の成功事例から成長ポテンシャルが高いと判断される候補者を発見できます。これにより、母集団の質と量の両立が可能となり、採用の選択肢を広げることができるのです。
書類選考・エントリーシートのスクリーニング
書類選考やエントリーシートのスクリーニングは、採用活動の初期段階で最も工数がかかる業務の一つです。応募者が多い企業では、数百から数千件の応募書類を確認する必要があり、採用担当者の負担が極めて大きくなります。
AIを活用することで、大量の応募書類を自動で解析・スコアリングできるため、選考初期の負担を大幅に軽減できます。AIは過去の選考データをもとに、採用に至った候補者の特徴やパターンを学習し、新たな応募者を評価します。これにより、人手で行う場合と比べて処理速度が格段に向上し、スピーディーな選考が可能になります。
評価基準を統一しやすく、担当者ごとの判断ブレを抑えられる点も大きなメリットです。人による選考では、担当者の経験や価値観によって評価にばらつきが生じることがありますが、AIは設定された基準に基づいて客観的に評価を行うため、公平性の向上にもつながります。
適性検査・性格診断の分析
適性検査や性格診断は、候補者のスキルや経験だけでは測れない、潜在的な適性や組織との相性を把握するために重要な評価手段です。従来は、結果を人が読み解き、主観的な判断を交えながら評価することが一般的でしたが、評価者の経験や解釈によって判断が分かれる場合もありました。
AIを導入することで、適性検査や性格データを多角的に分析し、職務要件や組織との相性を客観的に把握できるようになります。AIは膨大なデータから傾向やパターンを抽出し、候補者が特定の職種や業務にどの程度適しているかを数値化して可視化します。これにより、経験や印象に頼らない判断が可能になるのです。
特に、配属や定着を見据えた採用判断に活用しやすい点が特長です。例えば、営業職に求められるコミュニケーション能力やストレス耐性、エンジニア職に必要な論理的思考力や集中力など、職種ごとに異なる適性を客観的に評価できます。
一次面接・AI面接の実施
一次面接は、多くの候補者をスクリーニングし、次の選考ステップへ進めるべき人材を見極める重要なフェーズです。しかし、対面やオンラインでの面接は日程調整や面接官の確保が必要となり、特に応募者数が多い場合は大きな負担となります。
AI面接を活用することで、24時間対応や遠隔面接が可能となり、時間や場所の制約を受けることなく選考を進められます。候補者は自分の都合に合わせて面接を受けられるため、選考機会の損失を防げる点も大きなメリットです。地方在住の候補者や忙しい社会人にとっても、アクセスしやすい選考方法となります。
また、AI面接では音声や表情、回答内容をAIが分析し、コミュニケーション能力や論理性、積極性といった要素を評価します。よって、一次選考を効率化しつつ、人は最終判断や深掘り面接に集中できる体制を構築できます。採用担当者や面接官は、AIが高評価した候補者に対して集中的に時間を使うことで、選考全体の質を高めることができるのです。
面接日程調整・応募者対応の自動化
面接日程調整や応募者からの問い合わせ対応は、採用活動において避けて通れない業務ですが、非常に煩雑で時間がかかります。候補者一人ひとりとメールや電話でやり取りを重ね、面接官のスケジュールとすり合わせる作業は、採用担当者にとって大きな負担となっています。
AIを導入することで、日程調整や問い合わせ対応を自動化でき、煩雑なやり取りを大幅に削減できます。AIチャットボットや自動日程調整ツールが候補者からの質問に即座に回答したり、面接可能な日程を自動で提案したりすることで、採用担当者の手を煩わせることなくスムーズな調整が可能になります。
特に、応募者対応のスピードと一貫性が向上し、選考体験の改善にもつながる点が重要です。候補者にとって、質問への迅速な回答や柔軟な日程調整は、企業への印象を左右する要素です。AIによる自動対応により、候補者を待たせることなく、一貫した品質のサポートを提供できるため、選考途中での離脱を防ぎ、候補者満足度の向上にも貢献します。
候補者マッチング・採用要件との適合度評価
採用において最も重要な判断の一つが、候補者と自社の採用要件がどれだけ適合しているかを見極めることです。従来の方法では、採用担当者や面接官が応募書類や面接での印象をもとに主観的に判断することが多く、評価基準が曖昧になったり、担当者によって判断が異なったりする課題がありました。
AIを活用することで、候補者データと採用要件を照合し、マッチ度を定量的に可視化できます。AIは、スキル、経験、資格、適性検査の結果、志向性といった多面的なデータを総合的に分析し、候補者が自社の求める人物像にどの程度合致しているかをスコアとして算出します。
さらに、主観に頼らない判断が可能となり、ミスマッチや早期離職のリスク低減に寄与します。過去の採用データをもとに、入社後に活躍した社員の特徴をAIが学習することで、同様のパターンを持つ候補者を高精度で抽出できます。
AI採用を行う4つのメリットを解説!

これからAI採用を導入していくにあたって、気になるのはどんなメリットを受けられるのかという点が大きいかと思われます。コストがかかる部分もあるため、それをメリットが上回っていなければ魅力的とは言えません。
そこで、AI採用に関する具体的なメリットを解説します。
①人件費削減
採用担当者は、求人媒体の選定や掲載管理、応募者対応、選考フローの運用など幅広い業務を担っており、日々多忙を極めています。
こうした中でAIを導入すれば、マッチ度の高い候補者の抽出や広告配信、面接日程の調整といった、時間と手間のかかるプロセスを自動化でき、担当者の業務負担軽減や人件費の削減に大きく貢献します。
また、業務に余裕が生まれれば、入社後の研修や定着支援といった本質的な業務にも注力できるでしょう。
一方で、AI採用には「人間の感覚では拾えるはずの熱意やポテンシャルを見落とす可能性」や、「過去のデータに基づくバイアスの再生産」といったデメリットも存在します。
そのため、AIに任せきりにするのではなく、人的判断とうまく組み合わせながら活用することが重要です。
②公平な採用の実現
採用活動では、担当者の価値観や経験、感情によって判断にばらつきが生じることがあり、それが選考の一貫性や公平性を損なう原因となることもあります。
AI採用を活用すれば、事前に設定された客観的な評価基準に基づいて候補者を判断できるため、属人的な判断を避け、公平性の高い採用を実現できる点は大きなメリットです。
しかしその一方で、AIは過去のデータに学習して判断を下すため、元のデータに偏りが含まれていれば、そのバイアスを再現してしまう可能性もあります。
また、評価のプロセスがブラックボックス化しやすく、なぜその結果に至ったのかが不明瞭になる点もAI採用のデメリットです。
公平性を高めるには、AIの判断を鵜呑みにせず、人によるチェックと組み合わせることが不可欠です。
③スケジュール調整のしやすさ
AI面接を導入することで、採用担当者が日程を調整する手間が省け、応募者は自分の都合に合わせたタイミングで面接を受けることが可能です。
これにより、スケジュールのすれ違いによる面接機会の損失を防ぎ、結果として雇用のチャンスを逃さずに済むというメリットがあります。
また、担当者の面接対応やスケジュール管理にかかる工数も大幅に削減され、採用業務の効率化に繋がるでしょう。
ただし、AI面接にはデメリットも存在します。
たとえば、画面越しで機械に話すことに抵抗を感じる応募者も多く、「AIに自分の良さが伝わるのか」という不安や不信感から選考辞退につながる可能性があります。
また、非言語的な魅力や人間性といった要素をAIが正確に判断するのは難しく、優秀な人材を見落とすリスクもあるため、導入には慎重な検討が必要です。
④自社のアピールに時間を割くことが可能
採用担当者は、自社にマッチする人材を見極めるために多くの時間を費やす一方で、求人媒体の管理や面接調整など他の業務にも追われます。そして、自社の魅力を十分に伝える機会を確保できないケースも少なくありません。
こうした状況でAIを活用すれば、マッチ度の高い応募者の絞り込みや面接対応、情報収集、評価作業の効率化が可能になり、担当者は空いた時間を使って自社の事業方針やカルチャー、魅力を伝えることに注力できます。
その結果、より多くの応募者を惹きつけることができるうえ、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できるでしょう。
ただし、AIによる選考では、応募者の熱意や人間的な魅力、将来性といった要素を十分に汲み取るのが難しい点がデメリットです。
また、評価基準がブラックボックス化しやすく、誤った判断を下すリスクもあるため、AIの結果を鵜呑みにせず、人の目で補完する体制づくりが欠かせません。
AI採用を行うデメリットはある?

人の手を煩わせずとも、AIを活用することで得られるメリットは各種あることが分かりました。ですが、運用していくうえでメリットばかりに目を向けられるわけでもありません。
そこで、AI採用を活用する際のデメリットについても解説します。
AI採用の導入コストの発生
採用担当者の業務は、求人媒体の選定や管理、応募者対応、選考の進行など多岐にわたり、負担が大きいのが実情です。
AIを導入することで、マッチ度の高い候補者の抽出や広告配信、面接設定などの手間を削減でき、業務効率の向上や人件費削減にもつながります。
一方で、AI採用には「判断基準がブラックボックス化しやすい」「データに偏りがあると選考にも偏りが生まれる」といったデメリットもあります。導入する際は、AIに任せきりにせず、人の目で補完する体制が重要です。結果として、採用担当者は空いたリソースを研修や定着支援など、本質的な業務に充てることができるようになります。
AI学習用の過去のデータが必要
AIは機械学習によって精度を高めていく仕組みのため、過去の採用データが多いほど評価の正確性が向上します。
そのため、大規模な採用実績を持つ大手企業であればAIの力を十分に活用できますが、これまでの応募者数が限られている中小企業では、AIに過度な精度を期待するのは難しいのが現実です。
これはAI採用のデメリットの一つであり、初期段階では判断のばらつきや信頼性に課題が生じる可能性もあります。こうしたリスクを避けるためにも、まずは「応募者の絞り込み」や「マッチ度の高い候補者への広告配信」「面接日程の調整」など、一部業務に限定してAIを導入し、徐々にデータを蓄積していくことが現実的なアプローチと言えるでしょう。
差別的な傾向を助長する可能性
実際にはAI自体が過去のデータに基づいて学習するため、もともと人間の判断に含まれていた偏見や差別的傾向を引き継いでしまうリスクも存在します。
これはAI採用の大きなデメリットの一つです。
実際に海外では、黒人に多い名前の応募者が低評価を受けたり、職歴に空白期間があるだけで候補者から除外されるといった事例も報告されています。
AIは公平に見える一方で、その判断基準がブラックボックス化しやすく、気づかぬうちに不適切な選考が行われてしまう可能性があるため、慎重な運用と人の介在が不可欠です。
AI採用を実施する際の基本的な流れとは?

AI採用を導入するにあたり、いきなり全面的にシステムを入れ替えるのではなく、段階的に進めることが成功のカギとなります。自社の課題を明確にし、適切なツールを選定し、運用体制を整えながら、小さく始めて大きく育てるアプローチが重要です。
本セクションでは、AI採用を実施する際の基本的なステップを7つに分けて解説します。各段階で何をすべきか、どのような準備が必要かを理解することで、スムーズな導入と効果的な運用が可能になります。
採用課題・導入目的の整理
AI採用を成功させるための第一歩は、現状の採用活動における課題を正確に把握し、導入目的を明確にすることです。漠然と「AIを使ってみたい」という動機だけでは、導入後に期待した効果が得られず、かえって運用負担が増える可能性があります。
まず、どの業務に課題があり、何を改善したいのかを明確にすることが重要です。例えば、「応募者が集まらない」「書類選考に時間がかかりすぎる」「面接の日程調整が煩雑」「選考の公平性に課題がある」など、具体的な問題点を洗い出します。その上で、AIによってどの課題を解決したいのか、優先順位をつけて整理します。
次に、工数削減・公平性向上・スピード改善など、目的を言語化することで導入後の成果が測りやすくなります。「書類選考の時間を50%削減する」「応募から面接までの期間を2週間以内に短縮する」といった具体的な目標を設定することで、導入の効果を数値で評価できます。
AIを活用する採用業務の選定
採用プロセス全体を見渡すと、書類選考、スカウト送信、日程調整、面接、内定者フォローなど、多岐にわたる業務が存在します。しかし、すべての業務にAIを適用すれば良いというわけではありません。AIとの相性を見極め、効果が高い業務から優先的に導入することが重要です。
採用フロー全体を洗い出し、AIと相性の良い業務を見極める工程が必要です。一般的に、AIは定型的で反復性の高い作業、大量のデータを処理する作業、客観的な判断が求められる作業に適しています。例えば、書類選考、スカウト文作成、日程調整、候補者データの分析などは、AIが得意とする領域です。
一方で、候補者との対話を通じた深い理解や、企業文化との相性判断など、人間的な感性や経験が必要な場面では、AIだけに頼るのではなく人と併用する方が望ましいケースもあります。書類選考や日程調整など、定型・反復作業から導入するのが現実的であり、成果を実感しながら徐々に適用範囲を広げていくアプローチが推奨されます。
AI採用ツール・システムの選定
AI採用ツールは、スカウト送信特化型、書類選考支援型、面接支援型、総合型など、多様な種類が市場に存在します。自社の課題や目的に合ったツールを選ぶことが、導入後の成功を左右します。ツール選定を誤ると、期待した効果が得られず、現場での活用が進まない可能性もあります。
目的に合ったAI採用ツールを比較・検討し、機能や導入実績、操作性を確認することが重要です。まず、前の段階で整理した課題や目的を踏まえ、それを解決できるツールをリストアップします。次に、各ツールの機能、精度、サポート体制、料金体系を比較し、自社のニーズに最も適したものを選びます。
また、既存の採用管理システムとの連携や、サポート体制も重要な判断材料となります。例えば、すでに使用している応募者管理システム(ATS)やカレンダーツールとスムーズに連携できるかどうかは、運用効率に大きく影響します。無料トライアルやデモンストレーションを活用し、実際の使用感を確かめることも有効です。
導入前の準備(データ整備・体制構築)
AI採用ツールを導入する際、システムを入れるだけでは十分な成果は得られません。AIが高い精度で機能するためには、適切なデータと運用体制の準備が不可欠です。準備不足のまま導入すると、AIの判断精度が低く、現場の混乱を招くことにもなりかねません。
まず、AIの精度を高めるために、過去の採用データや評価基準を整理・統一することが重要です。例えば、過去に採用した候補者のプロフィール、選考結果、入社後のパフォーマンスデータなどを整備し、AIに学習させることで、より精度の高いマッチングや評価が可能になります。
同時に、AIと人の役割分担を明確にし、社内の運用体制を整える必要があります。AIにどこまで任せ、人はどの部分で判断・介入するのかを決めることで、現場の混乱を防げます。運用ルールや責任者を明確にし、全体がスムーズに機能する体制を構築することが、導入成功の鍵となります。
試験導入(スモールスタート)
AI採用ツールをいきなり全社的に展開するのは、リスクが伴います。システムの不具合や運用上の課題が発生した場合、採用活動全体に影響を及ぼす可能性があるためです。そのため、まずは一部の業務や職種で試験的に導入し、効果や課題を確認するスモールスタートが推奨されます。
いきなり全面導入せず、一部業務でAIを試験的に活用する段階として、例えば特定の職種の書類選考のみ、あるいは一部のスカウト送信のみにAIを適用します。これにより、AIの精度や運用負担、現場の反応を実際に確認でき、本格導入前に調整や改善が可能になります。
人による判断とAIの結果を比較し、精度や現場への影響を確認することも重要です。AIの評価結果と人の判断が大きくずれている場合は、評価基準の見直しやAIの学習データの再調整が必要になることもあります。試験期間中に得られたフィードバックをもとに、運用フローを最適化し、全面展開に向けた準備を整えることが、スムーズな本格導入につながります。
本格導入と運用開始
試験導入で得られたデータやフィードバックをもとに課題を改善したら、いよいよ本格的な運用フェーズに移行します。この段階では、対象業務や職種を広げながら、AIを活用した採用活動を組織全体に浸透させていくことが求められます。
試験導入の結果を踏まえ、対象業務を広げながら本格的な運用に移行します。例えば、書類選考だけでなくスカウト送信や日程調整にも範囲を拡大したり、特定の職種から全職種へと適用範囲を広げたりします。この際、試験導入で明らかになった課題や改善点を反映し、運用フローを最適化しておくことが重要です。
また、運用ルールや評価フローを明確にし、現場に定着させていくことが求められます。AIが出した判断をどのように活用するのか、人がどの段階で介入するのか、エラーや疑問が生じた場合の対応方法など、具体的なルールを文書化し、全員が理解できるようにします。
効果検証・改善(PDCA)
AI採用ツールを導入して終わりではなく、継続的に効果を検証し、改善を重ねることが重要です。導入当初は期待通りの成果が出ても、時間の経過とともに精度が低下したり、新たな課題が浮上したりすることもあります。そのため、PDCAサイクルを回し続けることが、長期的な成功につながります。
導入後は、工数削減や選考精度などの効果を定期的に検証します。例えば、「書類選考にかかる時間が何%削減されたか」「AIが推薦した候補者の採用率はどの程度か」「面接通過率や内定承諾率にどのような変化があったか」といった指標を定量的に測定します。これにより、AIの導入効果を客観的に把握できます。
さらに、結果をもとにAI設定や運用方法を見直し、継続的に改善していくことが重要です。AIの学習データを更新したり、評価基準を調整したり、新たな機能を追加したりすることで、精度や効率を向上させることができます。
AI採用を効果的に行うポイントを解説!
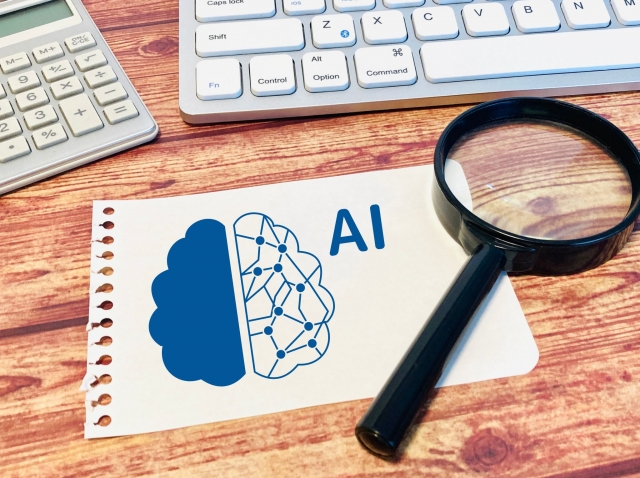
日々進化を遂げていき、私たちの生活にも少なからずかかわるようになってきたAI。様々なメリットがある一方で、採用の面で有効に活用するのであれば、ポイントを押さえておく必要があります。
そこで、AI採用を活用する際の具体的なポイントを解説します。
自社が求める人材を明確にしておく
AIにマッチ度の高い人材を正確に評価させるためには、単に過去の採用データを蓄積するだけでは不十分です。
自社が求める人物像や具体的な採用基準を明確に設定し、それをAIに学習させることで、より的確な人材の絞り込みが可能になります。
ただし、設定が曖昧だったり偏っていたりすると、AIの判断も不正確になり、適性のある候補者を見落とす恐れがあります。
このような精度のばらつきはAI採用のデメリットの一つです。
手軽に利用できる求人媒体や適性検査から始める
AIを導入している求人媒体の活用や、適性検査のAI評価などは、コストを抑えて手軽に始められるAI採用の手法として有効です。
特に初めてAI採用に取り組む場合は、求人媒体に搭載されている「絞り込み機能」や「マッチ度の高い求職者への広告表示・オファー機能」から活用するのがおすすめです。
ただし、AIの判断は入力データの質に大きく左右され、誤った条件設定や偏ったデータに基づくと、適切な人材を見逃す可能性がある点はデメリットとして認識しておくことが大切になってきます。
個人情報を取り扱いを厳重に行う
採用業務では、応募者の履歴書や評価情報など多くの個人情報を扱うため、情報管理の徹底が欠かせません。
万が一個人情報が漏えいすれば、企業の信頼性は大きく損なわれる可能性があります。
AIを活用する際にも同様で、特に生成AIなどにデータを入力する際は、外部への情報流出リスクを常に念頭に置く必要があります。
このような背景から、AI採用を導入する企業は、AIの使用範囲や取り扱う情報のレベルについて明確な基準を設け、従業員全体に共有・周知することが重要です。AIの便利さに頼りすぎると、意図せぬ形で機密情報が漏れるリスクがあることは、AI採用の大きなデメリットのひとつです。
技術面だけでなく、情報管理体制の整備と運用ルールの徹底が、安心・安全なAI活用には欠かせません。
AIだけでなく人による評価も取り入れる
AIを採用業務に活用する際は、どの工程をAIに任せ、どこを人が担うかをあらかじめ明確にしておくことが重要です。適用範囲を限定しておくことで、万が一問題が発生した場合でも迅速に対応しやすく、導入後の管理負担も軽減できます。
一般的には、スクリーニングや性格診断、適性検査、ソーシングなどの初期段階でAIを活用するのが効果的とされており、自社の採用フローに合わせて導入ポイントを見極めることが大切です。
ただし、AIは万能ではなく、応募者の人柄や企業との相性、熱意といった人間的な要素の判断には限界があります。
また、応募書類の表現がAIにとって解釈しづらい場合、内容が優れていても適切に評価されないリスクもあります。
これらはAI採用のデメリットであり、すべてをAIに委ねてしまうと、本来採用すべき人材を見落とす可能性も否定できません。
そのため、AIの分析結果と人間の経験や直感を照らし合わせながら、相互に補完し合う体制を整えることが、より精度の高い採用判断につながります。
AI採用を導入している企業事例5選

AI採用の導入を検討する際、実際にどのような企業がどのように活用し、どんな成果を上げているのかを知ることは非常に有益です。導入事例を参考にすることで、自社に適した活用方法や期待できる効果をイメージしやすくなります。
本セクションでは、AIスカウトサービス「RecUp」を導入し、採用活動の効率化や成果向上を実現した5社の事例を紹介します。それぞれの企業が抱えていた課題、導入の決め手、そして得られた成果について詳しく見ていきましょう。
イトーヨーカ堂様

イトーヨーカ堂様では、新卒採用を2名体制で進める中で、スカウト送信に充てる時間が確保できず、母集団形成に課題を抱えていました。業務の幅が広く、スカウトを送りたいと思いながらも終業時間になってしまう日が続いていたといいます。
AIスカウトサービス「RecUp」の導入により、毎日安定してスカウトが送れるようになり、イベント参加人数が倍増するという成果が生まれました。
AIが24時間稼働し、候補者ごとにカスタマイズされた文面を自動で送信してくれるため、採用担当者の精神的ストレスが激減し、学生と向き合う時間を確保できるようになりました。
さらに、RecUpの伴走型支援により、定例ミーティングで改善提案を受けることで、イベント予約率の向上にもつながったとのことです。
【小売業界】イトーヨーカ堂様の成功事例──AIスカウト『RecUp』を導入して送信数の担保と採用の質が向上を実現した、その方法とは?
オープンハウスディベロップメント様

オープンハウス・ディベロップメント様は、組織体制の変更により超若手中心の採用チームとなり、採用人数の目標も大幅に増加する中で、スカウト送信のノウハウや工数が不足していました。外注も利用していましたが、人に依存する限界を感じていたといいます。
RecUpを導入した結果、代行業者利用時の4〜8月で36承認だったものが、RecUp導入後の9〜10月の2ヶ月間で同じ36承認を達成し、通常早期に送るほど有利と言われるスカウトで、後半の方が高い成果を出しました。
AIによる文章の最適化と運用の安定性により、サマー採用期の反応率は前年の2倍以上となり、上司も驚く結果となったそうです。また、辞退がほぼゼロに近づき、承諾者も出ているとのことです。
承認数2倍以上を実現!ーAIスカウトRecUpを導入して、たった2ヶ月で代行業者に依頼していた時の承認数を超えた、不動産業界オープンハウス・ディベロップメント様の成功事例
株式会社エコスマート様

株式会社エコスマート様は、保険事業を展開する企業で、OfferBoxでスカウトを送っても承諾が得られず、ノウハウ不足により成果が出ない状態が続いていました。他社では普通に採用できていると聞く中、自社だけが結果が出ないという課題を抱えていました。
RecUpを導入したことで、オファー承諾数が明確に増加し、朝6時の更新時に満枠学生へのアプローチも可能になり、アプローチ数が最大化されました。
AIの文章が丁寧で、学生からも「プロフィールをちゃんと読んだうえで送ってくれたと感じた」という評価を得られたとのことです。RecUpの伴走型サポートにより、数字が落ちた際には先回りして改善提案を受けられる点も高く評価されています。
承認数・アプローチ数の最大化を実現!─他社にはない『AIスカウトRecUp』の伴走型支援で採用効率が劇的に改善した保険業界のお客様の成功事例
東栄ホームサービス株式会社様

東栄ホームサービス様では、26卒と27卒を同時に進める中で、スカウト送信に割く時間が取れず、母集団形成に課題を抱えていました。内定後のフォローや面談調整、選考案内など、選考以外の業務が増える中で、スカウトを送る時間が確保できない日が続いていたといいます。
RecUpを導入した結果、約3カ月間で承認者数が71名から98名へと27名増加し、昨年同時期の12名増加を大幅に上回る成果となりました。
さらに、スカウト作業に割いていた時間が学生との接触時間に置き換わり、説明会を週2回から隔日開催、1日2回開催する日もあるなど、母集団形成の質と量が向上しました。懇親会の回数も増やし、インターンの実施も視野に入れられるようになったとのことです。
「スカウト業務を自動化し、承認者数90名超を実現」AIスカウトで母集団形成を効率化した事例
株式会社オーレンジ様

株式会社オーレンジ様は、携帯キャリアショップの運営を中心に事業を展開する企業で、スカウト送信の工数負担が大きく、他の業務を削らないと数を増やせない状況でした。送りたいと思いながらも、残業しても限界があり、諦めざるを得ない場面もあったといいます。
RecUpを導入した結果、送信数が人で送る時の約4倍となり、承認数も2〜3倍に増加しました。費用対効果も高く、人件費換算で月20万円かかるところを月10万円で運用できるため、コスト面でも大きなメリットがあったとのことです。
AIが個別に最適化したメッセージを作成し、配信回数を最大化できたことで、学生との接点が大幅に広がり、面談の質も向上したと評価されています。
送信数4倍・承認数2〜3倍を実現ーAIスカウトRecUpにより「人力の限界」を突破したサービス業の企業様の成功事例
AI採用のメリットに関するFAQ

AI採用を検討する際、多くの企業が同様の疑問や不安を抱えています。本セクションでは、AI採用のメリットに関してよく寄せられる質問について、具体的に回答していきます。
導入を迷っている方や、社内での理解を得たい方は、ぜひ参考にしてください。
Q:AI採用を導入すると、具体的に何が一番変わりますか?
A. 採用担当者の工数が大幅に削減され、成果が安定します。
スカウト文面作成、候補者抽出、送信、効果分析といった”時間を奪われがちだが成果に直結しにくい作業”をAIが代替します。その結果、面接設計や候補者フォローなど、人がやるべき業務に集中できるようになります。
Q:採用の「質」は本当に上がるのでしょうか?
A. 条件マッチだけでなく、反応データを元に改善され続ける点がメリットです。
AIは過去の返信率・応募率などのデータを学習し、反応しやすい候補者や文面傾向を自動で最適化します。経験や勘に頼らないため、属人化しにくく、再現性の高い採用が可能になります。
Q:採用担当者がいなくても運用できますか?
A. 最低限の設定は必要ですが、専任で張り付く必要はありません。
職種要件や採用ターゲットの初期設計は人が行いますが、その後の運用はAIが自動化します。少人数の人事体制や、採用を兼務している企業ほど導入メリットが大きくなります。
AIを採用に活用するならAIスカウトならRecUp

AI採用の導入により、採用担当者の工数削減、母集団形成の効率化、選考精度の向上といった多くのメリットが期待できます。求人票作成、候補者探索、書類選考、面接、日程調整など、採用プロセス全体でAIが活躍できるシーンは広がり続けています。
特にスカウト送信においては、AIが候補者ごとに最適化した文面を自動で作成・配信できるため、限られたリソースでも大量のアプローチが可能になります。そこで注目されているのが、RecUp(リクアップ)というスカウト特化型サービスです。
AIを採用に活用するなら、まずはスカウト業務から始めてみることをおすすめします。RecUpは国内導入数No.1のAIスカウトサービスとして、400社以上の実績と伴走型サポートで、採用成功を全力で支援いたします。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。