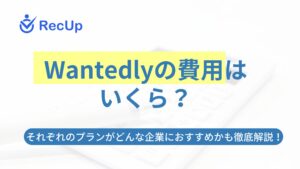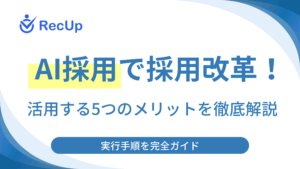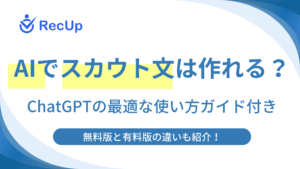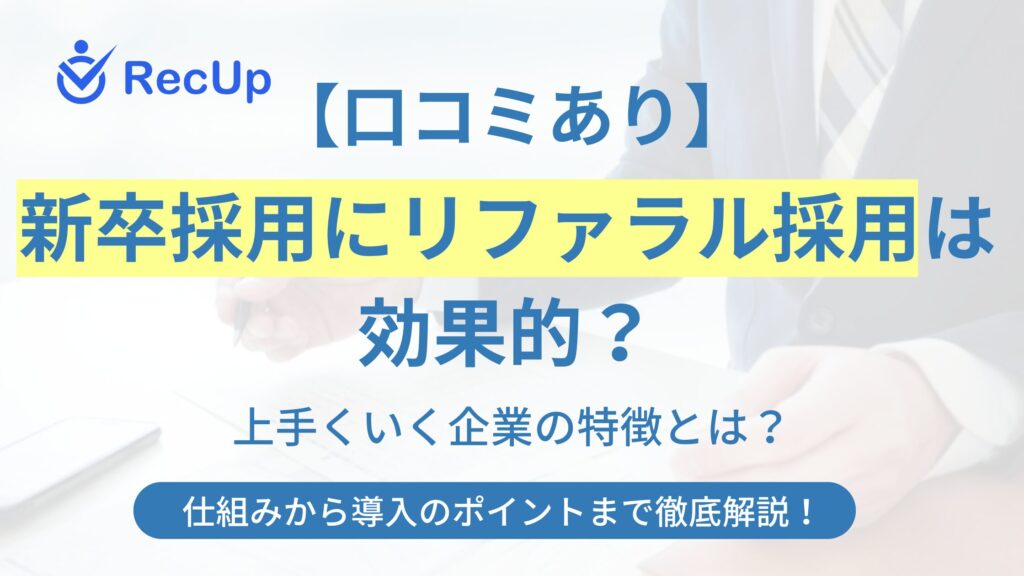
企業の採用活動において、近年ますます注目を集めているのが「リファラル採用」です。これは、社員や関係者からの紹介によって人材を採用する仕組みのことを指し、新卒採用の場面にも導入が進んでいます。
従来の求人媒体や説明会だけに頼る採用手法では、優秀な学生を早期に確保することが難しくなっているのが現状です。本記事では、新卒採用におけるリファラル採用の特徴やメリット・デメリット、導入時のポイントをわかりやすく解説していきます。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
リファラル採用とは?

企業の採用活動において、従来の求人媒体だけに頼らない新しいアプローチが広がりを見せています。特に近年、多くの企業が取り入れ始めている採用手法の一つが、社内の人的ネットワークを活用した方法、リファラル採用です。
リファラル採用とは、自社の社員や内定者が、一緒に働きたいと思う友人や知人を企業に紹介し、その紹介を通じて採用活動を行う手法のことを指します。英語の「referral(紹介・推薦)」が語源となっており、社内の人材ネットワークを活用することで、企業文化や業務内容を理解した上で応募してくる候補者を集めることができます。
この手法は、採用コストの削減だけでなく、企業文化にマッチした人材の確保という観点からも注目を集めています。
従来の採用活動では、求人サイトへの掲載や合同企業説明会への参加など、多額の費用と時間をかけて母集団を形成することが一般的でしたが、こうした方法では応募者の質にばらつきが生じやすく、選考に多くの工数がかかることも課題となっていました。そこで、より効率的で質の高い採用を実現する方法として、社員や内定者からの紹介による採用が選択肢の一つとして浮上してきたのです。
この採用手法の最大の特徴は、紹介者が自社のことを深く理解しているため、企業とのマッチング精度が高い候補者を集めやすい点にあります。また、紹介する側も自分の友人や知人を推薦する責任感から、慎重に候補者を選定する傾向があり、結果として質の高い人材との出会いにつながりやすくなります。
新卒採用でリファラル採用が注目されているのはなぜ?
新卒採用市場は年々変化を続けており、企業側にとっても学生側にとっても、従来の採用手法だけでは十分な成果を上げにくくなってきています。特に優秀な学生の獲得競争は激化しており、大手企業から中小企業まで、あらゆる規模の企業が新しい採用アプローチを模索している状況です。
こうした背景の中で、新卒採用におけるリファラル採用が注目を集めるようになった理由はいくつかあります。
ほかの採用手法との比較
| 採用手法 | 概算費用 | 必要工数 | 母集団形成 | ミスマッチ率 |
|---|---|---|---|---|
| リファラル採用 | 1人あたり10〜30万円程度 | 大 | △ | 低 |
| 就職サイト | 1週あたり10〜20万円程度 | 中 | ◎ | 高 |
| 人材紹介 | 1人あたり100万円程度 | 小 | ○ | 低 |
| 合同企業説明会 | 1ブロック75〜100万円程度 | 小 | ○ | 高 |
| ダイレクトリクルーティング | 成功報酬:1人あたり30万円程度 先行投資:年100〜400万円 | 大 | △ | 低 |
新卒採用には様々な手法があり、それぞれに特徴やコスト、期待できる効果が異なります。リファラル採用がどのような位置づけにあるのかを理解するため、主要な採用手法と比較してみましょう。採用コストの面では、リファラル採用は紹介者へのインセンティブを含めても1人あたり10〜30万円程度で済むことが多く、人材紹介会社を利用した場合の100万円程度と比較すると大幅にコストを抑えることができます。
就職サイトへの掲載は、1週あたり10〜20万円程度の費用がかかり、掲載期間が長期化すると総額が膨らむ傾向にあります。合同企業説明会への出展では、1ブロック75〜100万円程度の費用が必要となります。一方で、ダイレクトリクルーティングは成功報酬として1人あたり30万円程度に加え、年間100〜400万円の先行投資が必要になるケースが一般的です。
工数の観点から見ると、リファラル採用は社員や内定者への制度周知、フォロー体制の構築など、運用に一定の工数が必要となります。しかし、一度制度が定着すれば、継続的に質の高い候補者と出会える可能性が高まります。就職サイトは掲載後の応募対応に中程度の工数がかかり、人材紹介は比較的少ない工数で運用できますが、コストは最も高くなります。
リファラル採用は、採用コストを抑えながら質の高い候補者と出会える可能性が高い採用手法として、新卒採用市場で存在感を増しています。特に数十名規模の採用を目指す企業や、企業文化とのマッチングを重視する企業にとって、有効な選択肢の一つとなっています。
【口コミあり】新卒リファラル採用の5つのメリット!

新卒採用にリファラルを導入することには、多くのメリットがあります。従来の採用手法と比べてコストや工数を削減できるだけでなく、入社後の定着率や組織への貢献度といった面でもプラスに働くことが多いのです。
各種の課題を解決する選択肢としても、リファラル採用は企業の注目を集めています。ここでは、具体的にどのようなメリットがあるのかを順を追って解説していきましょう。
①採用や選考のコスト削減になる
採用活動において、予算管理は常に重要な課題です。特に新卒採用では、求人サイトへの掲載料、合同企業説明会の出展費、人材紹介会社への成功報酬など、様々なコストが発生します。リファラル採用を活用することで、こうした採用コストを大幅に削減できる可能性があります。
従来の採用手法では、1人を採用するために数十万円から数百万円の費用がかかることも珍しくありません。就職サイトへの掲載は継続的な費用が発生し、合同企業説明会は1回の出展で数十万円の出費となります。人材紹介会社を利用した場合は、採用が決まった際に年収の30〜35%程度を成功報酬として支払う必要があり、1人あたり100万円程度のコストが発生します。
一方、リファラル採用では、紹介してくれた社員や内定者に対してインセンティブを支払う場合でも、1人あたり10〜30万円程度が相場となっています。企業によってはインセンティブを設定しないケースもあり、その場合は採用コストをさらに抑えることができます。
また、選考プロセスにおけるコストも削減できる点も見逃せません。リファラル採用で紹介される候補者は、紹介者が企業文化や求める人物像を理解した上で推薦してくるため、選考の初期段階で多くの応募者をふるいにかける必要がなく、面接回数を減らしたり、選考プロセスを効率化したりすることが可能になります。
②採用までのスピードが上がる
採用活動において、優秀な人材との出会いから内定までのスピードは非常に重要です。特に新卒採用市場では、複数の企業から内定を獲得する学生も多く、採用プロセスが長引くことで他社に流れてしまうこともあります。リファラル採用は、この採用スピードの向上に大きく貢献します。
通常の採用プロセスでは、求人掲載から応募受付、書類選考、複数回の面接、最終選考と、内定までに数週間から数ヶ月かかることが一般的です。また、応募者の中には企業研究が不十分なまま応募してくる学生も含まれており、選考の初期段階で多くの時間を費やすことになります。
リファラル採用の場合、紹介者が事前に企業の魅力や業務内容を候補者に伝えているため、応募の段階ですでに一定の理解を持った状態からスタートできます。従来行っていた1次面接や2次面接を省略し、責任者クラスとの面接から選考を始めることも可能になるのです。
内定後の意思決定プロセスもスムーズに進む傾向があります。紹介者との信頼関係があることで、候補者は企業に対する安心感を持ちやすく、内定承諾までの検討期間も短くなることが期待できます。
実際の現場からも、リファラル採用によって採用スピードが向上したという声が聞かれています。例えば、専門性の高い職種であっても、知人からの紹介であれば話が早く進み、スピーディーに採用まで至ったというケースもあります。採用市場が活発化する中で、こうした採用スピードの優位性は企業にとって大きな競争力となります。
③学生の定着率が高まる
新卒採用において、入社後の定着率は非常に重要な指標です。せっかく時間とコストをかけて採用した人材が早期に離職してしまうことは、企業にとって大きな損失となります。リファラル採用は、この定着率の向上にも効果を発揮します。
早期離職の主な原因として、入社前に抱いていたイメージと実際の職場環境とのギャップが挙げられます。求人サイトや企業説明会だけでは、企業の実態を完全に理解することは難しく、「思っていた会社と違った」「こんなはずではなかった」という失望感から退職を選択する新入社員も少なくありません。
リファラル採用の場合、紹介者である社員や内定者が、企業の良い面だけでなく、業務の厳しさや職場の課題なども含めて、リアルな情報を候補者に伝えることができます。求人サイトには掲載されていない社内の雰囲気や、実際の業務内容、成長機会など、生の声を聞くことで、候補者は企業の実像をより正確に把握できます。
入社後も紹介者が身近にいることで、新入社員は相談しやすい環境が整います。業務上の疑問や職場での悩みを気軽に話せる先輩や同期がいることは、新入社員の心理的安全性を高め、早期離職の防止につながります。実際にリファラル採用した方が、入社後に実力を伸ばしているという声からも、それは明らかでしょう。
実際に、リファラル採用で入社した社員の定着率が高いという報告は多くの企業から聞かれます。企業文化とのマッチング精度が高く、事前の期待値と実際の職場環境との乖離が小さいことが、この高い定着率の背景にあると考えられます。
④紹介者にも還元できる
リファラル採用の制度設計において、多くの企業が紹介者へのインセンティブを設定しています。これは単なる謝礼ではなく、社員のエンゲージメント向上や組織活性化にもつながる重要な要素です。紹介者へのリターンを適切に設計することで、継続的な紹介を促進できます。
インセンティブの形態は企業によって様々です。金銭的な報酬として、5万円から30万円程度の紹介料を設定する企業もあれば、特別休暇や社内ポイント、商品券などの非金銭的な報酬を選択する企業もあります。また、紹介した人数や採用に至った人数に応じて表彰制度を設けることで、社員のモチベーション向上につなげている企業も見られます。
重要なのは、インセンティブの金額や形態そのものよりも、紹介という行為に対する企業からの感謝の意を示すことです。社員が自発的に友人や知人を紹介してくれることは、会社への信頼と愛着の表れでもあります。実施している方も、金銭からティファニーへ変えたことで業務へ活かせるようになったとコメントしています。
紹介した後輩が活躍する姿を見ることは、紹介者にとっても大きな喜びとなります。自分の判断で推薦した人材が企業に貢献している様子を間近で見られることは、金銭的な報酬以上の満足感をもたらすこともあります。このような精神的な充足感も、リファラル採用における重要な還元の一つと言えるでしょう。
⑤自社のことを深く理解してもらいやすい
企業選びにおいて、学生が重視するポイントは年々多様化しています。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業文化や働き方、成長機会など、様々な角度から企業を評価するようになっています。リファラル採用では、こうした多面的な情報を候補者に伝えやすい環境が整っています。
求人サイトや企業説明会では、限られた時間や文字数の中で企業の魅力を伝える必要があります。また、公式な場での情報発信であるため、どうしても企業の良い面を中心に紹介することになりがちです。一方で、社員や内定者からの紹介では、日常的な会話の中で自然に企業の話をすることができ、より立体的な情報を伝えることが可能になります。
例えば、実際のプロジェクトでの経験談、上司や同僚との関係性、キャリアパスの実例、業務のやりがいと同時に感じる苦労など、公式な場では伝えにくい生の情報を共有できます。こうした情報は、候補者が入社後の自分の姿をイメージする上で非常に有効です。
紹介者との信頼関係があることで、候補者は疑問や不安を率直に質問しやすくなります。「実際のところどうなのか」「本当に成長できる環境なのか」といった踏み込んだ質問にも、紹介者は自身の経験をもとに答えることができ、口コミでも優秀な幹部はリファラルから産まれているという声もあります。
入社前に企業のリアルな姿を理解していることは、入社後のパフォーマンスにも良い影響を与えます。事前の期待値が適切に調整されているため、入社後のギャップが小さく、早期から業務に集中できる環境が整いやすくなります。
【口コミあり】新卒リファラル採用の4つのデメリット!

リファラル採用は多くのメリットを持つ一方で、導入にあたっては注意すべきデメリットも存在します。これを先に抑えておくのも、メリットを最大化させるために大切な要素です。
本章では、新卒リファラル採用を導入する際に考慮すべき代表的なデメリットと、その背景について解説していきます。
①フォロー体制が必要になってくる
リファラル採用を継続的に成功させるためには、紹介者と候補者の両方に対する丁寧なフォロー体制の構築が不可欠です。適切なフォローがなければ、制度そのものが形骸化してしまう可能性があります。
紹介者である社員や内定者に対しては、制度の周知徹底が重要です。リファラル採用の目的や求める人物像、紹介の方法、インセンティブの内容など、詳細な情報を分かりやすく伝える必要があります。また、定期的に制度のリマインドを行い、紹介しやすい環境を維持することも大切です。
さらに、内定後から入社までの期間においても、継続的なフォローが重要になります。内定者懇親会や職場見学、アルバイト採用などを通じて、定期的に接点を設けることで、入社への期待感を高めることができます。特に内定者を通じた紹介の場合、内定者自身の入社意欲を維持することも、新たな紹介を促進する上で重要な要素となります。
実際の採用現場からも、フォロー体制の重要性を指摘する声が上がっています。内定者や新入社員を通じた紹介では、人事側のサポートがあってこそ、スムーズな紹介活動が実現できるという実感を持つ担当者も多いようです。
こうしたフォロー体制の構築には、人事部門の工数が相応にかかります。しかし、この投資を怠ると、せっかくの紹介が活かされず、紹介者のモチベーション低下にもつながりかねません。長期的な視点で、持続可能なフォロー体制を整えることが、リファラル採用の成功の鍵となります。
②自社に合うかはわからない
紹介者からの推薦があっても、その候補者が必ずしも企業の求める人物像に合致するとは限りません。友人や知人であるという理由だけで、業務適性や企業文化とのマッチングが保証されるわけではないことを理解しておく必要があります。
紹介者は、自分が良いと思う人物を推薦しますが、その判断基準は必ずしも企業側の採用基準と一致しているとは限りません。特に、入社して間もない社員や内定者の場合、企業のことを十分に理解していない状態で紹介を行う可能性もあります。
むしろ、通常の応募者と同様に、公平かつ客観的な選考プロセスを経ることが重要です。適性検査や複数回の面接、グループディスカッションなど、企業が定める選考基準に基づいて評価を行うことで、真に企業にマッチした人材を見極めることができます。紹介者への配慮は必要ですが、採用の質を担保することを最優先に考えるべきです。
採用実務に携わる方からも、リファラル採用であっても選考の厳格さは維持すべきという意見が聞かれます。紹介という特別なルートであっても、最終的には企業にとって最適な人材かどうかを見極める姿勢が欠かせません。
このバランスを保つことは容易ではありませんが、長期的な企業の成長を考えれば、適切な選考基準を維持することが、結果として紹介者にとっても良い結果をもたらすことになります。
③社員属性に偏りが出る
リファラル採用を進める上で、人材の多様性確保は常に意識すべき課題です。同じようなバックグラウンドや価値観を持つ人材ばかりが集まると、組織の硬直化につながる可能性があります。
人は自然と、自分と似た考え方や価値観を持つ人とつながりやすい傾向があります。そのため、社員や内定者が友人や知人を紹介する場合、同じ大学の出身者、同じサークルやゼミの仲間、似たような専攻分野の学生など、属性が偏る傾向が生じやすくなります。特に内定者からの紹介の場合、限られたコミュニティ内での紹介が中心となるため、この傾向はより顕著になります。
エンジニア採用に携わる方からも、リファラル採用における属性の偏りについて懸念する声が上がっています。同じ技術スタックや似た経験を持つ人材ばかりが集まることで、組織の視野が狭くなる可能性を指摘する意見もあります。
この課題に対処するためには、求める人物像を明確に定義し、多様な観点から評価できる基準を設けることが有効です。また、紹介を依頼する際に、「多様なバックグラウンドを持つ人材を求めている」というメッセージを明確に伝えることも、偏りを防ぐ一つの方法となります。
④紹介者にも配慮する必要がある
リファラル採用においては、候補者だけでなく、紹介者である社員や内定者への配慮も非常に重要な要素となります。紹介という行為には、紹介者の評判や人間関係が関わってくるため、通常の採用以上に慎重な対応が求められます。
最も配慮が必要となるのは、紹介した候補者が選考に落ちた場合です。紹介者は、自信を持って推薦した人物が不採用になることで、「自分の見る目がなかった」「会社に推薦したのに落とされて恥ずかしい」という思いを抱く可能性があります。また、候補者との関係においても、「せっかく紹介してもらったのに落ちた」という気まずさが生じることがあります。
こうした状況を避けるため、選考プロセスにおいては、紹介者と候補者の双方に対して、丁寧なコミュニケーションを心がける必要があります。不採用の場合は、その理由を可能な範囲で具体的に説明し、候補者の良かった点も併せて伝えることで、紹介者の自尊心に配慮します。「今回はご縁がなかったが、別の機会があれば」といった前向きなメッセージを添えることも有効です。
新卒のリファラル採用が上手くいく企業の特徴とは?

リファラル採用を導入しても、すべての企業で成功するわけではありません。特に新卒採用では、学生との接点や企業文化、社員構成などによって成果に差が出やすいのです。
リファラル採用が上手くいく企業には、共通していくつかの特徴があります。本章では、リファラル採用を成功に導く企業の特徴を具体的に解説します。
若手社員が多い
リファラル採用が新卒採用で成功しやすい企業の一つの特徴は、若手社員が多いことです。若手社員は同年代の学生との接点が多く、友人や後輩を紹介しやすい環境にあります。大学や専門学校の同期やサークル仲間など、自然なネットワークを活かして候補者を推薦できるため、リファラルの母集団形成がスムーズに進められるのです。
若手社員は入社間もない経験を持っているため、学生の目線に近く、応募を検討する際に具体的なアドバイスや職場のリアルな情報を提供できます。学生は企業理解を深めやすく、入社後のミスマッチを減らすことが可能です。
若手社員はSNSやオンラインコミュニティなどデジタルのツールに慣れていることが多く、遠方の学生や普段接点が少ない候補者にもアプローチできる点も強みです。このように、若手社員が多い企業では、自然な人脈やコミュニケーションのしやすさを活かして、リファラル採用を効果的に進めることができるのです。
自らアプローチする採用をしていない
もう一つの特徴は、企業が自発的に候補者にアプローチする採用活動を重視していないことです。従来型の新卒採用では、合同説明会や求人媒体、ナビサイトを中心に広く母集団を形成するスタイルが一般的です。しかし、この手法に依存していると、採用担当者や学生の負担が大きくなり、候補者との関係性を深める余裕がなくなります。
一方、リファラル採用を導入している企業では、社員が自らのネットワークを活用して候補者を推薦するため、企業から無理にアプローチする必要がありません。候補者は紹介者を通じて企業に接点を持つため、自然な形で応募が生まれやすく、採用プロセスもスムーズになるでしょう。
自発的な社員紹介を前提とした採用であれば、候補者の質やフィット感が高くなる傾向も見られます。紹介者が自分の経験や価値観をもとに推薦するため、企業文化や業務内容に適した学生が集まりやすく、入社後の活躍も期待できます。
このように、社員主体で候補者との接点を作れる企業ほど、リファラル採用が成功しやすいのです。
紹介したくなるような特徴がある
リファラル採用の成功は、社員や内定者が「友人や知人にぜひこの会社を紹介したい」と思えるかどうかにかかっています。企業自体が魅力的であることが、リファラル採用を機能させる最も重要な前提条件となります。
紹介したくなる企業の特徴として、まず挙げられるのは明確で共感できるビジョンやミッションを持っていることです。社員が自社の存在意義や社会的な価値を理解し、誇りに思える企業であれば、自然と周囲の人々にもその魅力を伝えたくなります。
次に、働きやすい職場環境が整っていることも重要な要素です。過度な長時間労働がない、有給休暇を取得しやすい、リモートワークなど柔軟な働き方が可能など、ワークライフバランスを保ちながら働ける環境は、社員にとって大きな魅力となります。自分自身が満足して働いている社員は、友人や知人にも自信を持って職場を勧めることができます。
成長機会が豊富で、キャリアパスが明確な企業も紹介されやすい傾向にあります。研修制度が充実している、挑戦の機会が与えられる、実力に応じた評価やキャリアアップが可能など、自己成長を実感できる環境は、特に若い世代にとって大きな訴求力を持ちます。
新卒リファラル採用を成功させるポイント

リファラル採用はメリットが大きい反面、運用方法を間違えると期待した成果が得られません。成功のポイントは、単に社員に紹介してもらうだけでなく、紹介制度やインセンティブの設計、社員への周知、候補者へのフォロー体制など、複数の要素をバランスよく整備することにあります。
本章では、リファラル採用を成功させるための具体的なポイントを解説します。
社員への周知を徹底する
リファラル採用の成功には、社員への周知が欠かせません。どれだけ魅力的な紹介制度やインセンティブを設けても、社員が内容を理解していなければ活用されず、候補者の母集団も広がりません。
周知のポイントは、制度の仕組みや目的、紹介方法を明確に伝えることです。社内メールやイントラネット、説明会など複数の方法で周知し、社員がいつでも情報を確認できる環境を整えることが重要です。
周知に加えて、社員が具体的に紹介しやすい工夫も必要です。候補者の紹介時に必要な書類やフォームを簡略化したり、FAQを用意して疑問を解消することで、社員の心理的ハードルを下げることができます。
周知と運用サポートを徹底することで、社員が主体的に紹介活動に関与しやすくなり、リファラル採用の成果を最大化することが可能になります。
理想の人材像を全社で共有しておく
リファラル採用において最も重要な準備の一つが、採用したい人材像の明確化と社内での共有です。紹介者が「どんな人を紹介すればいいのか」を正確に理解していなければ、効果的な紹介は期待できません。
人材像の定義は、単に「優秀な人」「頑張れる人」といった抽象的な表現では不十分です。より具体的に、求める能力、経験、価値観、性格特性などを明確にする必要があります。「主体的に課題を発見し、解決に向けて行動できる人」「多様な価値観を受け入れ、チームで協力して成果を出せる人」「新しいことに挑戦する意欲を持っている人」など、具体的な行動イメージが湧くような表現が効果的です。
必要なスキルや経験についても明確にすることが重要です。特定の専攻分野や技術スキルが必要な職種の場合、その要件を明示することで、適切な候補者の紹介につながります。一方で、スキルは入社後に習得できる場合は、むしろ人物面や姿勢を重視する方針を伝えることで、幅広い候補者の紹介が期待できます。
企業文化やチームの特性も共有しておくべき情報です。「当社はこんな価値観を大切にしている」「こんな働き方を推奨している」といった情報を伝えることで、紹介者は自分の知人の中から、文化的にマッチしそうな人を選定しやすくなります。単にスキルや能力だけでなく、価値観の適合性も考慮した紹介を促すことができます。
紹介制度の設計とインセンティブ設計を設ける
リファラル採用を成功させるためには、まず紹介制度の設計が重要です。社員が候補者を紹介しやすい仕組みを作ることで、自然と母集団が形成されます。具体的には、紹介フローの明確化や、推薦するタイミング、候補者の選定基準などを分かりやすく提示することが求められます。
加えて、インセンティブ設計も欠かせません。紹介者への報酬や評価ポイント、表彰制度などを設けることで、社員のモチベーションを高められます。
金銭的報酬だけでなく、キャリア評価や特別休暇など、多様な形で還元することで幅広い社員が参加しやすくなりますし、単発ではなく、継続的な制度として設計することがポイントです。
紹介制度とインセンティブの設計を丁寧に行うことで、社員が主体的にリファラル採用に参加でき、採用活動全体の効率化や成果向上に直結するのです。
面接で会社の理解度をしっかり確認する
リファラル採用で紹介された候補者に対しては、通常の選考以上に、企業理解度の確認を丁寧に行うことが重要です。紹介者から得た情報が正確かつ十分であるかを見極めることが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となります。
まず確認すべきは、候補者が紹介者からどのような情報を得ているかです。「紹介者からどんな話を聞きましたか」「当社のどんなところに魅力を感じていますか」といった質問を通じて、候補者が持っている企業イメージを把握します。この段階で、事実と異なる情報や、誇張された情報が伝わっていないかをチェックすることができます。
特に注意が必要なのは、入社間もない社員や内定者が紹介者となっている場合です。彼らは企業のことを十分に理解していない状態で、自分なりの解釈や期待を交えて情報を伝えている可能性があります。そのため、候補者が持っている情報と実際の状況とのギャップがないかを丁寧に確認し、必要に応じて正確な情報を提供する必要があります。
もし情報にズレや誤解があった場合は、その場で適切に修正することが重要です。ただし、候補者の期待を裏切るような形ではなく、「実際はこういう面もある」「このように理解してほしい」といった形で、前向きに正確な情報を伝える配慮が必要です。
候補者のフォローアップを充実させる
リファラル採用では、紹介された候補者へのフォローアップが非常に重要です。候補者は紹介者から企業情報を聞いているとはいえ、選考過程や入社前の不安を解消するためのサポートが不足すると、辞退や早期離職のリスクが高まります。
具体的には、候補者との定期的な連絡や質問対応、選考プロセスの進捗共有など、きめ細かいコミュニケーションを設計します。内定後も入社前研修やメンタリング制度を通じて、候補者が安心して入社できる環境を提供することが重要です。
候補者へのフォローアップ体制を充実させることは、リファラル採用の成果を最大化するための重要なポイントです。紹介者の信頼と企業側のサポートを両立させることで、入社後も定着率の高い新卒人材を採用できるのです。
新卒採用は複数のチャネル併用も有効!
新卒採用を成功させるためには、単一の採用手法だけに頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせることが効果的です。リファラル採用の強みを活かしながら、他の採用チャネルも戦略的に活用することで、より質の高い人材を効率的に獲得することが可能になります。
特に注目されているのが、ダイレクトリクルーティングとSNS採用という二つのアプローチです。ダイレクトリクルーティングは、企業側から積極的に候補者にアプローチする攻めの採用手法で、自社が求める人材に直接コンタクトを取ることができる点が大きな特徴です。
「RecUp」のようなサービスを活用することで、学生の プロフィールやスキルを確認しながら、ターゲットに合った学生にピンポイントでアプローチが可能になります。待ちの姿勢ではなく、能動的に理想の人材を探していく手法として、多くの企業が取り入れています。
一方、SNS採用は、企業の魅力を日常的に発信し、共感してくれる学生との接点を作る手法です。「RecBuzz」のようなサービスを活用すれば、企業の日常や社員の様子、プロジェクトの舞台裏など、求人サイトでは伝えきれない生の情報を継続的に発信できます。
新卒採用市場は年々変化しており、学生の情報収集方法や企業選びの基準も多様化しています。一つの手法だけに依存するのではなく、自社の状況や目標に合わせて最適な採用チャネルを組み合わせることが、これからの採用活動において重要な戦略となるでしょう。
リファラル採用とスカウト採用の違いは?それぞれの特徴と使い分けのポイント
【2025年最新】ダイレクトリクルーティングとは?新卒採用での活用方法とメリット・デメリット
新卒リファラル採用を自社に取り入れて、採用を活性化させよう

新卒リファラル採用は、従来の採用手法では難しかった効率的な母集団形成や選考コストの削減、入社後の定着率向上など、多くのメリットをもたらす有効な手法です。一方で、フォロー体制や社員への周知、紹介制度の設計など運用面の工夫が欠かせません。
導入にあたっては、社員のネットワークを活かした候補者紹介を促進しつつ、インセンティブやフォロー体制を整備することが成功の鍵です。候補者に対して丁寧なフォローアップを行い、入社前後のギャップを減らすことで、定着率の向上と長期的な戦力化も期待できます。
自社の特性に合わせたリファラル採用を戦略的に導入することで、新卒採用の効率化と質の向上を同時に実現できるでしょう。
リファラル採用だけに頼らず、スカウト業務を効率化したいのであれば「RecUp」によるAIスカウトサービスを利用するのがおすすめです。実績も豊富ですから、まずはお気軽にご相談ください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。