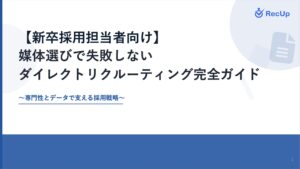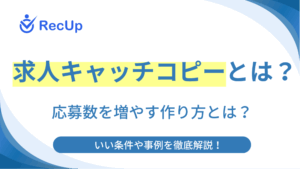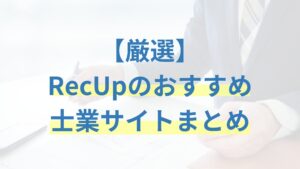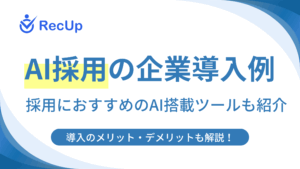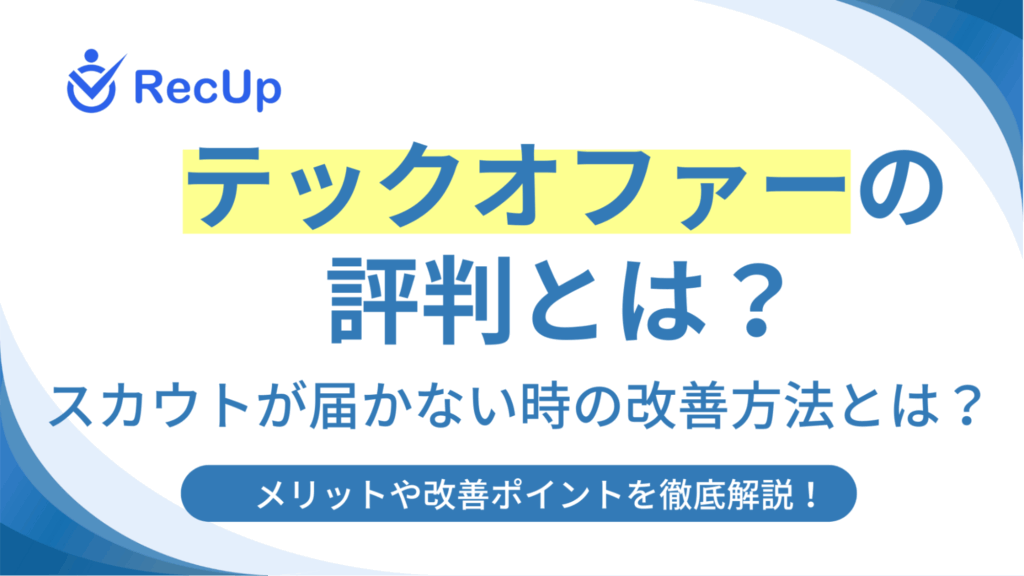
就活サービスの中でも注目を集めている「テックオファー(TECH OFFER)」は、ITエンジニアや理系学生に特化したスカウト型の新卒向け就活プラットフォームです。従来のように求人に応募して選考を待つのではなく、企業側から学生に直接オファーが届く仕組みが特徴といえます。
しかし、実際に利用を検討すると「本当に良い評判ばかりなのか?」「悪い口コミはないのか?」と気になる方も多いでしょう。そこで本記事では、テックオファーの基本情報から評判、メリット・デメリット、他社との比較、さらにはスカウトが届かないときに改善すべきポイントまで詳しく解説します。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
テックオファーとは?

テックオファー(TECH OFFER)は、理系学生やエンジニア志望の新卒向けに特化したスカウト型就活サービスです。従来の就活では、学生が求人情報を探して応募し、選考を受けるという流れが一般的でした。
テックオファーはその逆で、学生がプロフィールやスキルを登録すると、興味を持った企業から直接オファーが届く仕組みになっています。そのため、自分では出会えなかった企業や業界から声をかけてもらえるチャンスが広がるのです。
特に注目すべきは、AIがスキルや経験を分析して企業とのマッチングを最適化してくれる点です。プログラミング経験や研究テーマ、保有スキルを入力しておくと、企業が求める人材とマッチしやすくなり、効率的に就活を進められます。さらに「気になる」を送る機能もあり、学生側から企業にアプローチすることも可能です。
利用対象は主に理系やエンジニア志望の学生ですが、IT業界に強みを持つ企業が多く登録しているため、専門性を活かした就職を目指す方にとって有利な環境が整っています。スカウトを待つだけでなく、自己PRやスキルの入力次第でチャンスが広がるため、積極的に情報を充実させることが重要です。
テックオファーの評判は?実際に導入している企業の口コミを徹底解説!

テックオファーに関しては「効率的に就活できた」「企業とスムーズに出会えた」といった口コミが見られます。
ここでは実際の評判を解説していきます。
高スキル人材との獲得が実現した
ある企業では、テックオファーの導入により高スキル人材の獲得に成功しています。従来の採用手法では接点を持つことが難しかった、技術力の高い学生に対して直接アプローチできる点が大きなメリットとなりました。
この企業では、学生のスキルシートや開発経験を詳細に確認した上でスカウトを送信できるため、自社が求める技術要件にマッチした学生を効率的に見つけることが可能になりました。特にプログラミングスキルや開発実績を持つ学生に対して、具体的なプロジェクト内容や技術スタックを提示しながらアプローチできる点が評価されています。
実際の採用プロセスにおいても、事前に学生のスキルレベルを把握できているため、面接時の質問設計や選考フローの最適化につながったとのことです。結果として、従来よりも高い技術力を持つ人材の内定承諾を実現し、入社後の活躍も期待できる採用が行えたと報告されています。
さらに、スキルマッチングの精度が高いことで、学生側も自身の技術を評価してくれる企業として認識してくれるため、志望度の向上にもつながっているようです。技術力を重視した採用を行いたい企業にとって、テックオファーは有効なツールと言えるでしょう。
ナビサイトでは難しいスキルレベルの見極めが可能に。高スキルの人材獲得と同時にスカウト工数の削減も実現
ペルソナに近い学生の母集団形成に成功した
別の企業では、自社が求めるペルソナに近い学生の母集団形成に成功したという評価を得ています。テックオファーでは、学年や専攻、保有スキル、希望職種など多様な条件で学生を検索できるため、ターゲットを絞った効率的なアプローチが可能です。
この企業では、事前に採用したい学生のペルソナを明確に設定し、それに合致する条件で検索とスカウト送信を行いました。その結果、従来の採用手法では出会えなかった、自社の求める人物像に近い学生との接点を多数創出することができたとのことです。
特に評価されているのは、学生の詳細なプロフィール情報です。研究内容や使用している技術、開発したアプリケーションなどの情報が充実しているため、表面的なスペックだけでなく、学生の志向性や適性まで考慮した選定が行えます。
また、スカウト承認率も高く、送信したスカウトの多くが学生に興味を持ってもらえる結果となりました。これは、ターゲティングの精度が高いことで、学生にとっても自分に合った企業からのオファーとして受け取られているためと考えられます。母集団の量だけでなく質も重視したい企業にとって、有効な採用手法となっています。
カジュアル面談から本選考の参加率62.5%!大卒のエンジニア採用をTECH OFFERで初挑戦
データドリブンな採用ができた
テックオファーを導入したことで、データに基づいた採用活動が実現できたという評価もあります。管理画面では、スカウト送信数、承認率、返信率、面談設定率など、採用活動に関する様々なデータを可視化できるため、効果測定と改善を繰り返すことが可能です。
ある企業では、スカウト文面のA/Bテストを実施し、どのような訴求が学生に響くのかをデータで検証しました。その結果、技術環境の詳細を記載したスカウト文の方が承認率が高いことが判明し、以降のスカウト文を最適化することで全体の承認率向上につながったとのことです。
また、承認後の面談設定率や選考通過率なども追跡できるため、どの段階でどのような課題があるのかを定量的に把握できます。例えば、承認率は高いが面談設定率が低い場合は、初回のコミュニケーションに課題がある可能性があり、改善ポイントが明確になります。
さらに、採用チーム内で数値を共有することで、担当者による成果のばらつきを抑え、組織全体で採用力を向上させることができたという声もあります。勘や経験だけに頼らず、客観的なデータに基づいて採用戦略を立てられる点は、テックオファーの大きな強みと言えるでしょう。
地方中小企業で機械・電気電子系学生の採用に成功!採用過程をデータドリブンに可視化
理系学生への認知度が上がった
テックオファーの導入により、理系学生に対する企業認知度の向上を実感している企業もあります。特に知名度が高くない企業や、BtoB企業にとって、学生への認知拡大は採用活動における重要な課題の一つです。
この企業では、テックオファーを通じて継続的にスカウトを送信することで、理系学生コミュニティにおける自社の存在感を高めることに成功しました。スカウトを受け取った学生が、たとえその時点で選考に進まなくても、企業名を認識する機会となり、後の就職活動時に説明会への参加や選考への応募につながるケースが増えたとのことです。
また、テックオファーには学生同士の口コミやコミュニティがあり、良い体験をした学生が友人に紹介することで、間接的な認知拡大効果も期待できます。実際に「友人から聞いた」という理由で興味を持ってくれる学生もいたそうです。
さらに、スカウト文で自社の技術的な取り組みや開発環境を丁寧に説明することで、単なる求人情報ではなく、企業の技術力や文化を伝えるブランディングの場としても機能しています。理系学生に対する認知度向上と採用活動を同時に進められる点は、テックオファーならではの価値と言えます。
データコース採用過去最大の母集団形成に成功!データ人材・統計学人材のマッチングを実現
テックオファーが怪しいと言われる理由とは?
一部では「テックオファーは怪しい」という声も聞かれることがあります。この理由としては、主に以下のような点が考えられます。
まず、ダイレクトリクルーティングサービス全般に対する不信感です。学生にとって、突然企業からスカウトメッセージが届くことに対して、「本当に自分を評価してくれているのか」「誰にでも送っているのではないか」という疑念を持つケースがあります。一部の企業が適切なターゲティングをせずに大量のスカウトを送信していることが背景にあると考えられます。
次に、サービスの仕組みに対する理解不足も一因です。テックオファーは企業が学生のプロフィールを閲覧してスカウトを送るシステムですが、その仕組みを十分に理解していない学生からすると、どのように自分が選ばれたのか分からず、不安を感じることがあります。
新しいサービスであることから、実績や評判に関する情報が少なく、利用を躊躇する企業や学生がいることも事実です。特に保守的な業界や企業では、実績のあるサービスを優先する傾向があります。
しかし、これらの懸念は適切な運用によって解消できます。企業側が学生のプロフィールをしっかり確認し、個別性のあるスカウト文を作成すること、また学生側にサービスの仕組みを丁寧に説明することで、信頼関係を構築することが可能です。実際に適切に活用している企業では高い成果を上げており、「怪しい」という評価は当てはまらないと言えるでしょう。
テックオファーを導入するメリットを紹介!

採用活動の効率化や質の向上は、多くの企業が目指す目標です。しかし、従来の採用手法だけでは限界を感じている担当者も少なくありません。テックオファーの導入は、そうした課題を解決する一つの選択肢となります。
ここでは、テックオファーを導入することで得られる具体的なメリットについて解説します。リーチの拡大、効率化、工数削減という観点から、どのような価値が提供されるのかを見ていきましょう。
リーチが難しい学生ともマッチングすることができる
テックオファー最大のメリットの一つは、従来の採用手法ではリーチが難しかった学生層にアプローチできる点です。特に理系・情報系の優秀な学生は、就職活動においても選択肢が多く、一般的な求人媒体への登録や合同説明会への参加を積極的に行わないケースがあります。
このような学生は、研究室での活動や個人プロジェクトに注力しており、就職活動に割ける時間が限られています。しかし、自身のスキルや経験を評価してくれる企業からの直接的なアプローチには興味を示す傾向があります。
テックオファーでは、学生が登録したプロフィール情報をもとに、企業側から直接スカウトを送ることができます。これにより、就職サイトに頻繁にアクセスしない学生や、企業の説明会に参加する時間がない学生にも効果的にアプローチできます。
また、地方大学の学生や、専門性の高い研究をしている学生など、物理的・時間的な制約から都心の企業と接点を持ちにくい層にもリーチできる点は見逃せません。オンラインでのコミュニケーションが前提となっているため、地理的な制約を超えて全国の優秀な学生とマッチングすることが可能です。
母集団形成の効率化する
採用活動において、質の高い母集団をいかに効率的に形成できるかは、採用成功の鍵を握ります。テックオファーを活用することで、この母集団形成プロセスを大幅に効率化できます。
従来の採用手法では、説明会の開催や求人媒体への掲載を通じて、幅広く学生を集める必要がありました。しかし、この方法では自社に合わない学生も多数含まれてしまい、選考プロセスで多くの時間とリソースを消費することになります。
テックオファーでは、事前に学生のスキルや専攻、希望職種などの情報を確認した上でスカウトを送信できるため、最初から自社にマッチする可能性の高い学生だけを集めることができます。母集団の質が向上し、選考通過率や内定承諾率の向上にもつながる効果が期待できるというわけです。
検索条件を細かく設定できるため、採用ニーズに応じた柔軟な母集団形成が可能です。例えば、特定のプログラミング言語のスキルを持つ学生や、データサイエンスの研究をしている学生など、ピンポイントでターゲティングできます。
工数の削減ができる
採用活動には多くの時間と労力がかかります。特に採用担当者が少ない中小企業やスタートアップにとって、採用業務の工数削減は重要な課題です。テックオファーの導入により、この採用工数を大幅に削減することが可能です。
まず、説明会の開催や求人サイトの管理といった従来の採用活動に必要だった業務を削減できます。テックオファーでは、プラットフォーム上で学生とのコミュニケーションから面談設定まで完結できるため、複数のツールを使い分ける必要がありません。
学生のプロフィール情報が詳細に記載されているため、書類選考の時間を大幅に短縮できます。従来であれば履歴書やエントリーシートを一つ一つ確認する必要がありましたが、テックオファーでは事前に必要な情報を確認した上でスカウトを送るため、この工程を省略できます。
スカウト文のテンプレート機能や、一括送信機能を活用すれば、個別にメッセージを作成する手間を削減しつつ、一定のパーソナライズも実現できます。効率と質のバランスを取りながら、大量の学生にアプローチすることが可能です。
テックオファーの導入事例についても詳しく解説!

実際の導入効果を理解するには、具体的な事例を知ることが最も参考になります。ここでは、テックオファーを導入した企業の実績を、業界別に紹介します。
導入時期や承認数などの数値データとともに、どのような成果が得られたのかを見ていきましょう。
ITサービス業界(SES)
ITサービス業界のある企業では、2025年6月からテックオファーを導入し、短期間で成果を上げています。この企業は、エンジニアの派遣や技術支援を行うSES事業を展開しており、技術力のある若手人材の確保が経営上の重要課題でした。
導入初年度となる26卒採用では、51名の学生からスカウト承認を獲得しました。SES業界は一般的に学生からの認知度が低く、説明会への集客に苦戦するケースが多い中、この承認数は非常に高い成果と言えます。
さらに、27卒採用(大学3年生の9月時点)では、既に38名からの承認を得ており、前年を上回るペースで進んでいます。この企業では、スカウト文において具体的な技術スタックや、エンジニアとしてのキャリアパスを明確に提示することで、学生の不安を解消し、SES業界への理解を深める工夫をしています。
特に評価されているのは、学生の技術レベルに応じた丁寧なコミュニケーションです。プログラミング経験が浅い学生には研修制度の充実度を、既にスキルを持つ学生には参画できるプロジェクトの技術的な魅力を伝えるなど、個別対応を徹底しています。
この結果、従来は接点を持つことが難しかった技術志向の強い学生とのマッチングが実現し、採用の質も向上しているとのことです。
ITサービス業界(SIer)
大手クラウドインフラ企業も、2025年7月からテックオファーを本格導入し、目覚ましい成果を上げています。この企業は、クラウドサービスの構築・運用支援を行うSIer企業で、高度な技術力を持つエンジニアの採用を強化していました。
26卒採用では、281名という非常に多くの学生からスカウト承認を獲得し、そのうち1名が内定を承諾しました。母集団の規模としては非常に大きく、選考の選択肢が広がったことで、より自社にマッチした人材を選定できたとのことです。
27卒採用(大学3年生の9月時点)においても、既に124名から承認を得ており、2〜3名の内定承諾を予定しています。この企業の成功要因は、ターゲティングの精度の高さにあります。AWS、Azure、GCPなどのクラウド技術に興味を持つ学生や、インフラエンジニアを志望する学生に絞ってアプローチすることで、高い承認率と選考通過率を実現しています。
スカウト文では自社の技術的な強みや、大規模システムの構築に携われる点を具体的に説明したほか、承認後の面談では実際のエンジニアが技術的な質問に答える機会を設けることで、学生の志望度を高める工夫をしました。戦略的なアプローチにより、知名度だけに頼らない実力重視の採用を実現しているのです。
【数値付き】ダイレクトリクルーティングの事例集!自社のメリットや効果的に行う5つのポイントとは?
テックオファーの評判から見たおすすめできる企業とは?

ここまで、テックオファーの評判や具体的な導入事例を見てきました。しかし、すべての企業にとって最適なサービスとは限りません。
最後に、テックオファーの活用が特に効果的な企業と、逆におすすめできない企業の特徴について解説します。
テックオファーが効果的に活用できる企業
テックオファーの活用が特に推奨されるのは、以下のような特徴を持つ企業です。
まず、技術職の採用を強化したい企業です。エンジニア、データサイエンティスト、研究開発職など、専門的な技術スキルを持つ人材を求めている企業にとって、テックオファーは理想的なツールです。学生のスキルを詳細に確認した上でアプローチできるため、ミスマッチを防ぎながら効率的に採用活動を進められます。
次に、知名度が高くない企業や、BtoB企業です。学生への認知度が低い企業は、従来の採用手法では優秀な学生との接点を作ることが困難でした。しかし、テックオファーでは企業側から直接アプローチできるため、認知度に関わらず自社の魅力を伝える機会を創出できます。
採用工数を削減したい企業にも向いています。採用担当者が少ない、あるいは他の業務と兼務している場合、効率的な採用活動が求められます。テックオファーのプラットフォームを活用すれば、限られたリソースでも質の高い採用活動を実現できます。
さらに、データに基づいた採用改善を進めたい企業にもおすすめです。スカウト承認率や面談設定率などのデータを可視化できるため、PDCAサイクルを回しながら採用活動の質を継続的に向上させることが可能です。
テックオファーがおすすめできない企業
一方で、テックオファーの活用があまり推奨されないのは、以下のような企業です。
まず、非技術職のみの採用を行う企業です。テックオファーは理系・情報系学生に特化したサービスであるため、営業職や事務職、企画職のみを募集している企業にとっては、登録学生の層が合わない可能性があります。このような企業は、より幅広い学生が登録している総合型の採用サービスを検討すべきでしょう。
次に、即戦力の中途採用のみを行う企業です。テックオファーは新卒学生を対象としたサービスであるため、経験豊富なエンジニアを中途採用で確保したい企業には適していません。中途採用に特化した別のプラットフォームを利用する方が効果的です。
また、採用にリソースを割けない企業も注意が必要です。ダイレクトリクルーティングは、学生のプロフィール確認やスカウト文の作成、承認後のコミュニケーションなど、一定の工数が発生します。これらの業務に時間を割けない状況であれば、期待する成果を得ることは難しいでしょう。
さらに、大量採用を短期間で行いたい企業にも向いていない可能性があります。テックオファーは質の高いマッチングを重視したサービスであり、一度に数十名〜数百名規模の採用を行うには向いていません。大量採用が必要な場合は、合同説明会や求人媒体との併用を検討すべきです。
テックオファーを使うならAIスカウト・RecUp

RecUpは、AIを活用した新しい形のダイレクトリクルーティングサービスです。従来のように「企業が検索して候補者を探す」のではなく、候補者側が登録した情報をもとにAIが自動でマッチングを行い、相性の高い企業から効率的にスカウトが届く仕組みになっています。
プロフィール入力に時間をかけてもなかなかスカウトにつながらない…という課題を解消し、学歴・スキル・志向性などを踏まえた精度の高いレコメンドを受けられるのが特徴です。
さらに企業からのスカウトも一方的なアプローチではなく、候補者の希望や適性に寄り添った内容になるため、ミスマッチが起こりにくいのもメリットです。効率的に就職活動を進めたい学生や、企業との接点を増やしたい方は、ぜひ活用してみてください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。