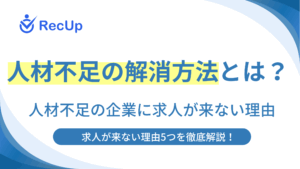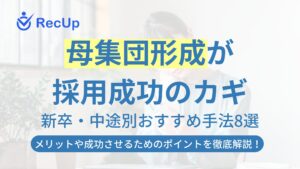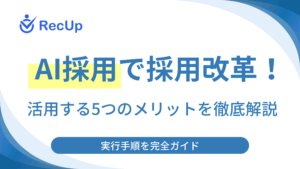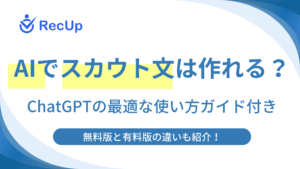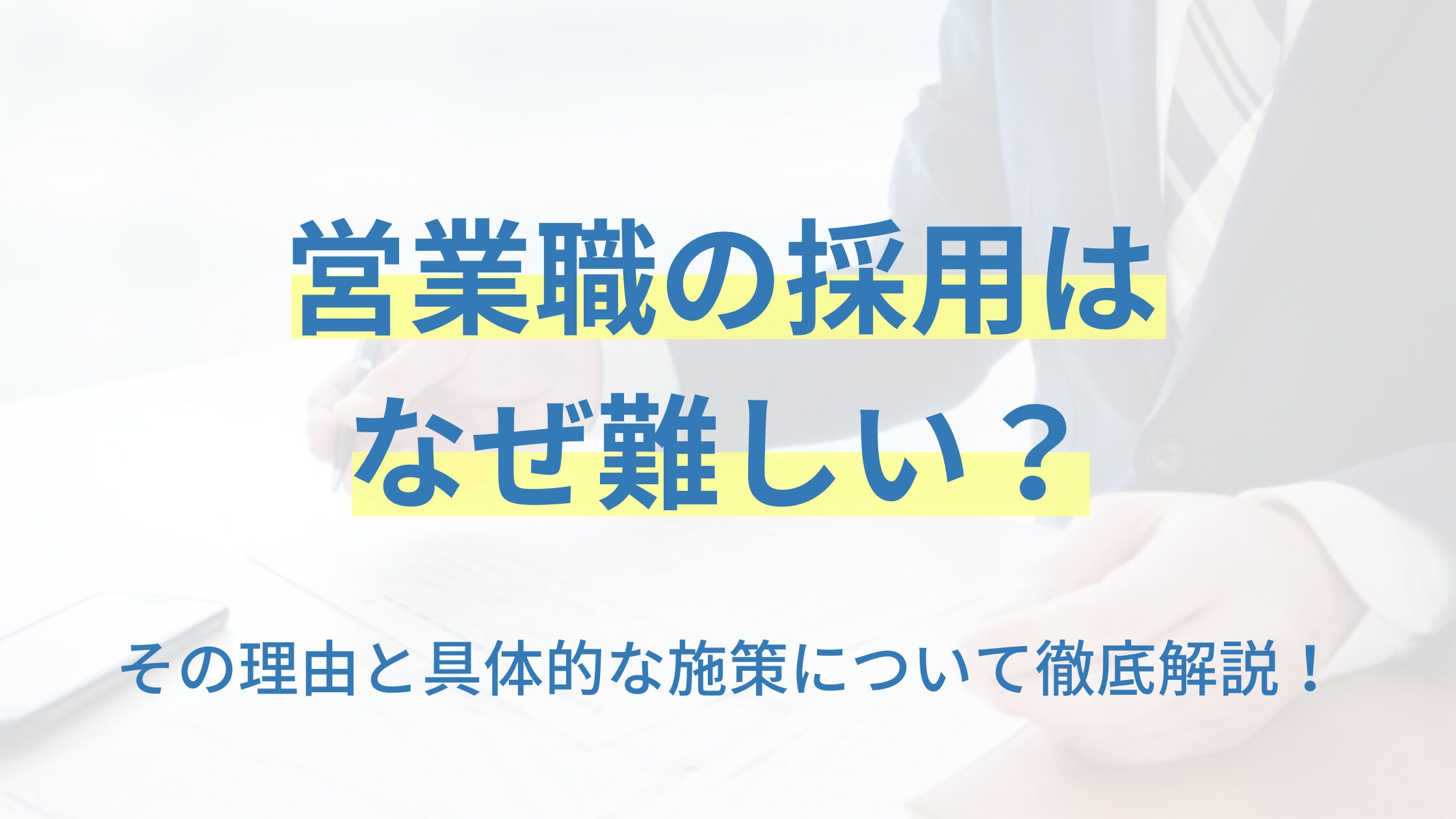
営業職の採用に悩む企業は少なくありません。どれだけ求人広告を出しても応募が集まらない、ようやく採用してもすぐに辞めてしまう、そんな声が多く聞かれます。
本記事では、採用が難しい理由と解決策を具体的に解説します。営業職の募集に応募がこない理由を深掘りし、現場の「あるある」から、見落としがちな課題まで丁寧に解説します。
応募を増やすための具体的な改善ポイントや最新の採用手法についてもご紹介しますので、ぜひ本記事を参考に、営業職の採用課題を根本から解決するヒントとしてご活用ください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
営業職の採用が難しいと言われている理由とは?
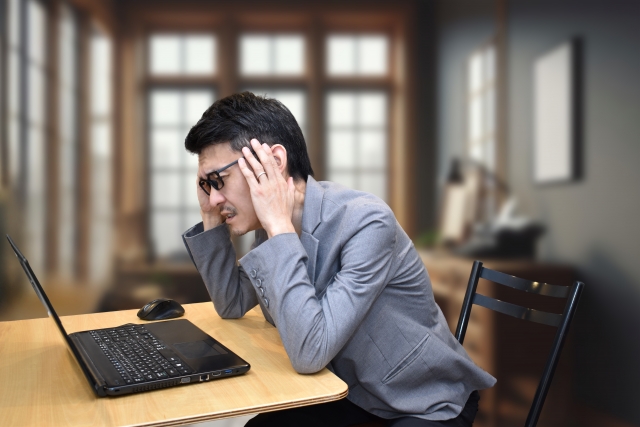
営業職の採用難は、決して最近始まった問題ではありません。しかし、近年はその傾向がより一層深刻化しています。なぜ営業職の採用がここまで難しくなっているのでしょうか。
その理由を把握することが、今後の採用成功につながります。ここでは、営業採用が難しいとされる背景について、3つの観点から整理していきます。
有効求人倍率が高いから
営業職は、有効求人倍率が常に高い水準で推移している職種の一つです。ハローワークのデータによると、営業関連職種の求人倍率は全職種平均を上回る傾向にあり、近年も比較的「売り手市場」が続いています。
求職者側にとっては選択肢が多く、企業は他社との競争にさらされることになります。また、コロナ禍以降、非対面営業やインサイドセールスなど新しい営業スタイルが浸透し、従来型営業から職種選択の幅が広がる傾向も見られます。
これがさらに採用難に拍車をかけています。企業側が人手不足を解消するためには、単に求人を出すだけではなく、求人内容や採用戦略を工夫する必要があります。従来のやり方では通用しなくなっているのが現実です。
営業人材の希少性が高いから
営業という仕事は、単にモノを売るだけでなく、相手の課題を見抜き、信頼関係を構築し、最終的に行動を促すという高度なコミュニケーション能力が求められます。そのため、誰もがすぐに成果を出せるわけではなく、経験や適性が大きく影響します。
特に「即戦力」として期待できる優秀な営業人材は、転職市場でも非常に人気があり、複数企業からのアプローチを受けていることが珍しくありません。そのような人材は、条件だけでなく、企業のビジョンやカルチャーも重視する傾向があり、採用側は戦略的にアプローチする必要があります。
このように、営業職においては「ただの人手」ではなく「成果を上げられる人材」を見極めて採用する必要があるため、難易度が非常に高くなっているのです。
採用ノウハウが不足しているから
営業職の採用がうまくいかない理由として、企業側に採用の知識やノウハウが不足していることも大きな要因です。とくに中小企業やベンチャー企業では、専任の人事担当者がいなかったり、営業経験者が採用に関わっていなかったりするケースも多く見受けられます。
その結果、求職者に対する訴求が的外れになったり、ミスマッチを招いたりする恐れがあります。また、選考スピードが遅かったり、面接内容が不明確だったりすることで、内定辞退につながるリスクもあります。
営業職を採用する際には、採用市場の動向を把握し、求職者目線のアプローチを徹底することが重要です。そのためには、現場の営業マネージャーと連携した採用設計や、競合他社の分析なども必要になってきます。
営業職を希望する人の特徴を解説!

営業職を目指す人材には、どのような傾向があるのでしょうか。ここでは、営業志望者の性格や動機、就職・転職時の価値観などに注目し、企業が採用時に意識しておくべきポイントを紹介します。
営業職に応募してくる人材は、自分の成果が数字で見える仕事にやりがいを感じるタイプが多い傾向があります。成果主義に魅力を感じる反面、ストレス耐性が問われる場面も多いため、精神的なタフさや自己管理能力が求められます。
また、近年では「人と話すことが好き」だけでなく、「課題解決を通じて顧客の信頼を得たい」という志向性の強い人も増えてきました。これにより、単なる営業力だけでなく、ロジカルな思考や分析力も重視されるようになっています。
一方で、働き方に対する意識は以前とは大きく変化しており、ワークライフバランスやリモート対応の可否なども、志望動機に大きく影響を与えています。企業は、そうした志望者の価値観を把握した上で、自社の強みをどのように訴求するかが重要です。
仕事にやりがいを感じたい
営業職を希望する人材の多くは、仕事を通じて達成感や成長実感を得たいという強い思いを持っています。数字という明確な指標で自分の成果が評価される営業職は、やりがいを求める人にとって魅力的な職種です。
目標を達成したときの喜びや、顧客から直接感謝の言葉をもらえる瞬間は、営業職ならではの醍醐味といえるでしょう。自分の努力が売上や契約という形で可視化されるため、成果と報酬の関係性が明確に理解できます。
また、営業活動を通じて幅広いビジネススキルが身につく点も、成長意欲の高い人材を惹きつける要因です。コミュニケーション能力や交渉力、課題解決力など、社会人として必要な能力を総合的に磨けます。
企業側は採用活動において、自社の営業職でどのようなやりがいが得られるのかを具体的に伝えることが重要です。成果に応じた評価制度や、キャリアアップの道筋を明示すれば、意欲的な人材からの応募を増やせるでしょう。
お客さんと接したい
対人コミュニケーションを重視する人材にとっても、営業職は理想的な職種といえます。デスクワーク中心の業務とは異なり、日々さまざまな顧客と接する機会があり、人間関係を構築する楽しさを味わえるからです。
顧客のニーズをヒアリングし、最適な提案を行う過程では、相手の立場に立って考える力が求められます。信頼関係を築きながら課題解決をサポートすることで、顧客満足度を高められるのです。
長期的な関係性を構築できれば、リピート受注や紹介案件にもつながっていきます。また、多様な業界や職種の人々と関わることで、視野が広がり人間的な成長も期待できます。
顧客との対話を通じて新しい価値観に触れたり、業界知識を深めたりする機会が豊富にあるでしょう。採用活動では、自社の営業スタイルにおいて顧客とどのような関わり方ができるのかを説明することが大切です。
新規開拓型なのかルート営業型なのか、BtoBかBtoCかによって、顧客との接し方は大きく異なります。求職者が求める顧客接点のスタイルと自社の営業手法がマッチすれば、採用成功率は高まるはずです。
チームワークを重視する
営業職は個人プレーのイメージが強いかもしれませんが、実際には チーム全体で目標達成を目指す協働作業の側面も大きい職種です。チームワークを大切にする人材にとって、仲間と切磋琢磨しながら成長できる環境は魅力的に映ります。
営業部門では、メンバー同士で成功事例やノウハウを共有することで、チーム全体のパフォーマンス向上につながります。経験豊富な先輩から学んだり、同僚と戦略を練ったりする機会は、個人の成長を加速させるでしょう。
また、他部署との連携も営業職には欠かせません。マーケティング部門と協力して効果的なプロモーションを展開したり、技術部門と連携して顧客の課題解決策を提案したりする場面が数多くあります。
組織横断的なコミュニケーションを通じて、一体感のある仕事ができるのです。採用においては、自社の営業組織がどのようなチーム体制で動いているのかを伝えることが重要になります。
定期的なミーティングや情報共有の仕組み、メンター制度の有無などを具体的に説明しましょう。協調性を重視する求職者に対して、チームで成果を追求する文化があることをアピールできれば、応募意欲を高められます。
営業採用が難しい場合の短期的な施策5選!

営業職の採用を成功させるためには、他社の成功事例から学ぶことも非常に有効です。自社だけで試行錯誤するのではなく、成果を上げた企業の取り組みを知ることで、新たな気づきや戦略が得られることもあります。
ここでは、実際に採用成果を出した5つの事例を取り上げながら、それぞれのポイントや工夫、採用活動に活かせるヒントについて詳しく解説していきます。
求人情報に十分な情報を掲載する
営業職と一口にいっても、求職者によって重視するポイントは異なります。たとえば、20代前半の若手はスキルアップや研修制度に関心があり、ミドル層は年収や裁量権を重視する傾向があります。
そのため、自社が求めるターゲット層に合わせて、求人原稿や面接での訴求ポイントを調整することが重要です。ペルソナを明確に定め、その層に刺さるキーワードや事例を盛り込むことで、応募意欲が高まります。
また、インセンティブ制度や成果が正当に評価される仕組みなども、営業職ならではの訴求ポイントです。あいまいな表現ではなく、具体的な数字や実績を提示することが説得力を高めます。
面接で魅力付けを行う
単なる仕事内容の説明ではなく、「なぜこの営業職が面白いのか」「どんな成長が得られるのか」を強調する説明会を実施することで、志望度の高い人材を惹きつけることができます。
とくに若手層にとっては、キャリアパスや実際の業務イメージが重要です。現場社員のリアルな声を交えたり、1日の流れや成長事例を映像で見せたりすることで、具体的なイメージを持ってもらえます。
参加型のワークショップや先輩社員との交流の場を設けることも、候補者との距離を縮める有効な方法です。応募前の段階でファンになってもらえれば、内定辞退の防止にもつながります。
選考フローを見直す
採用がうまくいかない場合、選考フローそのものに問題がある可能性を検討しましょう。各選考段階の目的が曖昧だったり、評価基準が統一されていなかったりすると、優秀な人材を見逃してしまうリスクがあります。
まずは現在の選考プロセスを可視化し、各段階で何を評価しているのかを明確にすることが大切です。書類選考では基本的な要件を確認し、一次面接ではコミュニケーション能力や営業適性を見極め、最終面接では企業文化とのマッチングを判断するといった具合に、段階ごとの役割を整理します。
また、面接官による評価のばらつきを防ぐため、評価シートの作成や面接官トレーニングの実施も効果的です。複数の面接官が同じ基準で候補者を評価できれば、選考の精度が向上するでしょう。選考フローの見直しによって、適切な人材を効率的に採用できる体制が整います。
競合調査を行う
まず実施すべきは、自社と同じ業界で営業職の採用に力を入れている企業の調査です。競合他社がどのような募集要項を掲げているのか、給与や待遇面、働き方の柔軟性にどれほどの差があるのかを知ることで、自社が改善すべきポイントが見えてきます。
また、競合が使っている採用媒体やSNSでの発信内容などを分析することで、求職者に響く表現のヒントも得られます。自社の魅力をどのように打ち出すかは、周囲の動きから学ぶことができるのです。
調査結果をもとに、自社の採用戦略をブラッシュアップすることで、求職者の関心を引く効果が期待できます。他社にない強みを明確に提示できれば、選ばれる理由をつくることが可能です。
採用手法を見直す・増やす
成果が出ていない採用活動を続けるよりも、思い切って採用方法自体を見直すことも選択肢です。たとえば、求人広告からダイレクトリクルーティングへの転換や、人材紹介会社の活用、採用コンサルタントの導入など、手段は多岐にわたります。
とくに、採用人数が多い場合や急募の場合は、外部の専門家と連携した方が効率的です。また、ATS(採用管理システム)などのテクノロジー導入によって、母集団形成から選考までのフローを可視化・改善することも可能です。
採用方法をアップデートすることで、これまで取りこぼしていた層へアプローチが届くようになり、新たな可能性が広がります。
中長期的に行いたい採用施策とは?

営業職の採用を成功させるには、目先の対策だけでなく中長期的な視点での施策が欠かせません。短期的な施策で応募者を集めても、根本的な課題が解決されていなければ、採用の難しさは続いてしまいます。
ここでは、採用活動を継続的に成功させるために取り組むべき中長期的な施策について解説していきます。企業の採用力を底上げし、優秀な営業人材を安定的に獲得するための方法を見ていきましょう。
慎重に採用基準を見直す
営業職の採用が難航している場合、採用基準そのものに問題がある可能性を検討する必要があります。理想とする人物像が市場に存在しないレベルまで高すぎたり、逆に基準が曖昧で選考軸がブレていたりすると、適切な人材を見極められません。
まずは現在の採用基準を明文化し、各項目が本当に必要なのかを精査していきましょう。例えば「5年以上の営業経験」という条件が絶対に必要なのか、それとも3年程度でも十分なスキルを持つ人材はいないかを検討します。
また、活躍している既存社員の特性を分析することも効果的です。実際に成果を上げている営業担当者に共通するスキルや性格特性を洗い出せば、より現実的で適切な採用基準を設定できるでしょう。
採用基準の見直しは一度で終わりではなく、定期的に行うことが重要になります。市場環境や事業戦略の変化に応じて、求める人物像も柔軟に調整していく姿勢が求められます。
採用後の定着率や活躍度合いを継続的にモニタリングし、採用基準の精度を高めていくことで、長期的な採用成功につながっていくのです。
営業未経験者の採用を検討
営業経験者だけをターゲットにしていると、限られた人材プールの中での競争が激化してしまいます。そこで中長期的な施策として、営業未経験者の採用を検討することが有効な選択肢となるでしょう。
未経験者を採用するメリットは、応募者の母数を大きく広げられる点にあります。他業種からの転職希望者や第二新卒など、営業職としてのポテンシャルを持つ人材は数多く存在しています。
これらの人材は営業経験者ほど高い給与を求めないケースも多く、採用コストの削減にもつながるでしょう。
ただし、未経験者を採用する場合は教育体制の整備が不可欠です。営業の基礎知識やスキルを体系的に学べる研修プログラムを用意し、OJTでのフォロー体制も構築しなければなりません。
メンター制度を導入して先輩社員がマンツーマンで指導する仕組みを作れば、未経験者でもスムーズに戦力化できます。未経験者採用では、営業適性を見極める選考方法の工夫も重要になります。
コミュニケーション能力や論理的思考力、ストレス耐性など、営業職として必要な素質を評価できる選考プロセスを設計しましょう。
ロールプレイング形式の面接や適性検査の活用も効果的です。長期的には、未経験者を自社で育成するノウハウが蓄積され、採用力そのものが向上していきます。
待遇改善や働き方の多様化を検討する
優秀な営業人材を継続的に獲得するには、待遇面や働き方の改善が欠かせません。特に近年は働き方に対する価値観が多様化しており、柔軟な勤務体制を求める求職者が増加しています。
給与体系の見直しでは、基本給と歩合給のバランスを再検討することが重要です。成果に応じたインセンティブ制度を充実させれば、高いモチベーションを持つ営業人材を惹きつけられるでしょう。
ただし、安定性を重視する求職者もいるため、過度に歩合給に偏らない設計が求められます。働き方の多様化としては、リモートワークやフレックスタイム制の導入を検討しましょう。
特に内勤業務が多い営業スタイルであれば、在宅勤務との相性も良好です。ワークライフバランスを重視する人材にとって、柔軟な働き方ができる環境は大きな魅力となります。
福利厚生の充実も見逃せないポイントです。育児や介護との両立支援制度、資格取得支援制度、健康管理サポートなど、従業員の生活全般を支える仕組みを整えることで、求職者からの評価が高まります。
これらの施策は実施後すぐに効果が出るわけではありませんが、企業の採用ブランディングを強化し、長期的な採用力向上に貢献していくでしょう。待遇改善によって既存社員の満足度も上がれば、離職率の低下や口コミでの応募増加といった副次的な効果も期待できます。
営業職採用に取り入れたい施策7選!

営業職の採用は、従来の手法だけでは思うような成果を得るのが難しい時代になってきました。求職者の価値観や働き方の多様化が進む中で、採用手法にも柔軟な対応が求められています。
そこで本章では、時代の流れに合わせて取り入れたい7つの最新採用施策をご紹介します。企業の規模や採用ニーズに応じて、どの施策をどう活用すべきかのヒントもあわせて解説します。
①人材紹介サービス
人材紹介会社を活用すれば、自社にマッチする人材を効率的に採用することができます。営業職専門の紹介サービスも多く、業界に詳しい担当者が求職者と企業のマッチングをサポートしてくれます。
紹介手数料が発生する点は注意が必要ですが、採用までのスピード感やミスマッチの少なさは大きなメリットです。特に採用の緊急度が高い場合や、社内に十分な採用リソースがない企業にとっては、非常に有効な手段といえます。
②リファラル採用
社員からの紹介によって候補者を募る「リファラル採用」は、ミスマッチが少なく、定着率の高い採用方法として注目されています。紹介者は自社のカルチャーや業務内容を理解しているため、適切な人材を推薦しやすいのです。
また、社員が自社に満足していなければ紹介はしづらいため、リファラル採用は社員満足度のバロメーターにもなります。成功率を高めるためには、紹介しやすい仕組みやインセンティブ制度を整えることがポイントです。
営業職は人脈が広いケースも多いため、社内の営業社員を巻き込んだリファラル採用は非常に効果的です。
③アルムナイ採用
過去に自社で勤務していた社員を再び採用する「アルムナイ採用」も、注目されている手法のひとつです。元社員は企業文化や業務フローをすでに理解しているため、再教育のコストが低く、即戦力としての期待も大きいです。
退職後も良好な関係を保ち、定期的に情報交換する「アルムナイネットワーク」を活用することで、将来的な採用母集団を維持できます。営業で成果を出していた人材を再びチームに迎え入れることで、組織の活性化にもつながります。
④ダイレクトリクルーティング
求職者からの応募を待つのではなく、企業側から直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」は、採用活動において主流になりつつあります。
特に営業職のように優秀人材の獲得競争が激しい領域では、この手法が有効です。LinkedInやビズリーチなどの転職プラットフォームを活用すれば、自社が求めるスキルや経験を持つ候補者にピンポイントでアプローチできます。
また、候補者と直接やり取りを行うことで、企業の魅力をダイレクトに伝えることも可能です。属人的な営業力を持つ人材は転職市場で目立ちやすいため、早期にアプローチし、選考へつなげることが採用成功へのカギになります。
以下の記事では、逆求人型サービス「オファーボックス」の特徴や評判、他のスカウトツールとの違いについて詳しく解説しています。スカウト型採用を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
【採用担当者向け】オファーボックスの評判・口コミを解説!比較・使えてない企業の特徴は?
⑤ヘッドハンティング
特定の業界で経験豊富なハイスキル営業人材を採用したい場合は、プロのヘッドハンターに依頼するのも一つの手です。
候補者の現在のポジションや転職意欲など、企業側では把握しづらい情報もキャッチしやすくなります。ヘッドハンティングはコストがかかる手法ですが、ピンポイントで狙った層へのアプローチが可能です。
とくにマネージャークラス以上の採用では有効な手段として導入が進んでいます。高単価・高成約率が期待される営業人材へのアクセスを広げたいときには、有力な選択肢です。
⑥紹介予定派遣
一定期間派遣として勤務してもらい、双方合意のもとで正社員化する「紹介予定派遣」は、ミスマッチを防ぎながら採用する手法です。実際に業務を体験してから正式に雇用契約を結ぶため、入社後の定着率が高くなります。
営業職は向き不向きが出やすいため、実際に仕事を通して適性を見ることができるこの方法は非常に相性が良いです。また、求職者側にとっても安心感があります。
⑦採用コンサルティング・業務代行を利用する
自社内で採用戦略の構築や運用が難しい場合には、外部の採用コンサルタントやRPO(採用業務代行)を利用することも検討すべきです。専門家による市場分析や選考設計により、より成果の出やすい採用活動が可能になります。
営業職に特化した採用支援サービスも存在しており、実績あるコンサルタントに依頼することで、短期間での採用成功も期待できます。忙しい営業マネージャーが採用活動に時間を割けない場合などに、有効なサポートとなります。
株式会社Delightで実際にやっている3つの営業職採用について

営業人材の獲得競争が激化する中、株式会社Delightでは複数の採用チャネルを組み合わせた戦略的なアプローチを展開しています。各手法には異なる特性があり、それぞれから集まる学生の傾向も大きく変わってくるものです。
ここでは、Delightが実践している3つの採用手法について、その特徴や集まる学生のタイプを詳しく解説します。採用成功の鍵は、各手法の強みを理解し、自社に最適な組み合わせを見つけることにあります。
① ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業側から学生に直接アプローチする採用手法です。従来の待ちの姿勢から脱却し、積極的に人材を探しに行くスタイルが特徴となっています。
この手法の最大のメリットは、企業側がターゲットを選定できる点にあります。自社が求めるスキルや経験を持つ学生を絞り込み、ピンポイントでアプローチできるため、効率的な母集団形成が可能です。
就職活動に対する意識が比較的高い学生とつながりやすく、早期段階から接点を持てる利点もあります。コスト面でも優位性があり、エージェントサービスと比較すると採用単価を抑えられる傾向にあります。
注意点として、エージェント経由と比べると、候補者情報が限られるためミスマッチのリスクもあることです。スカウト文面の工夫やフォロー体制の充実が成果に直結します。
② エージェント
人材紹介エージェント(以下、エージェント)を活用する方法は、第三者の専門家を介して学生とマッチングする採用手法です。
エージェントが学生の志向性を丁寧にヒアリングし、企業とのマッチングを図ってくれます。大きな利点として挙げられるのは、一定数の学生と効率的に面談できる点です。
エージェントが事前にスクリーニングを行い、企業の要件に合った学生を紹介してくれるため、マッチング精度が高まります。選考の初期段階で大きく絞り込む手間が省け、採用担当者の負担軽減につながるでしょう。
デメリットとしては、他の手法と比較して採用単価が高めになる点があります。成功報酬型が一般的であり、採用決定時に一定の費用が発生します。
エージェント経由で会える学生には、就活の進め方に不安を抱えている人や、第三者のサポートを求めている人が多く見られます。
③ SNS採用
SNSを活用した採用は、近年注目を集めている新しいアプローチです。InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などのプラットフォームを通じて、企業の魅力を発信し、学生との接点を作ります。
この手法の特徴は、就職活動の初期段階にいる学生や、まだ具体的に動き出していない超潜在層にもアプローチできる点です。会社の雰囲気や価値観をリアルに伝えやすいのも大きなメリットといえます。
社員の日常や職場の様子を写真や動画で発信すれば、テキストだけでは伝わりにくい企業文化を視覚的に訴求できるでしょう。
ただし、即効性は低い点に注意が必要です。SNSでの情報発信は継続的な取り組みが求められ、すぐに応募につながるわけではありません。一方で、ミスマッチは起きにくい特性があります。
応募数アップに繋がる魅力的な求人票作成のコツとは?

求人票は企業と求職者をつなぐ最初の接点であり、その質が応募数を大きく左右します。どれほど魅力的な職場環境や待遇を用意していても、求人票で適切に伝えられなければ応募には結びつきません。
ここでは、営業職の応募数を増やすために押さえるべき求人票作成のポイントを解説していきます。求職者目線に立った情報設計と、具体性のある記載内容が成功の鍵となります。
応募数を増やすための求人露出戦略
求人票の内容が優れていても、求職者の目に触れなければ意味がありません。まずは求人情報がしっかりと露出される仕組みを整えることが不可欠です。
求職者は検索機能を使って仕事を探すため、求人票には検索されやすいキーワードを適切に盛り込む必要があります。「法人営業」「ルート営業」といった職種の詳細や、「リモートワーク可能」などの働き方に関するワードを自然に含めましょう。
掲載する媒体の選択も露出戦略において重要な要素です。ターゲットとする人材がどの求人サイトを利用しているのかを把握し、適切なプラットフォームに求人を出稿します。
また、求人票の更新頻度も露出に影響するため、定期的に内容を見直して更新することで、常に新鮮な情報として求職者の目に留まりやすくなります。
詳細で具体的な仕事内容の記載
求人票における仕事内容の記載は、求職者が応募を決断する上で最も重視する項目の一つです。抽象的な表現ではなく、具体的なイメージが湧く記述を心がけましょう。
単に「営業職」と記載するのではなく、どのような商材を扱うのか、どんな顧客に対してアプローチするのかを明示します。
例えば「人材サービスの法人営業として、中小企業の経営者や人事担当者に対して採用課題のヒアリングと提案を行います」といった具合に、業務の全体像が伝わる書き方が効果的です。
一日の業務の流れを時系列で示すのも有効な手法となります。営業スタイルについても詳しく説明が必要です。新規開拓とルート営業の比率、テレアポの有無など、求職者が気になるポイントを明確にしましょう。
根拠を示した給与・年収例の記載
給与情報は求職者が最も注目する項目の一つですが、単に金額の幅を示すだけでは不十分です。具体的なモデルケースを示すことで、自分の場合どの程度の収入が見込めるのかを想像しやすくなります。
年齢や経験年数と紐づけた年収例を複数パターン提示しましょう。「28歳・入社3年目で年収450万円」「35歳・チームリーダーで年収600万円」といった具体例があれば、キャリアステップと収入の関係性が明確になります。
基本給と歩合給の内訳を明示することも大切です。営業職の場合、インセンティブ制度が設けられているケースが多いため、どのような条件で歩合が発生するのかを詳細に示しておくと、求職者もイメージしやすくなります。
賞与や各種手当についても忘れずに記載し、実際の手取り額を把握できるよう配慮しましょう。
検索結果画面での魅力的な訴求
求職者が求人サイトで検索を行うとき、最初に目にするのは検索結果一覧の画面です。この段階で興味を引かなければ、詳細ページを見てもらうことすらできません。
求人タイトルは最も重要な要素です。職種名だけでなく、自社の強みや魅力的なポイントを盛り込んだタイトルを設定しましょう。ただし、文字数制限がある場合が多いため、簡潔さと訴求力のバランスを取ることが求められます。
一覧画面に表示される企業ロゴや写真も重要な役割を果たします。視覚的な印象が応募意欲に大きく影響するため、プロフェッショナルで魅力的なビジュアル素材を用意しましょう。
求人サイトによっては、求人票の冒頭部分が検索結果に表示される場合もあるため、最も訴求したいポイントを厳選して記載することが大切です。
営業職採用で選考辞退・内定辞退を防ぐには

せっかく時間と労力をかけて選考を進めても、内定辞退や選考途中での離脱が続けば、採用活動そのものが無駄になってしまいます。特に営業職は、辞退や離脱が発生しやすい職種のひとつです。
だからこそ、応募者の気持ちや不安に寄り添った対応が求められます。ここでは、営業職の選考でありがちな辞退を防ぐために企業が実践すべき具体的な対策や工夫を、わかりやすく紹介します。
面接や合否連絡などのリードタイムを短くする
選考プロセスが長引くほど、候補者が他社に流れるリスクは高まります。優秀な営業人材ほど複数の企業から引く手あまたの状態であり、スピーディーな対応ができない企業は選ばれにくくなってしまうのです。
面接日程の調整は、候補者から応募があった時点で迅速に行いましょう。できれば応募から1週間以内に初回面接を設定するのが理想的です。日程調整の連絡が遅れると、それだけで候補者の志望度が下がってしまうこともあります。
合否連絡についても同様にスピードが重要です。面接実施後は遅くとも3営業日以内には結果を伝えるようにしましょう。待たされる期間が長いと、候補者は「自分は優先度が低いのではないか」と感じてしまいます。
選考の各段階でのリードタイムを短縮するには、社内の意思決定プロセスを見直す必要があります。面接官のスケジュールを事前に確保しておく、合否判断の権限を明確にしておくなど、組織としての体制を整えることが大切です。
ただし、スピードを重視しすぎて選考の質が下がってはいけません。迅速かつ丁寧な対応を心がけ、候補者に対する誠実な姿勢を示すことで、辞退リスクを効果的に低減できるでしょう。
必要書類や面接回数を減らす
選考プロセスが複雑すぎると、候補者の負担が大きくなり辞退につながりやすくなります。特に働きながら転職活動をしている求職者にとって、何度も時間を作って面接に参加するのは大きな負担です。
提出書類については本当に必要なものだけに絞り込みましょう。履歴書や職務経歴書は必須ですが、それ以外の書類が選考判断に活用されていないのであれば省略を検討すべきです。Webエントリーフォームの入力項目も最小限にとどめ、候補者のストレスを軽減します。
面接回数についても見直しが必要です。多くの企業では2〜3回の面接を実施していますが、各面接の目的が明確でない場合は統合できないか検討しましょう。例えば一次面接と二次面接で確認している内容が重複しているなら、1回にまとめられる可能性があります。
面接を効率化する方法として、オンライン面接の活用も効果的です。特に一次面接をオンラインで実施すれば、候補者の移動時間や交通費の負担を減らせます。遠方の求職者にとっては、応募のハードルが大きく下がるでしょう。
選考プロセスのスリム化は、採用担当者の業務負荷軽減にもつながります。効率的な選考フローを構築することで、より多くの候補者に対応できるようになり、採用活動全体の生産性が向上するのです。
社内見学や既存社員への質疑応答などを行なう
応募者にとって、入社後の働く環境がイメージできるかどうかは、入社意思決定に直結する要素です。社内の雰囲気やメンバーとの相性を感じ取れる機会を提供することは、内定承諾率の向上につながります。
たとえば、オフィス見学や営業現場の同席体験、先輩社員とのカジュアル面談など、選考の合間にリアルな接点を設けることが効果的です。こうした機会を通じて、不安の払拭やカルチャーマッチの確認ができると、入社後のミスマッチも防ぎやすくなります。
まとめ

営業職の採用には、求人倍率の高さ、優秀人材の希少性、企業側のノウハウ不足といった多くの課題が存在します。しかし、それらの課題も、戦略的な採用施策と最新ツールの導入によって解決することが可能です。
なかでも注目されているのが、AIを活用したスカウトサービス「RecUp(リクアップ)」です。RecUpは、営業職に特化したスカウトを可能にしており、精度の高い候補者リストの生成と、応募意欲を高めるスカウトメールの自動送信を実現します。営業職採用において最も重要とされる「スピード」と「精度」を両立できるのが、RecUpの強みです。
営業職採用に苦戦している企業様は、ぜひRecUpの導入をご検討ください。また、以下の記事では、RecUpの主な機能や導入メリット、他社ツールとの違いなどを徹底比較しています。
【2025年最新】AIスカウトサービス15選を徹底比較!メリットや選ぶ際のポイントを解説
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。