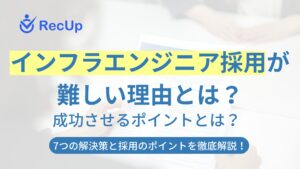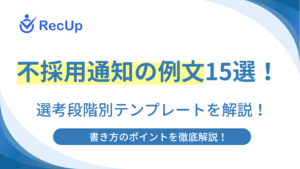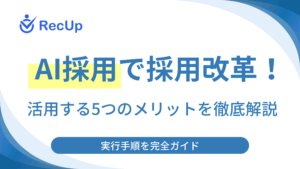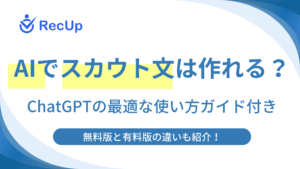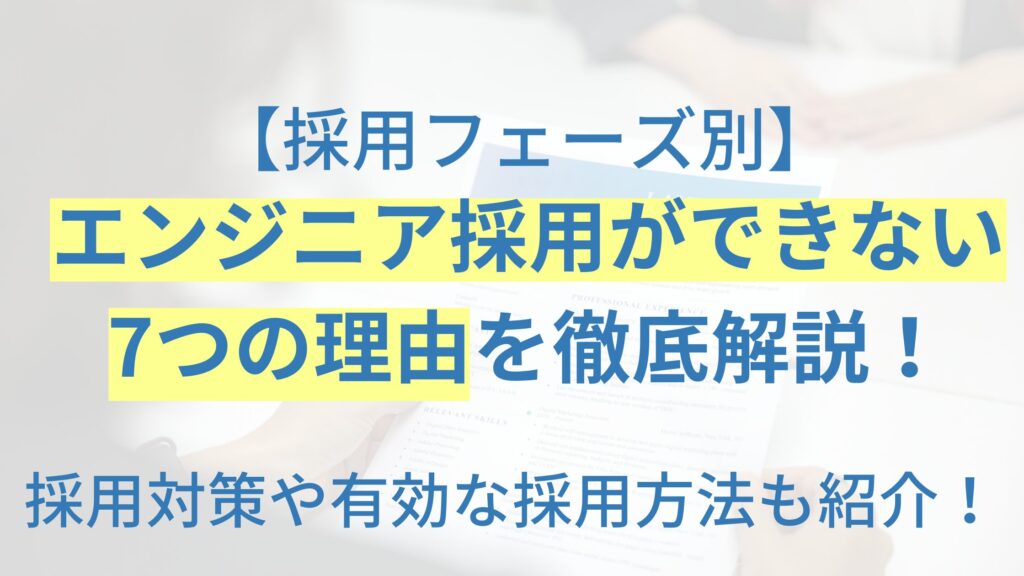
多くの企業がエンジニアの採用に課題を抱えており、「募集を出しても応募がない」「内定辞退が続く」などの声が絶えません。
技術職の需要は年々高まり続ける一方で、採用競争も激化しています。本記事では、エンジニアを採用できない企業が直面している主な原因や課題を洗い出し、採用成功のための具体策を徹底解説します。
さらに、効果的な採用手法として注目されている「RecUp」の活用方法もご紹介しますので、エンジニア採用に本気で取り組みたい方はぜひご一読ください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
エンジニアを採用できない7つの理由とは?

エンジニアの採用ができないという時には、現状を正しく理解し、改善していくことが重要です。しかし、うまくいかない理由には、社会的な情勢や企業側の採用活動における認識や戦略のズレなど複数の要因が関連していることもあり、非常に複雑化しています。
そこで、この章では、エンジニアの採用に失敗する主な要因を5つに分類して解説していきます。
②IT技術の変化が激しい
IT業界における技術の進化スピードは非常に速く、5年前に主流だった技術が今では使われなくなっているケースも珍しくありません。このような環境変化の中で、企業側が最新の技術トレンドに対応できていないことが、エンジニア採用の大きな障壁となっています。
技術志向の強いエンジニアにとって、「どのような環境で働けるのか」「どんなスキルを身につけられるのか」は、職場選びにおいて最も重視する要素のひとつです。そのため、求人票に記載されている開発環境や使用技術が古いままだと、優秀なエンジニアほど応募を見送ってしまう傾向があります。
例えば、求人票に時代遅れのツールや古い技術ばかりが並んでいたり、具体的な開発環境の記載がなかったりすると、「技術に関心がない企業」と見なされてしまいます。また、面接の場で現場の技術スタックについて質問された際、明確に答えられないと、候補者からの信頼を失う原因にもなります。
技術変化への対応が遅れている企業は、エンジニアから「成長できない職場」と評価されやすく、結果として候補者から選ばれにくくなってしまいます。最新技術を積極的に取り入れる姿勢や、学習機会の提供など、技術への投資を惜しまない企業文化を築くことが求められています。
③優秀なエンジニアが転職しにくい環境
優秀なエンジニアほど、現在の職場で重要なポジションを任されていたり、手厚い待遇を受けていたりするケースが多く、転職に対して慎重な姿勢を取る傾向があります。また、スキルの高いエンジニアは複数のプロジェクトに関わっていることも多く、簡単には抜けられない状況にあります。
現職での評価が高いエンジニアは、給与面や福利厚生で既に満足している場合が多く、新しい環境に移るメリットを感じにくい状況にあります。転職を検討する際には、「今の環境を捨ててまで移る価値があるか」という視点で慎重に判断するため、企業側から見ると採用のハードルが高くなります。
優秀なエンジニアは社内での信頼も厚く、上司や同僚からの引き留めにあうことも少なくありません。チームの中核を担っている場合、退職が決まると業務の引き継ぎにも時間がかかり、実際の転職時期が先延ばしになることもあります。
このように、能力の高いエンジニアほど転職市場に出てきにくい構造があるため、企業側は受け身の採用活動だけでなく、積極的なアプローチが必要になります。ダイレクトリクルーティングやスカウト型の採用手法を活用し、転職を具体的に考えていない層にも魅力を伝えていく工夫が求められています。
④フリーランスや副業など多様な働き方の選択肢拡大
近年、働き方の多様化が進み、エンジニアの間でもフリーランスや副業といった選択肢が広がっています。特にスキルの高いエンジニアにとって、フリーランスとして働くことで収入アップや自由な働き方を実現できるケースが増加しており、正社員としての採用が難しくなっている背景があります。
フリーランスエンジニアは、複数のプロジェクトを掛け持ちすることで収入を増やせるだけでなく、働く時間や場所を自由に選べるメリットがあります。クラウドソーシングサービスやエージェントを通じて案件を獲得しやすい環境が整ってきたことも、フリーランスという働き方を後押ししています。
副業に関しても、多くの企業が副業を解禁する流れが加速しており、正社員として働きながら別の仕事でスキルを磨いたり、収入源を複数持ったりするエンジニアが増えています。このような働き方を経験すると、一つの企業に縛られることに抵抗を感じるようになり、正社員としての転職に対する意欲が低下する傾向があります。
企業側としては、こうした働き方の変化を理解し、正社員採用にこだわらず、業務委託や契約社員といった柔軟な雇用形態も視野に入れることが必要です。副業を認める、リモートワークを推進するなど、多様な働き方に対応できる制度を整えることで、優秀なエンジニアを惹きつけやすくなります。
⑤企業の提示条件がエンジニアの期待に応えられていない
選考が順調に進んでも、最終的に給与や働き方などの条件面で折り合いがつかず、辞退されてしまうケースは少なくありません。特にエンジニアは、自身のスキルレベルに見合った報酬が得られるかどうか、リモートワークやフレックス制度が整っているかなどを重視する傾向が強いです。
給与水準が市場相場と比べて低い場合や、柔軟な働き方ができない環境では、それだけで候補補から外れてしまいます。また、企業が求めるスキルセットが過剰で、条件に対して現実味がない場合も、候補者の不信感を招く要因となります。
たとえば「年収400万円でGoやKubernetes、Reactまで全部扱える人材を募集」といった現実離れした要件を掲げてしまうと、優秀な人材ほど「この企業は市場を理解していない」と感じて敬遠してしまいます。
入社後の成長機会やキャリアパスについて明確に示せていないと、「長期的に働く意味が見えない」と判断されることもあります。エンジニアは技術力の向上やキャリアの発展を重視するため、単に業務をこなすだけの環境では満足できません。
こうした条件面の不一致を防ぐには、求人票や面談の段階で信頼感と納得感を丁寧に伝えることが重要です。エンジニアの視点に立った制度設計と、対話を重視した面接対応によって、条件面でのミスマッチを最小限に抑えることができます。
⑥採用チャネルや手法が難しくなっている
近年の採用市場では、求人広告や人材紹介だけでなく、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、SNS経由のスカウトなど、採用チャネルが非常に多様化しています。これにより、どのチャネルをどう使うべきか、どこにどれだけリソースを割けばいいのか、判断が難しくなっているのが実情です。
エンジニアの場合は、転職サイトに登録していないことも多く、Qiita、GitHub、X(旧Twitter)など技術系コミュニティでの接点が重要になるケースもありますが、多くの企業がそうした新しいチャネルに対応しきれておらず、優秀な人材と出会うチャンスを逃しています。
複数チャネルを同時に活用するには、戦略的な設計と綿密な運用が求められます。例えば、求人広告で母集団を広げつつ、スカウトでピンポイントにアプローチし、リファラルで信頼性の高い紹介を得るというような「組み合わせ」が必要ですが、それぞれのチャネルの特性を理解していなければ効果は現れず、コストばかりが膨らんでしまうことも珍しくありません。
⑦候補者に情報を届けられていない
求人を出しても応募がまったく来ない…。そんな状況に直面する企業は少なくありません。この背景には、単なる「人手不足」だけでなく、企業の情報がそもそも候補者に届いていないという根本的な問題があります。
また、求人票の内容が抽象的だったり、魅力が伝わりづらかったりすることで、候補者に「自分に合っているのか分からない」「この会社で働くメリットが見えない」と判断され、応募の意思が生まれないこともあります。
さらに、求人掲載媒体やSNS活用の選定ミスも見落とせません。エンジニアが普段から利用しているコミュニティやメディアに求人できていないと、どれだけ良い条件でも応募にはつながりません。「見つけてもらう」「知ってもらう」努力が、採用成功の第一歩なのです。
AIスカウトサービス「RecUp(リクアップ)」とは?サービスの特徴と導入事例を徹底解説!
エンジニアを採用できない企業が抱えるフェーズごとの課題とその解決策を徹底解説!
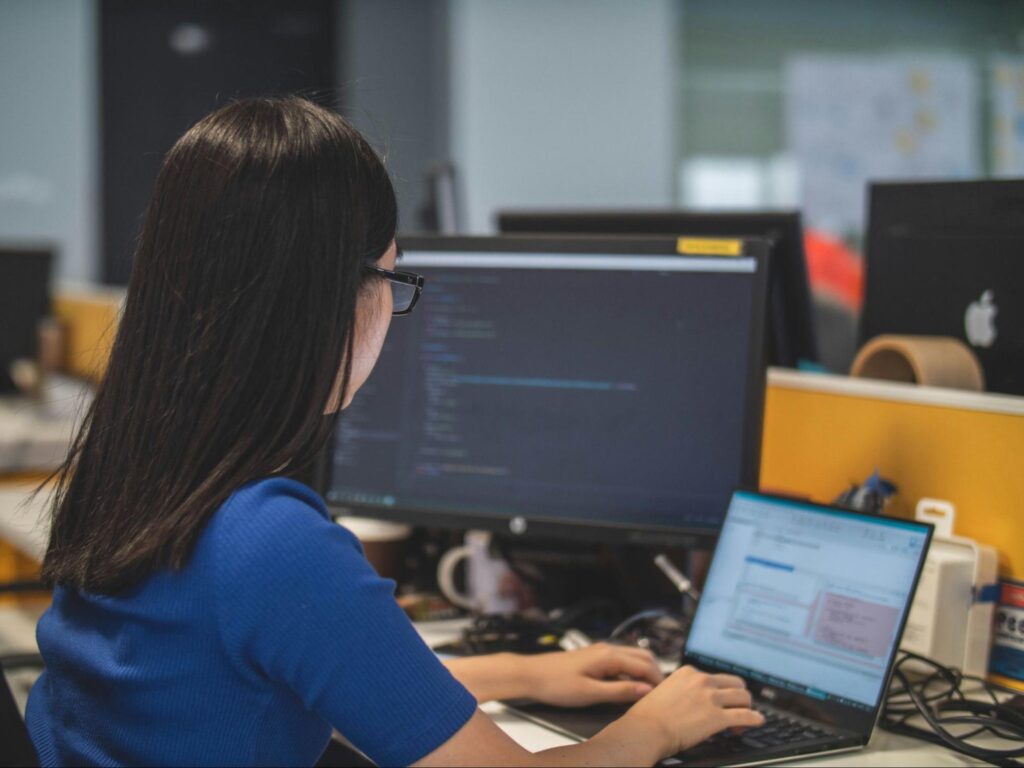
エンジニアの採用がなかなかできない企業には、共通するつまずきポイントが存在します。採用チャネルの選定だけでなく、選考基準の設定や内定後のフォロー、入社後のサポートなど、採用プロセス全体にさまざまな課題が潜んでいるのです。
この章では、応募から定着までの各段階でよく見られる代表的な4つの課題を取り上げ、それぞれがどのように採用の失敗につながるのかを詳しく解説します。
応募数が集まらない
エンジニア採用において、まず最初に直面するのが「そもそも応募が来ない」という課題です。求人を出しているにもかかわらず、応募者がほとんど集まらない状況は、採用活動の出発点で躓いている状態と言えます。
応募数が少ない原因は様々ですが、主に「企業の魅力が伝わっていない」「求人の露出が不足している」「ターゲットとなる人材に届いていない」といった点が挙げられます。特にエンジニア採用では、技術的な環境や成長機会について具体的に示せていないと、興味を持ってもらうことすら難しくなります。
こうした状況を改善するには、まず自社の魅力を明確に言語化し、適切な方法で発信していくことが必要です。以下では、応募数を増やすための具体的な施策について解説します。
エンジニア採用が難しい理由と解決策|効率的な方法やポイントを紹介
採用の本気度を伝えて応募数を増やす
企業として「本気でエンジニアを採用したい」という姿勢を明確に示すことが、応募数を増やす第一歩となります。候補者は、企業がどれだけ自分に関心を持ち、どれほど熱意を持って迎え入れようとしているかを敏感に感じ取ります。
特に効果的なのが、スカウトメールを活用したアプローチです。一般的な求人広告と異なり、スカウトメールは候補者一人ひとりに対して個別にメッセージを送る手法のため、「あなたに来てほしい」という企業の本気度が直接伝わります。候補者のプロフィールやスキルに言及した上で、なぜその人が必要なのか、どんな役割を期待しているのかを具体的に伝えることで、返信率は大きく向上します。
選考中のコミュニケーションも重要で、機械的なやり取りではなく、「あなたの強みをどう活かせるか」「どんな未来を一緒に描けるか」といった対話を心がけることで、企業の本気度が伝わります。積極的な姿勢は、採用活動そのものの質を高め、エンジニアからの信頼を得やすくなるでしょう。
採用チャネルを最適化して効率的に母集団を形成する
現在の採用市場では、採用チャネルの選定が成果に直結します。求人広告、人材紹介、スカウト、リファラル、イベント参加など、様々な手法が存在する中で、自社に合った方法を見極め、効果的に使い分けることが求められます。
たとえば、求人広告は母集団形成に優れる一方で、スキルマッチの精度が低くなりがちです。一方、スカウト型のダイレクトリクルーティングは、求める人材にピンポイントでアプローチできる反面、手間と時間がかかります。人材紹介は即戦力人材とのマッチングに強みがありますが、コストが高くなる傾向があります。
ここで重要なのは、「一つの手法に偏らず、複数のチャネルを戦略的に組み合わせる」ことです。求人広告で広く集めながら、スカウトで狙い撃ちし、リファラルで質の高い人材を紹介してもらう、というようなバランスの取れた施策が効果を発揮します。
具体的な施策としては、以下のような組み合わせが有効です。
- 求人媒体への掲載で認知度を高めつつ、ビズリーチやWantedlyなどのスカウト媒体で能動的にアプローチ
- 社員紹介制度を整備し、リファラル採用を推進
- 技術イベントやミートアップに参加し、エンジニアコミュニティとの接点を作る
各チャネルの特性を理解し、自社のフェーズや採用ターゲットに応じて最適な組み合わせを見つけることが、効率的な母集団形成につながります。
ペルソナを明確化して反応率を高める
なんとなく「経験者がほしい」と考えて求人を出していては、誰の心にも刺さりません。採用活動を効果的に行うには、「どんな人に来てほしいのか」を明確にすることが欠かせません。これが「採用ペルソナ」の設計です。
年齢や経験年数、スキルセットだけでなく、価値観や働き方の志向、理想のキャリア像までを言語化することで、より精度の高いメッセージ設計や媒体選定が可能になります。
例えば、「30代前半でフロントエンドが得意な人」と漠然と設定するのではなく、「Vue.jsに強く、チームでの開発経験が豊富。育児中でもフルリモートで働ける環境を重視している」といった具合に、具体的な人物像を描くことがポイントです。このように詳細にペルソナを設定することで、求人票の文言やスカウトメールの内容も、その人物に響くトーンや言葉選びができるようになります。
さらに、ペルソナが定まれば、SNSの投稿内容や求人票のタイトル・本文も、その人物に届くようなコミュニケーション設計ができます。結果として、応募の質が上がり、選考プロセスもスムーズに進みやすくなります。
エンジニア採用の成功は、「誰を採るか」ではなく「誰に響かせるか」の勝負でもあります。だからこそ、ペルソナ設計はすべての施策の土台になる重要な工程なのです。ペルソナに基づいた一貫性のあるメッセージを発信し続けることで、ターゲットとなる人材からの反応率を大きく向上させることができます。
求人内容を強化して応募したくなる募集にする
採用成功のカギを握るのが「求人内容」の作り込みです。ただの募集要項ではなく、「読み手の心を動かす求人」を作れているかどうかが問われます。
エンジニア向けの求人では、単に仕事内容やスキル要件を羅列するだけでなく、「開発環境」「使用している技術」「どんなチーム体制か」など、具体性のある情報を盛り込むことが重要です。例えば、「React、TypeScriptを使用したモダンなフロントエンド開発」「GitHub Actionsによる自動デプロイ環境」といった技術的な詳細を示すことで、エンジニアは入社後の業務をイメージしやすくなります。
また、「なぜこのポジションが必要なのか」「どんな未来を一緒に作っていきたいのか」といったビジョンや想いも伝えることで、エンジニアの共感を得やすくなります。単なる人員補充ではなく、事業成長における重要な役割であることを示すことが大切です。
加えて、求人票には人間味も必要です。社員インタビューやチーム紹介の文章、オフィスや開発風景の写真などを入れることで、会社の雰囲気が伝わりやすくなり、応募のハードルが下がります。「どんな人と働けるのか」が見える求人は、候補者の安心感を高め、応募意欲を引き出す効果があります。
書類・面接通過率が低い
応募は集まっているものの、書類選考や面接での通過率が低い場合、選考プロセスに何らかの問題がある可能性があります。特にエンジニア採用では、技術的なスキルの見極めが難しく、適切な評価ができていないケースが多く見られます。
通過率の低さは、単に候補者の質の問題だけでなく、企業側の選考体制や評価基準に課題があることも少なくありません。現場との連携不足や、採用担当者の技術理解不足などが、適切な人材の見極めを妨げている可能性があります。
以下では、書類・面接通過率を改善するための具体的な施策について解説します。
現場連携を強化してミスマッチを解消する
エンジニア採用において、現場との連携は極めて重要です。人事部門だけで採用を進めてしまうと、実際の業務内容や求めるスキルレベルとのギャップが生まれ、ミスマッチを招きやすくなります。
現場との連携を強化するには、まず「どんな人物が欲しいのか」を採用要件として一緒にすり合わせることがスタートです。どのようなプロジェクトに携わるのか、使用する技術は何か、どのくらいの経験が必要なのかなどを、実務レベルで整理することで、採用活動の精度が大きく向上します。
採用要件を決める際には、現場のエンジニアリーダーやマネージャーに参加してもらい、「本当に必要なスキル」と「入社後に学べるスキル」を明確に区別することが大切です。すべてのスキルを最初から求めるのではなく、コアとなる技術力とポテンシャルを見極める視点を持つことで、候補者の幅が広がります。
さらに、面接にも現場メンバーを積極的に同席させることで、候補者にとっても「誰と働くのか」が見えるようになり、入社後のイメージがしやすくなります。技術面接では、実際のコードレビューや簡単な課題を通じて、候補者の思考プロセスやコミュニケーション能力を確認することも効果的です。
技術理解を深めて適切にスキルを見極める
人事担当者がエンジニア採用において信頼を得るためには、一定の技術知識を持っていることが大切です。
もちろん、エンジニア並みのスキルを習得する必要はありません。ただし、「その職種でどんなスキルが求められるか」「技術トレンドにどう変化があるのか」などの基礎知識を持つことは、候補者と同じ目線で会話をするうえで不可欠です。技術用語の意味や、開発手法の違いなどを理解しているだけでも、面接の質は大きく変わります。
おすすめは、社内のエンジニアと定期的に1on1を行い、現場の技術について聞いたり、実際の開発環境を見学させてもらったりすることです。また、無料で学べる技術用語解説サイトやIT業界ニュースを日常的にチェックするだけでも、大きな差が出ます。
技術理解を深めることで、履歴書や職務経歴書に書かれている内容の価値を正しく評価できるようになります。例えば、「Reactの経験3年」と書かれていても、個人開発なのかチーム開発なのか、どの程度の規模のプロジェクトなのかによって、スキルレベルは大きく異なります。こうした違いを見抜くためには、ある程度の技術知識が必要です。
要件を最適化して通過率を改善する
採用要件を絞りすぎることは、候補者の母数を大きく狭めてしまう原因になります。特にエンジニアのように、スキルの幅が広く進化も早い職種では、「○○の経験が3年以上」「××の資格必須」などと条件を厳しくしすぎると、優秀な人材との出会いの機会を逃してしまいます。
求めるスキルや経験を明確にすることは大切ですが、「絶対に必要な要件」と「あると望ましい要件」を分けて整理し、柔軟に対応できる余地を持たせることが重要です。例えば、特定のプログラミング言語の経験は必須でも、フレームワークについては入社後に学べる環境があれば、経験がなくても採用を検討するといった考え方です。
また、若手層やポテンシャル採用を視野に入れることで、長期的に活躍できる人材を育てるという考え方も必要です。「今すぐ即戦力」だけでなく、「成長しながら戦力になる人」を受け入れる姿勢は、採用活動における視野を大きく広げてくれます。
要件の最適化にあたっては、以下のような視点を持つことが有効です。
- 技術スタックについては、類似の経験でも可とする
- 業界経験よりも、問題解決能力やコミュニケーション力を重視する
- 年齢や勤続年数などの形式的な条件を排除する
こうした柔軟な姿勢により、より多くの優秀な候補者と出会える可能性が広がり、結果として通過率の改善にもつながります。
内定辞退率が高い
選考を無事に通過し、内定を出したにもかかわらず、最終的に辞退されてしまうケースは、採用活動において最も避けたい事態の一つです。内定辞退は、それまでの選考にかけた時間やコストが無駄になるだけでなく、採用計画全体に影響を及ぼします。
内定辞退が起こる主な原因は、「他社との比較で劣っている」「入社への不安が解消されていない」「志望度が十分に高まっていない」といった点にあります。特にエンジニアは複数社から内定を得ることが多いため、最終的な意思決定の段階で、企業間の比較が厳しく行われます。
以下では、内定辞退率を下げるための具体的な施策について解説します。
キャリア支援を打ち出して志望度を高める
候補者が最終的に入社を決めるかどうかは、「この会社で働きたい」と思えるだけの動機づけができているかどうかにかかっています。
動機づけを高めるためには、選考過程で候補者のキャリアや価値観にしっかり耳を傾け、それに対して企業側が「あなたの目指すキャリアを、うちでこう支援できる」と具体的に返すことが大切です。単に業務内容を説明するだけでなく、入社後のキャリアパスや成長機会について、実例を交えて伝えることで、候補者は自分の将来像を描きやすくなります。
例えば、「入社後1年で○○のプロジェクトに携わり、3年後にはリーダーとして△△のような役割を担ってもらいたい」といった具体的なビジョンを示すことで、候補者の期待感は大きく高まります。また、既存社員のキャリア事例を紹介することも効果的です。
さらに、現場エンジニアとのカジュアル面談や、会社の取り組みを紹介するイベント、社内ブログや技術noteなどを活用して、候補者にリアルな職場の魅力を伝える工夫も効果的です。選考を「ジャッジする場」ではなく、「共感を生む対話の場」に変えることが、動機づけにおいて非常に重要です。
選考スピードを上げて他社流出を防ぐ
採用におけるスピード感は、採れるかどうかの分かれ道です。特にエンジニアのような売り手市場では、少しの遅れが命取りになります。書類選考から面接、内定までに1〜2週間以上かかっているようでは、他社に先を越されてしまう可能性が高いです。
選考を迅速化するためには、まずフローの見直しが必要です。「面接が3回もある」「合否連絡が遅い」などのプロセスを短縮・簡略化することで、候補者のストレスを減らし、他社との差別化ができます。例えば、1次面接と2次面接を同日に実施する、書類選考の合否を24時間以内に連絡するといった工夫が有効です。
さらに、候補者との面接日程調整にもスピード感が求められます。自動日程調整ツールを導入するなど、効率的な運用を取り入れることで、全体の採用リードタイムを短縮できます。候補者から希望日時を提示されたら、可能な限りその希望に沿うよう調整することも重要です。
早く動ける企業こそ、優秀な人材を確保できる可能性が高くなるのです。選考スピードは企業の本気度を示す指標でもあり、迅速な対応が候補者の志望度を高める効果もあります。
外部パートナーを活用して採用力を補強する
すべての採用活動を自社内だけで完結させるのは限界があります。特に採用の知見が少ない、社内リソースが不足している、難易度の高いポジションを採用したいといったケースでは、外部のプロフェッショナルに支援を依頼することも有効です。
たとえば、人材紹介会社を活用することで、特定スキルを持ったエンジニアに効率的にリーチできます。また、採用代行(RPO)サービスを利用すれば、求人票の作成からスカウト送信、日程調整、候補者管理までを専門家に任せることができ、採用工数を大幅に削減できます。
最近では、ダイレクトリクルーティングやスカウト業務を代行してくれるツールやエージェントも登場しており、「時間はないけど良い人に出会いたい」という企業にとって強力な武器となっています。特にエンジニア採用に特化したサービスを選ぶことで、より精度の高いマッチングが期待できます。
外部パートナーを活用する際のポイントは、丸投げにせず、自社の採用要件や文化を丁寧に伝え、協力しながら進めることです。適切なパートナー選びと連携により、採用活動の質とスピードを同時に向上させることができます。
手厚いフォローで内定辞退を防ぐ
内定後のフォローは、採用成功の最終ステップです。ここをおろそかにすると、せっかく出した内定が辞退されてしまう恐れがあります。エンジニアは転職先に慎重な判断を下すことが多く、内定をもらっても「本当にこの会社でいいのか?」と迷うケースは少なくありません。
そのため、内定承諾を得るには「安心感」と「納得感」の提供が重要です。内定通知と同時に、ポジションの役割、入社後のミッション、キャリアパスの提示などを丁寧に行い、「ここで活躍できるイメージ」が具体的に伝わるようにしましょう。書面だけでなく、面談の場を設けて直接話すことで、候補者の不安や疑問に答えることも大切です。
また、内定から入社までの期間も重要な接点です。Slackや社内イベントへの招待、先輩エンジニアとの交流などを通じて、入社前から社内の空気に慣れてもらう工夫が大切です。定期的な連絡や、技術書のプレゼント、歓迎メッセージなど、細やかな配慮が候補者の心を掴みます。
こうした取り組みは、エンジニアが安心して入社を決める後押しとなり、定着率の向上にもつながります。内定者フォローは単なる事務手続きではなく、入社後の活躍を左右する重要なプロセスと捉えるべきです。
すぐに離職してしまう
せっかく採用に成功しても、入社後すぐに離職されてしまっては意味がありません。早期離職は、採用コストの損失だけでなく、チームの士気低下や業務の停滞など、様々な影響をもたらします。
エンジニアの早期離職が起こる主な原因は、「入社前の期待と現実のギャップ」「働く環境への不満」「成長機会の不足」などです。特に、選考時に伝えられた情報と実際の業務内容が異なっていたり、評価制度が不明瞭だったりすると、エンジニアは早い段階で転職を考え始めます。
早期離職を防ぐには、採用段階でのミスマッチ防止に加えて、入社後の受け入れ体制やフォロー体制を整えることが不可欠です。また、働きやすい環境づくりや、適切な評価・育成の仕組みも重要になります。
以下では、早期離職を防ぐための具体的な施策について解説します。
制度を整備して働きやすさを向上させる
優秀なエンジニアほど、働きやすさや安心して力を発揮できる環境を重視します。どれだけ魅力的な仕事でも、制度が整っていなければ長く働く意欲は持てません。そのため、採用活動と並行して「制度面の整備」は必須です。
とくに重視されるのが、評価制度、労働条件、福利厚生、働き方の柔軟性などです。例えば、成果主義といっても明確な基準がなく、評価が属人的である場合には、エンジニアは「正当に評価されない」と感じてしまいます。評価基準を明確にし、定期的なフィードバックの機会を設けることで、エンジニアは自分の成長を実感しやすくなります。
働き方の柔軟性も重要なポイントです。リモートワークやフレックスタイム制度を導入することで、ライフスタイルに合わせた働き方が可能になり、離職率の低下につながります。また、技術書の購入補助やカンファレンス参加支援など、スキルアップを支援する制度も、エンジニアの満足度を高める要素となります。
そのため、制度整備では「制度があるかどうか」だけでなく、「それが運用されているか」「現場に浸透しているか」を重視すべきです。あわせて、制度の内容を求人票や面接で具体的に伝えることで、候補者の安心感や納得度を高めることができます。
メンター制度で早期離職の不安を解決する
新入社員が入社後に感じる不安や孤独感は、早期離職の大きな要因となります。特にエンジニアは、技術的な相談相手や業務の進め方について教えてくれる人がいないと、すぐに行き詰まってしまいます。こうした課題を解決するのが「メンター制度」です。
メンター制度とは、新入社員一人ひとりに対して、先輩社員がメンターとして付き、業務面だけでなく精神面でもサポートする仕組みです。定期的な1on1ミーティングを通じて、困っていることや不安に思っていることを相談できる環境を作ることで、新入社員は安心して業務に取り組めます。
メンターは、技術的な質問に答えるだけでなく、社内の文化や暗黙のルールを教えたり、キャリア相談に乗ったりする役割も担います。年齢やポジションが近い先輩をメンターに選ぶことで、新入社員は気軽に相談しやすくなります。
また、メンター側にとっても、後輩を育成することで自身のマネジメントスキルを磨く機会となり、組織全体の成長につながります。メンター制度を効果的に運用するには、メンター向けの研修を実施することや、メンターの負担が過大にならないよう配慮することも大切です。
技術スタックの定期的な見直しと適切な評価を行う
エンジニアは常に新しい技術を学び、スキルを向上させたいと考えています。しかし、会社で使用している技術が古いままだったり、新しい技術を導入する機会がなかったりすると、成長の実感が得られず、離職を考え始めます。
そのため、技術スタックの定期的な見直しを行い、必要に応じて新しい技術を導入することが重要です。ただし、やみくもに最新技術を追いかけるのではなく、事業の成長や開発効率の向上につながる技術を選定することが大切です。技術選定にはエンジニアの意見を積極的に取り入れ、現場の声を反映させることで、モチベーションの向上にもつながります。
エンジニアの技術力向上を適切に評価する仕組みも必要です。新しい技術の習得や、難易度の高い課題の解決などを正当に評価し、昇給や昇進に反映させることで、エンジニアは「この会社で頑張る価値がある」と感じられます。
社内勉強会や技術共有会を定期的に開催することで、エンジニア同士が学び合える環境を作ることも効果的です。こうした取り組みにより、技術的な成長を実感できる職場文化が育ち、長期的な定着につながります。
エンジニアの採用する方法とは?

ここまで、エンジニア採用ができない理由や具体的な対策を紹介してきました。ここからは、実際に「どうやってエンジニアを採用するか?」という手法ごとの特徴や活用ポイントについて詳しく解説します。
求人広告や人材紹介、リファラル、ダイレクトスカウトといった基本的な手法から、近年注目を集めるAIによるスカウト自動化まで、状況に応じて使い分けることで、採用活動の質とスピードは大きく変わります。ぜひ今の自社にぴったりの方法を選ぶ参考にしてみてください。
人材紹介
人材紹介は、専門エージェントを介して候補者を紹介してもらう採用手法です。求人要件に合った人材を探してもらえるため、「ミスマッチを減らしたい」「即戦力がほしい」と考える企業に向いています。
紹介会社は転職希望者と面談を行い、企業のカルチャーや要望に合う候補者をマッチングするので、自社にマッチした人材に出会いやすいというメリットがあります。また、選考から内定後のフォローまで一貫してサポートしてくれるため、採用リソースが限られている企業でも安心して任せられます。
一方で、成果報酬型のため費用は高めで、年収の30〜35%程度が一般的です。費用対効果を見極めつつ、信頼できるエージェントをパートナーとして選ぶことが大切です。特に、エンジニア採用に強い紹介会社を選べば、業界知識が深く、より的確なマッチングが期待できます。
求人広告
求人広告は、多くの候補者にアプローチできる“母集団形成”に優れた手法です。リクナビNEXTやGreen、Wantedlyなど、エンジニア向けの求人媒体に掲載することで、自社に興味を持ってくれる人材を広く集めることができます。自社の魅力をしっかり伝えれば、潜在層からの応募も期待できる点が魅力です。
ただし、掲載して終わりでは効果は出ません。ターゲットに刺さる求人原稿を作り、会社のビジョンやプロダクトの魅力、開発環境などを丁寧に伝えることが重要です。
反応が鈍い場合は、掲載する媒体や文面の改善、キャンペーン施策の活用などを行いながら、PDCAを回していくことも大切です。費用は比較的抑えやすいですが、「応募数は多くても通過率が低い」とならないように、しっかりとしたペルソナ設計と魅力の言語化がカギになります。
ダイレクト採用
ダイレクト採用とは、企業が求職者に対して自らアプローチする手法です。スカウト型採用とも呼ばれ、「欲しい人材に直接アプローチできる」ことが最大の特徴です。
スキルや経験、志向性などからマッチしそうな人材を自社で探し、スカウトメールやSNS、ポートフォリオサイトなどを通じて声をかけます。
この手法は、自社に本当に合う人材をピンポイントで狙える反面、人的リソースと時間がかかるというデメリットがあります。候補者に刺さるメッセージの作成、反応をもらうためのタイミング、温度感の見極めなど、ある程度のノウハウも必要です。
ただ、うまく活用すれば、転職潜在層にアプローチでき、他社との競合前に接点を持てるという強みがあります。また、AIスカウトサービスや採用代行を利用することで、業務負荷を抑えながら運用することも可能です。
リファラル採用
リファラル採用は、既存社員からの紹介で人材を採用する方法です。紹介者が社内の文化や業務を理解しているため、マッチ度が高く、定着率も良好になりやすいのが大きな特長です。コストを抑えながら質の高い採用ができる点で、近年ますます注目されています。
社員紹介制度をうまく設計すれば、採用チャネルの一つとして非常に強力です。たとえば、「紹介成功でインセンティブ支給」や「紹介者と候補者両方への感謝ギフト」など、紹介を促す仕組みをつくることで、社内に自然と“採用協力”の意識が生まれます。
ただし、制度だけを作っても社員が協力してくれるとは限りません。「誰を紹介すればいいのか」「どんなスキル・人柄が求められているのか」を具体的に共有し、社員にも採用の目的やメリットを理解してもらう必要があります。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、企業側から候補者に直接アプローチする採用手法です。従来の「応募を待つ」スタイルとは異なり、企業が能動的に人材を探し、スカウトすることで、優秀なエンジニアとの接点を作ります。
この手法の最大のメリットは、転職市場に積極的に出ていない「潜在層」にもアプローチできる点です。優秀なエンジニアほど現職で満足していることが多く、自ら求人を探していないケースが多いため、企業側からアプローチすることで、これまで出会えなかった人材との接点が生まれます。
そんなダイレクトリクルーティングの世界で近年注目を集めているのが「AIスカウト採用」です。従来、人事が手動で行っていたスカウト送信や候補者の選定をAIが自動で実行することで、作業の効率化と精度の向上を同時に実現します。
エンジニア採用に特化したサービス「RecUp」では、求人内容とマッチした人材に対し、AIが自動でスカウトを実行します。しかも、ただ機械的に送るのではなく、最適な文面・タイミングを判断してくれるため、スカウト返信率が大幅に向上する事例も報告されています。
人事のリソースが限られている企業や、スカウトに不慣れな企業にとって、AIスカウト採用は非常に有効な手段です。スピード感のあるアプローチが求められる今、こうしたテクノロジーを活用することが、採用競争を勝ち抜くポイントになります。
AI採用ツールの機能や最新トレンド、導入メリットについて解説
AIスカウトサービス「RecUp」でエンジニア採用を効率的に!

本記事では、エンジニア採用が上手くできない原因と解決策について解説しました。「どう動けばいいか分からない」「採用にかけられる時間がない」という企業も多いはず。そんなときに頼れるのが、エンジニア採用支援に特化したAIスカウトサービス「RecUp」です。
RecUpは、AIが自動で候補者を分析し、最適なタイミングと内容でスカウトを送ってくれる革新的なスカウトサービスです。人的工数を削減しつつ、ターゲット人材にしっかり届くアプローチが可能になります。
さらに、採用戦略の設計から運用支援、スカウト文面の改善提案までをワンストップで提供してくれるので、初めてのエンジニア採用にも安心して活用できます。
採用に悩む企業様にとって、RecUpは「採用成功に最短距離で近づける」パートナーです。エンジニア採用の第一歩に、ぜひRecUpをご活用ください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。