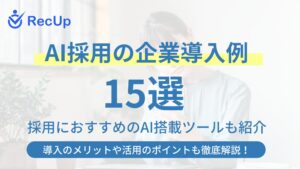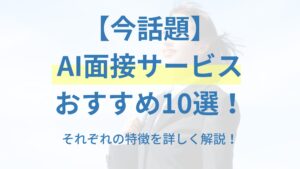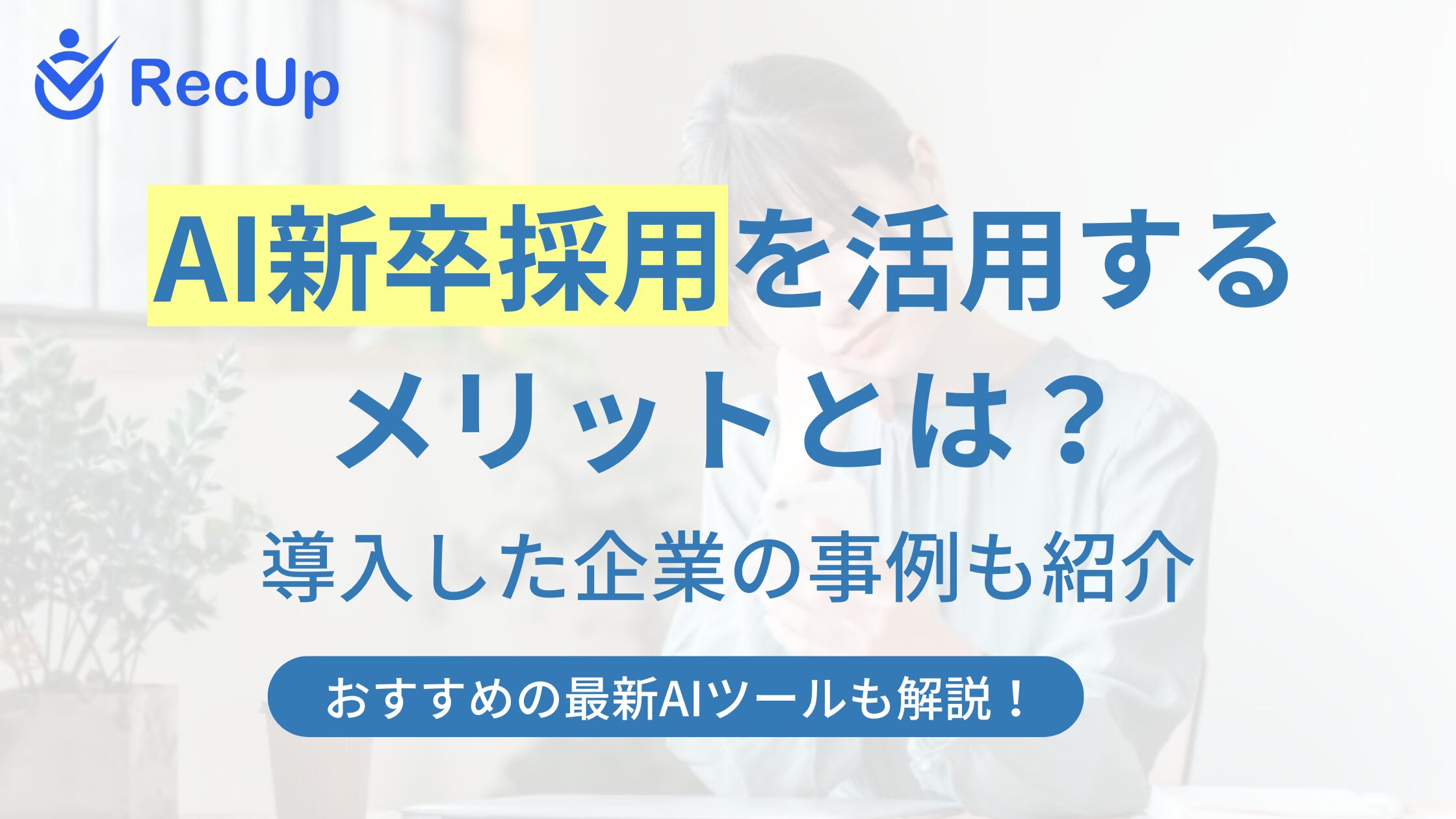
近年、さまざまな分野で活用が進んでいる生成AIですが、企業の採用活動でも導入が加速しています。急速な勢いで企業に普及しているAIは、採用活動において今後もさらに広まることが想定されるでしょう。
一方で、「採用にAIを利用したいと思っていても、具体的にどう利用してよいかわからない」「導入したけれど、思ったより成果が出ない」と悩みを抱えている企業は多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、生成AIを採用に活用するメリットデメリットや、効果的に使うためのポイントをわかりやすく解説します。おすすめのAIツールも紹介しますので、この機会に参考にしてみてください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
新卒採用でAIを活用する方法とは?

新卒採用の現場では、応募者数の増加や人材の多様化により、採用業務の負担が年々増しています。限られた人員で質の高い採用活動を実現するためには、業務の効率化が欠かせません。AI技術は単なる業務の自動化ツールではなく、採用の質を高めながら担当者の負担を軽減する強力なパートナーとなります。
従来は人の手で行っていた候補者のスクリーニングや面接の評価、学生とのコミュニケーションなど、様々な場面でAIの導入が進んでいます。ここでは新卒採用で実際に活用されているAIツールの種類と、それぞれの具体的な活用方法についてご説明します。
AIスカウトサービス
AIスカウトサービスは、求める人材要件に合った学生を自動で抽出し、一人ひとりに最適化されたスカウト文章を作成・送信するシステムです。従来のスカウト業務では、採用担当者が学生のプロフィールを一人ずつ確認し、手作業でスカウト文を作成していましたが、AIを活用することでこの工程を大幅に効率化できます。
AIスカウトサービスの特徴は、学生の専攻や経験、志向性などのデータを分析し、企業の求める人物像とのマッチング精度を高められる点にあります。また、送信する文章も学生一人ひとりの特性に合わせてパーソナライズされるため、従来の定型文よりも高い反応率が期待できます。
実際の運用では、採用担当者が求める人材の条件を設定するだけで、AIが自動的に候補者を選定し、適切なタイミングでスカウトメールを送信します。送信数や送信品質が安定するため、採用担当者の経験やスキルによる差が生じにくく、チーム全体として一貫性のある採用活動を展開できるメリットがあります。
AI適性検査
AI適性検査は、従来の適性検査にAI技術を組み込むことで、より精度の高い人材評価と不正行為の検知を実現するツールです。学生の性格特性や行動傾向、職務適性を高度に分析し、企業との相性を数値化します。
従来の適性検査では、あらかじめ設定された評価基準に基づいて結果が算出されていましたが、AI搭載の適性検査では過去の採用データや自社の活躍社員の特性を学習し、より自社にマッチした評価が可能になります。また、受検者の強みや弱みを言語化したり、入社後の活躍可能性を予測したりする機能も備えています。
さらに、AIがリアルタイムで受検状況をモニタリングすることで、カンニングや替え玉受検などの不正行為の検知も可能になりました。Webカメラを使用した監視システムにより、公平な選考環境を維持できます。
AI機能を活用すれば、面接で聞くべき質問も自動で生成されるため、人事担当者の負担軽減とともに、候補者の考えや価値観を効果的に聞き出せるようになります。インターンシップでも適性検査のAI機能を活用することで、学生の自己分析を支援したり、企業理解を深めたりする取り組みも行われています。
AI面接
AI面接は、AIが面接官の役割を担い、候補者の資質を客観的に評価するシステムです。学生は好きな時間と場所で面接を受けることができ、企業側は面接官のスケジュール調整が不要になるため、選考プロセスの効率化に大きく貢献します。
AI面接の最大の特徴は、構造化面接の手法をAIが学習しているため、すべての候補者に対して公平で一貫性のある評価を提供できる点です。人による面接では、面接官の経験や価値観によって評価にばらつきが生じる可能性がありますが、AI面接ではそのような心理的バイアスを排除できます。
候補者がどのように答えても、最後まで公正に話を聞き、きちんと資質を評価します。また、1時間程度の面接内容がすべてデータとして記録されるため、後から振り返って分析することも可能です。面接評価レポートには、候補者の強みや特性が詳細に記載され、次の選考ステップでの参考資料として活用できます。
ATS(採用管理システム)
ATS(Applicant Tracking System)は、採用活動に関わるすべての情報を一元管理し、業務の効率化とデータに基づく意思決定を支援するシステムです。近年のATSには様々なAI機能が搭載され、より高度な採用活動が可能になっています。
ATSの基本機能には、応募者情報の管理、選考フローの設定、面接日程の調整、評価情報の共有などがあります。複数の採用媒体からの応募者情報を自動で取り込み、一つのシステムで管理できるため、情報の見落としや対応漏れを防ぐことができます。
AI機能を活用したATSでは、求人原稿の自動生成や最適なエージェントのレコメンド、選考データの高度な分析などが可能です。例えば、過去の採用データを分析して選考プロセスのボトルネックを特定したり、内定辞退の傾向を把握したりすることで、採用活動の改善につなげられます。
面接官ごとの評価傾向を可視化する機能により、評価基準のすり合わせや面接官トレーニングにも活用できます。採用活動の進捗状況をリアルタイムで把握できるダッシュボード機能により、経営層への報告資料作成も効率化されます。
AIチャットシステム
AIチャットシステムは、学生からの問い合わせに24時間365日自動で対応するツールです。採用活動では、企業情報や選考フロー、福利厚生など、学生から様々な質問が寄せられますが、すべてに迅速に対応するのは担当者にとって大きな負担となります。
AIチャットボットを導入することで、よくある質問には自動で回答し、採用担当者はより重要な業務に集中できるようになります。従来のシナリオ型チャットボットと異なり、生成AI型のチャットボットは自然な対話形式で質問に答えられるのが特徴です。
学生は気軽なタイミングで知りたい情報を得られるため、企業理解が深まりやすくなります。また、メールでの問い合わせに比べてハードルが低いため、質問数も増加する傾向にあります。給与や休暇制度など、直接聞きづらい内容についても気兼ねなく質問できる環境が整います。
新卒採用にAIを活用する5つのメリットを解説!

では、生成AIを採用活動に導入し、メリットと採用活動の質を最大限上げるためにはどうしたらいいのでしょうか。ここからは、企業が得られる6つの主なメリットについて詳しく解説します。
①業務の効率化
採用活動にAIを導入することで、業務の大幅な効率化が実現できます。採用プロセスでは個別対応や採用プロセスで担当者が変わる場合が多く、情報の伝達ミスなど人的トラブルが頻繁に発生したため、採用担当者の大きな負担になっていました。AIを導入すれば、あらかじめ対応パターンを設定することで誰に対しても一定の品質で応答が可能になるため、人的ミスも減って作業効率も向上します。
さらに、AIは業務時間外や休日でも対応が可能です。これにより、応募者への対応の遅延を防いで採用活動全体のスピードと質の向上に繋がります。24時間365日稼働できるAIの特性は、採用活動において大きな強みとなるでしょう。
②コストの削減
AIは1年365日休まず稼働できるので、人件費や交通費といった採用業務のコストの大幅な削減が期待できます。ただし、生成AIの導入や設定には一定の費用がかかります。そのため、コストの懸念からAIの導入に慎重な企業もあるかもしれません。
しかし、AIを採用活動で上手く活用できるとAI導入にかかった費用を十分に回収できる可能性もあります。長期的な視点で見れば、初期投資を上回るコスト削減効果が期待できるでしょう。採用活動における費用対効果を常に意識することが重要です。
③採用基準の統一化
AIは人の主観や感情に影響されることが少ないので、採用基準を統一できるメリットがあります。あらかじめ定めた評価基準に基づいて判断するため、判断にブレが生じることなく採用基準が統一化されて、効率かつ公平性のある採用活動ができます。
採用基準を明確にして採用活動をするなら、生成AIの積極的な活用を検討してみましょう。一貫性のある評価は、候補者にとっても納得感のあるものとなるはずです。
④公平性の保証
生成AIを導入するメリットの1つに、採用の公平性を確保できるところがあります。なぜなら、人が判断する場合どんなに採用基準を厳格にしていても、個人の価値観や主観、経験で判断にばらつきが発生してしまうからです。あらかじめAIに採用基準やデータを学習させれば、人間の感情に左右されない一貫性のある判断が可能になります。
採用基準のブレを防ぎ、公平で効率的な採用活動を実現するためにも生成AIを積極的に活用しましょう。公平性の高い採用プロセスは、企業の信頼性向上にも繋がります。多様な人材を適切に評価できる仕組みづくりが大切です。
⑤重要な採用業務に専念
AIツールの導入により、定型的な業務が自動化されることで、採用担当者は本来注力すべき重要な業務に時間を使えるようになります。これは採用活動の質を高める上で非常に重要なメリットです。
従来の採用活動では、スクリーニング作業や日程調整、問い合わせ対応など、多くの時間が事務的な作業に費やされていました。AIがこうした定型業務を担当することで、採用担当者は学生との対話や企業の魅力を伝える活動、選考基準の設計など、より戦略的で価値の高い業務に集中できます。
具体的には、学生一人ひとりと向き合う時間を増やし、丁寧なコミュニケーションを取ることが可能になります。面接での深い対話や、内定者フォローでの手厚いサポートなど、人にしかできない価値提供に注力できるのです。
採用戦略の立案や選考プロセスの改善、面接官トレーニングなど、中長期的な採用力強化に向けた取り組みにも時間を割けるようになります。AIが蓄積したデータを分析し、より効果的な採用手法を考案することも可能です。
AIを採用に活用するデメリットとは?
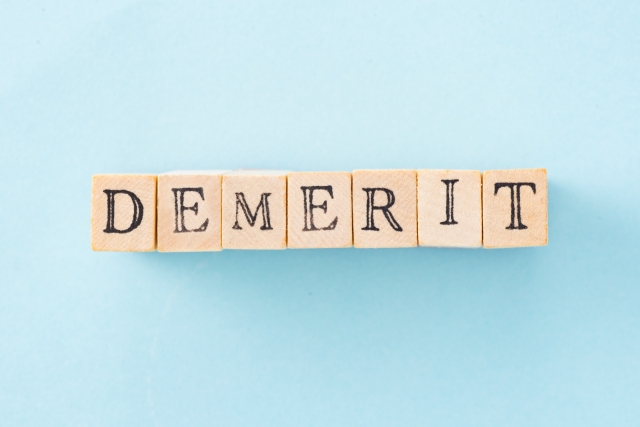
近年急速に広がりを見せている生成AIなだけに、採用活動に使う際には認識しておくべきデメリットも存在します。ここからは、企業が認識しておくべき4つの主なデメリットについて詳しく解説していきます。
過去の蓄積されたデータがないと正確な判断ができない
AIは、過去に蓄積されたデータを元にして判断を下すため、ビッグデータが十分に存在しない場合は正確な判断ができず、誤った結論を出す可能性があります。採用活動においてAIの利用は有効ですが、導入初期の段階ではAIが100%正しい結論を出すとは限りません。正確な判断ができるようになるまで、時間をかけて採用活動に関する大量なデータの蓄積が大切です。
AIにとってデータの蓄積は、性能を引き出すための重要なプロセスです。データが増えることで判断の精度が高まり、より使いやすく実用的になるため、日々の業務でデータを継続的に蓄積し続けてください。
数値化が難しい要素では判断ができない
生成AIでは、過去に蓄積されたデータを元にさまざまな判断を下します。そのため、数値化が難しい要素で質問された場合、正確な判断を下せない可能性があるので注意が必要です。特に応募者の人柄や人間性、マッチングに関しては、実際に対面して会話を交わさなければ深掘りができません。
これらの判断を全て生成AIに任せてしまうと、誤った判断を下す可能性があり、採用活動の質が下がってしまう恐れがあります。数値化が難しい要素に関しては、できる限り人間が判断するようにしましょう。AIと人間の役割を適切に分ければ、より質の高い採用活動が実現できるはずです。
柔軟性が損なわれる可能性がある
AIは、過去に蓄積されたデータに基づく分析や意思決定が得意です。一方で、採用活動の柔軟性が損なわれる可能性があるため、AIを使用する際には評価基準を一定のルールに基づいて画一化する必要があります。
ただし、全ての評価基準をAIに合わせて画一化すると、採用に関して柔軟な判断ができなくなり、将来性のある優秀な人材を見逃す恐れがあります。その結果、採用する人材の傾向が偏って人材の多様性が失われるリスクがあるので注意が必要です。
応募者の中には、面接時に会社への熱意や仕事に対する情熱をアピールする方もいます。こうした魅力はAIでは十分に評価できない場合があるため、採用活動を行う前にはAIに任せる部分と人間が判断する部分を明確にし、人材の評価基準をしっかり定めておきましょう。
AI採用に候補者が不安を抱くことがある
AIを採用活動に活用すると、候補者が不安を抱くこともあります。なぜなら、機械による人選によって差別的な判断をされるのではという懸念があるからです。
採用側は意図していなくても、AIが過去の通過率などのデータから無意識のバイアスをかける可能性があります。特に性別や人種、年齢など適切なスクリーニングが設定されていない場合、女性や高齢者、外国人が不当に判断する場合も考えられます。
不当な評価がされると、企業の評判や信頼を損ねるリスクもあるため注意が必要です。候補者が不安にならないよう、採用ポリシーや判断基準を丁寧に説明しましょう。透明性の高い運用が、候補者の安心感と企業への信頼につながります。
AIを新卒採用に導入している企業の事例を紹介!

実際に採用活動にAI採用を導入して、成果を上げている企業が増えています。今回は以下の代表的な2社の取り組みについて詳しくご紹介していきます。これらの事例を参考にすることで、自社でのAI活用のヒントが得られるでしょう。
株式会社イトーヨーカ堂様(AIスカウト)

株式会社イトーヨーカ堂様では、2名体制での新卒採用という限られたリソースの中で、AIスカウトサービス「RecUp」を導入することで、採用活動の質と量を大きく向上させました。
導入前の課題として、スカウト業務に十分な時間を割けず、送りたい学生に対してタイムリーなアプローチができていない状況がありました。採用担当者は「スカウトを送らなければ」と思いながらも、他の業務に追われて後回しになってしまう日々が続いていたといいます。
RecUp導入後は、毎日安定してスカウトが送れるようになり、イベント参加人数が倍増するという成果が得られました。AIは品質が安定しているため、忙しい日でも同じクオリティでスカウトを送信でき、「今日もちゃんと送れている」という安心感が得られるようになったそうです。
さらに特筆すべきは、単なるツール提供にとどまらず、定例ミーティングで数字の振り返りや改善提案を受けられる伴走型支援です。イベント予約導線の改善提案を受けて実行したところ、翌月には予約率が目に見えて向上したという実績もあります。採用を一緒につくるパートナーという認識が生まれ、社内の協力体制も強化されました。
【小売業界】イトーヨーカ堂様の成功事例──AIスカウト『RecUp』を導入して送信数の担保と採用の質が向上を実現した、その方法とは?
株式会社オープンハウス・ディベロップメント様(AIスカウト)

株式会社オープンハウス・ディベロップメントでは、新卒採用においてAI技術を積極的に活用しています。同社は不動産業界という人材獲得競争の激しい分野において、AI面接システムを導入することで採用活動の効率化を実現しました。AI面接を一次選考に取り入れることで、より多くの学生と接点を持つことが可能になったのです。
また、地方在住の学生も移動の負担なく面接を受けられるようになり、母集団形成の幅が大きく広がりました。同社の取り組みは、AI技術を活用した採用活動の成功事例として注目されています。活用事例の詳細については、下記記事で紹介しています。
■「求めていたのは『便利さ』ではなく『安心感』」-代行業者よりも承認数が2倍以上になった事例
アサヒ物産(AI適性検査)

飲食料品の卸売事業を行うアサヒ物産では、新卒採用で適性検査を実施していましたが、採用基準があいまいな状態で検査結果をうまく活用できていないという課題がありました。
具体的には、面接で「ぜひ入社してほしい」と思って採用しても早期離職してしまう状況が見受けられました。そこで、性格検査で組織分析ができる「ミキワメ適性検査」を導入し、従業員の特徴や部署ごとの傾向を明確にしたうえで、独自の採用基準を設定することにしました。
AI機能を利用することで「面接で聞くべき質問」が自動で生成されるため、人事担当の負担が軽減されるとともに、候補者の考えや価値観をより深く聞き出せるようになりました。また、インターンシップでも適性検査のAI機能を活用し、学生の自己分析(強み・弱み)に役立てる取り組みを実施しています。
AI搭載の適性検査を導入した結果、以前は新卒採用者の50%の人が離職していましたが、2024年1月現在で離職者がゼロになるという成果を上げています。適性検査のデータを活用することで、自社に合った人材を見極められるようになったことが、この成果につながっています。
株式会社ホリプロ(AI面接)

エンターテインメント業界で60年余りの歴史を持つ株式会社ホリプロでは、公平で客観的な評価を実現するためにAI面接サービス「SHaiN」を導入しました。
有名企業であるため毎年数多くの学生がエントリーしてくる中で、初見で人を判断・評価することの難しさに課題を感じていました。面接官の経験則や価値観に寄ってしまう部分があり、面接官によって関心を持つ点や深掘りするポイントが変わってしまう可能性がありました。
SHaiNが優れていたのは、構造化面接をAIが学習しているという点です。学生がどのように答えても、たとえ話下手でも、最後まで公正・公平に話を聞いて、きちんと資質を評価します。また、導入時に「SHaiNでは測れない資質もある」「社風や企業文化に合うかどうか、人の熱意や志望度合いは人が判断してください」という説明があり、信頼感が増したといいます。
トライアルでは新入社員に協力してもらい、AI面接と自分たちの面接での見立てにギャップがないことを確認。1時間あまりにわたり候補者がしっかり話してくれた内容がデータとして得られたことも大きな付加価値となりました。採用後の配属や育成にも活用できる可能性があり、今後の展開に期待が寄せられています。
株式会社明電エンジニアリング(ATS)

重電機器の保守メンテナンスを主な事業とする株式会社明電エンジニアリングでは、2名の採用担当者で機電系学生の採用を強化するために、ATS「sonar ATS」を導入しました。
電気設備の保守メンテナンスという事業は学生にとってイメージしづらく、事業内容を理解しないまま応募してくる方が多い状況でした。そこで、選考前に個別の面談を設けて事業や働き方について正しい情報を提供し、学生の理解を促す取り組みを実施。また、機電系の学生を優先的に採用するため、シンプルかつスピーディーに最終選考まで進む専用フローを新たに作成しました。
sonar ATSの導入により、エントリー時のアンケート回答結果をもとに自動で適切なフローに割り振れるようになり、手動での管理が不要になりました。また、履歴書などの面接書類をすべてシステム上で管理することで、印刷や配布の手間が大幅に削減され、面接官からも「やりやすくなった」と評価されています。
株式会社ソフトクリエイト(AIチャットボット)

株式会社ソフトクリエイトでは、新卒採用向けに生成AIチャットボット「ソフクリAI質問ルーム」を自社開発し、人事部門の業務負荷軽減と学生の企業理解向上を実現しました。
5名のスタッフで毎年100名規模の新卒採用を担当しており、数千名に上る学生からの問い合わせ対応だけでもかなりの業務負荷でした。また、メールでの問い合わせは学生にとってハードルが高く、有給休暇や離職率、給与についてなど聞きづらい内容もあると考えられました。学生が自分の知りたいタイミングで気兼ねなく問い合わせできる仕組みが必要だと感じていました。
生成AI型チャットボットは、事前準備が楽であることが大きな特長です。従来型のチャットボットでは一問一答形式のすべての回答と全分岐シナリオを用意する必要がありましたが、生成AI型では質問回答のテキスト情報をどんどん投げ込めば、AIが学習して必要な情報をピックアップし、自然な対話形式で回答してくれます。
導入後は、学生がチャットというインターフェースで気軽に質問できるようになり、担当者の負荷が大幅に軽減されました。面接の際に「使ってみましたか?」と質問を投げかけると、入社意欲の高い学生は実際に使ってくれており、そこから新しいテクノロジーに対する前向きな姿勢や興味を図ることもできたようです。
生成AIを新卒採用に効果的に使うポイントとは?
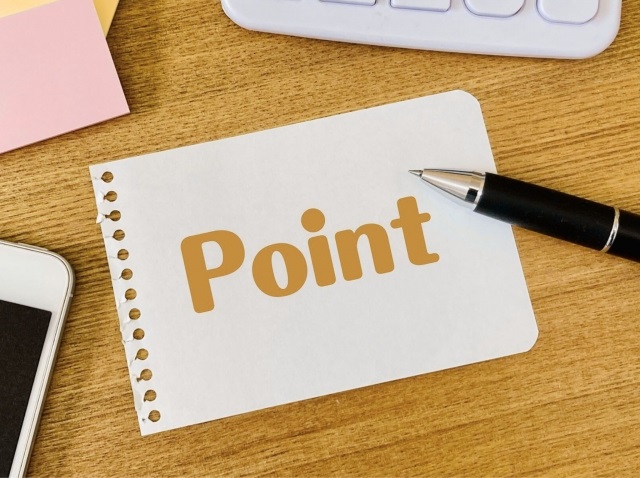
採用活動を成功させるには、AI採用のメリット・デメリットを両方踏まえたうえで、運用方法を知っておくことが重要です。ここからは5つのポイントを解説していきます。
生成AIが対応できる範囲を理解する
生成AIには得意・不得意があるので、使用する際にはどこまで対応できるのかをしっかり理解しておきましょう。なぜなら、生成AIは便利なツールですが全ての業務に対応できる訳ではないからです。AIはデータの効率化やデータ処理に関しては強みを発揮しますが、感情が混ざる工程や複雑な判断を下す場合には能力に限界があります。
このため、全ての作業をAIに一任するのではなく、信頼関係の構築や意思決定面では人間が判断するのが望ましいでしょう。それぞれの強みを活かしながら適切な役割分担を行うことが成功の鍵となります。AIと人間が協力し合う体制を整えることが大切です。
あくまでサポートツールとして使う
生成AIの使用には限界があるので、採用活動で使用する際はあくまでサポートツールとして生成AIを使用しましょう。AIに任せる業務と人間が担当すべき業務をあらかじめ明確に分けておくことで、採用活動を効率的に進めることができます。特に最終的な意思決定や、信頼関係や人間関係など繊細な対応をする際は、AIの誤判断によってトラブルに発展する可能性があります。
そのため、AIが得意な作業を事前に見極めサポートツールとして慎重に使用しましょう。AIはあくまで人間の判断を補助するものであり、最終決定権は常に人間が持つべきです。この原則を忘れないようにしましょう。
まずは一部の業務から導入してみる
生成AIには限界があるので、まずはサポートツールとして一部の業務から導入するのをおすすめします。導入にあたっては、まず人事部で行われている業務内容を棚卸しして、それぞれの作業にかかる所要時間と頻度を把握しましょう。次に、繰り返し行われている業務やパターン化されている業務を抽出し、工数がかかっている部分を重点的に確認します。
生成AIは採用担当者の負担を減らして効率的に業務を進めるパートナーになります。AIが活用できそうな作業から段階的に導入して、業務時間の削減を目指していきましょう。小さな成功を積み重ねることで、組織全体のAI活用に対する理解も深まります。
最終的な決定は人間が行う
AIツールはあくまで判断の参考となる指標を示すものなので、採用の最終的な判断は必ず人間が決断するようにしましょう。AIは指標を示してくれるツールなので、最後までAIに採用活動を完全に任せることはできません。
自社にとって本当に必要な人材かどうかを見極めるには、応募者とのコミュニケーションが重要となります。AIツールを上手に活用しつつ、対話を通じて応募者の魅力を引き出し最適な人材を見つけてみましょう。人間ならではの洞察力と、AIによるデータ分析を組み合わせることで、より確度の高い採用判断が可能になります。
定期的に結果を見直し改善していく
生成AIツールを導入したら、定期的に結果を見直し改善を重ねていくようにしましょう。効果を正しく検証するには、導入前後で比較できる具体的な成果指標(KPI)を3〜5項目設置します。
検証期間は1ヶ月〜3ヶ月を目安に行い、結果を元に効果と課題を明確化しましょう。AIを導入して十分な効果が見込める場合は、段階的に他の業務にもAIを導入していきます。
生成AIは特別なスキルが無くても誰でも扱えるツールです。最初は小さな範囲から段階的に導入し、少しずつ結果を見直しながら徐々に活用範囲を増やしていきましょう。継続的な改善が、AI採用の成功には不可欠です。
採用に活用できる生成AI搭載ツール3選!

採用活動に活用できる生成AI搭載ツールは数多く存在します。以下では、特に実績のある代表的な3つのツールについて詳しくご紹介していきます。
ツールの特徴を理解し、自社に最適なAIツールを選ぶ参考にしてください。
RecUp

株式会社Delightが運営するRecUpは、求職者のスカウトメールの自動生成が可能なAIツールです。求職者のプロフィールに基づき、心に響く魅力的なスカウトメールをAIが自動的に作成してくれます。ターゲット選定やスカウトメールの分析・改善も可能で、返信率や開封率の向上を通じて採用効率の向上を実現させます。
求職者の自己PRや職務経歴書を読み取った上で文章を生成できるので、スカウト承認率の向上にも繋がります。少しでも採用効率を高めたい場合や、より多くの求職者にスカウトメールを送りたいと考えている企業にとってRecUpは心強いAIツールと言えるでしょう。ぜひRecUpを有効に使用して、より効果的な採用活動に役立ててみてください。
HRMOS採用

HRMOS採用は、株式会社ビズリーチが提供する採用管理システムで、生成AIを活用した求人原稿の自動生成機能を搭載しています。AIがキーワードをもとに求人要件を作成してくれるため、要件定義が難しいポジションでも簡単な操作で誰でも求人を作成できます。
採用経験の少ないメンバーや、今までにない新規ポジションの採用においても、少ない工数で精度の高い求人が作成できるのが特徴です。また、ビズリーチをはじめ多くの求人媒体と応募者情報を連携し、一元管理できるため、採用業務全体の効率化に貢献します。
面接官や会議室の空き枠確認、日程調整機能も充実しており、Web面接のURL発行も同時に行えます。候補者ごとに評価情報を集約し、面接官との情報共有もスムーズに行えるため、選考プロセス全体の質が向上します。
ShaiN

ShaiNは、株式会社タレントアンドアセスメントが提供する対話型面接を実現させたAIツールです。すでに600社以上の企業で採用選考に活用されていて、利用企業の中には大手企業や老舗企業も含まれています。従来の面接は決められた時間に特定の場所に集まる必要があり、日程や場所の調整が難しいと選考を辞退する人も少なくありませんでした。
しかし、ShaiNを導入後は時間や場所に左右されず、候補者が好きなタイミングで面接ができるようになったので選考辞退の防止に効果を発揮しています。AI面接では戦略採用メソッドに基づきAIが面接官を務めるので、採用基準の統一が可能です。面接データは人事配置や人材アセスメントにも活用できるため、社員の育成や適材適所の判断にも役立ちます。
新卒採用にAIを活用することに対するFAQ

新しい技術の導入には、必ず疑問や不安がつきものです。特にAIのような先端技術を採用活動に取り入れることに対して、コストや効果、運用面での懸念を持つ企業も少なくありません。
ここでは、AI活用を検討している企業からよく寄せられる質問について、具体的な回答とともにご紹介します。実際の導入を検討する際の参考としてお役立てください。
AI導入はコストが高いのでは?
A. 小規模から始められるサービスが多く、新卒採用だけであれば数万円〜のプランも存在します。
スクリーニングやスカウト作業など、人事工数を数十時間削減できるため、トータルコストはむしろ下がるケースが多いです。
AIが学生の魅力や熱意を見落とすことはない?
A. 志望理由や個別のストーリー評価は人が行うべき領域です。
AIは主に定量的な情報整理・候補者の抽出・優先度付けを行い、人の判断を補完する役割のため、「見落とし防止」にもつながります。
AIを使うと選考が機械的になってしまわない?
A. 「どこをAIに任せて、どこを人が担当するか」を明確にすれば問題ありません。
AIはスクリーニングやタスク整理、メール文作成など事務的業務の効率化が得意であり、学生との対話や企業の魅力伝達といったホスピタリティが必要な部分に時間を回せます。
AI採用のデメリットを踏まえても、安心して導入できるのが「RecUp」

今回の記事では、AI採用におけるデメリットとメリット、そして効果的な活用方法について詳しく解説してきました。AI採用には過去データの不足や数値化が難しい要素への対応といったデメリットが存在する一方で、業務効率化やコスト削減、採用基準の統一化といった多くのメリットがあります。
株式会社Delightが提供する「RecUp」はデメリットを抑えながら、メリットを有効にする最適なソリューションです。AI技術と人の専門知識を組み合わせたハイブリッド採用支援サービスとして、スカウト自動化から採用代行、コンサルティングまで幅広く対応しています。RecUpは少人数の企業から上場企業まで400社以上の採用成功をサポートしてきた実績があり、業界や規模を問わず多くの企業にご利用いただいています。
AI採用のデメリットを理解した上で、それらを解消しながら効果的に活用したいとお考えの企業様は、ぜひRecUpの導入をご検討ください。専門のコンサルタントが貴社の採用課題を丁寧にヒアリングし、最適なソリューションをご提案いたします。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。