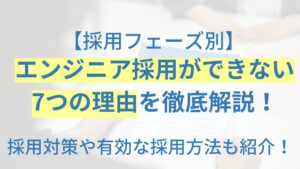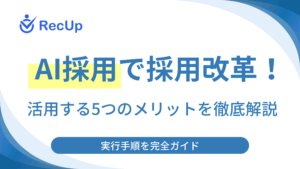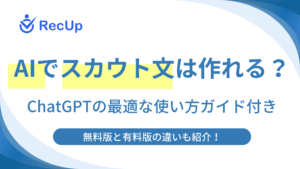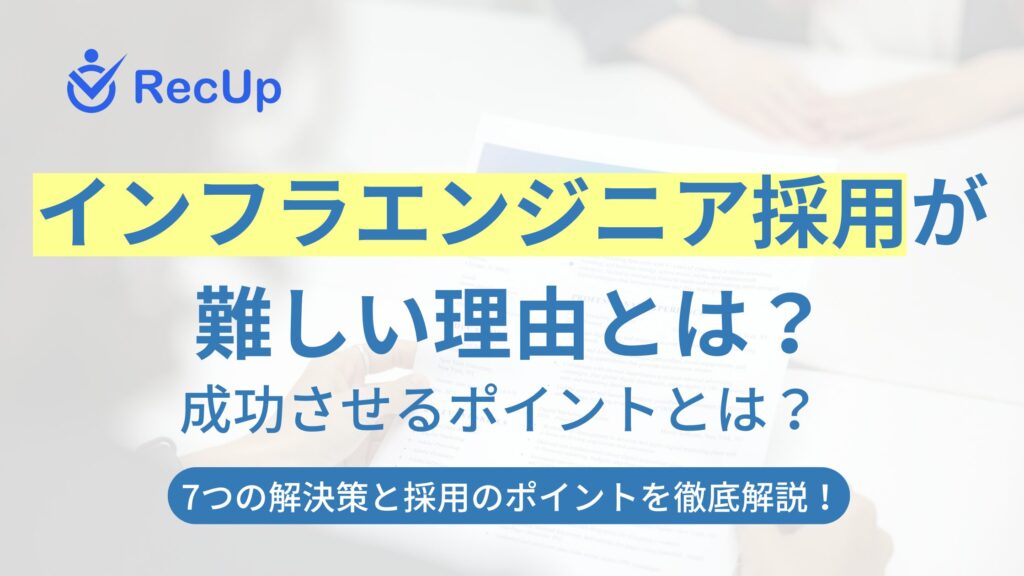
インフラエンジニアは、ITシステムの土台を支える非常に重要な職種です。しかし、その採用は年々難易度が高まっています。候補者を見つけるだけでも難しいとされている中、有効な手段を立てる必要性は高まるばかり。
本記事では、インフラエンジニア採用が困難な理由を3つに分けて解説し、具体的な採用手段や成功させるための工夫についても紹介します。
採用活動にお悩みの企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
インフラエンジニアの採用が難しい理由とは?

インフラエンジニアを採用する際、多くの企業が共通して直面する課題があります。
ITインフラの需要は年々高まっている一方で、それを支えるエンジニアの数は追いついていません。また、採用市場では優秀な人材を巡って企業間の競争が激しくなっており、自社の魅力を伝える戦略や迅速な対応が求められます。
ここからは、インフラエンジニアを採用するのが難しい5つの理由をそれぞれ解説していきます。
【新卒採用担当者向け】媒体選びで失敗しないダイレクトリクルーティング完全ガイド
需要と供給のバランスが成り立っていない
インフラエンジニア採用が難しいとされる最大の理由のひとつは、人材の「需要」と「供給」のバランスが崩れている点といえるでしょう。
特に近年は、クラウド化の急速な進展やDX(デジタルトランスフォーメーション)の波を受け、企業が求めるインフラエンジニアの数が急増しています。
従来のオンプレミス型インフラの運用に加え、AWSやAzure、GCPといったクラウド基盤の設計・構築・運用を担える人材が強く求められているのです。
しかし、それに対応するエンジニアの育成が追いついていないのが現状です。インフラ領域は高度な専門知識や実務経験が必要で、即戦力となる人材の育成には時間がかかります。
加えて、アプリケーション開発などの領域に比べて若年層の人気が低いこともあり、インフラ分野を志望する学生や若手エンジニアが少ない傾向にあります。
このような状況では、求人数が増える一方で応募者が少ない、つまり「売り手市場」の状態が続くことになります。その結果、企業間での人材の奪い合いが激化し、採用難易度はさらに高まっています。
特に即戦力クラスのエンジニアを求める中小企業やスタートアップにとっては、大手との競争で不利になりやすく、採用が思うように進まないケースも少なくありません。
このように、市場全体で需要過多の状態が続いていることが、インフラエンジニアの採用難を根本的に引き起こしているのです。採用を成功させるためには、この需給バランスの崩れを理解した上で、自社の採用戦略や魅力の打ち出し方を見直す必要があります。
優秀な人材を確保しようとする企業間の競争が激しい
インフラエンジニアの採用が難しいもうひとつの大きな壁が「企業間の人材争奪戦」です。特に経験豊富で即戦力となる人材は非常に希少であり、多くの企業がその獲得を目指して競争しています。
この競争の中で選ばれる企業になるには、給与や待遇だけでなく、「働きやすさ」や「成長できる環境」といった非金銭的な魅力も重要です。大手企業はこのような取り組みにも多くの予算を投じられるため、中小企業やスタートアップはどうしても不利になりがちです。
また、優秀な人材ほど自ら転職市場に出る機会が少なく、リファラルやスカウトなど、能動的なアプローチが不可欠になります。そのため、企業は人事だけでなく現場のエンジニアや経営層を巻き込んだ採用体制の強化が求められます。
採用に成功するためには、単に「自社の良さを伝える」だけではなく、候補者にとって「入社後にどんな成長や挑戦があるのか」を具体的に提示することが不可欠です。
このように、インフラエンジニアの採用市場では企業間の競争が常に発生しており、それが採用活動を一層難しくしているのです。採用成功の鍵は、他社との差別化と、候補者目線に立った魅力づけにあると言えるでしょう。
企業の提示する条件と候補者の希望のミスマッチしている
インフラエンジニアの採用活動において、企業が提示する条件と候補者が求める働き方や待遇の間にずれが生じるケースが多発しています。このミスマッチは、採用活動が思うように進まない主要因の一つとなっています。
企業側は即戦力として、オンプレミス環境での構築経験や24時間体制での運用保守対応ができる人材を求める傾向があります。一方で、候補者側はクラウド技術の習得やワークライフバランスを重視した働き方を希望するケースが増えています。
特に待遇面での乖離も見逃せません。レバテックの調査によると、IT人材の64%が企業選びにおいて給与を最も重視していることが明らかになっています。大手企業が高い給与水準を提示する中、中小企業では提示可能な条件に限界があり、優秀な人材の確保が難しくなっています。
また、技術要件の認識にもずれが生じやすい状況です。企業が「クラウド経験者」と記載していても、AWSなのかAzureなのか、どの程度の深さを求めているのかが明確でない場合、応募者は自分のスキルが適合するか判断できません。このような曖昧な要件定義がミスマッチを招き、選考が進んでも最終的に内定辞退につながるケースが後を絶ちません。
採用担当が候補者のスキルを見極めにくい
インフラエンジニアの技術力を適切に評価することは、採用担当者にとって大きな課題となっています。開発エンジニアのようにGitHubで公開されたコードやポートフォリオで実力を測ることが難しく、スキルの可視化が困難な職種だからです。
インフラエンジニアの成果物は、システムの安定稼働そのものです。ネットワークの設計図やサーバーの構成管理といった業務は、外部から見える形で残りにくく、職務経歴書に記載された技術用語だけでは実際の業務遂行能力を正確に判断できません。
企業ごとに求められる技術要件が大きく異なることも評価を難しくしています。あるプロジェクトではオンプレミス環境でのネットワーク構築が中心である一方、別のプロジェクトではクラウドネイティブなインフラの自動化が求められます。統一的な評価基準の設定が困難なため、面接官によって評価にばらつきが生じやすい状況です。
採用担当者や面接官の技術知識不足も見極めを困難にしています。インフラ領域は業務範囲が広く、ネットワーク、サーバー、クラウド、セキュリティなど多岐にわたる知識が必要です。人事部門だけでなく、技術部門の面接官でも最新の技術動向を把握していない場合、候補者の実力を正確に測ることができず、採用後のミスマッチにつながる恐れがあります。
転職市場にあまりいない
インフラエンジニアは、転職市場に出現する頻度が非常に低い職種として知られています。この流動性の低さが、企業の採用活動を一層困難にしている要因となっています。
インフラエンジニアの業務は企業のITシステムの根幹を支えるため、責任範囲が広く、業務の継続性が強く求められます。そのため、現職での役割が重要であればあるほど、転職を検討する時間的・心理的余裕が持ちにくくなります。また、待遇に満足している場合は積極的な転職意欲が生まれにくい傾向も強く、求人を出しても応募が集まりにくい状況が続いています。
厚生労働省の調査によると、インフラエンジニアの有効求人倍率は全国平均で2.23倍となっており、1人の求職者に対して2件以上の求人が存在する売り手市場が続いています。特にセキュリティ領域においては、レバテックの調査で有効求人倍率が50倍を超えたと報告されており、極端な人材不足が明らかになっています。
さらに、働き方の多様化も転職市場の流動性に影響を与えています。フリーランスや副業といった柔軟な働き方が普及したことで、正社員としての採用に応募する人材自体が減少している実情があります。優秀なインフラエンジニアほど、複数の企業とプロジェクト単位で契約し、自由度の高い働き方を選択する傾向が強まっているのです。
インフラエンジニアの採用を成功させるための7つのポイントを解説!

インフラエンジニア採用を成功させるには、単に求人を出すだけでは不十分です。優秀な人材の心をつかむには、企業側の情報発信の工夫や、候補者対応の質、社内の採用体制など、複数の視点での取り組みが必要です。
ここでは、実際の採用現場で効果的とされる7つのポイントについて詳しく解説します。これらを意識して改善していくことで、採用活動の成功率はぐっと高まります。
①採用したいターゲットを明確化する
採用活動の第一歩として、求める人物像を具体的に定義することが重要です。「経験者がほしい」「若手を採用したい」といった漠然としたイメージだけでは、効果的な採用活動は展開できません。
まず、自社が本当に必要とする技術要件を明確にしましょう。ネットワーク構築が中心なのか、クラウド環境の運用保守が主な業務なのか、セキュリティ対策まで含めた包括的な対応が求められるのか、具体的な業務内容に基づいて必要なスキルを洗い出します。この際、必須スキルと歓迎スキルを明確に分けることで、応募者が自分の適性を判断しやすくなります。
次に、ペルソナ設計を行うことをおすすめします。年齢、経験年数、保有資格、キャリア志向、ライフスタイルなど、採用したい人物像を詳細に描き出し、採用チーム全体で共有します。
ターゲットの明確化は採用チャネルの選択にも直結します。若手エンジニアを狙うならSNSやエンジニアコミュニティへのアプローチが有効ですし、ベテラン層を採用したいなら人材紹介会社やリファラル採用が効果的です。明確なターゲット設定は、採用活動の効率を大幅に向上させる基盤となります。
②インフラエンジニア目線の募集要項にする
採用ページは、候補者が最初に自社に触れる重要な接点です。求人票がただのスキルの羅列や業務内容の説明にとどまっていては、魅力は伝わりません。
とくにインフラエンジニアは、自身のスキルや志向に合った職場を慎重に選ぶ傾向があるため、ページ内の情報がその判断材料として大きな役割を果たします。
インフラエンジニアをターゲットにする場合、プロジェクトの具体例や使用している技術スタック、チーム体制などを丁寧に書くことで、自分が働く姿をイメージしやすくなります。
たとえば「インフラの設計・構築」といった抽象的な表現ではなく、「AWSを用いたネットワーク設計」「社内インフラの自動化対応」など、実際の業務イメージが明確に伝わる表現にすることが求められます。
次に意識すべきは、エンジニア目線での魅力訴求です。たとえば「技術選定にエンジニアが関与できる」「社内勉強会の実施」「最新技術に挑戦できる環境」など、エンジニアとして成長できる要素を強調することで、応募者にとっての価値を具体的に示すことができます。
さらに、働き方に関する情報も見逃せません。リモートワークの可否や残業の有無、ワークライフバランスへの配慮など、働きやすさに直結する要素をしっかりと記載することは、候補者の安心感や信頼につながります。
このように、ただの求人ページではなく、エンジニアにとって「読みたくなる」「応募したくなる」コンテンツに磨き上げることが、採用活動を前進させるカギとなります。
③効果のある採用チャネルを選択する
採用成功の鍵は、自社の求める人材像に合わせて複数の採用チャネルを効果的に組み合わせることです。単一のチャネルに依存すると、アプローチできる候補者の幅が限定され、採用機会を逃してしまう可能性があります。
主な採用チャネルには、求人サイト、人材紹介会社、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS活用などがあります。それぞれの特徴を理解した上で、自社の採用ニーズや予算に合わせて2〜3種類のチャネルを組み合わせることが効果的です。
たとえば、即戦力の採用を急ぐ場合はエージェントとダイレクトリクルーティングを併用することで、幅広い候補者層にアプローチできます。一方、じっくりと自社にフィットする人材を探したい場合は、リファラル採用や技術コミュニティへの参加を通じて、長期的な関係構築を図る方法が適しています。
各チャネルの費用対効果を定期的に検証し、データに基づいた改善を行うことが重要です。応募数、書類選考通過率、面接通過率、内定承諾率といった各段階の数値を追跡し、どのチャネルが最も効果的かを分析します。
効果の低いチャネルは思い切って見直し、成果の出ているチャネルに予算を集中させることで、採用活動全体の質を高めることができます。
④採用面接で自社をアピールする
インフラエンジニアの採用を成功させるためには、選考過程において面接の場を「評価するだけの場」ではなく、「自社を魅力的に伝える機会」として活用することが重要です。
とくに即戦力としての活躍を期待される中堅〜ベテラン層のエンジニアは、複数の企業から声がかかっていることが多いため、自社を選んでもらうための差別化が不可欠です。
まず意識すべきなのは、一方通行の質問形式を避けることです。求職者の経歴やスキルを確認するだけでなく、こちらから積極的に自社の魅力や今後の展望、技術的なチャレンジなどを丁寧に伝えることで、双方向のコミュニケーションが生まれ、相互理解が深まります。
また、面接官には現場のエンジニアやチームリーダーが同席することも効果的です。実際に働く人のリアルな声が伝わることで、候補者は職場の雰囲気や文化を具体的にイメージしやすくなります。
特にインフラエンジニアは、業務の中でチーム連携が多いため、「どんな人と働くか」が企業選びの判断基準になることも多くあります。
さらに、給与や待遇面ばかりでなく、成長機会やキャリアパスの提示も重要です。たとえば、クラウド領域へのスキルシフトを支援していることや、資格取得支援制度が整っていることなど、将来的な成長イメージを持たせられる内容を伝えることで、長期的な視点で入社を検討してもらいやすくなります。
このように、採用面接を「見極めの場」だけでなく、「選ばれるための場」と捉えることが、競争の激しいインフラエンジニア採用市場で成果を出すための鍵となります。
⑤採用担当者の知識を向上させる
インフラエンジニアの採用を円滑に進めるうえで見落とされがちなのが、採用担当者自身のスキルや知識のレベルです。
まず前提として、採用担当者がインフラエンジニアの職務内容や求められるスキルセットを正しく理解していることが不可欠です。
また、候補者と接する際には、技術に対するリスペクトや共感を示す姿勢が重要です。採用担当者が技術を理解し、的確な質問やコメントを投げかけることができれば、求職者側の信頼感は大きく高まります。
このように、採用担当者がテクニカルスキルとヒューマンスキルの両面で成長することは、インフラエンジニアのような専門職の採用において、非常に大きな差を生みます。
インフラエンジニアの人材不足が深刻化する中で、企業は「とにかく人を確保したい」という焦りから採用基準を下げてしまうことがありますが、採用ミスは組織全体に大きな負担をもたらすリスクがあるため、慎重な見極めが欠かせません。
採用ミスには大きく分けて2つのパターンがあり、ひとつはスキルや経験が自社の求める水準に達していないケース。もうひとつは、組織文化や働き方への適応が難しいケースです。
こうしたリスクを回避するためには、選考の初期段階から「スキルマッチ」と「カルチャーマッチ」の両面で丁寧に見極める視点が必要です。
インフラエンジニアの採用においては「妥協せず、時間をかけてでも適切な人材を選ぶ」という姿勢が、結果として組織の安定やプロジェクトの成功につながります。短期的な充足ではなく、長期的な戦力化を見据えた採用判断が求められるのです。
⑥現場との連携を強化する
採用活動を成功させるためには、人事部門と現場の技術部門が密接に連携することが不可欠です。特にインフラエンジニアのような専門性の高い職種では、現場の声を反映させないと採用要件のずれや評価基準の曖昧さが生じてしまいます。
まず、採用要件の定義段階から現場のエンジニアを巻き込みましょう。現場が本当に求めているスキルと、人事が想定しているスキルにずれがないか、定期的にすり合わせを行うことが重要です。
次に、面接段階では必ず現場のエンジニアを面接官として参加させます。技術的な質問を通じて候補者のスキルを正確に評価できるだけでなく、候補者にとっても実際の業務内容やチームの雰囲気を知る貴重な機会となります。面接官となる現場エンジニアには、質問技術や評価基準の統一など、面接官としてのトレーニングを事前に提供することで、評価の精度を高めることができます。
また、採用活動の振り返りも現場と共同で行いましょう。採用した人材が実際にどのように活躍しているか、当初の期待と実際のパフォーマンスにずれはないか、定期的にフィードバックを受けることで、次回の採用活動に活かせる貴重な知見が蓄積されます。
⑦応募者への対応は丁寧かつ迅速に行う
優秀なインフラエンジニアは、複数の企業から同時に声がかかっていることがほとんどです。そのため、選考プロセスにおける対応のスピードと丁寧さが、最終的な意思決定に大きく影響します。
問い合わせへの返答が遅かったり、面接結果の通知が何日もかかったりすると、それだけで信頼を失い、候補者の意欲が下がってしまう可能性があります。
連絡のスピードだけでなく、内容の丁寧さも重要です。テンプレート的な事務的対応ではなく、候補者一人ひとりに合わせた返信やフォローができると、企業の印象が格段に良くなります。
とくに選考中のフォローアップ、面接後のフィードバック、内定後のクロージング連絡などは、早さと誠意の両方が問われる場面です。システム化できる部分はツールを活用しつつ、人の手で温かみを加える工夫が求められます。
効果的な採用チャネルは?
インフラエンジニアの採用を成功させるためには、適切な採用チャネルの選択が鍵となります。各チャネルにはそれぞれ特徴とメリットがあり、自社の状況や採用ニーズに合わせて戦略的に活用することで、優秀な人材との出会いの確率を高めることができます。
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、企業が自ら候補者を探し、直接スカウトメッセージを送って採用につなげる手法です。待ちの採用から攻めの採用へと転換できる、近年注目を集めている採用手法の一つです。
この手法の最大のメリットは、転職を積極的に考えていない潜在的な候補者にもアプローチできる点です。優秀なインフラエンジニアの多くは現職で一定の満足を得ており、求人サイトに登録していないケースが少なくありません。ダイレクトリクルーティングを活用することで、潜在層に自社の魅力やビジョンを直接伝えることができ、興味を持ってもらえる可能性が高まります。
採用コストを抑えつつ、条件に合った人材に的確にアプローチできる点も魅力です。スカウト型のプラットフォームでは、候補者のスキルや経験、希望条件などが詳細に登録されているため、自社の求める人材像に合致する候補者を効率的に検索できます。
成功させるポイントは、まず求める人物像を明確にし、ターゲットに合わせた魅力的なスカウト文を作成することです。定型文ではなく、候補者のプロフィールを丁寧に読み込み、その人の経験やスキルに言及した個別性の高いメッセージを送ることで、返信率が大きく向上します。
ダイレクトリクルーティングの活用方法については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
【数値付き】ダイレクトリクルーティングの事例集!自社のメリットや効果的に行う5つのポイントとは?
求人広告
求人広告は、求人サイトや求人情報誌などに広告を掲載し、応募者を募る最もスタンダードな採用手法です。多くの企業が利用している手法であり、幅広い候補者層にアプローチできる特徴があります。
求人広告の最大のメリットは、企業の魅力や働く環境を自由に訴求できる点にあります。自社の技術スタック、取り組んでいるプロジェクトの内容、エンジニアとして成長できる環境、資格取得支援制度など、候補者が知りたい情報を具体的に打ち出すことで、自社にフィットする人材からの応募を集めることが可能です。
また、求人サイトごとに特色があり、ターゲットに合わせた媒体選択ができます。総合型の求人サイトは幅広い層にリーチできる一方、IT業界に特化した求人サイトでは技術的な詳細まで記載でき、専門性の高い候補者にアプローチしやすくなります。自社の採用ニーズや予算に応じて、最適な媒体を選ぶことが重要です。
求人広告を効果的に活用するには、原稿作成の段階からの工夫が必要です。ポジションの魅力だけでなく、チームの雰囲気や働き方、将来のキャリアパスなど、エンジニアが入社後のイメージを具体的に描ける情報を盛り込みます。また、掲載後も応募状況をモニタリングし、応募数が少ない場合は求人内容の見直しや掲載媒体の変更を検討するなど、定期的な改善を加えることで、より質の高い応募者を集めることができます。
エージェント
人材紹介会社(エージェント)を活用する手法は、特に専門性の高いインフラエンジニアの採用において非常に効果的なチャネルです。業界の動向に詳しいエージェントが、企業が求めるスキルや経験に合う候補者をピンポイントで紹介してくれます。
エージェント活用の最大のメリットは、採用要件に合致した候補者を効率的に紹介してもらえる点です。エージェントは登録者のスキルや経験、転職希望条件を詳細に把握しているため、企業のニーズと候補者の希望がマッチングしやすく、ミスマッチが起こりにくい特徴があります。
また、エージェントは候補者との間に立って、企業側が直接聞きにくい年収希望や転職理由といった情報も収集してくれます。候補者の本音を把握できることで、より精度の高い選考が可能になり、内定後の辞退を防ぐことにもつながります。
エージェントを効果的に活用するには、自社の魅力や採用における課題を正確に共有し、密なコミュニケーションを取ることが重要です。単なる紹介窓口としてではなく、採用パートナーとして位置づけ、定期的な情報交換や採用状況の共有を行うことで、エージェント側も自社に合った候補者をより的確に提案できるようになります。
紹介予定派遣
紹介予定派遣は、一定期間を派遣社員として働いてもらった後、双方の合意があれば正社員として直接雇用する採用手法です。実際の業務を通じて候補者のスキルや人柄を見極められるため、採用リスクを軽減できる特徴があります。
この手法の最大のメリットは、実際の業務パフォーマンスを確認してから正社員登用の判断ができる点です。面接だけでは見極めにくい技術力の実態や、チームとの相性、コミュニケーション能力などを、実務を通じて詳細に評価できます。
即戦力が必要な状況に対して、採用活動と並行しながらプロジェクトを進められる点も魅力です。派遣期間中から実務に携わってもらうことで、正社員登用時にはすでに業務に慣れており、スムーズな立ち上がりが期待できます。教育コストや時間を節約できる効果もあります。
紹介予定派遣を成功させるポイントは、派遣期間中の評価基準を明確にしておくことです。技術スキル、業務遂行能力、チームワーク、コミュニケーションなど、正社員登用の判断材料となる項目を事前に定義し、定期的な評価とフィードバックを行います。また、候補者に対しても正社員登用の条件や期待する成果を明確に伝え、双方が同じゴールに向かって進めるようにすることが重要です。
インフラエンジニアの採用のポイントをレベル別に解説
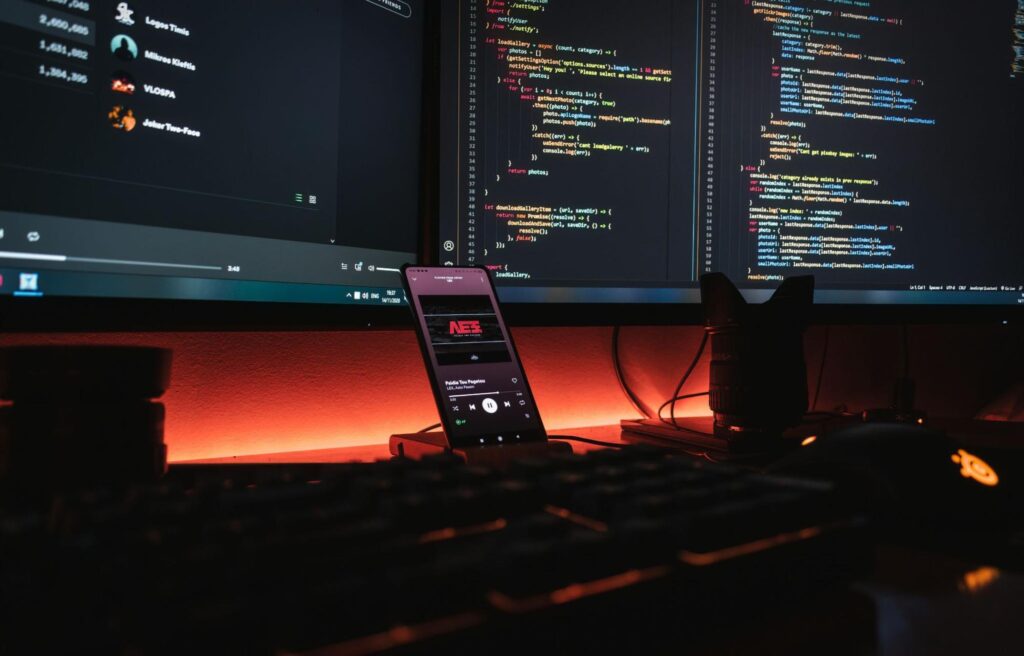
インフラエンジニアと一口に言っても、初心者から中堅、そしてハイレベルな即戦力人材まで、スキルや経験値には大きな幅があります。そのため、採用活動においては求める人材のレベルに応じて、アプローチや評価基準を柔軟に変えることが成功のカギとなります。
ここでは「初級〜中級の人材」「スキルアップ志向の人材」「年収アップを目指す人材」の3つのタイプに分けて、アプローチのコツや重視すべきポイントを解説していきます。
採用活動の戦略設計に、ぜひお役立てください。
初級から中級のインフラエンジニア
初級〜中級のインフラエンジニアは、基本的なサーバー・ネットワークの知識や経験を持ちつつも、まだ広範な領域をカバーするまでには至っていない人材層です。この層は非常に数が多く、育成を前提とした採用に適しています。
採用する側としては、「現場で学びながらスキルアップできる環境」をアピールすることが重要です。
たとえば、OJT体制や、資格取得支援制度、ナレッジ共有の文化があることなどを具体的に示せば、「ここで成長できそう」と感じてもらいやすくなります。
また、実務未経験者に対しても、ポテンシャル採用の姿勢を明確に打ち出せば、応募の裾野を広げることができます。初級層にとっては「働きやすさ」や「学べる環境」が応募動機になるため、それを分かりやすく伝える工夫が大切です。
技術レベルの向上を目指している方
インフラエンジニアとして成長を目指している若手〜中堅層の採用では、現在のスキルよりも「成長意欲」や「学習姿勢」に重きを置くことがポイントです。
すでに基礎的な知識や実務経験を持ち、次のステップとしてクラウドや自動化、セキュリティ分野などへスキルを広げたいと考えている候補者は多く存在します。企業側がそのような向上心にしっかり応える姿勢を見せることで、採用競争で優位に立つことができます。
たとえば、AWSやAzure、GCPなどのクラウド基盤への移行を進めている企業であれば、そのプロジェクトに参画できるチャンスがあることを明示すると、候補者にとって非常に魅力的に映ります。
この層の候補者は、「学べる環境」「実践で試せる機会」があるかどうかを重視しており、給与よりもキャリアアップのしやすさを判断基準にする傾向があるため、面接時には過去の成長事例や、入社後の技術的なチャレンジ内容を具体的に伝えることが重要です。
また、採用後の定着を図るうえでも、スキルアップの支援体制が整っているかどうかは大きなポイントになります。業務の中で任される領域に裁量があり、主体的に技術選定に関われる環境であることを伝えると、やりがいを感じてもらいやすくなります。
年収アップを目指している方
即戦力としての経験やスキルを武器に、年収アップを目的として転職活動を行うインフラエンジニアは少なくありません。
すでにサーバー・ネットワークの構築経験やクラウド運用、IaC(Infrastructure as Code)への対応力など、実務における確かな実績を持っているのが特徴です。そのため、採用企業側も「技術力に見合う待遇を提示できるかどうか」が重要なポイントになります。
まず意識すべきは、年収に見合う業務内容とポジションを明確に示すことです。「チームの中核を担ってもらう」「設計・技術選定から携わる」といった責任あるポジションを提示することで、候補者は自分の市場価値が正当に評価されていると実感できます。
また、インフラエンジニア市場は依然として売り手優位であり、想定年収に届かない場合は即時辞退となるケースも多いため、条件交渉の余地や昇給制度なども含めて丁寧に説明する必要があります。
さらに、年収アップを重視する層は「将来的な収入の伸び」も視野に入れているため、キャリアパスや評価制度の透明性を示すことも効果的です。
年収アップを目指すハイレベルなインフラエンジニアに対しては、報酬とやりがい、成長機会のバランスを提示し、自社で働くことのメリットを明確に伝えることが、採用成功のカギとなります。
インフラエンジニアの採用を成功させるなら「RecUp」!

インフラエンジニアの採用が難しい状況は依然として続いており、年々その傾向は強まっていますが、採用市場の特性や候補者のニーズをしっかりと把握し、戦略的にアプローチすれば、成功の可能性は高まります。
自社に合った採用手段を選び、採用ページや面接対応などを丁寧に改善していくことで、優秀なエンジニアと出会えるチャンスは確実に広がっていきます。
おすすめなのが、AIを活用したスカウト型の採用サービス、RecUpです。企業の採用ニーズにマッチする候補者をAIが自動で分析し、最適な人材へアプローチします。インフラエンジニアのような希少な人材にも効率よく接点を持つことが可能になります。
スカウト文の自動作成機能や返信率の高いタイミングでの配信など、採用担当者の負担を軽減する工夫も満載。人材不足に悩む企業にとって、非常に心強いサービスです。
ぜひ公式HPから詳細をチェックしてみてください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。