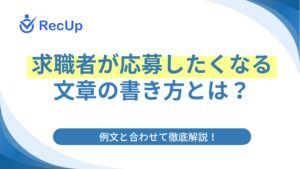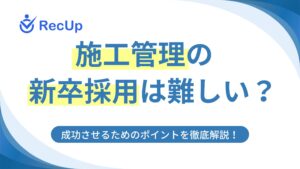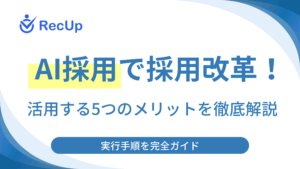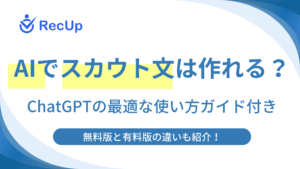企業の新卒採用において、今やSNS広告は欠かせない存在になりつつあります。就職情報サイトや合同説明会だけでは学生の関心をつかみにくくなり、情報過多の中で埋もれてしまうことも少なくありません。
そこで注目されているのが、学生が毎日利用するSNSを通じた広告活用です。身近なプラットフォームで企業の魅力を発信することで、自然にリーチでき、早い段階から応募意欲の醸成につながります。
一方で、媒体の選び方やメッセージ設計を誤ると、期待するほどの効果が出ない可能性もあります。そのため、学生の感覚に寄り添いながら、戦略的にSNS広告を運用することが成功のポイントになります。
この記事では、SNS広告を活用した新卒採用のメリットとデメリット、媒体ごとの特徴、効果的な運用のコツ、さらに実際の成功事例までを徹底的に解説します。採用活動に新しい一手を加えたい人事・採用担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
今すぐ無料で相談するSNS広告は新卒採用に有効?メリットとデメリットを整理

新卒採用にSNS広告を導入する際には、その効果やリスクを正しく理解することが大切です。求人媒体や合同説明会では接触できない層にリーチできる一方で、発信の仕方を誤れば学生に逆効果となる可能性もあります。
企業の採用戦略を練る際には、強みと注意点をバランスよく把握することが重要です。ここではまず、SNS広告がなぜ学生に届きやすいのか、従来の媒体との違いやデメリットも含めて整理していきます。
なぜSNS広告が学生に届きやすいのか
SNSが学生に届きやすい最大の理由は、生活導線の中に自然に情報が流れ込む点にあります。
例えば大学生の1日の平均SNS利用時間は複数の調査で3〜4時間とされており、空き時間に何度もアプリを立ち上げる習慣が根付いています。その中で、興味関心に基づいて表示されるアルゴリズム広告は、学生本人が検索していない状態でも接触を生むことができます。これにより、就活をまだ本格化していない時期に「何となく気になる企業」として意識させられるわけです。
さらにSNSはテキストだけでなく画像や動画に強く、企業文化や社風を視覚的に伝えられる点でも優れています。例えば、オフィスの雰囲気や先輩社員の声をショート動画で発信すると、学生は自分が働く姿を自然とイメージできます。
これは文字情報の多い求人サイトでは得がたい体験であり、新卒世代の価値観にマッチします。つまりSNS広告は、単に情報を届けるだけでなく、学生の記憶に残る「体験価値」を作り出せるのです。
新卒採用にSNSを使うメリットとリスク
SNS広告のメリットは、まず「費用対効果の高さ」が挙げられます。少額でもターゲットを絞って出稿できるため、大手だけでなく中小企業や地方企業も導入しやすいのが特徴です。
さらに、広告をクリックした学生を「採用ページ」「エントリーフォーム」へ直接つなげられることは、従来の媒体にはないメリットです。学生が関心を持った瞬間にアクションを起こせるため、応募への転換率を高めやすくなります。また、配信結果の数値データをその都度確認できるので「どんな広告が効果的か」を裏付けをもって検証できる点も大きいです。
一方でSNS広告にはリスクも存在します。なかでも炎上リスクは軽視できません。学生は企業発信に敏感で、上から目線の表現や不適切なクリエイティブは一気に拡散され、マイナスのイメージが広がるおそれがあります。また、広告が単なる宣伝にとどまり「学生の共感」を得られない場合、逆に関心を失わせてしまうこともあります。
そのためSNS広告は「学生の目線を理解して発信する」という意識が絶対条件になるのです。
従来の求人媒体との違い
従来の求人媒体との大きな違いは、アプローチのタイミングと接触方法にあります。
求人媒体は「就職活動を始めた学生」が情報を能動的に探しに行く場所であり、エントリー前提の層に効率的でした。しかしSNS広告は「就活を意識し始める前の層」にも自然に情報を届けられるため、潜在層に働きかけられる魅力があります。早期から企業を意識させることで、説明会や選考に進んだ際に印象を持ってもらいやすくなるのです。
さらに従来の求人サイトは学生が「検索」してはじめて接触するプル型ですが、SNS広告は学生が情報を受動的に受け取るプッシュ型です。これにより、企業側が伝えたい情報を必要なターゲットに直接届けられるのが特徴です。また、SNSの広告フォーマットは動画やカルーセルなど多様で、インパクトのある訴求方法を取りやすいのも大きな違いです。
求人媒体とSNS広告を競合関係で見るのではなく、それぞれの役割を理解し併用することで、より効果的な採用活動を実現できるでしょう。
新卒採用でSNS広告を効果的に運用する6つのポイントを解説!

SNS広告は、ただ配信するだけでは成果を出すことができません。学生の関心を引きつけ、自社の魅力を効果的に伝えるためには、戦略的な設計が求められます。特に新卒採用では、短期間で母集団を形成しなければならないため、効率的かつ継続的に学生に接触できるSNSの特性を最大限に活かすことが鍵になります。
ここでは、新卒採用でSNS広告を運用する際に押さえておくべき6つの重要ポイントを詳しく解説します。どれも実践的で、すぐに取り入れられる内容ですので、ぜひ自社の採用活動に役立ててください。
①ターゲット設定を明確にする
SNS広告運用の最初のステップは、狙うべき学生層を徹底的に具体化することです。専攻分野や学年、居住地域といった顕在的な条件だけでなく、部活動や趣味、関心分野など、潜在的な特性をも考慮したターゲティングが求められます。
例えば、理系採用を強化したいのであれば、工学系やIT関連のコミュニティをフォローしている学生を中心に設定するなどが効果的です。ターゲットが曖昧だと広告の内容もぼやけ、結果的に学生の関心を引けない可能性が高まります。
またSNS広告は、他の媒体に比べてターゲティング精度が非常に高いのが特徴です。地域や年齢といった基本情報に加えて、アルゴリズムが興味関心を自動的に分析し、適したユーザーに優先的に広告を表示します。
この機能を活用すれば、就活に積極的でない学生に対しても早期に企業を認知させることが可能になります。明確なターゲット設定は、限られた広告予算を無駄なく活かすための基本中の基本なのです。
②学生目線を意識したクリエイティブ制作を行う
SNS広告の成果は、配信するクリエイティブに大きく左右されます。ここで重要なのが「学生目線」を徹底的に意識することです。企業が伝えたいメッセージをそのまま出すのではなく、学生が共感できるストーリーや表現に落とし込む必要があります。
例えば「安定した企業基盤を持つ」ことを訴求したい場合、堅い言葉よりも「先輩社員が安心してキャリアを築けている事例」を動画やインタビューとして見せる方が効果的です。
さらに新卒世代は、押し付け感のある宣伝よりも、自分と重ね合わせられるナチュラルな表現を好む傾向があります。そのため、過度な演出ではなく、等身大の社員の姿や働く現場の雰囲気を盛り込むことが大切です。
また、広告用のテキストは長文よりも短く端的にまとめ、ビジュアルとの組み合わせで直感的に理解できる構成にすると反応率が高まります。学生にとって「この会社なら自分も働けそう」と思わせる具体的なきっかけを作ることが、優れたクリエイティブ制作の目標です。
③定期的に更新していく
SNS広告は、一度配信しただけで終わりにするのではなく、継続的に更新することが成功への近道です。学生がSNSを利用する頻度は非常に高いため、広告が毎日更新されるタイムラインの中で埋もれてしまうリスクも考えなければなりません。
同じ広告を長期的に出し続けると、学生の目に新鮮味を欠き、クリック率やエンゲージメント率が下がる傾向があります。そのため、内容やデザインを一定のサイクルで更新することが重要です。
更新の際は、ただ新しく作り直すだけでなく、過去の配信データを分析して改善点を洗い出すと効果が高まります。
例えば、動画広告の視聴完了率が低ければ、尺を短縮したり冒頭にインパクトのある要素を加えるといった調整が有効です。つまり、定期的に更新を行うことは単なる「新規作成」ではなく、「ブラッシュアップの積み重ね」であるべきなのです。この姿勢を持つ企業ほど、学生の反応を安定的に引き出す広告運用が可能になります。
④ハッシュタグ機能を活用する
SNS広告を広げる上で、ハッシュタグは非常に強力な武器になります。特にInstagramやXでは、学生が興味のある分野やキーワードを検索するときにハッシュタグを使う習慣が定着しています。したがって、広告で適切なハッシュタグを併用することで、広告のリーチ範囲を自然に広げられるのです。
例えば「#就活準備」「#27卒」「#企業研究」などのタグを活用すれば、就活関連の情報を求めている学生が自然に広告と接触する機会が増えます。また、企業独自のオリジナルハッシュタグを設定し、複数の投稿で一貫して利用するのも効果的です。
これによって学生が関連投稿をまとめて閲覧しやすくなり、企業全体のブランディング力も高まります。ハッシュタグは小さな工夫で大きな成果をもたらすため、広告戦略の一部として計画的に取り入れるべきです。
⑤社員を巻き込む
SNS広告の効果を最大化するには、採用担当者だけでなく社員全体を巻き込む姿勢が不可欠です。広告そのものだけでなく、社員が自発的に自身の言葉で発信するコンテンツが加わると、学生にリアルな雰囲気が伝わりやすくなります。社員の声は広告より強い信頼感を与え、学生が「本当に働いている人が言っていることなんだ」と感じられる点で有効です。
例えば、社員が社内の出来事を簡単にシェアしたり、求人キャンペーンに参加して投稿を拡散する仕組みを整えるだけでも、広告の到達範囲は大きく広がります。企業の公式アカウントが発信する情報と、社員個人の発信が連動することによって、学生は企業文化を立体的に理解することができます。採用広報を「自社全体で取り組むプロジェクト」とすることが、SNS広告をより強力に活用するための秘訣です。
⑥データに基づいた改善を繰り返す
SNS広告の最大の強みは、数値データを詳細に確認できる点にあります。クリック率、エンゲージメント率、動画視聴完了率など、多角的な指標をその都度把握し、効果の高い広告と低い広告を比較することで改善につなげられます。このデータ活用こそが、従来の求人媒体にはないSNS広告ならではのメリットです。
例えば、同じ広告テキストでも画像を変えるだけでクリック率が倍増する例は珍しくありません。そのため、A/Bテストを小さく繰り返し行い、最も反応の良い広告を蓄積していくことが重要です。改善サイクルを怠ると、学生の嗜好やトレンドの変化に取り残されるリスクがあります。
反対に小まめにデータに基づく改善を積み重ねれば、少ない予算でも大きな成果を上げることが可能になります。SNS広告の運用は、「試行錯誤を前提」として回していくのが成功への道筋です。
どのSNSが新卒採用に向いている?媒体別の特徴を解説

SNS広告を新卒採用に活用する際には、媒体ごとの特性を把握することが欠かせません。
SNSには、InstagramやTikTokのようにビジュアルに強いプラットフォームもあれば、X(旧Twitter)のように拡散性の高さが特徴のものもあります。また、FacebookやLinkedInは利用者数こそ学生層全体の中では限定的ですが、他のSNSにはない信頼性と専門性を持つものもあります。
また、学生がどのSNSをどのような目的で利用し、どんなコンテンツに関心を示しているかを理解することで、より的確なアプローチをすることができるでしょう。
Instagram:学生の生活感に訴求しやすい
Instagramは、特に大学生の利用率が高いSNSの一つであり、日常のシェアやトレンド発信の場として幅広く浸透しています。写真や動画で直感的に情報を伝えられるため、企業の雰囲気や社員の姿をリアルに見せるには最適なプラットフォームです。学生は「自分がそこで働く姿」をイメージしたいと考えているため、オフィスや働く社員の様子を自然に切り取った投稿は強い影響力を持ちやすくなります。
またInstagramのストーリーズ機能やリール機能は、短時間で多くの情報を届けられる手段として有効です。例えば「社員の1日を追うショートムービー」や「採用担当者からのメッセージ」を配信することで、応募意欲の醸成につなげられます。さらにハッシュタグ文化が根付いているため、「#就活準備」「#27卒」など学生が調べやすいタグを活用すればリーチを拡大できます。Instagramは感覚的な共感を呼びやすく、採用広報において親近感を演出できる点が大きな魅力です。
一方で、Instagramはビジュアルに依存するため、クリエイティブの質がそのまま成果につながります。画質やデザインの完成度が低い投稿は学生にネガティブな印象を与えかねないため、写真や動画の撮影・編集には十分な注意が必要です。広告予算に加えて、ビジュアルコンテンツの制作体制を整えることが成果創出に欠かせません。
X(旧Twitter):拡散力とリアルタイム性が強み
Xは、情報が拡散されやすく、リアルタイムで学生に情報を届けられるSNSとして大きな特徴を持っています。学生は日常的にトレンドを確認するため、企業の投稿も自然にタイムラインに流れる可能性が高いです。ニュース性のある情報やイベント告知など、即時性を求められる発信では特に効果を発揮します。就活のピークシーズンや説明会の日程告知などは、Xを通じて広く拡散できるため、母集団形成に直結します。
さらに、学生が「リツイート」や「いいね」を通じて広告や投稿を拡散していくため、自社のフォロワー以外にも認知が広がりやすいのが大きな魅力です。例えば、面白みを持たせた広告やキャンペーンを企画すれば、学生同士の間で自然に共有され、広告費以上の効果を得られることもあります。タイムリーな話題を組み込み、親しみやすいトーンで発信することが成功の鍵になります。
ただし拡散力が強い分、炎上リスクには十分注意しなければなりません。表現が不適切だったり、学生の感覚からずれていた場合、批判が一気に広がる危険性があります。投稿前に複数人でチェックする体制を整え、慎重に情報を発信することで、ポジティブな拡散を意識しましょう。Xは扱い方次第で「バズ」を生み出す大きな可能性を持つ媒体です。
TikTok:短尺動画で企業文化を伝える
TikTokは短尺動画形式が中心のSNSで、大学生の間でも飛躍的に利用者が増加しています。視覚的に訴えかける動画は学生に強い印象を残しやすく、企業のカルチャーや働き方を感覚的に理解させる効果があります。広告としても「縦型動画フォーマット」が主流であり、自然にタイムラインに溶け込むため、学生が違和感なく閲覧できます。
採用活動においては「職場ツアー」「先輩社員の自己紹介」「社内イベントの様子」など、数十秒で伝えられる動画が親和性の高いコンテンツとして有効です。特にZ世代は動画を通じた情報収集が習慣化しているため、文字や画像よりも動画が与えるインパクトは絶大です。結果として、TikTokは企業文化や雰囲気を短期間で多くの学生に印象づけるのに優れた媒体だといえます。
またTikTokはエンタメ要素が強いため、硬すぎるトーンよりも親近感を持たせた軽快な表現が好まれます。例えば採用担当者や社員が出演して「一問一答」をする動画などは、学生との距離を縮めると同時に、柔らかい企業文化を伝えられます。動画編集が手軽になっている一方で、中途半端な仕上がりは逆効果となるため、企画力と短時間でメッセージを届ける構成力が求められます。
Facebook・LinkedIn:信頼性・専門性の高い情報発信
Facebookは学生層の利用率が以前に比べて減少しているものの、コミュニティ形成やイベント告知の場としては一定の役割を果たします。特に大学の研究室や学科単位では、Facebookグループが現役で活用されており、そこにリーチする形で広告を展開できる可能性があります。
一方、LinkedInは日本国内ではビジネス層寄りのプラットフォームですが、外資系志望の学生や意識の高い層では利用が進んでいます。企業の信頼性や専門性を示す場として活用でき、研究分野や国際志向を持つ学生との接点を作りやすい点が特徴です。例えば採用関連の記事コンテンツをLinkedInに投稿すれば、他のSNSに比べ知識志向の強い学生に刺さりやすくなるでしょう。
これらの媒体はInstagramやTikTokほどライトな接触は見込めない反面、「真剣に情報を集めている学生層」に確実にアプローチできる強みがあります。広く母集団形成を狙うのではなく、学生の特性に応じて「信頼性・専門性を持った発信チャネル」として併用するのが効果的です。
実際の成功事例とは?SNS広告で成果を上げた企業
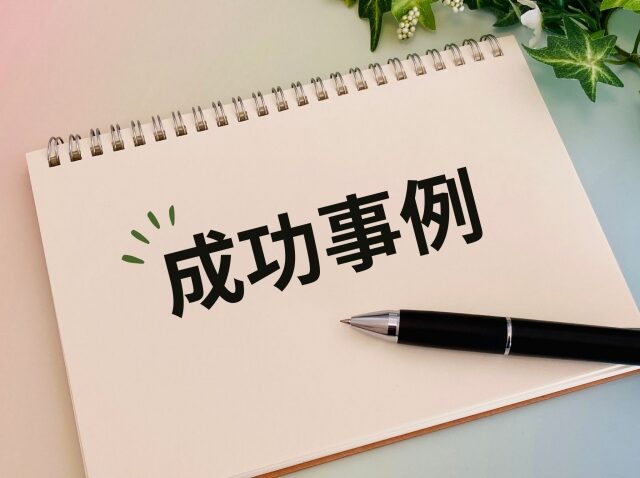
SNS広告が新卒採用に効果的だと分かっても、「実際にどのような場面で結果につながったのか」を理解しなければ運用のイメージは掴みづらいものです。
そこでここでは、SNS広告を戦略的に活用して成果を上げた企業の事例を取り上げます。各事例を通じて、自社でも応用できるポイントを見つけてみてください。
大手企業のブランディング強化事例
ある大手メーカーは、新卒採用における最大の課題として「学生にとって硬い・堅実なイメージが先行し、企業文化の柔らかさが伝わらない」という悩みを抱えていました。そこで同社はInstagramとTikTokを中心に、社員インタビューや社内のイベント風景をショート動画として広告配信する取り組みを開始しました。従来は合同説明会や就職サイトを通じてしか伝えられなかった社風を、SNS上で日常的に露出することで、企業イメージを刷新することに成功したのです。
特に効果が大きかったのは「若手社員のリアルボイス」を前面に出したシリーズ投稿でした。学生に近い世代の先輩社員が登場し、自身の就活体験や入社後の感想を語る形式が人気を集め、広告クリック率は同社の従来比で約2倍に向上しました。その結果としてインターンシップ応募者数が増加し、エントリー数全体も前年同期比で大幅に伸長しました。大手企業においても「堅実さ」と「親しみやすさ」を両立し、ブランディングを強化するにはSNS広告が有効に機能することを示しています。
中小企業が知名度を高めた事例
ある地方の中小IT企業は、知名度不足によって優秀な学生へリーチできないことが長年の課題でした。就活情報サイトに掲載しても、学生から積極的に検索されなければ埋もれてしまうことが多く、母集団形成に苦戦する状況が続いていたのです。そこで同社は予算を抑えながらもターゲティング精度の高いSNS広告に注目し、InstagramとXを中心に採用広報を展開しました。
戦略としては、まず動画広告で「地方から全国にサービスを発信する挑戦的な社風」を打ち出し、次に社員の普段の業務風景やオフィスの様子を写真とテキストで紹介するという、段階的な訴求を行いました。その結果、学生から「地元でこんなに将来性のある会社があるとは知らなかった」という声が多く寄せられるようになり、説明会参加者数は前年比で約1.5倍、エントリー数も飛躍的に増加しました。
この事例から分かるように、中小企業はSNS広告を活用することで地理的な制約や知名度不足を乗り越え、魅力を直接学生へ届けることが可能になります。ただし、そのためには「単なる情報発信」ではなく「学生が知らなかった新しい価値」を提示するストーリーを組むことが成功への鍵となります。
動画広告でエントリー数を増加させた事例
あるベンチャー企業では、事業のスピード感や「挑戦できる社風」を学生にどのように伝えるかに課題を持っていました。そこで注目したのがTikTokとYouTubeショートを組み合わせた動画広告戦略です。採用ターゲットである理系学部生やイノベーション志向の強い学生層に向けて、短尺の動画広告を継続的に配信しました。
動画の内容は「1日の業務を30秒で紹介」「プロジェクトの舞台裏を社員が語る」といったリアル感のあるテーマを中心に構成しました。その結果、学生の視聴完了率は高く、広告から採用サイトへ遷移する割合も大きく向上しました。特に印象的だったのは、動画を見て説明会に参加した学生のエントリー率が通常の約1.7倍に達した点です。これにより全体の応募数も過去最高を記録し、動画広告の即効性と訴求力が裏付けられました。
この事例が示すのは、若年層において文章や静止画よりも動画が圧倒的に強力な情報伝達手段になっているということです。採用においても「映像による体験の再現」がエントリー数に直結するため、今後のSNS広告戦略において動画活用は必須と言えるでしょう。
SNS広告を活用した新卒採用で差別化しよう

新卒採用においてSNS広告は、学生の生活導線に自然に組み込める有効な手段です。従来の求人媒体では届きにくい層にもリーチでき、動画や写真を用いることで直感的に企業文化を伝える力があります。一方で、炎上リスクや発信内容の質に対する厳しい目も存在するため、戦略的かつ誠実な姿勢が欠かせません。
効果的に活用するには、ターゲットを明確化し、学生目線を反映したクリエイティブを制作し、定期的な更新やハッシュタグを活用することが重要です。さらに、社員を巻き込んだ自然な発信やデータに基づく改善を繰り返すことで、成果は確実に積み重なります。また、InstagramやTikTok、Xなど各SNSの特徴を理解し、自社の課題に合った媒体を選ぶことも成功の鍵です。
SNS広告は単なる広報手段にとどまらず、学生の共感を引き出しエントリーへとつなげる強力なツールとなります。他社との差別化を目指す採用担当者は、ぜひ積極的に取り入れ、自社の未来を担う人材獲得に役立ててください。
今すぐ無料で相談する