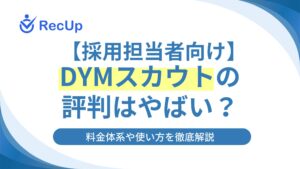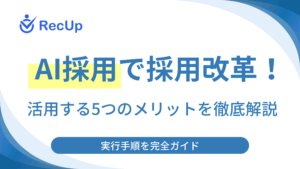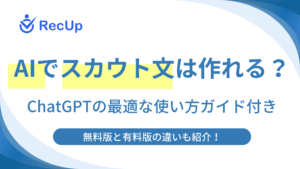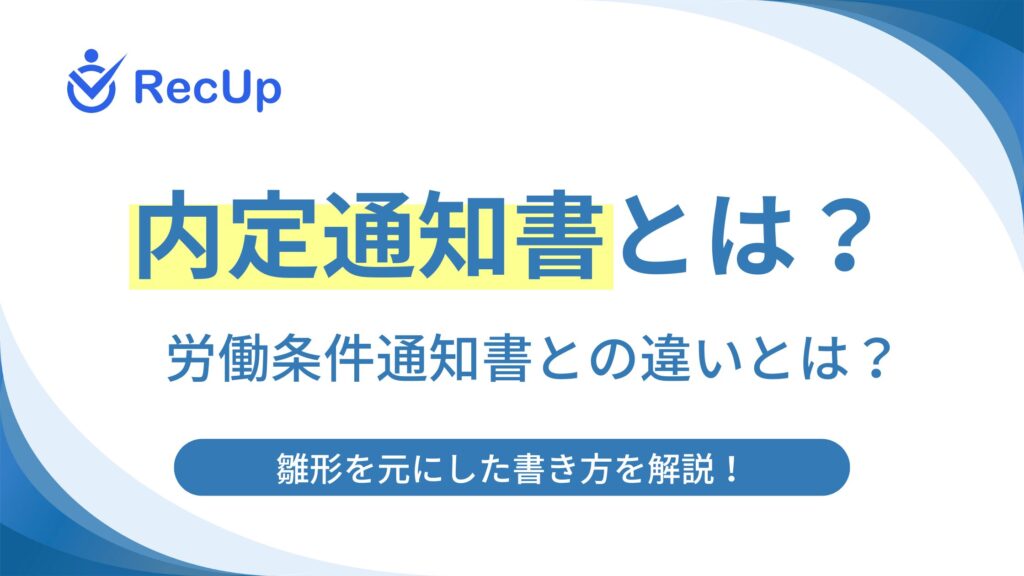
内定通知書は、企業が求職者に対して「あなたを採用します」という意思を正式に伝える重要な書類です。採用活動の最終段階で送付されるこの書類は、単なる合否連絡ではなく、内定者との信頼関係を構築する第一歩でもあります。
一方で、内定通知書と混同されやすいのが「労働条件通知書」です。両者の違いを理解し、適切に作成・送付することは、採用後のトラブル回避や円滑な労務管理のためにも欠かせません。
本記事では、内定通知書の法的な位置付けや書き方、雛形の活用法まで、詳しく解説していきます。
採用結果を伝える内定通知書とは?

内定通知書は、企業が採用候補者に対して正式に採用を通知する文書です。口頭での内定伝達だけでは記録として不十分なため、書面での通知を行うことで、双方の認識を明確にし、後々のトラブルを防ぐ効果があります。
まずは、内定通知書がどんな書類で、どのような効力を持っているのかについて解説しましょう。
法的効力
内定通知書は、採用決定の意思を正式に伝えるための重要な文書ですが、法的には「雇用契約書」とは異なります。つまり、内定通知書そのものには雇用契約の効力が自動的に発生するわけではありません。あくまで「採用予定である」という企業側の意思表示であり、労働契約が確定するのは、内定者がその内容を承諾し、実際に労働契約を締結した段階です。
ただし、注意すべきなのは「法的拘束力がまったくない」わけではない点です。裁判例では、企業が内定通知を出したあとに一方的に内定を取り消した場合、一定の条件下で“解雇に準じる行為”とみなされるケースもあります。
そのため、企業は軽い気持ちで内定通知を発行してはいけません。送付前に採用条件や選考結果を再確認し、内定取り消しが起きないよう慎重に判断する必要があります。
内定通知書に記載する文言も重要です。「採用を内定いたします」と明言する場合は、強い意思表示とみなされやすく、「採用予定といたします」などの表現にすれば柔らかい通知になります。
送付方法
内定通知書の送付方法には、主に「郵送」「メール」「手渡し」の3パターンがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、内定者の状況や企業の規模に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
まず最も一般的なのは郵送による送付です。特に正式な採用通知として扱う場合は、書留や簡易書留を利用し、受領記録を残すことが推奨されます。内定者に確実に届いたことを証明でき、トラブル時の証拠としても活用できるのです。
次に、最近増えているのがメール送付です。リモート採用や地方在住者の採用など、スピーディに通知を行いたい場合に便利です。ただし、メール本文だけで完結させるのではなく、内定通知書をPDF形式で添付し、改ざん防止のためパスワードを設定するのが望ましいです。
最後に、対面での手渡しです。小規模企業や採用説明会の場で内定を伝える場合に向いており、内定者に直接言葉を添えて説明できるのが利点です。どの送付方法を選ぶ場合も、「確実に届き、証拠が残る」形を意識することが基本です。
送付タイミング
内定通知書の送付タイミングは、採用決定が確定した直後、できるだけ早く行うのが理想です。特に複数社の選考を同時に受けている応募者に対しては、通知が遅れることで他社へ流れてしまう可能性があるため、スピード感が非常に重要です。
一般的には、最終面接から3〜5営業日以内に内定通知書を送付するのが望ましいとされています。その際、内定承諾書の返送期限を明確に設定し、スケジュール管理をしやすくしておくとスムーズです。承諾書の提出先や提出方法も併せて明記しておくと、内定者が迷わず対応できるでしょう。
企業によっては、口頭で先に内定を伝え、その後に正式な内定通知書を送付するケースもあります。この場合は、口頭連絡と書面内容に矛盾がないよう注意しましょう。特に給与額や入社日など、数字や日付が絡む情報は二重チェックが必須です。
労働条件通知書との違いを解説!

内定通知書と混同されやすいのが「労働条件通知書」です。どちらも採用に関する文書ですが、その目的や法的な位置づけはまったく異なります。
この2つを正しく区別できていないと、思わぬトラブルを招く可能性があります。ここでは、労働条件通知書の内容と、内定通知書との明確な違いについて詳しく見ていきましょう。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、労働基準法第15条に基づいて企業が労働者に交付する義務を負う書類です。この文書の目的は、雇用契約を結ぶ前に「どのような条件で働くのか」を明確に伝えることにあります。通知すべき項目は、賃金、勤務時間、休日、就業場所、契約期間、退職条件など、労働者が就労の可否を判断するうえで重要な要素です。
この書類を交付することによって、企業と労働者の間で条件の食い違いを防ぎ、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。書面の交付は義務であり、口頭で伝えるだけでは法的要件を満たしません。また、近年では電子交付も認められていますが、その場合でも内容の改ざん防止や受領確認の仕組みを整えておく必要があるのです。
労働条件通知書は、内定通知書よりも法的効力が強く、実際の労働契約の土台となる書類です。これを省略したり、記載に誤りがあったりすると、未払い残業や労働条件トラブルなどの原因になることもあるため、企業側には慎重な作成が求められます。
2つの通知書の違い
内定通知書と労働条件通知書の違いは、「目的」「法的効力」「交付の義務」にあります。内定通知書は採用決定を伝える“意思表示”であり、交付義務はありません。
内定通知書は企業が任意で作成する文書で、主な目的は「採用意思を明確にし、内定者に安心感を与えること」です。
一方、労働条件通知書は法律で交付が義務づけられた“契約関連書類”であり、実際の労働契約成立に関わる正式な文書です。
交付のタイミングにも違いがあります。内定通知書は採用決定後すぐに送付されるのが一般的ですが、労働条件通知書は入社日または労働契約締結時までに交付しなければなりません。
内定通知書は企業と内定者の信頼関係を築くための“礼儀的な書類”であり、労働条件通知書は法的義務を果たすための“契約的な書類”です。両者を正しく使い分けることが、採用後のトラブル防止と企業の信用維持につながります。
雛形に沿った内定通知書の書き方とは?
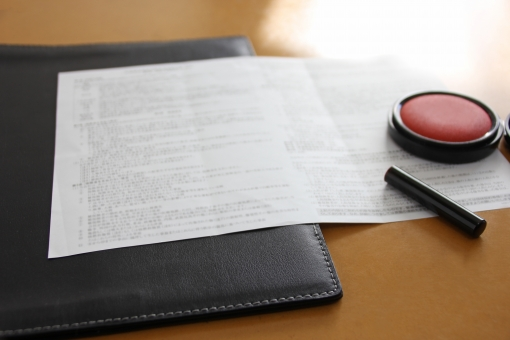
内定通知書を作成する際は、雛形に沿って必要項目を整理し、誤解を生まないような文面に仕上げることが重要です。内定者との最初の正式な書面やりとりとなるため、企業の印象を左右します。誤字脱字はもちろん、曖昧な表現や曖昧な条件提示は避けることが大切です。
以下で、基本的な構成などについてポイントを詳しく見ていきましょう。
内定通知書のテンプレート
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社
〒000-0000 東京都〇〇区〇〇町0-0-0
TEL:00-0000-0000〇〇〇〇 様
採用内定通知書
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、先般ご応募いただきました弊社の採用選考の結果、
貴殿を弊社の〇〇職として採用することを内定いたしましたので、ここに通知いたします。入社予定日は令和〇年〇月〇日を予定しております。
なお、雇用条件の詳細につきましては、後日お渡しする労働条件通知書にてご案内いたします。つきましては、同封の内定承諾書に署名・捺印のうえ、
〇月〇日までにご返送くださいますようお願い申し上げます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
以上
〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇 印
内定通知書のテンプレートは、ビジネス文書としての基本構成を押さえながら、誰が見ても内容が分かりやすい形に整えることが大切です。
全体のレイアウトは読みやすく整え、フォントサイズや余白のバランスにも配慮すると好印象です。テンプレートをそのまま使ってもある程度は問題ありませんが、自社の業種や採用フローに合わせて適宜調整することで、信頼性のある書面を作れるでしょう。
一般的な記入項目
内定通知書に記載すべき項目は、採用の基本情報を明確に伝えることを目的としています。まず必要な項目を以下にまとめました。
- 宛名
- 発行日
- 件名
- 採用決定の旨
- 入社予定日
- 勤務予定地
- 職種
- 連絡先
- 差出人情報(会社名・代表者名)
まずは、これら基本情報の記載が必須です。これらは誤記があるとトラブルに直結するため、必ず正確な情報を記載しましょう。
本文には、応募者への感謝と採用決定の文面を記載します。たとえば「貴殿を弊社の〇〇職として採用することを内定いたしました」と明確にし、その後に「入社日は〇月〇日を予定しております」と続けます。ここでは「予定」という表現を使い、法的拘束力を生じさせないように注意が必要です。
承諾書の返送期限や入社手続きに関する連絡事項も忘れずに記載しましょう。「〇月〇日までに内定承諾書をご提出ください」「入社に関する詳細は追ってご案内いたします」といった文言を入れることで、手続きの流れが明確になります。
これらの項目を正確に記入することで、応募者に安心感を与え、スムーズな採用手続きへとつなげられます。
内定通知書の記入例を紹介!

内定通知書は、採用担当者にとって応募者へ「正式な内定を伝える」重要な書面です。テンプレートを参考にしても、実際にどう記載すればいいか迷う担当者は多いでしょう。ここでは、実務で使える具体的な記入例を紹介します。
【内定通知書 記入例】
令和7年4月10日
株式会社サンプルテック
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1
TEL:03-0000-0000田中 花子 様
採用内定通知書
拝啓 春暖の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、このたびは弊社の採用試験にご応募いただき、誠にありがとうございました。
選考の結果、貴殿の入社が内定いたしましたので、ここに通知いたします。入社予定日は令和7年4月1日を予定しております。
雇用条件の詳細につきましては、後日お渡しいたします「労働条件通知書」にてご確認ください。つきましては、同封の内定承諾書に署名・捺印のうえ、令和7年4月20日までにご返送くださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、担当者(00-1111-0000)までご連絡ください。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。以上
株式会社サンプルテック代表取締役 町田太郎 印
このように、内定通知書の記入例では文体を丁寧語で統一し、「予定」「ご案内いたします」などの柔らかい表現を用いるのが基本です。法的拘束力を避けるために「採用いたしました」ではなく「採用することを内定いたしました」と表記する点も重要です。
このテンプレートをベースに自社名や日付を差し替え、必要に応じて内定承諾書の有無や担当者情報を追加することで、どの企業でも応用できる実務的な文面を作ることができるでしょう。
内定通知書を作成する際の注意点とは?

内定通知書は企業にとって、採用活動の最終段階で応募者へ信頼を伝える重要な文書です。内容に不備があると、内定辞退や誤解を招くトラブルの原因にもなるため、作成時は正確性と丁寧さの両立を意識することが大切です。
ここからは、実際に作成する際に気をつけるべき代表的なポイントを具体的に解説します。
記載ミスをしない
内定通知書の記載ミスは、最も起こりやすく、かつ信用を失う原因となりやすいミスです。特に、氏名・日付・入社予定日・職種・会社情報などは、誤りがあると応募者に混乱を与えるだけでなく、後日のトラブルに発展するリスクもあります。誤字脱字はもちろん、数字や日付の入力間違いも必ず複数人で確認することが望ましいです。
他の候補者の情報を誤って記載してしまうケースも少なくありません。これは最も避けるべきミスであり、個人情報の漏洩として企業の信用を大きく損ないます。特にテンプレートを流用する際は、差し替え忘れがないかを慎重に確認しましょう。
文体の統一にも注意が必要で、「です・ます調」と「である調」が混在すると、ビジネス文書としての完成度が下がります。社内で統一ルールを設け、複数の担当者が作成しても一貫した形式になるよう管理することが重要です。細部まで丁寧に確認する姿勢が、信頼を築く第一歩となるのです。
複数人に出す場合は宛先に注意する
複数の応募者に同時に内定通知書を送る場合、宛先の管理には特に注意が必要です。名前の入力ミスや宛名の差し替え忘れは、最も起こりやすいミスのひとつです。Aさん宛ての通知にBさんの名前が記載されていたとなれば、応募者の信頼を大きく損ねるだけでなく、個人情報保護の観点からも重大な問題となります。
メールで送付する際には、誤送信にも細心の注意を払いましょう。複数人に一括送信するのではなく、必ず個別に送信し、添付ファイル名やファイル内の宛名も一人ひとり確認するようにしましょう。
社内で共有する場合にも、個人名が含まれたファイルを複数部署にむやみに転送しないよう徹底します。宛先管理は地味な作業ですが、採用の信頼性を支える極めて重要な部分です。
会社印を押印する
内定通知書には、会社としての正式な意思表示であることを示すため、必ず会社印を押印します。押印がない書類は、受け取る側から見れば「正式な通知ではないのでは?」と疑念を抱かせる原因になりかねません。
一般的には、代表取締役印(実印)または会社角印を使用します。社内ルールによっては採用担当者の個人印を押すケースもありますが、正式な採用通知書としての信用度を保つためには、会社名義の印鑑を用いるのが基本です。印影が薄くならないよう朱肉の状態を確認し、印の位置は文末右寄せ、代表者名の下にきれいに押印するのが望ましいとされています。
電子データとして送付する場合も、押印欄を省略してはいけません。最近では電子印鑑(デジタルスタンプ)を使った書類が増えていますが、フォーマット上には会社名・代表者名・印影をしっかり配置し、見た目にも正式な書面であるとわかるように整えることが重要です。
受け取り確認ができるようにする
内定通知書を送付する際は、応募者が確実に受け取ったことを確認できる仕組みを整えることが大切です。郵送の場合は、普通郵便ではなく「簡易書留」や「特定記録郵便」を利用することで、配達記録を残すことができます。特に、内定承諾書の返送が必要なケースでは、往復書簡の形式を取ると管理がスムーズです。
メール送付の場合は、開封確認機能を活用する方法が有効です。送信後に「開封通知」を設定したり、ファイル転送サービスを利用してダウンロード履歴を確認したりすることで、受け取りの有無を客観的に把握できます。
送付後は電話やメールでフォロー連絡を行い、「内定通知書は無事届きましたでしょうか」と丁寧に確認を入れるのも効果的です。小さな気配りではありますが、応募者に安心感を与え、信頼関係を築く第一歩になります。
トラブルのない内定通知書を作成して、スムーズな採用手続きを進めよう!

内定通知書は、採用活動の最後を締めくくる重要な文書であり、企業と応募者の信頼関係を正式に形づくる第一歩でもあります。記載内容の正確さ・文体の統一・押印・送付方法の適正など、どれか一つでも欠けると、後のトラブルに発展しかねません。だからこそ、内定通知書は「迅速かつ丁寧に、そして誤解のない内容で」作成することが求められます。
特に注意したいのは、法的拘束力をもたせすぎない表現と、応募者への丁寧な対応です。「採用予定」と「内定決定」は似て非なるものです。曖昧な言い回しを避け、会社としての意志を明確に伝えつつも、最終的な労働契約は労働条件通知書で締結される旨をはっきり示すことが大切です。
送付後のフォローや承諾書の管理も怠らず行いましょう。内定通知書は単なる形式的な文書ではなく、企業の誠意を伝える手段です。細やかな配慮を積み重ねることで、応募者に「この会社で働きたい」と思わせる信頼を築けるでしょう。