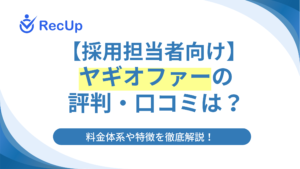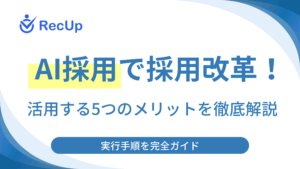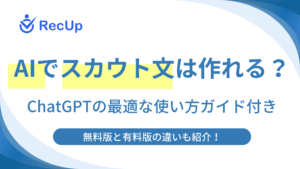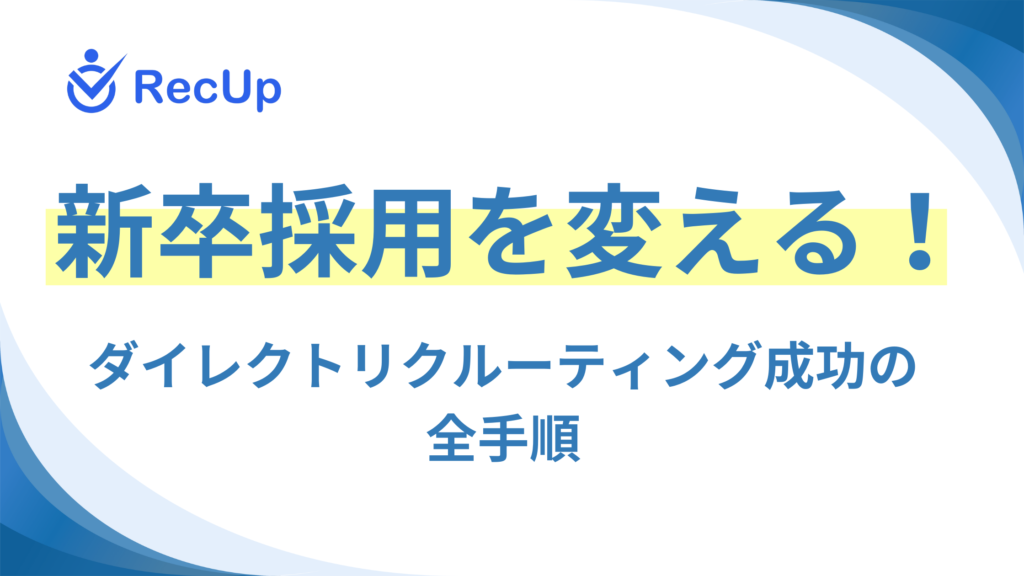
ここ数年、新卒採用の現場では「学生が企業を選ぶ時代」へと急速に移り変わっています。従来のナビサイト中心の採用活動では母集団の形成が難しくなり、特に優秀層とのマッチングに課題を抱える企業が増えています。
そんな中、注目を集めているのが、企業が自ら学生にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」です。企業が応募を“待つ”のではなく、自ら“探して口説く”という攻めの採用手法が、成果を大きく左右する時代に突入しました。
この記事では、新卒採用でダイレクトリクルーティングが注目されている理由や導入による効果、運用のポイントや成功事例まで、わかりやすく解説します。ぜひ自社に合った導入の方向性の検討にご活用ください。
なぜ今、新卒採用でダイレクトリクルーティングが注目されるのか

まずは、近年新卒市場で「ダイレクトリクルーティング」が多くの企業に注目されている理由について見ていきましょう。ダイレクトリクルーティングが注目されている理由には、さまざまな社会的な背景から就活のスタイルが変化していることが挙げられます。詳しく見ていきましょう。
ナビサイト依存の限界と母集団形成の変化
これまで多くの企業が採用活動の中心に据えてきたのが、マイナビやリクナビなどの新卒向けナビサイトを活用したオーソドックスな手法です。しかし、近年の調査では学生の登録数自体は堅調に増えているものの、企業側の掲載数も急増しているため、学生一人が目にする企業数には限りが生まれています。この結果、企業のエントリー獲得数が思うように伸びず、従来のような大量応募型の母集団形成が難しくなっています。
さらに、エントリー数を確保できた場合でも、ミスマッチによる辞退や説明会参加の低下、内定承諾に結びつかないケースが目立ちます。学生の行動として「とりあえずエントリーする」スタイルも減少し、双方向かつ個別性の高いコミュニケーションがより求められるようになりました。
こうした市場変化の中で、企業が自らターゲット学生に直接アプローチできる「ダイレクトリクルーティング」が改めて注目されています。この手法は、「数」による母集団形成から「質」を重視した採用へシフトする上で非常に有効と言えます。ナビサイトだけではカバーしきれない優秀層や意欲層にもリーチできるため、新卒採用戦略の柱として導入している企業も急増しています。
学生の就活行動が「待ち」から「選ぶ」へ変化している背景
Z世代の新卒学生は、就職活動において「待ち」の姿勢から「自ら選ぶ」姿勢へと大きく変化しているのも、ダイレクトリクルーティングが注目される理由です。彼らはデジタルネイティブならではの情報収集力を活かし、SNSや口コミサイト、OB・OG訪問など多様なチャネルを駆使して主体的に企業研究を進めています。
また、SDGsや社会課題への関心が高まり、早期からキャリア教育や探究学習で「自分らしさ」や社会に貢献したい意識を育んできているのも特徴です。勤務地や働き方、企業のリアルな価値観や制度など、多面的な視点で企業を見極めるスタイルが一般化しています。この結果、学生は単純な募集情報や知名度だけで就職先を選ぶことは少なくなり、むしろ自分の条件や将来像を重視し「企業を選びながら」自ら行動を起こすようになっています。
企業側も従来のアプローチでは埋もれてしまうリスクが強まっており、“求める学生にピンポイントで働きかける”採用戦略が不可欠になりました。ダイレクトリクルーティングは、このような能動的な学生のニーズに応える有力な手段として注目されており、相互に納得度・マッチ度の高い採用に繋がっています。
企業が“能動的に出会う”採用へシフトすべき理由
少子化による学生数の減少や、採用スケジュールの早期化、インターンシップの重要度の高まりなどにより、2025年の新卒採用市場はかつてないほど競争が激化しています。限られた期間で多くの学生にアプローチする従来型の採用手法では、母集団形成やマッチングの精度が低下し、採用単価の上昇も課題となっています。
一方で、ダイレクトリクルーティングは、企業が求める人物像を明確にしたうえで、学生のプロフィールや志向性、価値観に合わせてピンポイントでアプローチできるのが強みです。採用の“数”よりも“質”を重視する傾向が高まっている社会的な背景もあるでしょう。
このように、「待ち」の採用から「出会いに行く」能動的な採用活動への転換こそが、今後の新卒採用競争を勝ち抜くためのカギとなっています。早期からターゲット学生と関係を築き、内定後の定着率向上や企業のファン化に繋げることが大事です。
ダイレクトリクルーティングで変わる3つの採用効果

新卒採用にダイレクトリクルーティングを導入すると、これまでの採用活動では得られなかった新たな効果が表れます。従来の手法では難しかったターゲット層への直接アプローチが可能になり、採用の「質」「コスト」「企業イメージ」という3つの側面で大きなメリットをもたらします。
ここでは、その中でもとくに注目すべき3つの効果について、具体的に解説していきましょう。
効果① 優秀層や意欲層とのマッチング精度が高まる
ダイレクトリクルーティングの最大の特徴は、企業が学生のプロフィールやスキル、志向性を詳細に把握したうえで、ピンポイントでスカウトを送れる点にあります。これにより、求める人物像や価値観に合った学生へ直接アプローチでき、採用後のミスマッチを大幅に減らすことが可能です。
一方、学生にとっても、自分に関心を持つ企業から複数のスカウトを受け取ることで、より自分に合った企業を選びやすくなるというメリットがあります。企業と学生の双方が能動的にコミュニケーションを取ることで、内定承諾率の向上や早期離職の防止にもつながります。
さらに近年では、AIや高度なマッチングアルゴリズムの進化により、表面的なスキルだけでなく、企業文化とのフィット感や将来性までを考慮した精度の高いマッチングが可能になりました。こうした技術の進歩により、企業と学生の「本当に良い出会い」が生まれやすくなっています。
効果② 採用コストの削減ができる
従来のナビ媒体や合同説明会では、多額の掲載料や参加費用が発生しながらも、必ずしも効率的な採用につながらないケースが少なくありません。ダイレクトリクルーティングは、企業が求める人材に絞って直接アプローチできるため、広く広告を打つ従来手法と比べて費用対効果が高いのが大きな特徴です。
また、ミスマッチによる不必要な面接や選考を減らし、的確な人材へのアプローチで選考効率が向上するため、時間的なコストや人件費の削減にもつながります。採用活動を効率化することで運用負担を軽減させることができるのです。成果報酬型のサービスを利用する場合は、実際に面談や内定承諾が成立した学生に応じて費用が発生する仕組みのため、さらに無駄なコストを抑えることができるでしょう。
これらのことから、ダイレクトリクルーティングは限られた予算で最大の効果を狙いたい企業にとって合理的な採用手法として評価されています。
効果③企業ブランディング力が向上し、学生の認知拡大につながる
ダイレクトリクルーティングは、学生一人ひとりに合わせたメッセージ発信が可能なため、単に企業情報を発信する以上に、学生の関心や将来像に沿った訴求ができるというのも特徴です。パーソナライズされたコミュニケーションをとりつつ企業の魅力を具体的かつリアルに伝えれば、採用活動の初期段階から共感度の高い学生を惹きつけることができるでしょう。
また、こうしたやり取りは学生間の口コミやSNSで拡散され、企業のブランディングが高まる可能性もあります。企業ファンを増やすことは、長期的な採用成功の基盤形成につながります。ダイレクトリクルーティングは、単なる目先の採用手法ではなく、企業の価値向上と組織強化にもつながる戦略的施策と言えるのです。
導入前に押さえるべき!新卒ダイレクトリクルーティングの注意点

新卒のダイレクトリクルーティングは、ターゲット学生に直接アプローチできる魅力的な採用手法です。しかし、導入すればすぐに成果が出るわけではなく、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。
成否を分ける主な要素として、運用負担の大きさ、成果が見えるまでの期間、そして既存チャネルとの併用戦略の3つが挙げられます。これらをあらかじめ把握し、適切な体制とスケジュールを整えておくことで、導入後の失敗リスクを大幅に減らすことができます。詳しく見ていきましょう。
スカウト文面・送信設計など、運用負担が発生する
ダイレクトリクルーティングでは、学生一人ひとりの関心や志向に合わせたスカウト文面の作成が欠かせません。画一的なメッセージでは反応率が下がりやすいため、プロフィール内容や志望動機を踏まえた個別対応が求められるのです。さらに、スカウト送信のタイミングや頻度の設計、学生からの返信対応や進捗管理など、運用面でのタスクも多岐にわたります。
これらをすべて手作業で行うと大きな負担となるため、場合によっては専任担当者の配置やスカウト支援ツールの活用が必要となるでしょう。適切なリソースを確保しないまま運用を続けると、対応の遅れやテンプレート感のある返信が増え、学生にネガティブな印象を与えるリスクもあります。質とスピードを両立するためには、運用設計を事前にしっかり固めておくことが重要です。
以下の記事では、ダイレクトリクルーティングの運用負担を軽減する手段として注目されている「AIスカウトツール」について詳しく解説しています。スカウト文面の自動作成やターゲット選定を効率化したい企業の方は、ぜひ併せてご覧ください。
【2025年最新】AIスカウトサービス15選を徹底比較!メリットや選ぶ際のポイントを解説
成果が見えるまで一定の運用期間が必要
ダイレクトリクルーティングは、短期間で効果を出そうとすると挫折しやすい施策です。導入初期はスカウト送信数に対して反応が少なく、なかなか成果が見えにくいこともあるからです。そのため、学生の興味関心や業界トレンドに合わせて文面やターゲティングを見直しながら、PDCAサイクルを数か月単位で回し続けることが大切です。
また、成果が出るまでには忍耐力と長期的な視点が欠かせません。焦って頻繁に方針を変えてしまうと、学生に一貫性のない印象を与え、かえって反応率が下がる可能性もあります。
効果検証を行いながら段階的に改善を重ね、少なくとも3〜6か月は腰を据えて運用することが理想です。スカウトの反応率から面談設定率、内定承諾率へとつながる流れを継続的に追いながら、仮説と検証を繰り返すことが、ダイレクトリクルーティング成功のカギとなります。
ナビ媒体との併用戦略でリスクを分散する
ダイレクトリクルーティングは効果的な採用手法である一方、単独での運用にはリスクも伴います。特に導入初期はノウハウの不足や反応率のばらつきが起こりやすく、採用計画全体の安定性を欠く恐れがあります。そのため、従来のナビサイトや合同説明会、リファラル採用などと併用し、複数チャネルからの母集団形成を並行して行うのが理想的です。
複数チャネルを組み合わせることで、ターゲット層ごとの特性に合わせた柔軟なアプローチが可能になり、どのチャネルにも依存しないリスク分散型の採用活動を実現できます。また、各チャネルのデータを分析して成果を比較すれば、自社に最も合った採用戦略の最適化にもつながるでしょう。
目的別に選べる!新卒向けダイレクトリクルーティングサービスの比較

新卒採用でダイレクトリクルーティングを活用する際、企業の目的や採用ターゲットによって適したサービスは変わります。特徴やコスト形態、掲載方式などの違いが大きく影響するため、自社に合ったサービス選びが重要です。
ここでは、ターゲット学生層別、コストや掲載方式別のダイレクトリクルーティングを紹介し、それぞれのサービスの特徴を解説します。ぜひ自社の状況と比較して、「これぞ」というサービスを見つけてみてください。
ターゲット学生層別|総合型・理系特化・ベンチャー志向型
ダイレクトリクルーティングのサービス選びでは、まず自社が採用したい学生層を明確にすることが重要です。
ダイレクトリクルーティングサービスには、総合的に幅広い学生を網羅するタイプから、理系学生に特化したもの、ベンチャーやスタートアップ志向の学生に強いものまで多様な選択肢があります。
下記に、それぞれのターゲット別のサービスの特徴と注意点、代表的なサービスについてまとめました。
| ターゲット学生層 | 特徴・メリット | 注意点 |
| 総合型 | 文理問わず幅広い学生にアプローチ可能。幅広い人材による母集団形成に最適。 | 人材が幅広い反面、本当にフィットする人材確保にはスカウト文面や条件の調整が必要。 |
| 理系特化型 | 技術・研究職志望の理系学生に強み。専門的プロフィールで高精度マッチング。 | 登録者数は総合型より少なめ。複数媒体併用や評価軸を文面に反映する工夫が必要。 |
| ベンチャー志向型 | 挑戦・成長志向の強い学生にリーチ。ベンチャーや成長企業に適す。 | 母集団数が限られるため他媒体との併用が推奨。魅力的な社風やストーリー訴求が必須。 |
総合型は多様な学生と幅広く接点を持ちたい企業に向いていますが、理系特化型は技術・研究職採用に、ベンチャー志向型は挑戦意欲の高い人材獲得に特化しています。それぞれの特徴を踏まえて、狙いたいターゲットと企業の採用戦略に合わせて最適な媒体を選定しましょう。
コスト・掲載方式別|成果報酬型/定額制の違い
ダイレクトリクルーティングの費用体系は大きく分けて成果報酬型と定額制に分かれており、多くのサイトではどちらかを企業が選択できるようになっています。
成果報酬型は面談成立や内定承諾などの成果に応じて費用が発生する仕組みで、定額制は月額や期間ごとに定められた利用料を支払う形になっています。それぞれの特徴や注意点、向いている企業については下記の通りです。
| 料金体系 | 特徴 | 注意点 | 向いている企業 |
| 成果報酬型 | 採用が決定した場合に費用が発生。年収の15~20%程度が相場。 | 採用人数増で総コスト増。採用遅延で効率悪化。 | 少数採用やスポット採用で初期投資抑制したい企業 |
| 定額制 | 月額・期間契約制。スカウト通数や採用人数などでプランが変わる。 | 採用がなくても費用発生。計画的な利用が必要。 | 複数名同時採用や長期運用を計画する企業 |
また、OfferBox、dodaキャンパスのように、定額制で募集をしてプランの人数を超える場合には成果報酬型に自動的に移行されるサイトも多いです。この仕組みを上手く利用すれば、定額制で決まった人数を採用し、優秀な人材が多く集まっている場合には成果報酬型で採用するという、ハイブリッド型の採用を行うことも可能です。
そのほか、定額制とは少し異なり、特定のキャンペーン採用、インターンシップ参加者募集、季節限定の合同説明会など、特定の期間や採用プロジェクトだけ短期間で利用できるスポット契約型という採用形態を提供しているサイトもあります。これは、一時的な母集団形成が求められる場面で効果的です。
自社の採用計画や予算に合わせて最適な料金体系を選ぶようにしましょう。
主要なダイレクトリクルーティングのサービスと特徴
上記でご紹介したダイレクトリクルーティングサービスの料金体系や特徴、向いている企業についても見ていきましょう。
| サービス名 | 料金体系 | 主な特徴 | 向いている企業 |
| OfferBox | 成果報酬型早期定額型 | 採用1名あたり38万円の成果報酬制、早期定額型は3名75万円~。スカウト枠制限で開封率87%の高水準。 | 積極的母集団形成を行う企業。大手から中小企業まで幅広く対応。 |
| dodaキャンパス | 定額制成果報酬型 | 定額制は3名60万円~、成果報酬は35万円/人。低学年層へのアクセス強化や長期の採用戦略に強み。 | 大手パーソルグループの安心感。長期・多角的採用計画に対応。地方の採用に強み。 |
| キミスカ | 定額制成果報酬型 | 定額プラン中心、成果報酬は35万円/人の追加料金あり。業界・職種問わず幅広く母集団形成可能。 | 中堅・中小企業に適し、コストパフォーマンス重視の企業向け。 |
| iroots | 成果報酬型 | 初期費用90万円~+成果報酬。理系特化で、詳細プロフィール+価値観分析で上位校理系層に強い。 | 技術系・理系専門職の採用をしたい企業。高度専門職を獲得したい企業。 |
| LabBase | 定額制スポット契約型 | 利用期間やスカウト数に応じた定額料金。理系院生・研究者中心で短期・スポット的な採用におすすめ。 | 高度専門職や限定的な理系人材採用を目指す企業。 |
| TECH OFFER | 成果報酬型定額制プラン有り | 成果報酬は49.8万円+1名あたり85万円。IT・理系に特化し自動オファーなど機能も充実。 | IT・理系専門職で即戦力を求める企業。 |
| チアキャリア | 主に定額制 | 月額3~9万円の複数プラン。ベンチャー・成長企業志望者多数で、文化・社風訴求に強み。応募率・開封率ともに高い。 | 特にベンチャー企業やスタートアップ企業。成長意欲が高い人材雇用を考えている企業 |
| Wantedly | 定額制 | 月額利用料で無制限スカウト可能。企業ビジョンと文化で学生を引きつけファン採用が可能。 | 特にスタートアップ企業やベンチャー企業。企業理念や社風に共感する学生と良質な接点を持ちたい企業。 |
ダイレクトリクルーティングは、特に今成長が著しいサービスで、ほかにも多くのサービスが提供されています。このサイトでは、さまざまなダイレクトリクルーティングサービスについてご紹介していますので、ぜひ上記以外のサービスについてもチェックしてみてください。
ダイレクトリクルーティングの成功には、各媒体の特徴を活かすことが不可欠です。ぜひ自社にぴったりのダイレクトリクルーティングサービスを見つけましょう。
以下の記事では、ダイレクトリクルーティングの代表的なサービスであるOfferBoxについて、評判や口コミ、他サービスとの比較を詳しく解説しています。自社での導入を検討している方は、活用のポイントや成功企業の傾向をぜひ参考にしてください。
【採用担当者向け】オファーボックスの評判・口コミを解説!比較・使えてない企業の特徴は?
自社で成功させるための3ステップ

新卒採用においてダイレクトリクルーティングを効果的に活用するためには、導入後にただスカウトを送るだけではなく、戦略的な運用体制を構築することが欠かせません。成功している企業の多くは、明確なターゲット設計からスカウト文面の最適化、そして継続的な改善までを一貫した流れで実行しています。
ここでは、成果を最大化するための3つのステップをわかりやすく解説します。
Step1:採用ターゲットを明確化し、訴求軸を設計する
ターゲット設計の精度が低いと、スカウトの内容がぼやけて学生に響かず、返信率やマッチング率の低下につながってしまいます。反対に、狙う人材像を明確にしておくことで、無駄なアプローチを減らし、限られたリソースを最も効果的に活用することができます。
そのために、まずは自社が本当に採りたい人物像をできるだけ具体的に描くことが大事です。学部・専攻やスキル、志向性だけでなく、働き方の好みや価値観、将来のキャリアビジョンまで深掘りすると精度が上がります。
ターゲットが明確になれば、スカウトの訴求ポイント・トーン・チャネルが自然と定まり、反応率を高めることができます。例えば、技術重視なら研究実績や開発環境を前面に出し、社風重視なら業務の裁量や成長ストーリーを訴求する──といった具合です。
このペルソナは、必ずしも1人である必要はありません。現場・人事・経営で合意した複数のペルソナを用意し、優先順位を付けておけば、運用中の微調整もしやすくなるでしょう。
Step2:効果的なスカウトテンプレートを作成し送信戦略を立てる
ターゲットが明確になったら、その学生層の関心や特徴に合わせてスカウト文面を設計しましょう。
テンプレートの活用は採用担当者の負担軽減に効果的ですが、単なる定型文ではなく、必ず各学生にカスタマイズできる要素を含めることが重要です。たとえば学生のプロフィールから「◯◯の研究を拝見しました」「サークルでの◯◯の経験に共感しました」といった一言を添えるだけで、“ひとりひとりに届くメッセージ”へと変わります。こうしたパーソナライズされた文章は、親近感を生み出すとともに開封率や返信率を高めるために欠かせない要素です。
また、スカウト送信のタイミングと頻度も成功の鍵です。就活解禁前やインターン期間など、学生の動きを見ながら段階的にアプローチすることで、自然な関係構築が可能になります。
ダイレクトリクルーティングを成功させるには、送信数をやみくもに増やすよりも、反応のあった学生とのコミュニケーションを丁寧に続ける方が大事です。その方は、企業理解度の高い優秀な人材獲得につながるためです。そのためには、一人ひとりと向き合う時間を大切にすることが重要です。
Step3:データ分析で改善を回す「運用型採用」を定着させる
ダイレクトリクルーティングの効果を最大化するには、集めたデータをもとに継続的に施策を改善する仕組みが不可欠です。
メールの開封率、返信率、面談設定率などの各指標を定期的に分析し、どの文面やアプローチが効果的かを定期的に把握しましょう。そして、効果が低い場合は文章の修正やターゲット層の見直しを行い、PDCAサイクルを速やかに回していきます。上記で紹介したようなテンプレートも、一度作って終わりではなく、開封率・返信率を分析しながら改善していくことが大事です。
こうした「運用型採用」を組織に根付かせることで、長期的に安定した成果を上げられるでしょう。専任担当者やチームを設けることも成功のポイントです。
導入企業の成功事例から学ぶ、成果を出す組織の共通点
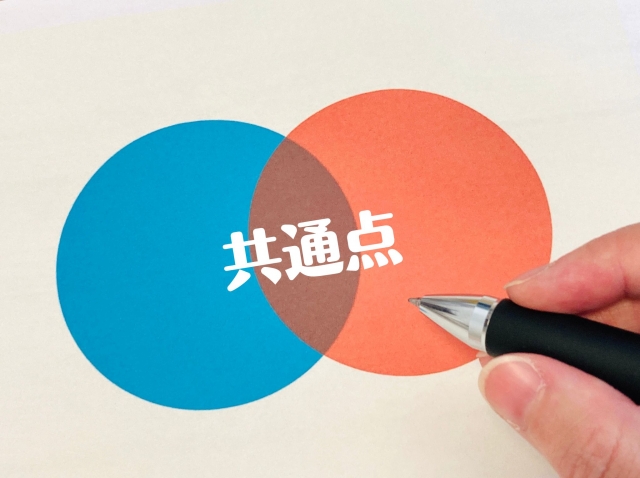
新卒向けダイレクトリクルーティングを導入して成果を上げている企業には、共通する成功パターンがあります。単にスカウト機能を使うだけでなく、データ分析やチーム体制の工夫、他媒体との併用など、戦略的な運用が成果を左右しているのです。
ここでは、実際の導入事例をもとに、内定承諾率を高めた施策や少人数体制でも成果を出す運用ノウハウ、ナビサイトとスカウトを組み合わせた効果的な採用手法についてご紹介します。
内定承諾率が向上した企業のアプローチ戦略
ある企業が内定承諾率を大きく向上させた成功事例をご紹介します。
この企業は、学生が重視するポイントを「成長機会」「技術環境」「社風」など複数の軸で整理しました。そしてそれらに合わせて複数のスカウト文面パターンを用意し、送信時には学生のプロフィールに基づいたパーソナライズを徹底し、具体的な一文を添えて送信しました。さらに、スカウトメールを送信しても開封しなかった学生には、文面を変えたフォローメールを段階的に送る戦略を採用しました。これにより反応率を高め、学生との関係構築を進めることができたといいます。
こういった細やかな段階的アプローチを続けた結果、内定承諾率が大幅に改善し、企業側が求める優秀な人材を効率よく採用できるようになったといいます。採用ターゲットを深く理解し、丁寧なコミュニケーションを積み重ねることが、内定承諾率向上に効果的であることが示された好事例です。
少人数チームで成果を上げた運用工夫
次に、少人数チームで新卒採用に成功した企業の運用工夫を紹介します。ある中小企業では、限られた人員・予算環境の中で新卒採用を戦略的に進めるため、以下の3つのポイントを徹底しました。
まず、「効率的な魅力発信」です。SNSや自社サイトなどオンラインの情報発信を強化し、企業理念や働く環境、キャリアパスの魅力を学生に分かりやすく伝えました。
次に「社内の協力体制構築」です。経営層や現場社員を積極的に採用活動に巻き込み、生の声を伝えられる体制を作りました。
最後に「入社後の定着支援の仕組みつくり」です。個別フォローやオンボーディング制度を整え、早期離職の防止と長期活躍をサポートしました。
これらの施策で企業の魅力を具体的に伝えられ、学生の共感を呼んだ結果、限られたリソースでありながら安定的に優秀な人材を獲得し、内定辞退率の低減にもつながっています。少人数でも戦略的に工夫することで結果が出せることを示す事例です。
ナビ×スカウトのハイブリッド採用による効果
ある企業では、従来のナビ媒体中心の採用から、ダイレクトリクルーティングのスカウト機能を組み合わせたハイブリッド採用に転換し、採用効果を大きく向上させました。
この企業は、従来のナビサイトでの大量応募では対応しきれなかった採用課題を抱えており、特にターゲット層の質を高める必要がありました。そこで、ナビサイトで広く情報発信しつつ、専門的なスカウトサービスも導入し、細かくターゲットを絞ったスカウトで効率的に有望学生を発掘しました。
スカウト文面は企業の事業内容や社風をわかりやすく伝えるとともに、動画など視覚的なコンテンツも組み込んだことで学生の興味を強く引きつけました。ナビの広範なリーチとスカウトの精密な個別アプローチの組み合わせにより、母集団の質と量の両面を強化することができ、結果的に内定承諾につながる候補者の質が向上し、効率的に採用活動を進められたことが報告されています。
ハイブリッド採用の成功は、目的に応じて媒体特性を活かしつつ、従来の求人手法と革新的なスカウト施策を併用することで得られる成果の一例です。
以下の記事では、実際にダイレクトリクルーティングを導入した企業の成功事例をもとに、効果を高める5つのポイントや具体的な運用ノウハウを解説しています。導入を検討している方は、実践的なヒントとしてぜひ参考にしてください。
【自社事例あり】ダイレクトリクルーティングの導入事例まとめ!メリットや効果的に行う5つのポイントとは?
ダイレクトリクルーティングで“選ばれる企業”へ

新卒採用の現場では、従来のナビサイト依存型の戦略が通用しづらくなり、ダイレクトリクルーティングが重要な採用手法として定着しつつあります。ダイレクトリクルーティングは、企業が自らターゲット学生へ能動的にアプローチすることで、優秀層とのマッチング精度が高まり、採用コスト削減や企業ブランド力向上にもつながるのが大きな魅力です。
ただし、効果を出すためには、運用負担の理解や一定期間の継続的な改善、既存チャネルとの併用によるリスク分散が欠かせません。導入企業の成功事例からも明らかなように、ターゲットの明確化、効果的なスカウト文面、そして運用型採用の仕組み化も重要です。
さらに、この記事では、いくつかの新卒向けダイレクトリクルーティングサービスの選び方や特徴のご紹介もしました。自社の採用力を大きく強化するために、ぜひこの記事を参考にダイレクトリクルーティングの活用を前向きに検討してみてください。