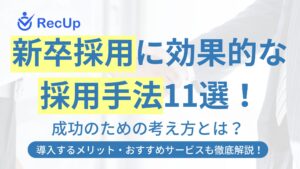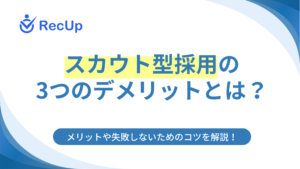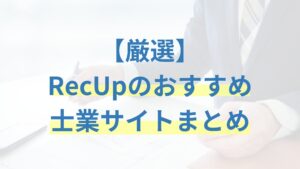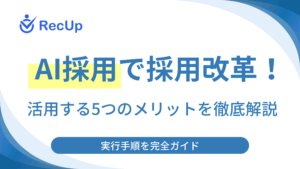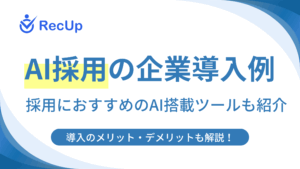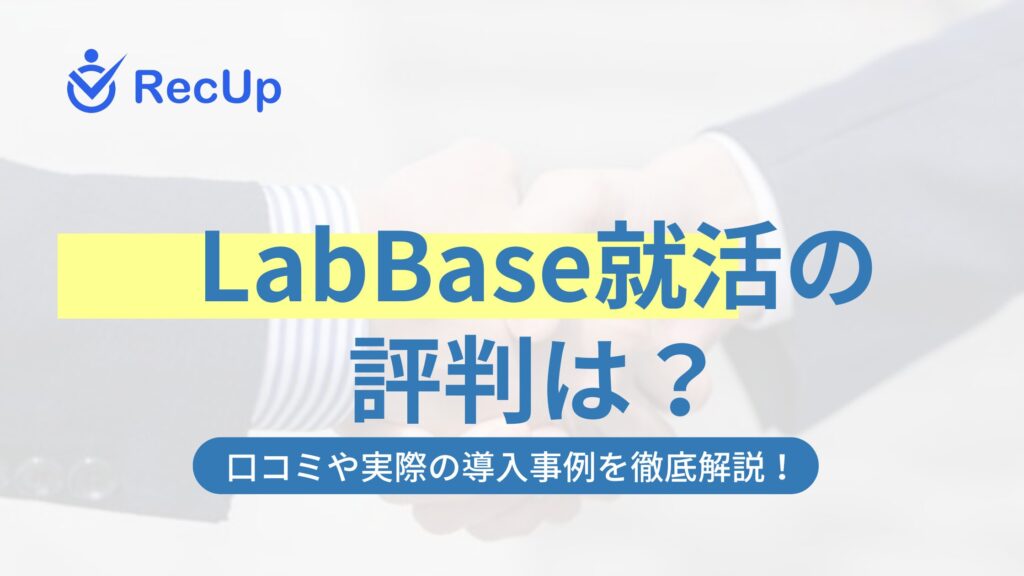
理系学生の採用は、年々競争が激化していますが、そんな中で注目を集めているのが「LabBase(ラボベース)」です。理系新卒学生に特化したダイレクトリクルーティングサービスで、多くの企業が研究開発職やエンジニア職の採用活動に活用しています。
本記事では、LabBaseの特徴や機能、料金体系、実際の口コミ、さらに利用するメリット・デメリットを徹底的に解説し、どのような企業に向いているのかを整理しました。理系学生の採用に課題を感じている採用担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
LabBase就活の評判は実際どう?

LabBaseは理系学生に特化したダイレクトリクルーティングサービスとして注目を集めていますが、実際に利用した企業の声を知ることは導入を検討する上で重要です。「効率的に学生とマッチングできた」「研究内容やスキルを確認しやすい」といった好意的な意見がある一方で、「費用対効果に課題を感じた」「母集団の規模が限られている」といった懸念の声も見られます。
ここでは、企業がどのようにLabBaseを評価しているのか、良い評判と悪い評判をそれぞれ整理してご紹介しましょう。
質・量ともに高い出会い
化粧品・医薬部外品の研究開発から生産まで一貫して行うポーラ化成工業株式会社は、生産技術職の母集団形成という長年の課題を抱えていました。化粧品業界のイメージから、生産技術職は学生にとって遠い存在と受け取られがちで、採用予算も限られている状況です。
同社が「LabBaseNow」という一社単独開催の採用イベントを活用したところ、質と量を兼ね備えた理系学生との出会いが実現しました。参加学生のモチベーションが高く、「とりあえず参加」ではなくしっかりと情報を得ようという前向きな姿勢の学生が多いと評価しています。
採用担当の福田様は「エントリーしてくださった学生の質と量は十分と感じており、自社ではこのレベル感の学生を複数名集めることは非常に困難です」とコメントしています。
LabBase就職に登録されている学生は研究と就活を両立させる中で考える力が高く、やりたいことが明確になっているため、主体的に会社を選んでくれる方が多く、結果として内定辞退の少なさにもつながっていると実感しているそうです。
ミスマッチのない理系採用
高精度なソケット製造技術で電子・半導体分野を支える山一電機株式会社では、将来の幹部候補となるようなハイレベル人材の確保が急務となっていました。従来のナビサイトや合同説明会では、優秀な学生とそうでない学生の二極化が顕著で、埋もれた逸材にリーチできないことが多かったといいます。
同社がLabBase就職を選んだ決め手は「プロフィールの研究に関する充実度」でした。理系学生、特に大学院生が多く登録しており、自身の研究内容を詳細に記載している点が特徴です。これにより、学生の研究テーマに基づいた精度の高い検索が可能となりました。実際に、過去3年でLabBase経由で12名の学生に内定を出し、10名が実際に入社しています。
採用担当の山下氏は「LabBase経由で採用した学生は、自身の研究内容や専門分野を就職活動の軸としているため、入社後のミスマッチが非常に少ないと感じています」と評価しています。プロフィールには学生がこれまで取り組んできた研究内容や勉強内容が詳細に記載されており、履歴書以上に学術的な背景を深く理解するのに役立っているとのことです。
スカウトを送りたくなる学生数の多さが最大の魅力
日本最大級のポータルサイトを運営するヤフー株式会社は、認知度が高い人気企業でありながら、LabBase就職を導入しています。導入前は不特定多数の学生に対してPRをしてエントリーを待つPull型の手法を中心に採用活動を行っていましたが、ヤフーが求める人物像ではない方も多く応募してくる結果となり、双方にとって不健全だという課題を抱えていました。
LabBase就職を再導入してからは、スカウトを送付した学生をいきなり選考へと案内するのではなく、その前に面談やイベントを挟むことで志望度を上げる仕掛けを実施しました。その結果、22年卒の採用はLabBase就職経由で前年比約3倍の内定承諾に繋がりました。
採用担当の福島様は「LabBase就職は私たちが求めているターゲットが多く登録しているデータベースと認識しています。スカウト送付数、選考参加数、内定承諾数いずれも、LabBase就職がダイレクトリクルーティングツールの中でトップクラスの実績となっております」とコメントしています。
学生と1to1の関係性を構築
電気機器業界の世界的リーディングカンパニーとして知られるキヤノン株式会社は、新卒の技術者採用において独特の課題を抱えていました。キヤノンと言えば「カメラ」「プリンター」といったイメージが強すぎて、機械や物理領域に応募が集中する一方で、電気・情報領域にはなかなか学生が集まらないという領域による応募者数の偏りが顕著だったのです。
LabBase就職を使ってみた感想として、採用担当の吉澤様は「文字数に制限がある従来のナビ型のエントリーシートと比べて、プロフィールをしっかり書いている学生さんが多いことに、まず驚きました」とコメントしています。情報の質・量ともに中途採用向けのダイレクトスカウト型転職サイトとほぼ同等と言えるくらい、プロフィールの充実度には満足しているとのことです。
特に印象的だったのは、スカウトを打った学生から回答をもらった後に、企業と学生の1対1の関係を築くことができた点です。一般的にはあまり知られていない専門領域でスカウトメールを打つ場合でも、1対1でじっくりと話をする機会を持てたことで、今まで同社にあまり関心がなかった方が就職先として興味をもってくださったことが大きな成果だったそうです。
ナビサイトで出会えない人材に会える
半導体の設計、供給において日本トップクラスの実績と知名度があるルネサスエレクトロニクス株式会社がLabBase就職を導入したのは、サービスローンチ後間もない2017年の年初でした。半導体を研究している学生からの知名度は抜群のはずの同社がなぜ逆求人サービスを検討したのでしょうか。
採用担当の藤原様によると「これまでは大手ナビサイトをメインで利用していたのですが、半導体設計を研究している学生をターゲットにしているのでBtoCの有名大手企業が競合となってしまい、知名度で負けてしまうケースもしばしば見られるようになってきました」とのことです。会社の魅力に加えて半導体の魅力を候補者一人ひとりに伝えられる採用ツールを探していた時に出会ったのがLabBase就職でした。
導入の決め手として、個々の志向性や特性に合ったアプローチができることに加え、理系人材に特化している点が大きな要素になったそうです。「逆求人系のサービスはいくつかありますが理系に特化しているのはLabBase就職だけ。
母数は多い方が良いのですが限られた時間で密度の濃いアプローチをするのであれば、優秀な理系人材がいるとわかっているサービスの方が良いですよね」と藤原様は語っています。リクルーター制度や研究室訪問など既存の手段でカバーできなかった研究室や学生へのアプローチが可能になり、20卒に関しては3名の方に内定承諾をいただいたとのことです。
LabBaseとは?サービスの特徴を紹介!

理系人材の採用は年々難易度が高まり、従来の合同説明会や求人サイトだけでは十分な母集団を形成しにくい状況になっています。そんな中で注目されているのが「LabBase(ラボベース)」です。
ここではまず、LabBaseがどのような仕組みのサービスで、採用活動にどう役立つのかについてご紹介します。
理系新卒学生特化のダイレクトリクルーティングサービス
LabBaseの最大の特徴は、理系新卒学生に特化している点です。研究職や開発職を希望する学生は、自身の研究テーマやスキルを重視してくれる企業を求めています。しかし一般的な就活サイトでは、理系学生の情報が浅く、研究内容が十分に伝わらないことが多いです。
その点、研究分野や所属研究室、学会発表の実績などまで入力できるプロフィール設計をしているため、企業は「研究に真剣に取り組んできた人材」と出会いやすい仕組みになっています。
さらに、企業はただ待つだけでなく、条件に合った学生へ直接スカウトを送れるため、優秀な人材に先手を打ってアプローチが可能です。特に採用競争が激しいAI、バイオ、機械工学などの分野では、LabBaseのように専門学生へ直接アプローチできるサービスは大きな強みとなります。
従来の母集団形成の限界を補い、理系採用の効率化を実現するツールとして、多くの企業に活用されているのです。
他の媒体よりもスカウト返信率が高い
LabBaseは、他のダイレクトリクルーティングサービスに比べてスカウトの返信率が高いといわれています。その理由の一つは、利用している学生層の特性です。
LabBaseを使う学生は、自分の研究やスキルを評価してもらいたいという意識が強く、企業からのスカウトに対して前向きに反応する傾向があります。結果的に「送っても返事が来ない」という採用担当者の不満が軽減され、効率的なアプローチが可能になります。
プラットフォーム自体も返信率を高める工夫がされていて、スカウトメールは単なるテンプレートではなく、学生一人ひとりのプロフィールを踏まえたパーソナライズ型の送信が基本であるため、学生にとって「自分に向けられた特別なメッセージ」として受け取られやすいのです。
これらに加えて、学生がスカウトに応じやすいタイミングを見極める機能も備えており、他サービスと比較しても高い成果を挙げています。採用担当者にとっては、無駄打ちの少ない効率的な採用活動が実現できる点で大きな魅力となっているのです。
学生プロフィールが充実している
LabBaseに登録している学生のプロフィールは、他の媒体に比べて非常に情報量が豊富です。基本的な学歴や専攻だけでなく、研究テーマ、使用している実験手法、論文や学会発表の有無、取得済み資格など、理系採用に不可欠な情報が揃っています。
企業側からすると「どのような分野で強みを発揮している学生か」を具体的に把握したうえでスカウトを送ることができるのです。
一般的な就活サイトでは、理系学生の情報が浅く「理系枠」として一括りにされがちですが、LabBaseではより個別性が高いマッチングが可能です。こうした仕組みのため、採用後のミスマッチを防ぎ、企業と学生双方にとって納得感のある出会いを実現できるのです。
特に研究開発職や高度な技術職を求める企業にとっては、プロフィールの充実度が高いことは非常に大きなメリットです。結果として、企業は効率的に採用活動を進められ、学生は自分の能力を正当に評価してくれる企業とつながることができるというわけです。
LabBaseの機能を解説!

LabBaseは単なる学生データベースではなく、企業の採用活動をぐっと効率化するさまざまな機能を備えています。理系学生に特化した検索機能やスカウト配信はもちろん、企業ページを活用して自社の魅力をアピールできたり、データに基づいた運用改善も可能です。
ただ学生を探すだけでなく、戦略的に採用活動を進められる便利なツールとして活用できるのが大きな魅力です。ここではLabBaseが提供する主な機能をわかりやすく整理して紹介します。
理系学生に特化したデータベースを使える
LabBaseの最大の強みは、理系学生に特化したデータベースを自由に活用できる点です。一般的な就職サイトでは、学部や学科といった基本情報しか取得できず、学生の研究内容や専門性まで深く理解することは難しい場合が多くあります。
そこでLabBaseでは、学生が所属する研究室や研究テーマ、使用している技術や手法、論文や学会発表の有無など、理系採用に必要な詳細情報まで閲覧可能になっています。企業は単に「理系学生」というくくりではなく、自社の技術領域や求めるスキルセットにマッチした人材をピンポイントで探すことができるのです。
検索機能やフィルターも充実しており、専門分野やスキル、研究の深さ、興味領域などで候補者を絞り込むことが可能で、効率的に採用ターゲットを見つけられるだけでなく、スカウトの精度も高まります。
特に研究開発職や技術職の採用では、学生の研究内容と企業の事業領域がマッチしていることが重要ですが、LabBaseならその精度を格段に上げることができるというわけです。
企業ページの活用がで知名度が上がる
LabBaseでは、ただ学生にスカウトを送るだけでなく、企業自身の情報を魅力的に発信できる「企業ページ」を設けることができます。これは採用活動において非常に重要な役割を果たします。というのも、学生はスカウトを受け取った際、その企業に関心を持った場合にまず企業ページを確認するからです。
企業ページには、事業内容やビジョン、技術領域、研究開発への取り組み、社員のインタビューなどを自由に掲載できます。特に理系学生は、自身の研究やスキルがどのように活かせるのかを重視するため、そうした学生のニーズに合った情報を掲載することで、自然に企業の魅力を伝えられる仕組みが整っているのです。
この企業ページは、単にスカウトを受け取った学生だけでなく、検索経由でLabBaseを利用している他の学生にも見られるため、認知度の向上にもつながります。知名度が高い企業だけでなく、これまであまり学生に知られていなかった中堅・ベンチャー企業にとっても、自社を効果的にアピールする場となり得ます。
結果的に、企業ページを活用することで「スカウトの返信率を上げる」「学生の志望度を高める」「自社の知名度を広げる」という三つの効果を同時に得ることができるというわけです。
データドリブンな運用が行える
LabBaseの特徴のひとつに「データドリブンな採用活動が可能になる」という点があります。
従来の採用活動では、感覚や経験に基づいて学生へアプローチを行うケースも多く、結果として効率が悪くなったり、採用担当者ごとのやり方にバラつきが出てしまう課題がありましたが、LabBaseでは、学生の反応率やスカウト開封率、面談設定数などのデータを可視化できるため、数値に基づいた改善を行うことができます。
例えば、あるスカウト文面の返信率が低い場合、そのデータを分析することで「学生に刺さる表現に変える」「送信する対象を絞り込む」といった改善策を立てることが可能です。また、送信するタイミングや対象学生の属性ごとの傾向も把握できるため、どのアプローチが効果的かを検証しながら運用できます。
蓄積されたデータは中長期的な採用戦略にも役立てられ、どの分野の学生が多いのか、どの大学や研究室からの反応が良いのかといった情報を基に、次年度以降の採用計画を精度高く立てられるようになります。
LabBaseは、単なる「出会いの場」を提供するだけでなく、採用活動をデータで最適化できる点が大きな強みです。データドリブンな運用を行うことで、企業は採用活動を改善し続け、より高い成果を出すことができるのです。
LabBase就活の導入事例は?

実際の企業がどのような背景でLabBase就活を導入し、どのように活用しているのかを知ることは、自社での導入を検討する上で非常に参考になります。導入のきっかけや運用方法、そして得られた成果は企業によってさまざまです。
ここでは、業種や規模の異なる3社の具体的な導入事例を通じて、LabBase就活がどのように活用されているのかを詳しく見ていきましょう。
ポーラ化成工業株式会社
ポーラ化成工業株式会社は、化粧品・医薬部外品の研究開発から生産まで一貫して行う企業です。同社は毎年、生産技術職の母集団形成という継続的な課題を抱えていました。化粧品業界という業界イメージから、生産技術職に合う学生には遠い存在と受け取られがちで、さらに採用予算も限られている中での採用活動でした。
そこで採用施策の一つとして、一社単独開催採用イベント「LabBaseNow」を3度にわたって活用しています。導入の決め手となったのは、LabBase側が広報活動を行えるノウハウを持っていたことに加え、理系学生の登録が多いこと、LabBaseという媒体が学生からの認知が高いことでした。また、広く宣伝しても集客につながりにくい状況だったため、「個に向き合う」スタイルの直接的なアプローチが可能な点も同社に合っていると判断されました。
イベント実施後の効果として、エントリーした学生の質と量については十分と感じており、自社ではこのレベル感の学生を複数名集めることは非常に難しいと評価しています。また、イベントを通して学生の当社への興味の有無・範囲がある程度分かるため、その後のフォローにもつなげやすくなったとのことです。
学生とのコミュニケーションにおいては、技術だけでなく人との関係性のよさに焦点をあててお話することが多いそうです。特に生産工場という組織の中では人との関係性が重要であり、技術を活かす上では人との関係性が円滑な方が自身の成長にもつながると考えているためです。イベント後は学生ごとに個別に対応することを重視し、興味を持ってくれた方がどこに本当の興味があるのかを把握した上で、個別に話ができる場を設けています。
山一電機株式会社
高精度なソケット製造技術で電子・半導体分野を支える山一電機株式会社では、近年の開発領域の高度化により、将来の幹部候補となるようなハイレベル人材の確保が急務となっていました。採用担当の山下氏は「会社の成長や今後の幹部候補になるようなワクワクする人材に出会いたい」と考えていましたが、実際にはそういったハイレベルな理系人材に出会うことが難しい状況でした。
これまで国公立大学出身の理系人材が社内にほとんどおらず、彼らが加わることでどのような変化が起きるのかを経営陣や社内に示したいという思いもありました。従来はナビサイト、従来型のエージェント、イベント型、合同説明会などあらゆる採用ツールを利用してきましたが、年々採用ツールやトレンドが多様化・細分化し、表面的な情報で選ぶ学生も増えていたそうです。
LabBaseを導入する決め手となったのは、その「プロフィールの研究に関する充実度」でした。理系学生、特に大学院生が多く登録しており、自身の研究内容を詳細に記載している点が特徴で、学生の研究テーマに基づいた精度の高い検索が可能となります。
過去3年でLabBase経由で12名の学生に内定を出し、10名が実際に入社しており、着実に成果を積み重ねています。LabBase経由の学生は総じて「勉強熱心」「研究熱心」で、特に院生が多く、専門性・スペシャリストタイプも見受けられます。早期から就職活動を始めていて志望度も高く、他サービスの学生とは反応や採用スピードが違うのも特徴的だと評価しています。また、入社後のミスマッチが非常に少なく、定着率も高い傾向にあるとのことです。
ウイングアーク1st株式会社
データ活用領域でBIと帳票の両事業を柱とするウイングアーク1st株式会社は、24卒の新卒採用において、LabBase就職を導入し、初年度でエンジニアの上位層9名の採用に成功しました。導入前は、プロダクト開発に取り組む「開発エンジニア」職の採用について、エンジニアに特化した人材紹介を活用し採用していましたが、採用チャネルを新卒紹介だけに依存していることに危機感を感じていたそうです。
採用担当の南氏は「採用の『あるべき状態』として、自社にとって必要な人材を、自社の力で、事業成長に資する質と量とスピードでもって獲得できる、これを目指さないといけないと考えました」と語っています。このような背景から、採用チームとして「自社採用力」を向上させるべく、新しいエンジニアの獲得チャネルを模索することになりました。
導入初年度で採用ターゲットレベル60名規模の有効募集団の形成ができ、その中からエンジニア上位層9名の採用につながりました。最もスカウトを積極的に送信していた期間は5月から8月までで、承諾率は61.6%でした。前年に比べてプログラミング経験のある学生との接触数が10倍増加し、非常に満足しているそうです。
スカウトでは初回接触で必ず採用担当者とのカジュアル面談を案内しており、学生1人1人のニーズに合わせて個別に次回接点の内容を提案し、もう1度カジュアル面談の案内やCTOセッション、インターンシップ、コーディング面談など、アトラクトのためのさまざまなコンテンツを提供しています。
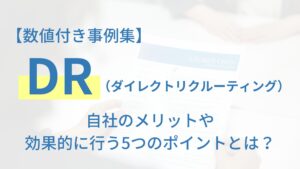
LabBase就活の料金体系は?
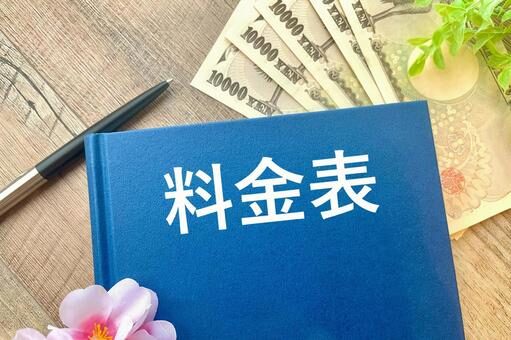
LabBaseの料金体系は、基本的に「月額でのデータベース利用料金」のみとなっており、学生がLabBase経由で内定を承諾した場合にも成果報酬は発生しません。成果報酬型のサービスと異なり、採用が成立するごとに追加コストがかからないため、計画的に採用を進めたい企業にとって費用面での見通しが立てやすい点が大きな特徴です。
料金プランは一律ではなく、企業の採用計画や抱えている課題に応じて、最適な形を提案する仕組みが取られています。導入前にヒアリングを行い、自社の採用人数やスカウト通数、必要とするサポート体制に合わせて見積もりが提示されるため、目的に合った柔軟な利用が可能です。
提供されているプランは、スタンダードプラン、自社完結プラン、少人数採用を支援するプラン、大量採用に対応するプラン、さらに理系採用を全面的に任せられるプランといった複数の選択肢が用意されています。
料金の具体的な金額は公式には公開されていませんが、成果報酬なしの定額制という仕組みを採用しているため、年間を通じて安定的に利用したい企業にとってコストパフォーマンスは高いといえるでしょう。
LabBaseはどんな企業におすすめ?

LabBaseはすべての業種・企業に向いているわけではなく、理系学生に特化した特徴を持つサービスであるため、特に効果を発揮しやすい企業があります。導入を検討する際には「どんな採用ニーズに強いのか」を理解しておくことが大切です。
ここでは、LabBaseが向いている企業像についてご紹介します。
技術系・研究開発職の採用を強化したい企業
LabBaseが特におすすめできるのは、技術職や研究開発職といった理系人材の採用を重視している企業です。登録している学生の多くが理系の研究室に所属しており、工学系、情報系、化学系、さらにはバイオ系など幅広い分野の人材が集まっています。
学生のプロフィールには研究内容や研究テーマに取り組んだ理由まで詳細に記載されているため、単なるスキルチェックにとどまらず、課題解決への姿勢や探究心といった人物像を把握できる点が強みです。
特に、研究職やエンジニア職は従来の就活サイトでは十分にマッチングが進まないケースが多く、専攻や研究テーマを深く理解しないと採用に結びつけにくい領域です。その点、LabBaseではスカウト前から詳細な情報を得られるため、ミスマッチを減らして効率的に母集団形成を進められます。
自社の技術力や研究分野を強みにしている企業にとっても、LabBaseの企業ページを通じてその魅力を学生に訴求できるため、知名度が十分でない中小・ベンチャー企業でも優秀な理系学生との接点を作りやすくなります。競合との差別化を図りながら採用力を強化したい企業にとって、非常に有効な手段といえるでしょう。
以下の記事では、AIを活用したスカウトサービスについて、最新のトレンドやメリット、選び方のポイントを詳しく解説しています。理系人材の獲得競争が激化する中で、より効率的にスカウトを行いたいと考える企業様は必見です。自社に合ったAIスカウトツールを見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。
【2025年最新】AIスカウトサービス15選を徹底比較!メリットや選ぶ際のポイントを解説
また、以下の記事では、理系・文系問わず幅広い学生層にアプローチできる逆求人型サービス「オファーボックス」の評判や機能、他社との違いについて詳しく解説しています。LabBaseと比較検討を進めたい方は、あわせてご覧ください。
【採用担当者向け】オファーボックスの評判・口コミを解説!比較・使えてない企業の特徴は?
LabBaseを活用するなら、AIスカウト・「RecUp」を活用がおすすめ!

理系採用の競争が激化する中、AIを活用したスカウトサービスとして注目されているのが「RecUp」です。
RecUpは、学生のプロフィールや志向性をAIが分析し、企業に最適な候補者を自動でスカウト送信する仕組みを備えており、スカウトの効率を格段に向上させられ、採用担当者の工数を大幅に削減できます。
さらに、候補者の特性や志向に基づいた精度の高いマッチングが可能で、理系学生だけでなく幅広い職種の採用にも対応しています。初めてダイレクトリクルーティングを導入する企業にもおすすめのサービスです。詳細は公式ページをご覧ください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。