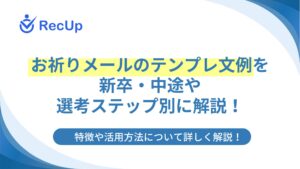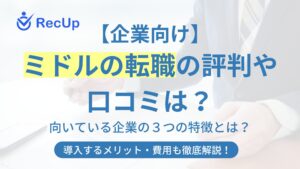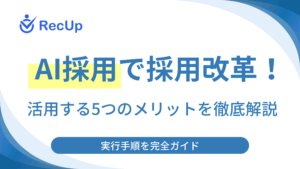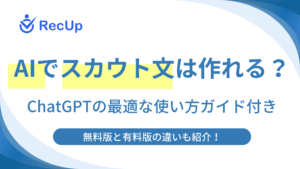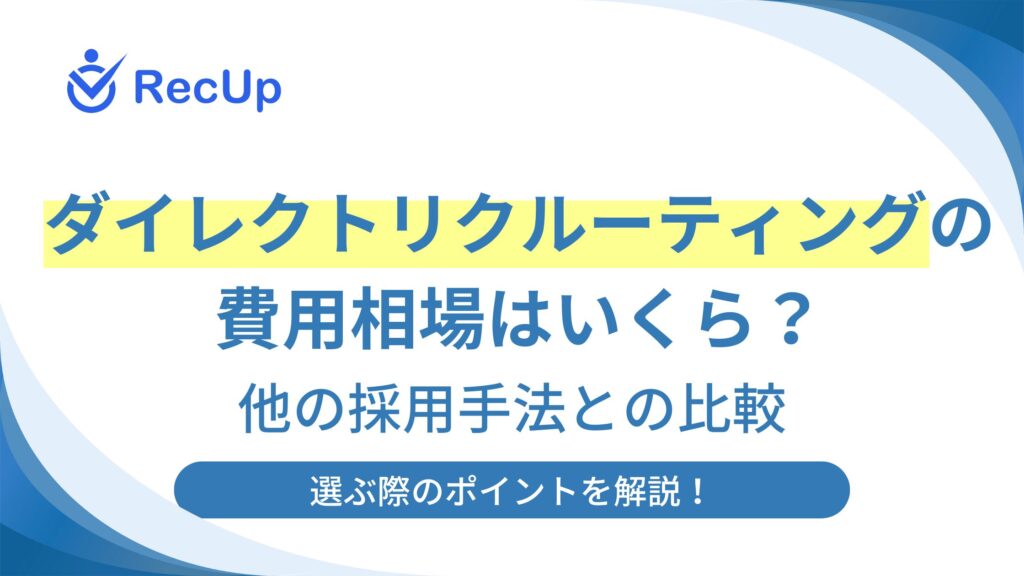
ダイレクトリクルーティングは、企業が直接候補者にアプローチし、質の高い人材を効率的に獲得できる採用手法として注目されています。しかし、費用面が気になり導入をためらう企業も多いのではないでしょうか。
この記事では、ダイレクトリクルーティングの費用相場や料金体系について詳しく解説し、他の採用手法との比較も行います。さらに、最適なサービスを選ぶためのポイントもお伝えします。採用コストを抑えつつ質の高い人材獲得を目指す人事担当者・採用責任者・経営者の方必読です。
ダイレクトリクルーティングとは?

ダイレクトリクルーティングとは、求人広告や人材紹介会社を介さず、企業が自ら候補者に直接アプローチする採用手法のことです。従来の「応募を待つ採用」ではなく、企業が持つ人材データベースやスカウトサービスを活用し、経験・スキル・価値観などからマッチする人材を見極め、1対1のメッセージで積極的に接触します。
この手法の最大の特徴は、自社にフィットする人材を効率よく探せる点です。さらに、転職活動をまだ本格的に始めていない「転職潜在層」にもアプローチできるため、他社よりも早く優秀な人材に出会える可能性が高まります。
企業が直接採用活動をコントロールできるため、採用プロセスの透明性と費用対効果の高さも大きな魅力です。仲介手数料が不要な分、広告費や採用コストを抑えながら、候補者と丁寧にコミュニケーションを重ねることができます。結果として、ミスマッチの少ない採用が実現しやすくなります。
このように、ダイレクトリクルーティングは、主体的・戦略的に人材獲得を進めたい企業に最適な採用手法として、多くの中小企業から大手企業まで幅広く導入が進んでいます。
ダイレクトリクルーティングの費用相場はいくら?

ダイレクトリクルーティングの費用は、主に「成功報酬型」と「定額型」の2種類に分かれています。どちらのタイプを選ぶかによって、コストの発生タイミングや採用戦略の立て方が大きく変わるため、特徴を理解しておくことが大切です。
ここでは、それぞれの仕組みと費用相場を詳しく見ていきましょう。
成功報酬型の場合
ダイレクトリクルーティングの成功報酬型は、採用が決まった人材に対してのみ費用が発生する料金体系です。
費用相場は中途採用の場合、採用者の想定年収の15%~20%程度、新卒採用の場合は一人あたり30万~40万円程度が一般的です。
この方式の大きなメリットは、採用に成功しなければ費用が発生しないため、採用リスクを抑えられる点にあります。ただし、サービスによっては成功報酬以外に初期費用やシステム利用料が別途発生するケースもあるため、事前に費用の詳細を確認することが大切です。
成功報酬型は、特に人材の質を重視した採用をする企業に適しています。また、初めてダイレクトリクルーティングを導入する企業や、他の求人媒体と併用したい企業におすすめされています。
成功報酬型のデメリットとしては、複数名採用するとその分費用が積み上がりやすいこと、また採用直後に退職や内定辞退があった場合の返金対応の有無をサービスごとに確認しておく必要があることが挙げられます。費用の支払いタイミングや返金規定が異なるため、これらは契約前にしっかりと確認することが安心につながります。
定額型の場合
ダイレクトリクルーティングの定額型は、一定期間の利用料を固定で支払う料金体系です。費用の相場は年間60万円~330万円程度で、サービスによって3ヶ月などの短期間プランや、採用人数に応じたプランも用意されています。
定額型の大きなメリットは、採用人数が多い場合や長期的な採用活動で一人あたりのコストを抑えやすく、予算の見通しが立てやすい点にあります。また、求人掲載やスカウトメールが一定数まで送信可能なケースが多く、採用活動の幅を広げやすいのも特長です。
一方で、採用計画が曖昧であったり、採用人数が予定より少なかった場合でも費用は発生するため、予想外のコストがかかるリスクがあります。契約期間中の解約や未使用期間の返金対応は原則難しいことが多いので、事前に採用計画をしっかり整理することが重要です。
また、プランによっては初期費用やシステム利用料が別途必要な場合もあるため、費用の詳細は契約前に確認しましょう。さらに、スカウト機能の使いやすさやサポート体制の充実度も比較材料に加え、自社の採用ニーズに最適なプランを選ぶことが成功のポイントです。
ダイレクトリクルーティングと他の採用手法と費用を比較!

ダイレクトリクルーティングの費用相場や特徴を理解したところで、次に他の主要な採用手法と比較してみましょう。
転職イベント、合同説明会、人材紹介、ソーシャルリクルーティングなど、採用の方法にはさまざまな選択肢があります。それぞれに特徴やコスト構造が異なるため、費用面や採用効果を比較しながら、自社の目的や採用ターゲットに最も適した手法を見極めることが大切です。
転職イベントや合同説明会
転職イベントや合同説明会は、企業が多くの求職者と一度に接点を持てる貴重な採用の場として利用されています。実際に会場で求職者と直接対話できるため、自社の魅力や強みをリアルに伝えられ、企業ブランディングの向上や母集団形成にも大きく貢献します。これにより、求職者の生の反応を受けて採用活動の改善ポイントを即座に把握できるのも大きな利点です。
ただし、転職イベントや合同説明会に出展するには、ブース設営費や出展料など初期コストが発生します。エリアやイベントの規模によって異なりますが、費用の相場は数十万円から百数十万円程度と幅があります。特に東京や大阪などの大都市圏では40万円から130万円、主要な転職フェアでは85万円から200万円程度が一般的です。大規模イベントになるとこれを超える費用がかかることも珍しくありません。
さらに、標準サイズのブースは幅約2メートル、奥行1メートル半程度と限られているため、より多くの求職者を呼び込みたい場合は、ブースの拡張や大型ブースの利用が必要となり、費用は倍近くになることもあります。また、資料配布やスタッフ用椅子・テーブルの貸出し、面接ブース設置、スカウトメール配信といったオプションサービスは別途料金がかかり、利用するほどコストが嵩みます。
採用成功に直結しない場合でも費用が発生するため、費用対効果を慎重に見極めたうえで参加を検討することが重要です。最近ではオンライン合同説明会の開催も増えており、こちらは対面開催に比べて出展コストが低減される一方で、求職者とのリアルなコミュニケーション機会が限られるため、使い分けも検討ポイントとなっています。
人材紹介
人材紹介サービスは、採用が決定した時点で費用が発生する「成功報酬型」が一般的です。この成功報酬の手数料は、採用者の年収の約30%前後が相場であり、高年収の専門職や管理職を採用する場合では、1人あたり100万円を超えることも珍しくありません。たとえば、想定年収600万円の人材の採用であれば、約180万円が紹介手数料として発生するケースが多いです。
人材紹介の最大のメリットは、求めるスキルや経験を持った即戦力人材を効率的に採用できる点にあります。専門知識や管理能力を求めるポジションで特に効果が高く、忙しい企業にとっては採用活動の負担軽減にも貢献します。また、紹介会社が候補者の事前審査や面談調整をサポートするため、採用の質を高めやすい点も評価されています。
しかし、人材紹介を利用する際は費用負担が大きくなる点には注意が必要です。成功報酬型は採用が成立して初めて費用が発生するため導入のハードルは低いものの、採用後にミスマッチが起きて早期離職が発生すると、支払った手数料が無駄になるリスクもあります。特に高額な手数料がかかるハイクラス向け人材では、その損失が企業にとって大きな痛手になることがあります。
そのため、利用時は紹介会社との事前すり合わせを丁寧に行い、自社に合った候補者を見極める体制づくりが重要です。
ソーシャルリクルーティング
ソーシャルリクルーティングは、SNSや専門コミュニティを活用して候補者と直接つながり、採用活動を行う最新の手法です。企業が自社のブランドやカルチャーを自然に発信しながら、明確に絞ったターゲット層に対して効果的にアプローチできることが大きな魅力です。SNSの特性を活かし、普段の投稿やストーリー、ライブ配信など多様な手段で企業の魅力を候補者に伝えられ、応募意欲を喚起することができます。
一方で、ソーシャルリクルーティングは短期間で劇的な成果を上げるのが難しい側面もあります。効果的な運用には、定期的かつ継続的な情報発信と、その発信に対する効果測定、改善サイクルを丁寧に回すことが求められます。コンテンツの質やタイミングを工夫し、候補者とのコミュニケーションを深めていく運用が必要なため、計画的なリソース配置と長期的な視点での戦略立案が不可欠です。
広告費や運用代行費用が主なコストで、月額数十万円前後が費用相場となります。採用成功時に発生する固定費用はなく、主な支出は広告運用コストと担当者の人件費となるため、こちらも採用に成功しなくてもかかることに注意が必要です。
これらの採用手法と比較すると、ダイレクトリクルーティングは中長期的にコストを抑えながら、求める人材に直接アプローチできる点が強みといえるでしょう。
ダイレクトリクルーティングサービスを選ぶ際の3つのポイントとは?

ダイレクトリクルーティングの効果を最大限に発揮し、費用対効果の高い採用を実現するためには「サービス選び」が鍵となります。単に費用の安さだけで判断するのではなく、自社の採用ターゲット・体制・採用スピードなどに合ったサービスを見極めることが重要です。
ここでは、導入前に押さえておきたい3つの選定ポイントをわかりやすく解説します。
①自社の採用ターゲットが人材が豊富に登録されているサービスを選ぶ
まず最も重視すべきなのは、自社が採用したい人材層がどれだけ豊富にかつ的確に登録されているかという点です。業種や職種によって求める人材の属性は異なるため、ITエンジニア、営業職、女性スタッフ、販売職など、自社のターゲットに最適化されたサービスを選択することが採用成功の鍵となります。たとえばITエンジニアの採用には、技術職が多く登録された専門性の高いプラットフォームを利用することで、求める人材を効率よく探せる確率を高められます。
登録者の「質」と「量」のバランスがとれていることも重要です。専門性の高い職種やニッチな業界ではたとえ登録者数が少なくても、ターゲットにマッチした質の高い登録者が多いことが成果につながります。一方で、登録者数が多くても求める属性に合わない場合は、コストや時間が無駄になる可能性もあります。そのため、表面的な登録者数だけでなく、スキルや経験年数、志向性など多角的なデータを確認することが必要です。
こういった情報を揃えるためには、導入前に、データベースの傾向を十分にリサーチが欠かせません。また、無料トライアルやデモ版が使えればぜひ活用し、自社に合った検索条件で候補者層を実際にチェックしてみることも大事です。あわせて操作性やサポート体制も評価し、長期間安心して利用できるかどうかを見極めましょう。
②採用人数やスケジュールに合わせた料金プランを選択する
採用規模や時期に応じて最適な料金プランを選ぶことも重要です。大量採用を短期間で行う場合は、定額制のプランが向いています。定額制は期間中の利用料が固定されているため、採用人数が増えるほど1人あたりのコストを抑えられ、予算管理がしやすいメリットがあります。反対に少人数の厳選採用や質重視の採用には、成果が出た場合にのみ料金を支払う成功報酬型が適しています。これにより、無駄な費用を抑えつつ、リスクを最小限にできます。
また、採用シーズンや事業計画により採用活動のピークが限られている企業は、繁忙期だけ利用する期間限定プランや、必要に応じて料金体系を柔軟に変えられるサービスを選ぶのがおすすめです。そうすることで、不必要な期間の固定費用を避け、コスト効率を最大化できます。
さらに、契約時には料金表だけでなく解約条件や自動更新の有無、追加料金の仕組みも確認することも忘れないようにしましょう。とくに追加スカウトや延長オプションなどは料金が別途発生するケースがあるため、運用計画に組み込んだうえで検討してください。こうした料金面の細かい確認を怠ると、想定外のコスト増加につながるリスクがあります。
③スカウト機能の充実度や運用サポート体制で比較する
スカウトメールの成果を大きく左右するのは、文面のパーソナライズ性や候補者とのマッチング精度です。最近の採用サービスでは、AIを活用してスカウト文面の自動生成や最適化を行い、候補者一人ひとりのプロフィールに合わせた魅力的なメッセージを送れる機能が充実しています。こうした機能の有無や使いやすさは、返信率や応募率に直結するため、管理画面の直感的な操作性や検索機能の精度も重要な比較ポイントとなります。
加えて、専門の運用サポートやコンサルティングが充実しているサービスは特に注目すべきです。採用ノウハウがまだ十分でない企業や初めてダイレクトリクルーティングを導入する企業にとっては、サポート体制が整っているかどうかがスムーズな運用の鍵となります。例えば、スカウト文面の改善点をアドバイスしてもらえたり、効果的なターゲット選定の提案を受けたりできるサービスは、運用効率と採用成功率を高めるうえで大きな助けになります。
また、サービスによっては、AIによる候補者の傾向分析や行動予測を行い、最適なタイミングでスカウトを自動送信する機能が備わっているものもあります。これにより、採用担当者の工数削減と同時に、応募者にとって魅力的なアプローチが可能になります。
以下の記事では、実際にダイレクトリクルーティングを導入した企業の事例を紹介しています。導入によって得られた効果や成功のポイントを知りたい方は、あわせて参考にしてみてください。
【自社事例あり】ダイレクトリクルーティングの導入事例まとめ!メリットや効果的に行う5つのポイントとは?
AIスカウトならRecUp

AIスカウトサービス「RecUp(リクアップ)」は、ダイレクトリクルーティングを効率的かつ効果的に進めたい企業に最適なツールです。人間の採用担当者に代わってAIが候補者データを分析し、マッチング精度の高い人材を自動で抽出してスカウトメールを送信します。そのため、求人業務の負担を大幅に軽減しながら、短期間で質の高い応募を獲得できるのが特徴です。
RecUpは、候補者のスキル、経験、志向など複合的なデータを活用し、多角的にマッチングを行うため、単なるキーワード検索では見つけにくい潜在層にもリーチすることが可能です。また、AIがスカウト文面を最適化し、返信率や内定承諾率の向上にも寄与しています。
初心者でも使いやすい管理画面と運用サポートも充実しており、ダイレクトリクルーティングの成功率を高めるための強力な支援体制が整っています。詳しいサービスや事例については、下記よりご確認ください。