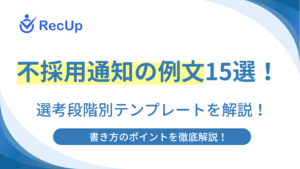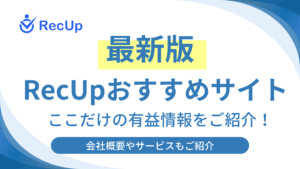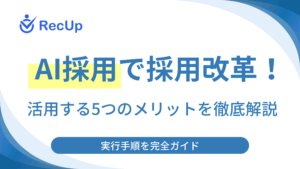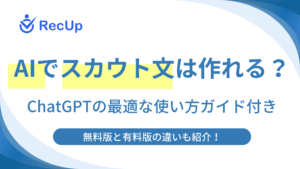近年、「労働人口の減少」や「即戦力人材の確保」などの影響を受け、採用手法を見直す企業が増えています。
その中で特に注目されているのが「ダイレクトリクルーティング」というアプローチです。企業が求職者へ直接アプローチできるこの方法は、うまく活用することで、採用コストの削減やミスマッチの防止など多くのメリットを得られる可能性があります。
本記事では、ダイレクトリクルーティングの概要や他の採用手法との違い、メリット・デメリットから成功のコツ、そして導入事例までを徹底解説します。
ぜひ最後までご覧いただき、自社に合った採用手法の構築にお役立てください。
ダイレクトリクルーティングとは?他の採用手法の違いも解説

新たな採用手段として注目を集めているのが「ダイレクトリクルーティング」です。
企業が自ら候補者にアプローチできる点が特徴ですが、従来の求人媒体や人材紹介など他の採用手法とは具体的にどのように異なるのでしょうか。ここでは、ダイレクトリクルーティングの概要と、そのほかの採用手法との違いをわかりやすく解説していきます。
ダイレクトリクルーティングの概要
ダイレクトリクルーティングとは、企業側から求職者に直接アプローチできる採用方法を指します。
具体的には、求職者の情報を保有するプラットフォーム運営企業と提携し、自社にフィットしそうな候補者を選び出したうえでスカウト連絡を行います。スカウトを受け取った求職者とコミュニケーションを図り、カジュアル面談や本格的な選考へと進め、最終的に採用に至るという流れです。
従来の採用手法では「企業が求人票を出す→求職者が応募する→書類選考・面接」というプロセスが一般的でした。しかし、ダイレクトリクルーティングでは、企業側から積極的に「探しに行く」姿勢が求められます。これにより、特定のスキル・経験を持つ人材や、自社に強い興味を持ってくれそうな人物にピンポイントでアプローチできる利点があります。
ダイレクトリクルーティングが注目される理由
少子高齢化の進行による労働人口の減少と、それに伴う優秀な人材獲得競争の激化により、従来の求人媒体を使った「待ちの採用」だけでは十分な人材確保が難しくなってきました。
そこで、企業が自ら条件に合った候補者を探し、スカウトを送ることで能動的かつ戦略的に採用を進める「攻めの採用」の必要性が高まり、その手段としてダイレクトリクルーティングが大きく注目されるようになったのです。
ダイレクトリクルーティングの基本の流れ
求職者が人材データベースに登録する
ダイレクトリクルーティングのプラットフォームには、転職を検討している人や潜在層を含む多くの候補者が履歴書や職務経歴書などを登録しています。
企業が人材データベースからマッチする人材を探す
企業側はシステム上でスキルや経験、希望条件などを絞り込み、人材をスクリーニングします。
条件に合った求職者にスカウトメールを送る
候補者の職務経歴やプロフィールを見て、魅力的と思われる人材にはスカウトメールを送ります。
求職者とコミュニケーションを図る
スカウトを受け取った求職者が興味を示せば、オンラインや電話でのやり取りを開始します。軽い相談やカジュアルな面談でお互いの要望や条件をすり合わせることが多いです。
面談や選考へ進み採用を行う
求職者との相性や具体的な能力を見極めながら、最終的に選考フローへ進んでいきます。
ダイレクトリクルーティングと他の採用手法の違い
求人媒体との違い
一般的な求人媒体では、企業が求人広告を掲載し、求職者を待つスタイルが主流です。そのため「応募が来るかどうか分からない」「応募者が本当に自社に合うか判断しにくい」といった課題が残ります。一方、ダイレクトリクルーティングでは自ら候補者を探してアプローチするため、より効率的にターゲットを絞ることが可能です。
人材紹介との違い
人材紹介は、エージェントが求職者を集めて企業に紹介し、採用が決まれば紹介手数料を払う仕組みです。企業側はエージェントが持つネットワークを活用できますが、比較的高額な紹介料がかかることが多いです。
就職フェアとの違い
就職フェアでは、イベントに来場した求職者と直接会って話せるメリットがある一方、開催地域や日程に左右され、優秀な人材を取りこぼしてしまうリスクがあります。ダイレクトリクルーティングはオンライン上でのアプローチが中心なので、時間や場所を選ばず、より幅広い層にアプローチできます。
ダイレクトリクルーティングの4つのメリット

ここからは、企業がダイレクトリクルーティングを導入する際に期待できるメリットを4つ解説します。
①企業と求職者の双方にとってミスマッチが起こりにくい
ダイレクトリクルーティングでは、企業が候補者の情報を事前に確認し、スキル・経験・志向性などが自社に合いそうかを判断した上でスカウトを送ります。
応募の時点で応募者側も企業の業務内容やカルチャーをイメージしやすく、事前のコミュニケーションを通じて相互理解を深められるため、ミスマッチが起こりにくいのが特徴です。
②転職潜在層へのアプローチが可能
ダイレクトリクルーティングでは、まだ積極的に転職活動をしていない「潜在層」にアプローチできる点が大きな魅力です。
一般的な求人サイトには登録しておらず、いわゆる“今すぐ転職を考えているわけではないが、魅力的な企業があれば検討したい”という層に向けてスカウトを送れるため、優秀な人材を早期に確保するチャンスが高まります。
③採用コストの削減
ダイレクトリクルーティングにかかる費用は、基本的にプラットフォームの「利用料」+「成功報酬」が中心となるモデルが多いです。
成功報酬は一般的には数十万円〜という幅がありますが、平均約60万ほどとなっています。多額の広告費やエージェントへの手数料と比較しても、コストを抑えながら効率的な採用活動ができるケースが増えています。
④採用力の向上
ダイレクトリクルーティングを導入することで、企業は自社の魅力や価値提案を再度整理し、どのような人材が必要なのかを改めて深く考えるきっかけにもなります。
自社にマッチする人材を探す過程で「どのような能力を優先すべきか」「どのようにアピールすれば興味を持ってもらえるか」が明確になるため、採用力が総合的に高まるメリットがあります。
ダイレクトリクルーティングの市場規模についてはこちら
新卒ダイレクトリクルーティングの市場規模は?中途採用の市場規模や市場拡大の理由を徹底解説
ダイレクトリクルーティングの3つのデメリット

一方で、ダイレクトリクルーティングには注意すべきデメリットも存在します。導入前に把握しておくことで、リスクを軽減しつつ運用体制を整えることが可能です。
①業務負荷の増加
ダイレクトリクルーティングでは、企業側がスカウトメールを送る候補者を選定し、文章を作成して個別にやり取りを行う必要があります。
従来の求人広告や人材紹介に比べ、採用担当者の業務範囲や対応件数が増大する可能性が高いです。そのため、専任担当者を設置したり、業務プロセスを効率化したりする施策が欠かせません。
②長期的なアプローチが必要
潜在層へのアプローチができるというメリットの裏には、「すぐに転職を決める人ばかりではない」という現実もあります。
スカウトを送ってから実際に転職・入社するまでに時間がかかるケースも多く、短期的な成果を求める企業には物足りなく感じられるかもしれません。長期的に候補者とコミュニケーションを取りながら、関係を構築していく姿勢が求められます。
③現場との協力が必要
スカウトを送る際や面談時には、求めるスキルや人材像を正確に把握しておくことが重要です。実際にそのポジションで働く現場の声をしっかりと吸い上げ、社内で一貫性のあるメッセージを発信しなければなりません。
現場社員やマネージャー、経営陣との連携が不十分だと、ミスマッチを起こしたり、候補者に不安を与えたりするリスクが高まります。
ダイレクトリクルーティングが向いている企業や職種の特徴

ダイレクトリクルーティングは万能ではなく、向いている企業や職種には一定の特徴があります。以下でそれぞれ見ていきましょう。
ダイレクトリクルーティングが向いている企業の特徴
- 積極的な採用姿勢がある
攻めの採用を行いたい、採用活動を自社主導でコントロールしたいという企業には非常に適しています。 - 自社の魅力を明確に打ち出せる
候補者に直接アプローチする際、自社の魅力をうまく伝える必要があります。ブランド力や社風、社員の働き方など、他社との差別化ポイントをアピールできる企業ほどメリットを享受しやすいでしょう。 - 採用に充てるリソースを確保できる
スカウトメールの作成や候補者とのコミュニケーションなど、企業側の業務負荷が増すため、採用担当者や現場との連携、専任スタッフなどのリソースを確保できる体制が望ましいです。 - 急ぎではないが、継続的に優秀な人材を確保したい
ダイレクトリクルーティングは短期的に大量採用を行うよりも、中長期的な視点で優秀な人材を確保していくのに向いています。
ダイレクトリクルーティングが向いている職種の特徴
- 専門的なスキルを求める職種
エンジニアやデータサイエンティストなど、専門性の高い職種では、転職市場に出ていない優秀な人材をピンポイントで狙うことができるダイレクトリクルーティングが効果的です。 - 採用が難しいニッチな職種
一般的な求人媒体では応募が集まりにくい、競合が多い、希少性の高いスキルを必要とする職種などでも、ダイレクトリクルーティングであれば候補者を効率的に探せます。 - マネジメントポジション
マネジメント経験のあるミドル〜シニア層は、常時転職サイトをチェックしているわけではない場合も多く、潜在層にアプローチできるダイレクトリクルーティングが効果的です。
人材紹介との違いについてはこちら
ダイレクトリクルーティングと人材紹介の3つの違いとは?他の採用方法との違いも解説
ダイレクトリクルーティングを成功させるコツ

ダイレクトリクルーティングを導入する際、成果を出すためのポイントを押さえておくことが大切です。ここでは代表的なコツを4つ紹介します。
自社の採用課題を洗い出す
まずは自社の採用課題を明確にすることが重要です。
例えば「応募が少ないのか、多いのに辞退率が高いのか」「現場が求める人材像と実際に採用される人のギャップは何か」など、現在の採用プロセスや成果を振り返り、課題を整理しましょう。
その上で、ダイレクトリクルーティングで何を解決したいのかを明確にすることが、成功への第一歩です。
長期的なプランを計画し専任の担当者を決める
ダイレクトリクルーティングはすぐに成果が出るとは限りません。
スカウトを送る対象を選定し、やり取りを行い、関係性を構築していくには時間がかかります。
そのため、長期的な採用計画を立て、プロジェクトをリードする専任担当者を置くことが望ましいです。採用担当者が他業務との兼務で手が回らない状況を避けるためにも、ある程度のリソースを確保して運用に当たる必要があります。
経営陣や現場社員も巻き込む
ダイレクトリクルーティングでは、現場が求める人物像や社風に合うかどうかなどの見極めが重要になります。実際に候補者と近い距離で仕事をするのは現場社員やマネージャーであり、経営方針を示すのは経営陣です。
現場と経営層を巻き込み、採用要件やアプローチ戦略を共有し、社内全体で候補者を歓迎する雰囲気を作り出すことで、スカウトに対する反応率や内定承諾率が大きく向上します。
スクリーニングを行うときはターゲットを絞り込み過ぎない
スキルや経験、年齢、勤務地など、条件を厳密に設定しすぎると候補者が極端に少なくなる可能性があります。潜在層であるほど、転職に対するスタンスが曖昧な場合もあるため、少し広めに設定してアプローチして関係を構築していくのが効果的です。
スクリーニングの段階では「絶対に譲れない条件」と「多少妥協してもよい条件」を明確に区別し、募集要件が広すぎず狭すぎない最適なラインを探ることを心がけましょう。
ダイレクトリクルーティングでスカウトメールを送る際のポイント

スカウトメールはダイレクトリクルーティングにおける最初の接点です。ここでは、候補者に興味を持ってもらえるスカウトメールのポイントを5つ紹介します。
ターゲットとするペルソナを明確にする
「どのようなスキルや経験、志向を持った人にアプローチしたいのか」を明確にすることで、スカウトメールの内容も的確に絞り込むことができます。ペルソナ像が曖昧だと、「どんな人材を求めているか」「企業のどんな魅力を伝えるべきか」が分かりにくくなり、スカウトを受け取った側も響きにくいメッセージとなってしまいます。
事務的な文面を避ける
形式的な文面だけでは、相手に響きません。候補者のプロフィールや経歴、実績に関心を示し、「なぜこの候補者にスカウトしたのか」「自社でどのように活躍してもらいたいか」を具体的に伝えると、相手の興味を引きやすくなります。また、堅苦しい表現ばかりでなく、丁寧かつ親しみを感じられる文面を意識することもポイントです。
わかりやすい内容にする
スカウトメールを受け取った候補者が、すぐに「この企業はどんな環境なのか」「どんな役割を期待されているのか」をイメージできるよう、要点をシンプルに整理しましょう。
長文すぎると読み手が負担に感じ、途中で読むのをやめてしまうこともあります。箇条書きや短い段落で、必要な情報を端的に伝えるのがおすすめです。
開封率が高い時間帯にメールを送る
ビジネスパーソンがメールをチェックするタイミングは、通勤時間帯や業務開始前、昼休み、業務終了後などが多いと言われています。
開封率が高い時間帯を狙って送ることで、スカウトが読まれる可能性が高まり、返信も得やすくなります。具体的には朝8時〜9時、昼12時前後、夜20時〜22時あたりが目安となるでしょう。
以下の記事では、スカウト型採用ツールとして注目される「オファーボックス」の評判や他のサービスとの比較、導入時のポイントなどを詳しく解説しています。自社に合ったスカウトサービス選定の参考として、ぜひご覧ください。
【採用担当者向け】オファーボックスの評判・口コミを解説!比較・使えてない企業の特徴は?
RecUpを利用する
スカウトメールの文面作成やターゲットへのアプローチを効率化するには、「RecUp」のようなAIスカウトサービスの活用がおすすめです。
AIが候補者の情報を分析し、最適なアプローチタイミングや文面を提案してくれるため、採用担当者の負荷軽減やスカウトの精度向上が期待できます。特に業務量が多い採用担当者にとって、工数削減の観点からも大きなメリットがあります。
今すぐ無料で相談するダイレクトリクルーティングの導入事例3選

ダイレクトリクルーティングを導入して成果を上げている企業は国内外に多数存在します。ここでは、代表的な事例を3つご紹介します。
キリンホールディングス株式会社
キリンホールディングスでは、従来の求人媒体や採用サイトへの掲載だけでなく、ダイレクトリクルーティングプラットフォームを活用して幅広い候補者にアプローチしています。
スカウト型採用を取り入れ、さらにターゲットを明確にしたことで従来の手法では出会えなかったタイプの人材を確保し、組織のイノベーションを加速させています。
株式会社日産フィナンシャルサービス
株式会社日産フィナンシャルサービスでは、専任の担当者が運用の流れをサポートしたり、人材の市場感を踏まえたアドバイスを受けられるサービスを活用しました。
その結果、採用コスト削減と採用率のアップを叶えました。
Chatwork株式会社
ビジネスチャットツールを提供するChatwork株式会社は、ダイレクトリクルーティングを活用しています。
同社は募集要件に限らない「優秀な人材」を求め、候補者との初期段階のコミュニケーションを手厚くサポート。応募前から相互理解を深めるアプローチによって、採用活動の質を大きく向上させています。
以下の記事では、実際にダイレクトリクルーティングを導入した企業の具体的な事例を紹介しています。自社での導入を検討している方は、成功企業の取り組みや成果を参考に、より効果的な活用方法を学んでみてください。
【自社事例あり】ダイレクトリクルーティングの導入事例まとめ!メリットや効果的に行う5つのポイントとは?
AIスカウトならRecUp

ダイレクトリクルーティングは、企業にとって大きな可能性を秘めた採用手法です。しかし、スカウト文面の作成や候補者の選定、日々のコミュニケーションなど、担当者に大きな負担がかかることも事実。そこでおすすめしたいのが、AIを活用したスカウトサービス「RecUp」 です。
RecUpを活用することで、ダイレクトリクルーティングにおける煩雑な業務を大幅に軽減し、成果につながるアプローチを効率的に進められます。
貴社の採用活動がよりスムーズに、そして成果につながることを願っております。ダイレクトリクルーティングをうまく活用し、優秀な人材との新しい出会いを創出していきましょう。