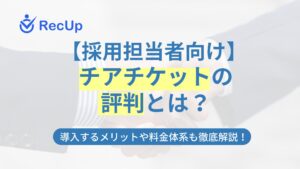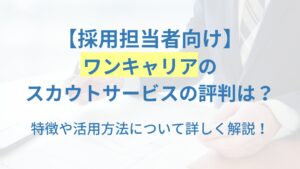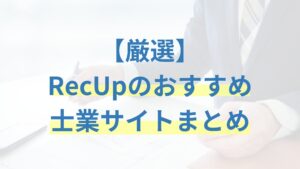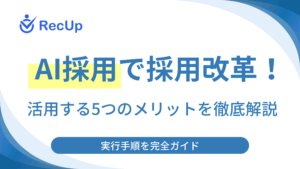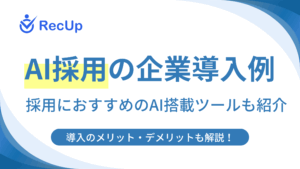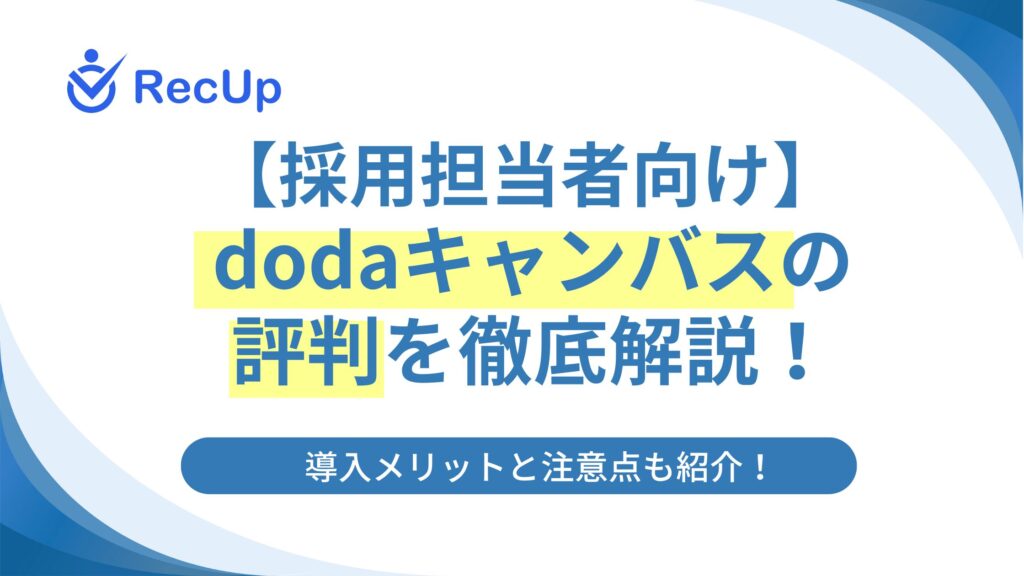
dodaキャンパスは、新卒採用やインターン採用を検討する企業の人事・採用担当者にとって非常に注目されている逆求人型プラットフォームです。学生からの高い支持を誇り、2025年時点で登録学生数は113万人、オリコン顧客満足度®調査「逆求人型就活サービス」ランキングでも4年連続で1位に選ばれるなど、安定した人気を誇るサービスです。
そんなdodaキャンパスは、企業からも効率的な母集団形成や優秀な人材と早期にアプローチできると評判です。しかし、リアルな口コミを調べてみると、いくつか注意したいポイントもあるようです。
そこでこの記事では、dodaキャンパスの特徴や料金体系、企業から見たリアルな評判を解説していきます。また、どんな企業に向いているかや利用するメリット、ほかの媒体との比較などを取り上げますので、自社の新卒採用に活用すべきかどうかの判断材料にしていただければ幸いです。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
dodaキャンパスの評判は?企業から見たリアルな声を紹介!

採用活動において新しいサービスを導入する際、最も気になるのが実際に利用している企業の声ではないでしょうか。dodaキャンパスは逆求人型の新卒採用サービスとして近年注目を集めていますが、導入を検討する企業にとっては「本当に効果があるのか」「自社に合っているのか」という疑問が生じるのは当然のことです。
ここでは、実際にdodaキャンパスを導入した企業の生の声をご紹介します。早期選考を目指す優秀な学生との出会い、学生一人ひとりに寄り添った丁寧な採用活動の実現、効率的なデータ活用による採用戦略の最適化など、具体的な成功体験から見えてくるdodaキャンパスの特徴を明らかにしていきます。
早期選考学生にもアプローチができた
株式会社メンバーズでは、dodaキャンパスを活用することで早期に動き出す優秀な学生層へのアプローチに成功しています。同社が特に重視したのは、従来の採用手法では出会えなかった層の学生との接点づくりでした。
dodaキャンパスの逆求人型というシステムにより、企業側から学生のプロフィールを閲覧し、自社にマッチしそうな学生に直接アプローチできる点が大きなメリットとなりました。特に、就職活動を早期からスタートさせている意識の高い学生が多く登録している点が、同社のニーズと合致したのです。
実際の運用では、学生のプロフィールから興味関心や専攻分野を詳しく確認し、自社のビジョンや事業内容とマッチする可能性の高い学生を絞り込んでオファーを送付しました。その結果、従来の採用ルートでは接点を持ちにくかった早期選考層の学生との面談機会を多数創出することができたといいます。
さらに、オファーを通じた初期接点から選考プロセスへの移行がスムーズである点も評価されています。学生側も企業からの直接的なアプローチに対して関心を持ちやすく、メッセージのやり取りを通じて相互理解を深められる仕組みが、採用活動の効率化に貢献しました。
理念に共感しdodaキャンパスを導入!採用課題だった早期母集団形成に成功
学生さんに寄り添った採用活動ができた
株式会社IRRCでは、dodaキャンパスの導入により、学生一人ひとりに丁寧に向き合う採用活動を実現できたと評価しています。同社が重視したのは、単に内定者数を増やすことではなく、企業と学生の相互理解を深めながら、お互いにとって最適なマッチングを図ることでした。
dodaキャンパスのプラットフォームでは、学生が自身の経験や価値観、志向性などを詳細にプロフィールとして記載しています。企業側はこの情報を事前に把握した上でオファーを送ることができるため、初回接触の段階から学生の個性や背景を理解した状態でコミュニケーションを開始できる点が大きな特徴です。
IRRCでは、この仕組みを活用して画一的な採用メッセージではなく、各学生の関心領域や経験に合わせたパーソナライズされたオファー文を作成しました。その結果、学生からの返信率が向上し、面談の場でも既に相互理解が一定程度進んだ状態からスタートできるようになったといいます。
また、従来の大量エントリー型の採用活動と比較して、少数精鋭でじっくりと学生と向き合える環境が整った点も評価ポイントです。採用担当者が一人ひとりの学生のキャリア観や人生観に耳を傾け、自社での成長イメージを具体的に伝えることで、学生側も企業への理解と興味を深めていきました。このような丁寧な採用プロセスは、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的な定着率向上にもつながると期待されています。
ダイレクトリクルーティングだからこそできた、学生に寄り添った採用の秘訣とは?
データ活用がしやすい
東京ガスホールディングス株式会社では、dodaキャンパスが提供する充実したデータ分析機能を高く評価しています。採用活動の効果測定や戦略立案において、客観的なデータに基づいた判断ができることは、採用担当者にとって非常に重要な要素です。
同社が特に注目したのは、オファーの送付数や承認率、メッセージの既読率など、採用活動のあらゆるプロセスを数値で可視化できる機能でした。これにより、どのようなプロフィールの学生に対してオファーを送ると承認率が高いのか、どのようなメッセージ内容が学生の関心を引きやすいのかといった分析が可能になりました。
実際の運用では、初期段階でテスト的に複数パターンのオファー文を送付し、その反応率をデータで比較することで、最も効果的なアプローチ方法を特定しました。学生の所属大学や専攻、興味関心の傾向などのクロス分析を行ったことも、自社にマッチしやすい学生層の特徴を明確化し、ターゲティングの精度を高めるのにつながったといいます。
さらに、採用チーム内でのデータ共有が容易である点も運用上の利点として挙げられています。複数の採用担当者が同じダッシュボードを確認することで、チーム全体で採用活動の進捗や課題を共有し、迅速な改善アクションにつなげることができました。
dodaキャンパスのデータ活用で採用戦略を最適化【導入事例:東京ガスホールディングス株式会社】
dodaキャンパスが怪しいと言われる理由とは?
インターネット上では「dodaキャンパスが怪しい」という声が一部で見られることがあります。新しいサービスに対して慎重な姿勢を持つことは当然ですが、こうした評判の背景には具体的な理由があります。ここでは客観的な視点からその理由を分析します。
まず挙げられるのが、逆求人型サービスに対する理解不足です。従来の就職活動では学生が企業にエントリーするのが一般的でしたが、dodaキャンパスは企業側から学生にアプローチする仕組みです。この新しい形式に馴染みのない学生や企業担当者が、システムの仕組みを十分に理解しないまま「通常とは異なる」という理由で警戒心を抱くケースがあります。
次に、企業からのオファーメッセージの質にばらつきがある点も一因として考えられます。dodaキャンパスに登録している企業は多様であり、中には学生のプロフィールをあまり読まずに大量のオファーを送付する企業も存在します。このような画一的なアプローチを受けた学生が、サービス全体に対してネガティブな印象を持つ可能性があります。
また、個人情報の取り扱いに関する懸念も見られます。プロフィールに詳細な情報を登録する必要があるため、その情報がどのように管理・活用されるのか不安を感じる学生がいるのも事実です。ただし、dodaキャンパスを運営するベネッセi-キャリアはプライバシーマークを取得しており、情報管理体制は整備されています。
このような「怪しい」という評判の多くは、サービスの仕組みへの理解不足や、一部の不適切な利用事例から生じている側面が大きいと言えます。実際には多くの企業が適切に活用し、成果を上げているサービスです。導入を検討する際は、こうした評判の背景を理解した上で、自社の採用方針に合致するかどうかを判断することが重要です。
dodaキャンパスとは?

dodaキャンパスは、企業が直接スカウトを送る逆求人型の新卒・インターン採用支援プラットフォームです。2025年時点で約113万人の学生が登録し、国内最大級の学生データベースを誇っており、オリコン顧客満足度®調査「逆求人型就活サービス」ランキングでも4年連続で1位に選ばれるなど、安定した人気を得ています。
dodaキャンパスは企業からの信頼も厚く、これまで6,200以上の企業が活用しています。まずはそんなdodaキャンパスの特徴について詳しく見ていきましょう。
【採用担当者向け】dodaキャンパスの料金体系とは?利用期間や運用のコツを徹底解説!
逆求人型プラットフォーム
dodaキャンパスは「逆求人型」と呼ばれる新しい採用サービスで、学生が企業を探すのではなく、企業が学生のプロフィールを閲覧して直接スカウトを送る仕組みをとっています。
この仕組みの最大のメリットは、企業が自社の求める条件やスキルに合った学生に効率よくアプローチできる点にあります。学生にとっても、自分から積極的に応募しなくても、自身の強みや経験を見た企業からスカウトが届くため、新たな出会いや選択肢が増えます。
逆求人型プラットフォームでは、一般的な求人サイトのように大量応募で選考に時間がかかることが少なく、マッチングの精度が高まるため、採用活動の負担軽減にも役立っています。採用工数を削減しつつ的確にターゲット人材を獲得したい企業にとって、非常に有効な仕組みとなっています。
登録学生に独自のキャリア教育を実施
dodaキャンパスが他の採用プラットフォームと大きく異なる点は、登録学生に対して独自のキャリア教育プログラムを提供していることです。dodaキャンパスは、教育や人材・転職サービスに特化したベネッセとパーソルキャリアの合同会社が運営しています。学生はこれらの企業に裏打ちされた自己分析や適性検査、面接対策など多彩なサポートを受けられるため、早期から自分の強みや将来の方向性を明確にできます。
特に、大学1・2年生向けの大型キャリアイベント「キャリアゲートウェイ」は2025年で4年目を迎え、累計4,200人以上の学生が参加。参加学生の後輩へのおすすめ度は10点満点中8.32点と高評価を得ています。
こうした教育プログラムを通じて、成長支援型のサービスとして質の高い人材供給を実現していることが、企業からの信頼を集める理由のひとつとなっています。採用後のパフォーマンス向上や定着率アップにもつながるため、企業の長期的な採用戦略に適したサービスといえるでしょう。
就活生だけでなく、低学年にもアプローチ可能
dodaキャンパスの大きな強みは、大学1年生や2年生などの低学年層にも早期からアプローチできる点です。多くの採用サービスが3年生以上を対象としている中、dodaキャンパスは成長意欲の高い低学年の学生に対し、キャリアイベントや業界理解促進の案内を送ることが可能です。
これにより、学生はまだ進路が決まっていない段階から幅広く企業を知り、キャリア観を育むことができ、企業は長期的に母集団を形成できます。また、早期に自社の魅力を伝えられることで、採用競争において優位に立ちやすく、インターンや選考へとつながりやすいのも特徴です。
人材獲得競争が激化する昨今において、特に低学年からの戦略的な接触は将来の採用成功に欠かせない施策となっています。
dodaキャンパスを活用して採用に成功した事例を紹介!

実際にdodaキャンパスを導入し、採用活動において具体的な成果を上げている企業の事例をご紹介します。サービスの導入時期や承認数、内定承諾に至るまでのプロセスを詳しく見ていくことで、dodaキャンパスがどのように採用成功に貢献しているのかが明らかになります。
業種や企業規模によって活用方法や成果は異なりますが、共通しているのは戦略的にサービスを活用し、学生との丁寧なコミュニケーションを重視している点です。以下で紹介する事例から、自社での活用イメージを具体的に描いていただければと思います。
株式会社Delight
株式会社Delightは2025年3月からdodaキャンパスを導入し、新卒採用活動に活用しています。同社の導入事例は、サービスを初めて利用する企業にとって非常に参考になる内容となっています。
初年度となる26卒採用では、50名の学生からオファーの承認を獲得しました。初めての試みということもあり、手探りの部分もありましたが、学生とのコミュニケーションを通じてサービスの特性や効果的な活用方法を学びながら進めたといいます。最終的な内定承諾者数は0名という結果でしたが、この経験を踏まえて次年度に向けた改善策を明確にすることができました。
27卒採用では大きく方針を見直し、早期からの積極的なアプローチを開始しました。大学3年生の9月時点で既に320名の学生からオファー承認を獲得しており、前年比で大幅な増加を実現しています。承認率を高めるために、学生のプロフィールをより詳細に分析し、自社の求める人物像とのマッチング精度を向上させる取り組みを行いました。
また、オファー文の内容も学生一人ひとりに合わせてカスタマイズし、企業の魅力や具体的な仕事内容をより分かりやすく伝える工夫を重ねました。その結果、27卒では2〜3名の内定承諾を予定しており、サービス活用の効果が着実に表れています。同社の事例は、初年度の経験を活かして継続的に改善を図ることの重要性を示しています。
小売業界
小売業界のある企業では、2025年3月からdodaキャンパスを導入し、店舗スタッフや本部職の新卒採用に活用しています。小売業界は就職先としての認知度向上や、業界の魅力を効果的に伝えることが採用活動における課題となることが多い業界です。
26卒採用の初年度では、256名の学生からオファー承認を獲得し、2名の内定承諾に成功しました。小売業界に対して先入観を持っている学生も多い中、dodaキャンパスを通じて直接企業の魅力や働き方、キャリアパスを伝える機会を得られたことが大きな成果につながりました。
特に効果的だったのは、店舗での具体的な仕事内容や、若手社員の活躍事例をオファー文や面談の中で丁寧に説明したことです。学生が抱く「小売業は大変そう」というイメージを払拭し、やりがいや成長機会の豊富さを理解してもらうことで、興味を持つ学生を増やすことができました。
27卒採用では、前年度の経験を活かして更に活動を拡大し、大学3年生の9月時点で既に426名の学生からオファー承認を獲得しています。承認数は前年比で約1.7倍に増加しており、4〜5名の内定承諾を予定しています。この企業の事例は、業界の魅力を効果的に伝えることで、当初は志望していなかった学生層にもアプローチできる可能性を示しています。
外食業界
外食業界のある企業は、2025年8月からdodaキャンパスを導入した比較的新しい事例です。外食業界も小売業界と同様に、労働環境や働き方に対する学生の先入観が採用活動のハードルとなることがあります。
27卒採用での初導入となり、大学3年生の9月時点で106名の学生からオファー承認を獲得しています。導入からまだ数ヶ月という短期間でこの数字を実現できたのは、外食業界の魅力や自社の強みを明確に打ち出したアプローチが効果を発揮したためです。
同社では、単に「飲食店で働く」というイメージではなく、食を通じた顧客体験の創造や、店舗マネジメント、商品開発など、多様なキャリアパスがあることを積極的に発信しました。また、働き方改革への取り組みや、若手社員の裁量権の大きさなど、学生が気になるポイントについても率直に情報提供を行いました。
導入からまだ日が浅いため内定承諾の実績は出ていませんが、学生との面談では業界や企業への理解が深まり、前向きな反応を得られているといいます。今後、選考プロセスを進めていく中で、dodaキャンパスを通じた採用がどのように結実していくかが注目されます。この事例は、導入初期段階でも適切な戦略で一定の成果を上げられることを示しています。
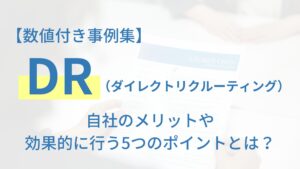
dodaキャンパスを活用する3つのメリットを徹底解説!

ここまで、dodaキャンパスの特徴や評判、向いている企業について詳しく解説しました。しかし、たくさんの逆スカウトサービスがある中で、dodaキャンパスが多くの企業に選ばれているのには、それだけ強いメリットがあるはずです。
繰り返しになりますが、ここでdodaキャンパスを活用する3つのメリットをおさらいしておきましょう。
①ターゲット層に直接アプローチできる
dodaキャンパスの最大の強みは、企業が学生の学歴、スキル、志望条件など詳細なプロフィールに基づいて検索を行い、自社に合った学生に直接スカウトメッセージを送れる点です。
これにより、企業は受け身で応募を待つ従来の方法と違い、積極的にターゲット層に働きかけることができ、より効率的な母集団形成が可能になります。
実際に、求める人物像に合致した学生に狙い撃ちでアプローチできるため、ミスマッチが減少し、採用成功率が高まる傾向にあります。学生側も自らの適性や志向に合ったオファーを受けられるため、双方にとって質の高いマッチングが実現しやすいことが特徴です。
以下の記事では、AIを活用したスカウトサービスの選び方や、おすすめのツールを多数紹介しています。dodaキャンパスと併用することで、より効率的な採用活動が可能になりますので、ぜひ参考にしてみてください。
【2025年最新】AIスカウトサービス15選を徹底比較!メリットや選ぶ際のポイントを解説
②早期から学生と接点を持てる
dodaキャンパスの大きな特徴のひとつは、大学1年生から登録可能である点です。これにより、学生がまだ就職活動を本格化する前の段階から企業が直接アプローチできるため、早期に自社の魅力を伝え、インターンシップ参加者の獲得につなげやすくなります。
さらに、dodaキャンパスは低学年の学生に対してもキャリア支援の情報やイベント案内を提供できるため、学生の成長に合わせつつ、長期的な関係構築が可能です。こうした早期接点づくりは、近年の採用トレンドに合致しており、効率的かつ計画的に質の高い母集団を形成できるため、企業の採用競争力を大きく高めるポイントとなっています。
③自社の知名度が低くても採用機会を得られる
一般的な就職サイトでは、企業のブランド力が応募数に大きく影響します。知名度が高い大手企業は多くの学生から人気を集めやすい一方、中小企業や地方企業は注目されにくく、優秀な学生を見つけるのが難しいことも少なくありません。
しかし、dodaキャンパスは学生個々のプロフィールに基づいてターゲットを絞り、企業から能動的にスカウトを送る逆求人型のサービスです。そのため、知名度が低い企業でも、優秀な学生に直接アプローチでき知ってもらう機会を得られるのが特徴です。
隠れた優秀人材の発掘や、採用効率の向上にも繋がるため、限られた採用コストで成果を出したい企業には特に適しています。企業の魅力を動画や企業ページで強くアピールできるので、ブランド力が不足している企業でも学生に訴求しやすい環境が整っているのも魅力と言えるでしょう。
dodaキャンパスはどんな企業に向いている?

上記のように、dodaキャンパスは、良い評判も悪い評判もあります。しかし、そもそも向いている企業であれば、dodaキャンパスのメリットを存分に享受することができるでしょう。
それでは、dodaキャンパスはどのような企業に向いているのでしょうか。ここで、詳しく解説していきます。
大手と競合せず学生に直接アプローチしたい中堅・中小企業
大手求人ナビサイトでは、知名度の高い大企業が多くの学生から注目を集めるため、中堅・中小企業はどうしても埋もれてしまいがちです。しかし、dodaキャンパスは逆求人型のスカウトサービスなので、学生側が企業を探すのを待つだけでなく、企業自らが優秀な学生を積極的に見つけて直接アプローチできます。これにより、知名度が低くても自社の魅力をしっかりと伝え、採用のチャンスを増やすことができるのが大きな強みです。
また、大手企業と同じ土俵で競い合うのではなく、独自の採用戦略を展開できるため、中堅・中小企業でも戦略次第で採用競争において有利に立つことが可能です。後でお話するように、dodaキャンパスでは低学年の学生にも早期からアプローチでき、将来の優秀な人材と長期的なつながりをつくることができるので、その点もうまく活用すると良いでしょう。
インターンや早期接点を重視する企業
近年の新卒採用では、インターンシップや早期から学生との接点づくりが極めて重要な戦略になっています。dodaキャンパスは大学1・2年生などの低学年から学生に直接アプローチできるため、早期に企業の魅力や業界のリアルな情報を伝えやすい特徴があります。これにより、インターンシップへの参加者を増やすだけでなく、選考前の段階から学生との関係構築をスムーズに進めることが可能です。
さらに、dodaキャンパスは学生のアクティブ率を高める工夫や、オファー枠の柔軟な管理システムを備えており、効率よく質の高い母集団形成ができる可能性が高いです。動画配信やキャリア相談、座談会など多様な接点を組み合わせ、単発のインターンだけでなく継続的な関係性を築けば、内定辞退率の低減や入社後の定着率向上にもつながります。
早期接点を重視し、計画的かつコスト効率の良い採用活動を目指す企業にとって、dodaキャンパスは最適なサービスといえるでしょう。
幅広い専攻学生と接触したい企業
dodaキャンパスは、大手企業から中小・ベンチャー企業まで約6,200社以上の企業が利用しており、さまざまな志向やスキルセットを持つ学生にアプローチできる環境が整っています。そのため、理系・文系問わず多くの大学や学部、専攻の学生が登録しており、企業は多様な人材にリーチすることができるようになっています。
この状況は、専門職や事務系、技術系など幅広い分野の学生から応募を促せるため、複数の職種で採用を行う企業にとって非常に効果的な採用チャネルとなるでしょう。特に、新規事業の立ち上げや多様なバックグラウンドを持つ若手を求める企業においては、効率良くターゲット層を拡げられるのは大きなメリットとなるはずです。
dodaキャンパスを効果的に活用するならAIスカウト「RecUp」!

dodaキャンパスは、多様な学生層に効率的にアプローチできる国内最大規模の新卒採用に特化した逆求人型スカウトサービスです。約113万人のキャリア情報を持つ学生データベースから、自社の求める条件に合致したターゲットをピンポイントで検索・接触できるため、質の高い母集団形成ができるのが魅力です。また、大学1年生のうちから優秀な学生との接点が持てるため、多くの企業から良い評価を得ています。
しかし、逆求人型スカウトサービスは、詳細な候補者選定やメッセージ作成、応募対応、面談調整といった運用には相応の人的リソースが必要になります。そこで、採用担当者の負担を軽減するためにオススメしたいのが、AIスカウトサービス「RecUp(リクアップ)」です。RecUpはAIが候補者のプロフィール分析を行い、最適なスカウトメッセージを自動生成するサービスです。これにより、人事担当者の手間を省きつつ、より高精度なマッチングと効率的な採用活動が可能となります。
こういったダイレクトリクルーティングでは、カスタマイズされたメッセージが開封率やその後の応募率に大きく影響します。ぜひ最新のAI技術を活用したサービスを取り入れて、限られたリソースでも効果的な新卒採用を推進していきましょう。詳しい情報は下記よりご確認ください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。