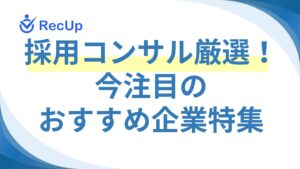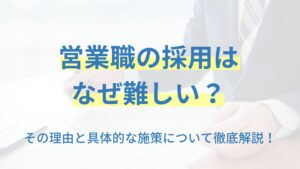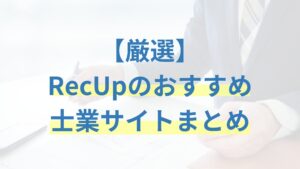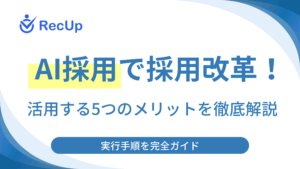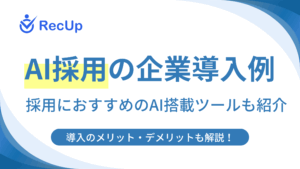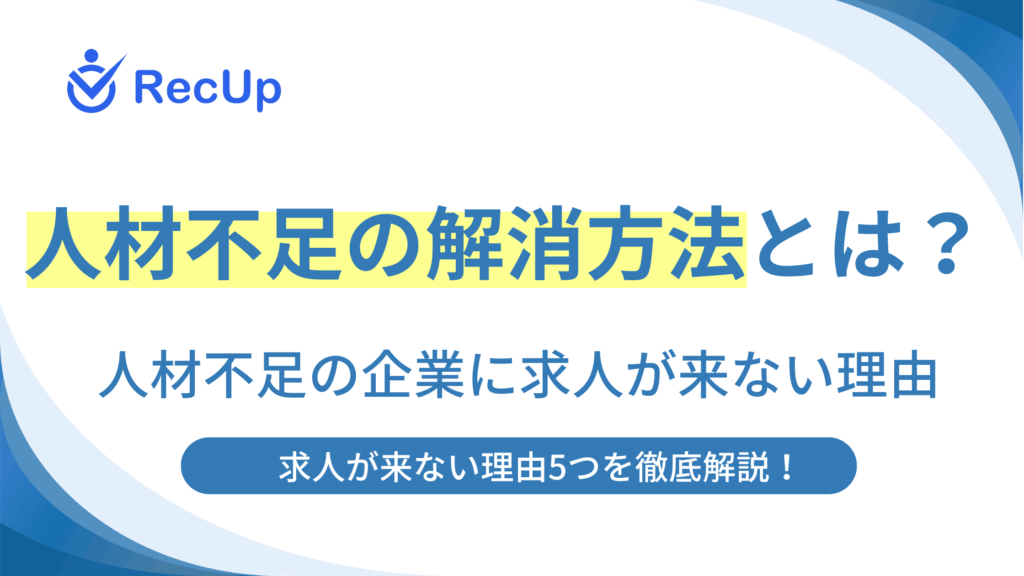
近年、多くの企業が「人手不足」という大きな課題に直面しています。せっかく求人を出しても応募がまったく来ない、来てもすぐ辞めてしまう――そんな悩みを抱える企業も少なくありません。
この記事では、なぜ求人に応募が来ないのか、その代表的な理由を5つに分けて詳しく解説するとともに、応募者に選ばれる求人内容の作り方や人手不足を解消するための具体策について紹介します。
採用活動の改善に向けたヒントを探している企業担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
人手不足に困っている企業の割合はどれくらい?

現在、日本国内の企業の多くが深刻な人手不足に直面しています。帝国データバンクが発表した「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」によると、2025年4月時点で「正社員が不足している」と回答した企業は51.4%にものぼり、特に建設業・運輸業・サービス業ではその傾向が顕著になっています。また、非正規社員についても30%以上の企業が不足を感じており、業種や規模を問わず「人が足りない」という声が後を絶ちません。
こういった人手不足の背景には少子高齢化や働き方の多様化により、働き手そのものの数が減っているという構造的な問題があります。また、採用競争の激化や求職者側の価値観の変化により、従来の採用手法が通用しなくなってきているのも一因です。今後もこの傾向は続くと見られており、多くの企業が早急な対策を迫られています。
加えて、地域や業種によっては人材の定着率も低く、採用してもすぐに辞めてしまうといった課題も無視できません。そのため、単なる募集ではなく、求職者に「選ばれる工夫」が必要とされています。
人手不足を解消したい企業の求人に応募が来ない5つの理由

せっかく求人を出しても、応募がまったく来ない――そんな悩みを抱える企業は少なくありません。人手不足の解消を目指すうえで、まず見直すべきは「求人の出し方」です。
求職者が求人情報を見るとき、仕事内容や条件、働く環境などを総合的に判断しています。つまり、求人票の作り方や媒体の選定を間違えると、いくら人手を欲していても誰にも届かないのです。
以下では、特にありがちな応募が来ない5つの理由について詳しく解説します。
①仕事内容に関する明確な記載がない
求人票で最も重視される要素のひとつが「仕事内容」です。しかし、具体的な業務内容が曖昧なまま掲載されている求人も多く見受けられます。
「営業スタッフ募集」とだけ記載されていても、どのような商材を扱い、どのような営業手法をとるのかが分からなければ、求職者は不安を抱いてしまいます。仕事内容が曖昧な場合、「ブラック企業かもしれない」「ミスマッチが起こるかも」といったネガティブな印象を与えるリスクもあります。また、入社後のイメージが湧かず、応募自体を見送るケースも少なくありません。
求職者に安心感を与えるためにも、「どんな業務を」「どんな目的で」「誰と一緒に」行うのかを具体的に記載することが重要です。たとえば「法人向けの既存顧客に対するルート営業」「2人1組で訪問し、提案や納品まで一貫して担当」など、実際の仕事の様子を描写するように心がけましょう。
②自社のターゲットがいない求人媒体を活用している
求人広告を出しても応募がまったく来ない場合、その媒体が自社の求める人材とマッチしていない可能性があります。求人媒体にはそれぞれ特徴があり、登録者の年齢層・職種・勤務地志向などが異なります。たとえば、若年層を採用したいのに中高年の利用者が多い媒体を選んでしまうと、そもそもターゲットに情報が届かず、応募が見込めないのです。
また、業種や職種に特化した媒体を活用することも大切です。専門職であれば、汎用的な求人サイトよりも専門サイトの方がマッチング率は高くなります。地域密着型の採用であれば、地方に強い媒体を使うなど、ターゲットに合わせて使い分ける工夫が求められます。加えて、近年ではSNS広告やスカウトサービスなど、新たな手法も増えてきており、これらを組み合わせて効率よくアプローチするのも有効です。
重要なのは、「求人広告は出せば効果がある」という前提を捨てること。自社の採用ターゲットを明確にし、その層が実際に使っている媒体にアプローチできているかを見直すことが、応募数の向上には不可欠です。
③応募条件が厳しすぎる
求人に応募が来ない理由として、「応募条件が過剰に厳しい」というケースも非常に多く見られます。たとえば「即戦力のみ歓迎」「〇〇業界で3年以上の経験必須」「30歳以下限定」など、条件を狭めすぎることで、そもそも多くの求職者が応募対象から外れてしまうことになります。
もちろん、採用したい人物像にマッチする条件を設定すること自体は間違いではありません。しかし、条件を絞り込みすぎると、実力はあっても少し経験が足りない人や、転職回数が多いが熱意のある人など、可能性を持った人材を逃してしまうリスクが高まってしまいます。
また、条件を厳しく設定している企業に限って、実際の面接で柔軟な対応をしていることも少なくありません。それならば、最初から「必須」ではなく「歓迎」「優遇」といった表現を使い、幅広い層に門戸を開いておいた方が効果的です。
応募条件の見直しは、募集数を増やすうえで即効性のある改善ポイントといえます。経験や資格だけでなく、人柄やポテンシャルに注目する採用スタンスへと転換することで、応募者の層が一気に広がる可能性があります。
④競合となる企業に比べて給与や福利厚生が劣っている
求人情報を見た求職者は、同じ職種・地域で募集している他の企業とも必ず比較します。その際、給与や福利厚生などの条件が他社に比べて明らかに見劣りしていれば、応募を敬遠されてしまうのは当然です。
たとえば、同じ営業職であっても「月給25万円+インセンティブ」の企業と「月給20万円・賞与なし」の企業とでは、待遇面での印象に大きな差が出ます。「ウチの会社は予算がないから」と諦めてしまう前に、まずは競合他社の求人内容をリサーチし、自社がどの位置にいるかを把握しましょう。
給与を大きく上げることが難しい場合でも、福利厚生や柔軟な働き方、職場の雰囲気など、他にアピールできる強みを整理して発信することが重要です。また、見せ方の工夫によって印象は大きく変わります。たとえば「残業なし」「土日休み」「子育てと両立できる環境」など、求職者の関心が高い情報を前面に出すだけでも、応募率が上がることがあります。
⑤人間関係や社風に馴染めるかを不安に感じる
給与や条件が良くても、「この会社に馴染めるか不安…」という気持ちがぬぐえず、応募をためらう求職者は意外と多いものです。特に近年では、働きやすさや人間関係、社風との相性を重視する人が増加しており、求人票からそれらの情報がまったく読み取れない場合は、「ギスギスしてそう」「古い体質かも」といったネガティブな印象を持って敬遠してしまうこともあるでしょう。
このような不安を解消するためには、職場の雰囲気や社員の声を積極的に発信することが重要です。たとえば「20代社員が多く活気ある雰囲気」「月1回の交流ランチあり」「中途入社率80%でなじみやすい職場」など、実際の社内の様子がイメージできるような情報を求人票や採用サイト、SNSで紹介するのがおすすめです。
職場の雰囲気は数値化できるものではない分、伝え方の工夫が問われます。求職者が「ここでなら働いてみたい」「自分にも合いそう」と感じるような情報を積極的に出していくことで、応募のハードルを大きく下げることができるでしょう。
人手不足を解消するために知っておくべき応募者側が求める条件

企業が人手不足を解消するためには、「どんな条件が求職者にとって魅力的なのか」を正しく理解することが不可欠です。企業側の一方的な視点で求人内容を作成しても、求職者のニーズに合っていなければ応募にはつながりません。
応募を増やすためには、求職者がどのような条件を重視し、何を軸に職場を選んでいるのかを知ることが重要です。
以下では、特に注目される3つのポイントを紹介し、それぞれどのように求人票や制度に反映させるべきかを詳しく解説します。
今よりも昇格や昇給の可能性があるか
多くの求職者は「今よりも成長できる職場かどうか」「キャリアアップが望めるか」を重視して仕事を選んでいます。特に20代〜30代の若手層にとっては、昇給・昇格の見込みがあるかどうかが応募の決め手になるケースが多く、将来的な展望が見えにくい企業にはなかなか応募が集まりません。
単に「昇給あり」「評価制度あり」と記載するだけでは不十分で、どのような仕組みで評価され、実際にどれくらいの期間でどんな昇進・昇給が可能なのかを明確に伝えることが大切です。たとえば「入社2年目でリーダー昇格の実績あり」「年2回の人事評価制度により昇給機会あり」など、具体的な事例や制度の流れを示すと、求職者は安心感を持って応募できます。
また、スキルアップのための研修制度や資格取得支援なども、キャリア形成を支援する仕組みとして高く評価されるポイントです。「将来に希望が持てる会社か」という観点から、自社の強みを求人票でしっかりアピールしましょう。
労働時間や休日はどれくらいか
労働時間や休日といった「ワークライフバランス」に関する条件は、今や多くの求職者が最重視する項目です。特に、働き方改革の浸透やコロナ禍以降の価値観の変化により、長時間労働や休日の少なさに対して敏感になっている傾向があります。いくら給与が高くても、プライベートの時間が確保できなければ応募をためらう人も少なくありません。
このため、求人票には「月の平均残業時間」や「年間休日数」「週休の形態」などをできるだけ具体的に記載することが重要です。「年間休日120日以上」「残業は月10時間以内」「完全週休2日制(土日)」といった明確な情報は、求職者に安心感を与えます。また、有給休暇の取得率や育児・介護休暇の実績なども、応募者の信頼を得る材料になるでしょう。
企業側としては、単に制度があるだけでなく「実際に休めるか」が重視されていることを意識する必要があります。現場の運用状況もふまえて、休暇の取りやすさや定時退社の文化があることなどを積極的に発信すれば、他社との差別化にもつながって応募数も増加していくでしょう。
自分の求める勤務地なのか
勤務地も、応募を左右する大きなポイントのひとつです。通勤の利便性や勤務地の希望との一致度は、求職者が応募を検討するうえで欠かせない条件です。特に、地方では「車通勤OKか」「駅から徒歩何分か」なども重要な判断基準となりますし、都市部では「在宅勤務可否」や「配属拠点の選択自由度」が注目されます。
勤務地に関する情報が曖昧だと、求職者は「希望に合わなかったらどうしよう」と不安になり、応募を見送ってしまうことがあります。「勤務地:本社(東京都新宿区)」のように具体的に記載することはもちろん、「転勤なし」「希望考慮」「在宅・ハイブリッド勤務可」などの補足もあれば、求職者は安心して応募することができるでしょう。
また、勤務地が複数ある場合には、希望に応じて配属されるのか、会社都合で決まるのかを明記することも大切です。「東京・大阪いずれか」ではなく、「本人の希望をふまえて決定」など、柔軟さを伝える表現があると応募率が高まります。
求人に応募が来ないという悩みを解決し人手不足を解消する方法

求人を出しても応募が来ないという問題は、多くの企業が直面しています。その背景には、情報の伝え方やターゲットの選定ミス、魅力の打ち出し不足など、さまざまな要因があります。
こうした課題を解決するには、単なる「募集情報の掲載」だけでなく、戦略的な求人施策が求められます。以下では、実際に効果が期待できる4つの対策を紹介します。求職者の目に留まり、かつ応募意欲を高めるためのポイントを押さえて、より質の高い採用活動を実現しましょう。
自社に合った求人媒体を活用する
求人広告を出す際、最も重要なのが「どの媒体を使うか」です。媒体によって登録者層や利用目的が異なるため、自社の採用ターゲットと合っていない媒体を選んでしまうと、いくらコストをかけても期待した反応は得られません。
まず、自社の「理想の人材像」を明確にしたうえで、そのターゲットが日頃どんな媒体を利用しているかを把握しましょう。若年層ならSNSやアプリ系求人、中堅層ならスカウト型サービス、専門職なら業界特化型媒体が有効です。また、複数の媒体を併用し、効果測定をしながら最適な媒体に絞っていくのも賢い方法です。
さらに、最近ではオウンドメディアリクルーティングや採用特化LPを活用する企業も増加しています。これは自社のWebサイト内で求人情報を発信する方法で、自社の文化や魅力を深く伝えるのに最適です。
条件を明確に記載し自社の魅力が伝わる求人内容にする
求人票に記載する内容が曖昧だったり、魅力が伝わりにくかったりすると、求職者は不安を感じて応募を控える傾向があります。逆に、条件や仕事内容が明確で、働くイメージが湧く内容になっていれば、応募意欲を大きく高めることができます。大切なのは、ただ情報を羅列するのではなく、「誰に向けて何を伝えるか」を意識して構成することです。
仕事内容は、どのような業務を・どのような体制で・どんなやりがいがあるのか、といった具体性を持たせると効果的です。また、給与や休日数は、明確な数字で示すようにしましょう。「月給25万円以上+インセンティブ」「年間休日120日」「残業月10時間以内」など、数字を入れることで説得力が増します。
これらに加えて、「この会社で働く魅力は何か」を盛り込むことで、他社との差別化ができます。たとえば「社員同士のコミュニケーションが活発」「研修制度が充実」「社長との距離が近い」など、自社ならではの良さをしっかりアピールしましょう。文章のトーンも、フレンドリーな文体や写真・動画の活用によって、応募者にとって「親しみやすさ」や「安心感」が生まれます。
入社後のキャリアアップを想像できる施策を導入する
応募者にとって、入社後の未来が見えるかどうかは大きな判断基準です。ただ「仕事がある」だけでなく、「この会社で成長できるか」「長く働き続けられるか」といったキャリアの展望が見えると、応募のハードルは下がります。
そのため、求人内容には入社後のキャリアプランや社内制度をしっかりと盛り込むべきです。たとえば、「入社半年後にはリーダーを目指せる」「年2回の人事評価制度により昇給・昇格が可能」「外部講師による研修制度あり」など、実績や具体例を交えて記載することで、応募者は将来像を描きやすくなります。
さらに、キャリアアップ支援制度が整っている場合は、資格取得支援、eラーニング、ジョブローテーションなどの内容を詳しく説明しましょう。キャリア形成を重視する人材を獲得するためには、「育てる姿勢」が伝わる情報発信が不可欠です。
AIスカウトを活用する
求人広告だけで人材を集める時代は終わりつつあり、最近では「スカウト型」の採用手法が注目されています。特に、AIを活用したスカウトサービスは、求職者の行動履歴や志向をもとに、企業側から最適な人材にアプローチできるため、効率的な採用活動が可能になります。中でも注目されているのが、AIスカウト型採用サービス「RecUp(リクアップ)」です。
RecUpは、企業の求人内容に合った求職者をAIが自動で分析・選定し、スカウトメールを自動送信してくれるサービスです。これにより「待ち」の採用から「攻め」の採用へと転換でき、従来の求人広告では出会えなかった層へのアプローチが実現します。
さらに、RecUpは掲載作業やターゲット設定の手間を最小限に抑え、運用の手間を大幅に軽減できる点も魅力です。AIによる分析と自動化の力で、より精度の高いマッチングが可能になり、人手不足の課題にスピーディに対応できます。採用活動の効率化と成果の最大化を同時に実現したい企業にとって、非常に有効な選択肢となるでしょう。
求人に応募が来ても人手不足を解消できない理由

求人に応募が集まったとしても、それだけでは人手不足を根本的に解決することはできません。
採用活動の真のゴールは「長期的に活躍してくれる人材の定着」であり、応募者とのマッチング精度や入社後のフォロー体制が不十分であれば、結果的に離職が相次ぎ、採用活動を繰り返す悪循環に陥ってしまいます。
ここでは、応募が来た後でも人手不足が解消できない主な3つの理由について解説し、対策のヒントをお伝えします。
ミスマッチが起こり内定辞退や入社後の早期退職につながる
せっかく応募があっても、「思っていた仕事と違った」「社風が合わなかった」といった理由で内定辞退や早期退職が起こることは少なくありません。このようなミスマッチは、求人内容と実際の仕事内容・職場環境のギャップが大きいほど発生しやすくなります。特に、給与や福利厚生、働き方などの条件面で誤解があった場合は、入社直前や直後での離脱が発生する傾向があります。
これを防ぐためには、求人情報の段階から「ありのままを伝える」ことが重要です。メリットだけでなく、業務の難しさや求められる能力も正直に伝えることで、求職者の期待値と現実のギャップを最小限に抑えることができます。
また、面接の場でも仕事内容を具体的に説明し、実際に働く現場の様子を写真や動画で見せると、理解が深まり、納得感のある入社につながります。
さらに、入社後すぐにフォロー面談を行う、メンター制度を導入するなど、定着支援の仕組みを整えることも大切です。「雇う」だけでなく「活かす」「続けてもらう」視点を持つことが、人手不足解消のカギとなります。
採用担当者の負担が多く応募者や内定者への対応が疎かになる
採用担当者の業務負担が大きいと、応募者への対応が遅れたり、連絡が不十分になったりすることがあります。その結果、求職者は「不安」「雑に扱われている」と感じて応募を辞退してしまうケースが少なくありません。特に複数の採用業務を少人数で回している企業では、面接日程の調整や応募書類の確認、社内調整などに追われ、きめ細かな対応が難しくなる傾向があります。
また、連絡の遅れだけでなく、質問への対応が曖昧だったり、面接での印象が悪かったりすると、求職者の企業への印象が一気に悪化し、他社に流れてしまうことも珍しくありません。人材が不足している企業ほど、採用活動が雑になってしまいがちですが、それがさらに人手不足を悪化させる原因になっているのです。
この問題への対策としては、採用管理システム(ATS)の導入や、面接日程調整の自動化ツールを活用することで、業務の効率化と対応スピードの向上が図れます。また、AIスカウトのように採用活動の一部を自動化することで、担当者のリソースを「人と向き合う時間」に集中させることも可能になります。人手不足の時代だからこそ、採用の質を上げるための業務改善が求められます。
面接や応募者の評価が属人化しミスマッチを引き起こす
採用プロセスが属人化している場合、評価基準に一貫性がなくなり、結果としてミスマッチが起こるリスクが高まります。たとえば、ある面接官は「即戦力かどうか」を重視するのに対し、別の面接官は「人柄」や「チームへの適応力」を重視しているようなケースです。
属人化を防ぐためには、採用基準を言語化し、共通の評価指標を設けることが大切です。具体的には、面接評価シートの導入や、質問項目の統一、面接官同士の事前すり合わせなどを行うことで、誰が面接しても同じ視点で判断できるように整備しておく必要があります。
また、最終的な判断をチームで行う「合議制」にしたり採用管理ツールを活用して候補者に関する情報を社内で共有するのも、客観性と納得感のある採用につながるためおすすめです。評価プロセスを可視化し、組織全体で納得のいく判断ができる仕組みを整えることで、採用の質と定着率の向上が期待できるでしょう。
AIスカウトならRecUp

求人に応募が集まらない、集まっても定着しない――そんな採用の悩みを根本から解決するには、AIスカウト型サービス「RecUp(リクアップ)」の活用がおすすめです。
RecUpは、企業の採用ニーズに合致する求職者をAIが自動で抽出し、最適なタイミングでスカウトを送信するため、効率よくターゲット人材とつながれます。
また、応募から面談までの導線設計も自動化されており、採用担当者の負担を軽減しながらマッチング精度を高めることが可能です。スピード感と質を両立した採用を実現したい企業にとって非常に有効な選択肢となるしょう。気になった方はぜひ公式HPをチェックしてみてください。