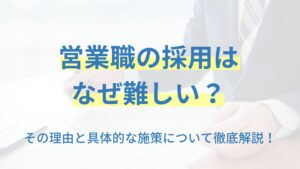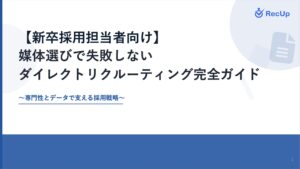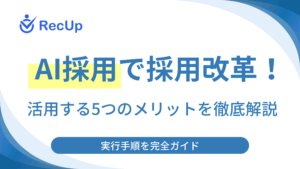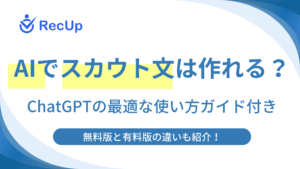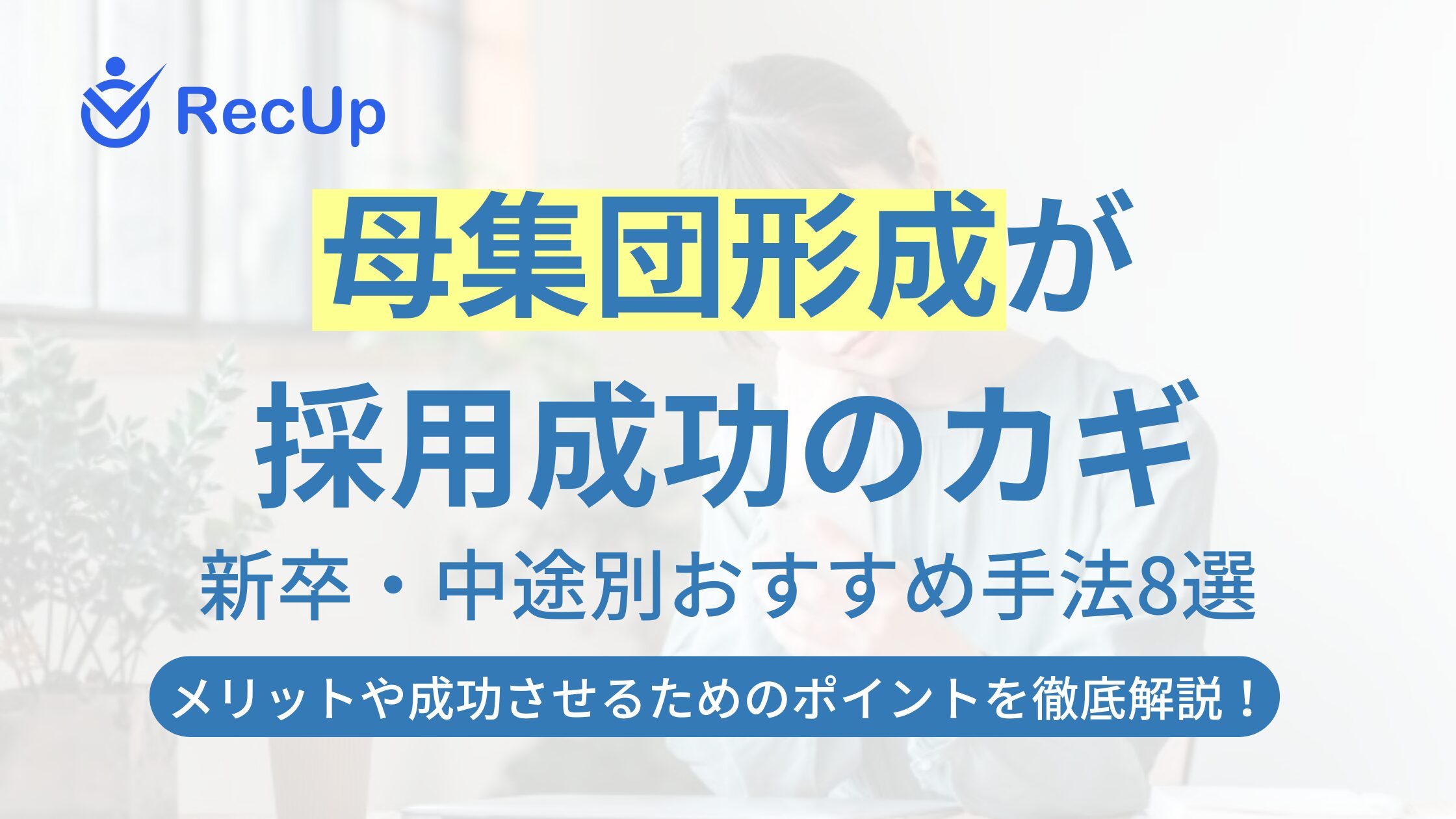
採用活動において「母集団形成」は、採用の成否を大きく左右する重要な工程です。昨今はただ単に応募者数を増やすだけでなく、自社が求める人物像に合う人材を確保できるかが重要です。また企業の成長や定着率の向上のためにも、採用活動を戦略的に進める必要があります。
本記事では、母集団形成の定義や重要性、メリット、効果的な手法、そして成功のためのポイントを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
\スカウト業務の効率化ならAIスカウト「RecUp」にご相談ください/

400社以上のお取り組み実績
国内導入数No.1のAIスカウトサービス
採用のプロとAIが連携し、貴社に最適な採用活動をサポート。
人手不足・母集団形成の悩みを根本解決する『攻めの採用支援』を今すぐ体験。
母集団形成とは?採用活動における重要性を解説

企業の採用活動は、多くのステップから成り立っています。その中でも応募者との出会いをつくる最初の段階は、採用全体の成果に大きく関わります。この段階でどのような準備や取り組みを行うかによって、後の選考や定着にも影響を及ぼすのです。
母集団とは、自社に応募する可能性のある候補者の集まり全体を指します。そして母集団形成とは、その候補者を意図的かつ計画的に集める活動のことです。ここで押さえておきたいのは、単純に応募者数を増やすことだけが目的ではないという点です。
重要なのは、求める人物像に合致した候補者を一定数確保することです。例えばエンジニア職の採用であれば、必要なスキルセットや実務経験年数、携わってきた業界やプロジェクトの種類などを事前に整理します。その上で、条件に見合う人材が集まりやすい採用チャネルを選定し、アプローチ方法を検討していきます。
母集団形成は採用計画全体の土台となる活動です。しっかりとした母集団があることで、採用人数の目標設定や選考スケジュールの立案、予算配分といった計画を具体的に進めやすくなります。
つまり母集団形成の目的は、企業のニーズに合致した人材を確保するための基盤をつくり、採用活動全体を効率的かつ戦略的に進めることにあります。この段階での取り組みが、その後の選考品質や内定承諾率にも影響を与えるため、採用プロセス全体を見据えた設計が求められます。
母集団形成の4つのメリットを紹介!
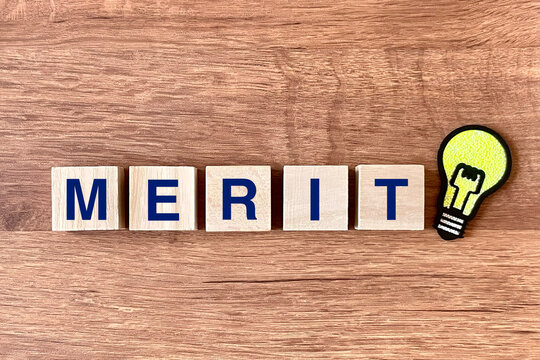
採用活動において母集団形成を計画的に行うことは、単に候補者を集めるだけではなく、採用全体の質と効率を大きく高める効果があります。十分な人数と適切な人材を確保できれば、選考スケジュールを安定的に進められ、急な採用ニーズにも柔軟に対応できます。
ここからは、母集団形成がもたらす具体的なメリットとして「採用活動の効率化」「事業成長」「離職率低下」の3つに焦点をあて、それぞれ詳しく解説していきましょう。
①採用活動の効率化につながる
計画的な母集団形成は、採用活動全体の効率化に直結する要素です。まず、採用フローごとに必要な人数を逆算できるため、応募段階から内定までを効率化できます。
例えば、最終的に5名採用する場合、過去のデータから応募数や面接通過率を分析すれば、応募段階で何名確保すべきかが具体的に把握できるのです。これにより、採用目標に合わせた施策や目標が立てられるので、無駄な広告出稿や過剰な説明会の開催などを避けられます。
さらに、採用チャネルを複数組み合わせることで、一つの手法に依存せず、応募数の波や市場変化にも柔軟に対応できます。このように、母集団形成を戦略的に行うことで、必要な人材を最短ルートで確保でき、全体の採用コストと時間を大幅に削減できるのです。
さらに、効率化させたいならこちら
AI採用を行うメリットとは?効果的に行うポイント・活用事例を徹底解説
②人材の採用が事業成長につながる
母集団形成は、単なる採用活動の一環ではなく、企業の中長期的な成長戦略にも直結します。質の高い人材を計画的に確保できれば、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大をスムーズに進められるでしょう。
特に競争の激しい市場においては、事業戦略を実行できる即戦力やポテンシャルの高い人材が、企業の競争優位を左右します。母集団を広く、かつ適切に形成しておくことで、採用ターゲットの幅が広がり、必要なスキルや経験を持つ人材を確実に選び出すことが可能となるでしょう。
さらに、優秀な人材が加わることでチーム全体のパフォーマンスが向上し、組織の生産性やイノベーションの創出にもつながります。この積み重ねが結果として業績向上や市場シェア拡大を後押しし、企業の持続的成長を実現するのです。
③離職率低下につながる
母集団形成がしっかりできていると、企業に合った人材を採用しやすくなり、結果として離職率の低下につながります。採用時に求めるスキルや価値観がマッチしている人が多ければ、入社後のギャップが少なくなり、早期退職を防げるのです。
反対に、母集団が薄く人数だけを追いかけると、採用後にミスマッチが発生しやすく、短期間で辞めてしまうケースが増えてしまうのです。離職率が高いと、再度採用活動をしなければならずコストや時間がかさみ、組織の安定性も損なわれます。
質の高い母集団を形成することは、社員の定着率向上に直結し、長期的な組織の強化に役立ちます。結果として企業は育成に注力できる環境が整い、生産性の向上や企業文化の形成にも良い影響をもたらすことができるでしょう。
④採用コストを適正化できる
母集団形成を適切に実施することで、採用にかかる費用の適正化につながります。十分な母集団が確立できていない状態で採用活動を進めてしまうと、目標の採用人数を達成できず、二次募集や三次募集が必要となり、採用活動は長期化してしまいます。その結果、採用にかける人件費や広告費用など、全体のコストが膨らんでいくでしょう。
一方、母集団形成を意識した採用活動では、過去の採用実績を参考にしながら各選考ステップを通過する人材の割合を想定し、目標値を設定します。例えば、最終的に10人を採用したい場合、二次選考では20人、一次選考では50人というように、各フェーズでの目標人数を逆算して決めていきます。
このように計画的に採用活動を進められるため、採用活動の長期化を抑制し、費用の適正化を図ることが可能です。また、特定のプロセスで目標人数に達しなかった場合も、早い段階で立て直しを図れるため、無駄なコストの発生を防ぐことができます。
母集団が重要視されるようになった背景とは?

近年、採用市場において母集団形成の重要性が高まっています。人手不足や採用競争の激化により、従来と同じように募集を行っても十分な応募者が集まりにくくなっています。
ここでは、母集団形成が注目されるようになった背景について詳しく見ていきましょう。
転職が一般的になり転職市場が活発化
かつては一つの企業で定年まで働き続ける終身雇用が当たり前でしたが、現在では転職が一般的なキャリア形成の選択肢として定着しています。内閣府の調査によると、働き方やライフスタイルの多様化により、転職を通じてキャリアアップを目指す人材や、より良い労働環境を求めて転職活動を行う人材が増加しています。
この転職市場の活発化により、応募者も企業とのマッチングをこれまで以上に重視するようになりました。従来のように給与や勤務地といった条件だけでなく、企業の理念や社風、キャリアパスなど、多角的な視点から就職先を選ぶようになっているのです。
また、転職が珍しくなくなってきた現在、応募者が複数の企業を比較検討するのは当たり前の状況です。精度の高い母集団形成によって、自社に本当にマッチする人材と出会える確率を高めることが、採用成功の鍵となっています。転職市場の活性化は、企業にとって母集団形成の質を向上させる必要性をより強く示す要因となっているのです。
企業の人手不足と人材獲得競争の激化
日本では少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少し続けています。総務省の情報によると、2015年の生産年齢人口は7,629万人でしたが、2030年には6,773万人まで減少すると予測されており、人材の希少化が進んでいることがわかります。これは企業にとって、求職者に有利な売り手市場が続いていることを意味しています。
厚生労働省が発表している有効求人倍率の推移を見ると、長年1.0倍以上を推移しており、求職者1人に対して1件以上の求人がある状態が続いています。つまり、従来と同じように募集をかけても、以前のように応募が集まりにくいというケースが多く見られるようになったのです。
人材の希少化が進む中で、優秀な人材を獲得しようとする企業間の競争も激しくなっています。大手企業だけでなく、中小企業やベンチャー企業も積極的に採用活動を展開しており、限られた人材を巡る人材獲得競争は年々激化しています。
そのため、ただ応募を待つだけでなく、自ら積極的に動いて求職者にアプローチし、応募を喚起する必要性が高まっているのです。こうした背景から、母集団形成の重要性がますます高まっています。
採用を戦略的に進める重要性の高まり
従来の採用活動では、新卒採用は採用人数を満たすことを、中途採用は欠員を補充することを重視する傾向がありました。しかし近年では、企業の事業戦略に紐づいた人材戦略へと変化しています。単に人数を確保するだけでなく、企業の成長に必要な人材を計画的に採用していくことが求められるようになったのです。
採用活動において質の高い母集団形成を行うことで、自社が必要としている人材をどれだけ集めることができるかが重要視されるようになっています。マッチする人材の募集・採用に重点を置くことで、採用活動の効率化だけではなく、入社後のミスマッチも軽減でき、定着率向上にもつながります。
採用市場では求人サイトに募集広告を出稿するだけでなく、ダイレクトリクルーティングやSNSを活用するなど、採用手法が広がってきました。求職者も多様な方法で採用情報の収集を行っているため、企業はターゲット人材の動きをつかみながら募集活動を幅広く展開していく必要があります。
母集団形成を成功させるための4つのポイント

母集団形成を成功させるには、単に多くの応募者を集めるだけでは不十分です。求める人材を明確にし、関係部署と連携しながら進めることが重要です。また、施策の効果測定を行い、常に改善を繰り返すことで、より良い母集団を形成できます。
ここからは、母集団形成の質と量を両立させるために必要な3つのポイントを詳しく解説します。
①求める人材を明確にする
母集団形成の第一歩は、どんな人材を採用したいのかを具体的に明確にすることです。曖昧なままだと、多くの応募者が集まっても、企業の求める人物像に合わないケースが増えてしまいます。
まずは仕事内容や部署のニーズをしっかりと分析し、スキル、経験、性格、価値観など求める要素を整理しましょう。これにより、求人票や説明会の内容もターゲットに合わせて作成でき、ミスマッチを減らせます。
さらに、求める人材のイメージを具体化するために、既存の優秀な社員の特徴を参考にすることも効果的です。彼らの成功体験や行動パターンを分析し、理想的な人材像を描くことで、採用基準の精度が上がります。
②配属先の部門を巻き込んで進めていく
母集団形成を成功させるためには、配属予定の部門を積極的に巻き込むことが欠かせません。採用は人事部だけの仕事と思われがちですが、実際には現場のニーズを正確に把握し反映させることが重要です。
また、現場の意見を取り入れることで、求人票の内容がよりリアルで魅力的なものになります。これにより、応募者が実際の業務内容や職場環境を理解しやすくなり、ミスマッチを防ぐ効果もあるのです。
加えて、採用後の教育やフォローアップも部門と連携して行うことで、新入社員がスムーズに職場に馴染みやすくなります。これにより、離職率の低下や組織全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
③効果測定と継続的改善を行う
母集団形成を成功させるには、実施した施策の効果測定を定期的に行い、その結果をもとに継続的な改善を進めることが欠かせません。採用活動には多くのコストと時間がかかるため、どの手法が効果的かを把握し、無駄を省くことが重要です。
具体的には、応募数や面接通過率、内定承諾率などの指標を定量的に分析し、どのチャネルや施策が母集団形成に貢献しているかを明確にします。さらに、定性的なフィードバックも取り入れ、候補者や面接官の声を反映させることで、より実態に即した改善が可能になります。
これらのPDCAサイクルを継続的に回すことで、母集団形成の質が向上し、効率的な採用活動も実現可能。改善の成果は組織全体に共有し、関係部署の理解と協力を促すことも大切です。
④一貫性を持った採用を行う
母集団形成を実施するメリットとして、一貫性のある採用活動を実現できる点が挙げられます。母集団形成を実施するにあたっては、まず「自社が求める人材像」を明確にするところから始まります。これにより社内の採用基準が定まり、求める人材像の認識を擦り合わせることができるため、一貫性のある採用が可能となります。
応募数を増やすだけでなく、入社後のミスマッチの予防につながる点も母集団形成の大きな価値です。採用ターゲットを明確にした母集団形成では、応募段階で自社の理念や社風に合わない候補者をスクリーニングします。それにより、採用後のミスマッチを防ぐことができ、自社にマッチする人材を獲得しやすくなるのです。
自社にマッチする人材は長期的に勤続する確率が高まり、内定辞退や早期離職を防ぎやすくなります。また、母集団形成によって求める人材像を明確にすることで、採用に関わる全てのメンバーが共通の基準を持つことができます。人事部門だけでなく、現場の管理職や面接官も同じ方向を向いて採用活動を進められるため、候補者に対して一貫したメッセージを伝えることができるでしょう。
人材が必要になってから、それでは長い時間がかかってしまいます。まずは、どのような人材構成で会社を成長させるか、どのような年齢構成でバランスが取れているのかを考える必要があります。その上で、採用は事業戦略の一環としてとらえ、計画的に進めていくことが求められているのです。
【新卒採用向け】効果的な母集団形成手法4選!

母集団形成を成功させるためには、さまざまな手法を効果的に組み合わせることが重要です。近年では、従来の求人媒体だけでなく、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、SNSやオウンドメディアの活用など、多様な方法が活用されています。
それぞれの手法には特徴があり、企業の業種や求める人材像によって適したものを選ぶことが求められます。ここからは、代表的な母集団形成の手法を紹介し、効果的な活用方法について見ていきましょう。
インターンシップや説明会の実施
インターンシップや説明会は、母集団形成において非常に有効な手法です。これらのイベントを通じて、求職者は企業の雰囲気や業務内容を直接体験・理解することができ、応募へのモチベーションを高めやすくなります。
特に新卒採用では、学生が早期から企業と接点を持つことで、他社との差別化や親近感の醸成につながります。また、企業側にとっても、インターンや説明会参加者の中から自社の求める人材を見極められる貴重な機会です。
効果的なインターンシップや説明会の運営には、内容の充実はもちろん、タイミングや参加者のニーズに合わせたプログラム設計が求められます。また、オンライン開催と対面開催のメリットを理解し、適切に使い分けることも重要です。
求人広告(就活サイト中心)
新卒採用における母集団形成の王道といえば、就活サイトへの求人広告掲載です。多くの学生が利用する就活サイトは、幅広い層にアプローチできる有効な手法として、今なお多くの企業に活用されています。
代表的な就活サイトとしては、マイナビ、リクナビ、キャリタス就活の3つが挙げられます。マイナビは2025年卒で約57万人の学生が登録しており、中小企業から大手企業まで幅広い企業が掲載しています。特に地方企業の登録数も多いため、地方採用を強化したい企業に適しています。
リクナビは業界最大手のリクルートが運営しており、2025年卒で約45万人の学生が登録しています。大手企業の求人が豊富で、説明会の日程検索機能が充実しているのが特徴です。キャリタス就活は、大学のキャリアセンターとの連携が強く、地方志向や中小企業志望の学生との親和性が高い媒体です。
就活サイトは認知度の向上と母集団の量を確保する上で非常に効果的です。ただし、掲載企業数が多いため、オプションを活用して上位表示させるなど、他社との差別化を図る工夫が必要になります。また、インターンシップサイトを併用することで、早期から学生との接点を作ることができ、より効果的な母集団形成が可能になるでしょう。
新卒向けダイレクトリクルーティングサービス
企業側から学生に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングは、近年注目を集めている採用手法です。就活サイトのように応募を待つのではなく、自社が求める人材に対して積極的にスカウトを送ることで、質の高い母集団形成を実現できます。
代表的なサービスとしては、OfferBox、dodaキャンパス、キミスカが挙げられます。OfferBoxは就活生の3人に1人が利用しており、登録学生数は約20万人です。企業のオファー送信数と学生のオファー受信数に上限があるため、オファー開封率が87%と高水準を保っています。
dodaキャンパスはベネッセとパーソルキャリアが共同運営しており、登録学生数は約104万人(26卒~29卒)です。大学1・2年生からアプローチが可能なため、早期から接点を作りたい企業に適しています。オファー送信数が無制限なのも大きな特徴です。キミスカは3種類のスカウト機能を使い分けることができ、学生に対して本気度を伝えることができます。
ダイレクトリクルーティングは工数がかかりますが、自社にマッチする人材にピンポイントでアプローチできるため、採用の質を高めることができます。早期から運用を開始することで、優秀な学生との出会いが期待できるでしょう。
関連記事:
【新卒採用担当者向け】媒体選びで失敗しないダイレクトリクルーティング完全ガイド
【企業向け】OfferBox(オファーボックス)の使い方完全ガイド!新卒採用を成功させる7つのコツを徹底解説!
【2025最新】キミスカの料金を徹底解説!費用対効果と効果を高める方法を徹底解説!
SNS・オウンドメディアの活用
近年、SNSやオウンドメディアを活用した母集団形成が注目されています。SNSは企業の魅力をリアルタイムで発信できるため、求職者との距離を縮める効果があるとされているため、X(旧:Twitter)やInstagramなどのプラットフォームの活用によって、求職者の関心を引きやすくなります。
一方、オウンドメディアは企業が自社で運営する情報発信サイトであり、採用情報に加え、業界のトレンドや働き方の紹介、社員インタビューなど多様なコンテンツを掲載できます。これにより、企業の専門性や価値観を求職者に伝え、応募意欲を高めることが可能です。
これらのツールは採用ブランディングにも寄与し、中長期的な母集団形成に効果的です。さらに、SNSやオウンドメディアは双方向のコミュニケーションが可能なため、求職者からの質問や反応を直接受け取りやすく、採用担当者が迅速に対応できる点もメリットです。
採用SNS運用支援サービスのRecBuzzでは、企業のSNS採用活動を効果的にサポートしています。SNS投稿の企画から運用までをトータルでサポートし、学生との接点を最大化することができます。定期的な情報発信によって、企業の認知度向上とブランディングを同時に実現できるでしょう。
RecBuzzの詳細はこちら
関連記事:
SNS採用とは?企業の成功事例と効果を最大化するコツを徹底解説!
【保存版】新卒採用が劇的に変わる!TikTok採用トレンドと成功ポイント
【中途採用向け】効果的な母集団形成手法4選!
![400+] Business Pictures | page 7 | Wallpapers.com](https://wallpapers.com/images/hd/interview-pictures-1920-x-1080-rk9g11ejx5cb8pbd.jpg)
中途採用を実施する場合には、新卒採用とはまた違った視点での母集団形成の手法をとる必要も出てきます。手法としては同じでも、その内容は別物ということも珍しくありません。
ここからは、中途採用向けの母集団形成手法をご紹介します。
求人広告(転職サイト中心)
中途採用における母集団形成でも、転職サイトへの求人広告掲載は依然として有効な手法です。転職を検討している求職者の多くが転職サイトを利用しており、幅広い業種・職種の人材にアプローチできます。
代表的な転職サイトとしては、doda、リクナビNEXT、マイナビ転職が挙げられます。dodaはパーソルキャリアが運営する総合転職サイトで、幅広い年齢層と職種をカバーしています。転職エージェントサービスと連携しているため、サイト掲載と人材紹介を併用できるのが特徴です。
リクナビNEXTは国内最大級の転職サイトで、登録者数が非常に多いのが強みです。特に即戦力として活躍できる人材が多く登録しており、経験者採用に適しています。マイナビ転職は20代〜30代の若手層に強く、第二新卒や若手のキャリアチェンジ層へのアプローチに効果的です。
転職サイトは認知度が高く、求職者が日常的にチェックするツールであるため、母集団の量を確保しやすい手法です。ただし、掲載企業が多いため、求人原稿の質を高め、自社の魅力を効果的に伝える工夫が必要になります。また、スカウト機能を活用することで、より積極的なアプローチも可能です。
中途向けダイレクトリクルーティングサービス
中途採用においても、ダイレクトリクルーティングの活用が進んでいます。転職潜在層を含めた幅広い人材に直接アプローチできるため、転職サイトでは出会えない優秀な人材との接点を作ることができます。
代表的なサービスとしては、ビズリーチ、リクルートダイレクトスカウト、Greenが挙げられます。ビズリーチは即戦力人材に特化したプラットフォームで、ハイクラス人材の採用に強みを持っています。管理職や専門職など、経験豊富な人材へのアプローチに適しています。
リクルートダイレクトスカウトは、リクルートが運営するハイクラス向けのダイレクトリクルーティングサービスです。年収600万円以上のポジションを中心に、経営層や管理職クラスの採用に活用されています。GreenはIT・Web業界に特化したサービスで、エンジニアやクリエイター職の採用に強みを持っています。
中途採用のダイレクトリクルーティングでは、転職顕在層だけでなく転職潜在層にもアプローチできるのが最大のメリットです。魅力的なスカウト文面を作成し、自社の魅力を効果的に伝えることで、優秀な人材の採用につながります。ただし、スカウト文面の作成や候補者とのコミュニケーションに工数がかかるため、運用体制の整備が重要です。
関連記事:
【採用担当者向け】dodaダイレクトの料金を徹底解説!それぞれのプランについて詳しく紹介!
【採用担当者向け】OpenWorkのスカウト評判は?メリットから注意点まで企業目線で徹底解説!
人材紹介エージェント
人材紹介エージェントは、採用のプロが企業と求職者の間に入り、マッチングをサポートするサービスです。完全成功報酬型が一般的で、初期費用をかけずに採用活動を進められるのが特徴です。
人材紹介エージェントの最大のメリットは、採用工数を大幅に削減できる点です。求人票の作成、候補者のスクリーニング、面接日程の調整、条件交渉など、採用活動における多くの業務をエージェントが代行してくれます。また、エージェントが保有する独自のネットワークを活用することで、転職サイトには登録していない優秀な人材にもアプローチできます。
特に専門職や管理職など、採用難易度が高いポジションでは、エージェントの専門知識とネットワークが大きな力を発揮します。業界や職種に精通したエージェントであれば、求める人材像を的確に理解し、マッチ度の高い候補者を紹介してくれるでしょう。
ただし、成功報酬として理論年収の30〜35%程度の費用がかかるため、採用単価は高くなります。また、エージェント任せにするのではなく、自社の魅力を効果的に伝え、求める人材像を明確に共有することが成功の鍵となります。転職サイトやダイレクトリクルーティングと併用することで、より効果的な母集団形成が可能になるでしょう。
リファラル採用(社員紹介)
リファラル採用とは、現社員からの紹介によって候補者を採用する方法です。社員が知人や友人、元同僚など、自社に合いそうな人材を推薦するため、ミスマッチが起きにくいのが特徴です。
紹介者が自社のカルチャーや仕事内容をよく理解しているため、適切な人材を選びやすく、入社後の定着率向上にもつながります。また、社員が自らのネットワークを活用することで、求人媒体では届きにくい優秀な人材にもアプローチできるメリットがあります。
ただし、紹介を受ける際には公平性や透明性を保つことが重要で、社員間でのトラブル防止や選考プロセスの適正化を図ることが必要です。効果的に運用するためには、紹介インセンティブの設計や紹介者への感謝の表明も欠かせません。
母集団形成の成功事例

母集団形成を効果的に進めるためには、成功事例から学ぶことが重要です。さまざまな企業が取り入れている工夫や戦略には、自社の採用活動にも応用できるヒントが多く含まれています。
特に新卒採用と中途採用では、ターゲットや手法が異なるため、それぞれに適したアプローチが求められます。ここでは、ダイレクトリクルーティングサービス「RecUp」を活用した企業の成功事例をご紹介します。これらの事例から、効果的な母集団形成のヒントを見つけていただければ幸いです。
株式会社イトーヨーカ堂様

大手小売企業である株式会社イトーヨーカ堂様は、全国に多数の店舗を展開する中で、優秀な人材の確保が常に課題となっていました。従来の採用手法では、応募者数は確保できるものの、自社が求める人材像とのマッチング精度に課題を感じていました。
そこで、ダイレクトリクルーティングサービス「RecUp」を導入し、自社が求める人材に直接アプローチする戦略に転換しました。学生のプロフィールを詳細に確認し、小売業への関心や接客スキル、チームワークを重視する姿勢など、自社の求める要素を持つ学生に絞ってスカウトを送信しました。
その結果、応募者の質が大幅に向上し、面接通過率も従来の手法と比較して高い水準を維持できるようになりました。また、入社後のミスマッチも減少し、定着率の向上にもつながっています。イトーヨーカ堂様の事例は、大手企業においてもダイレクトリクルーティングが有効であることを示しています。
詳細はこちら:『毎日スカウトが送れる』──RecUpで送信数の担保と採用の質が向上した事例
東栄ホームサービス様
不動産業界で事業を展開する東栄ホームサービス様は、中小企業ならではの採用課題に直面していました。大手企業と比較して知名度が低く、従来の就活サイトだけでは十分な母集団を形成できない状況でした。
RecUpの導入により、企業側から積極的に学生にアプローチできるようになり、知名度のハンデを克服することができました。スカウト文面では、自社の強みである風通しの良い社風や、若手でも責任ある仕事を任せる文化、充実した教育制度などを丁寧に伝えました。
その結果、自社の価値観に共感する学生との出会いが増え、内定承諾率も大幅に向上しました。入社後も高いモチベーションを持って業務に取り組む社員が増え、組織全体の活性化にもつながっています。東栄ホームサービス様の事例は、中小企業こそダイレクトリクルーティングを活用すべきであることを示しています。
詳細はこちら:【数値付き】ダイレクトリクルーティングの事例集!自社のメリットや効果的に行う5つのポイントとは?
株式会社オルグ様
IT業界で事業を展開する株式会社オルグ様は、エンジニア採用において競争が激化する中で、自社にマッチする人材の確保に苦戦していました。多くの応募者が集まるものの、技術力と自社の文化への適合性を両立する人材を見つけることが難しい状況でした。
RecUpを活用することで、学生の専攻やスキル、価値観などを詳細に確認した上でスカウトを送信できるようになりました。特に、技術への探究心や成長意欲、チームでの開発経験など、自社が重視する要素を持つ学生にターゲットを絞ってアプローチしました。
その結果、技術力と文化適合性を両立する優秀な人材の採用に成功し、採用の質を大幅に向上させることができました。また、ダイレクトリクルーティングを通じて学生と深いコミュニケーションを取ることで、入社前から企業理解を深めてもらうことができ、入社後の早期活躍にもつながっています。
詳細はこちら:「思っていた4倍すごい!」-RecUpで母集団形成・面談の質が向上した成功事例
その他の成功事例:
【成功事例】母集団形成とは?採用を成功させるポイントや手法について詳しく解説!
AIスカウトならRecUp

採用活動で効率的に母集団形成を進めるには、AIを活用したサービスが有効です。RecUp(リクアップ)は、AIを活用した次世代スカウトサービスです。
RecUpは生成AIが求職者一人ひとりのプロフィールをもとに、最適化されたスカウトメールを自動で作成・送信する仕組みを備えています。これにより、担当者の業務負担を大幅に削減できるだけでなく、開封率や返信率を高め、採用の成功確率が飛躍的に向上します。
スカウト文は継続的にブラッシュアップするため、常に効果的で精度の高いアプローチが可能です。気になる方は、是非一度公式サイトよりサービス内容をご確認ください。
より詳細な活用イメージや、他社の導入事例について知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。